![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
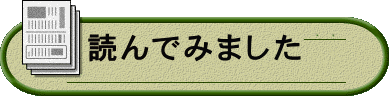
2021年7月~12月
|
| 柳広司著『太平洋食堂』(小学館、2020年) |
|
「『目の前で苦しんでいる人から目を背けることは、どうしてもできん』 |
| マシュー・サイド著『失敗の科学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016年)(前) |
| マシュー・サイド著『失敗の科学』 (ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016年)(後) |
| (承前) 第4章では、何らかの結果を得るには小さな改善(マージナル・ゲイン)の積み重ねが重要であることが述べられる。 最初に取り上げられるのは、イギリス人初のツール・ド・フランス総合優勝を成し遂げた自転車競技のチームの例。 A地点からB地点までいかに早く到達するかという単純な目標。しかしその前には、専用マットレスや枕の導入で同じ質の睡眠をとること、新しいホテルに滞在する時には事前にスタッフが選手の部屋に掃除機をかけて感染症予防、もちろん自転車のデザインごとのテスト、トレーニング方法等々・・・。こうした小さくとも数多くの要素が積み重ねられた結果、詳細なデータベースが作成され、それが成果につながることになった。 またF1を勝ち抜いたメルセデスでは、マシンに取り付けたセンサーから集められるデータは1万6000チャンネル、そしてさらにそこから5万におよぶチャンネルが派生して取り出せるという。 このことが意味するのは、「大きな目立つ要素より、何百、何千という小さな要素を極限まで最適化すること」、つまり小さな改善がとても大切だと言うことだ。 それでは、このやりかたは別の分野にはどのように応用できるだろうか。 本書ではアフリカへの開発援助の例が取り上げられる。開発援助に関しては、「さらに援助すれば貧困を解消できる」という研究もあるし、「援助しない方がアフリカの状況は向上する」とする説もある。相反する議論に決着をつけるのにはランダム化比較試験が有効だけれど、アフリカは一つしか無いからそれは無理。ではどうするか。 開発援助は、例えばマラリア予防、識字率や学力の向上、インフラ整備等々さまざまな分野に分かれている。なので、その一つを対象として人や地域を介入群と対照群に分ければプログラムの効果を比較検証できる。つまり、アフリカ全体をまとめての比較は難しくとも、小さなプログラムに分けて検証すれば明確な裏付けが取れるので、そこから一つずつ改善を重ねていけばいいということになり、まず経済学者による小さな教育プログラムで行うことになった。 そこで教科書の無償配布を行ったが、予想に反する結果となった。配布したグループとしなかったグループに成績の差異は出なかったのである。原因は英語(当地の第3言語)で書かれた教科書では内容が把握しづらかったためだった。もし検証をしなかったなら依然として効果の無い教科書を配布し続けていたかもしれない。そこで、今度は理解しやすいように図表にしてイーゼルに立てたり壁につるしたりする視覚教材を使ったが、やはり結果は同じだった。 しかし経済学者たちはあきらめなかった。対象地方の子どもたちに寄生虫感染が多いことに気づいていた彼らは、今度は「駆虫薬の配布」を思いついた。それは子どもたちの発育不良や無気力、そして学校を欠席する原因ともなっていたからだ。そしてそれは予想よりもはるかにすばらしい結果を出した。スタッフの一人は次のように記している。 「駆虫薬配布プログラムは大成功だった。子どもたちの身長が伸び、再感染率が下がり、学校の欠席率は25%も下がった。しかも、コストはほとんどかからなかった」 このことは、「わかったつもり」になることなく、「小さなレベルで、何が有効で何が有効でないかを見極めること」が必要であり、たとえ「それぞれのステップは小さくても、積み重なれば驚くほど大きく」なるということを示している。 この章では他に、Googleが選んだ「最高の青色」と、大食いコンテストに「伝説」を残した日本人のエピソードが出ている。いずれも小さな改善を重ねて大きな結果を得た例となっている。 第5章は、ものごとを単純化し、責任者を捜し出して非難の矛先を向けて懲罰を加えるという、人の心のバイアスに関して述べる。 航空業界では通常ではミスを罰しないにもかかわらず、1989年、「ノベンバー・オスカー事件」と呼ばれるニアミスによって非難を一身に浴びて裁判にかけられた機長が、のちに自殺に追い込まれた事件を取り上げている。機長が直面したきびしい現実を検証すれば、機長の判断は「完璧ではなかったかも知れないが、犯罪に値する行動ではなかった」し、「機長を非難するのは間違いだ」という点では大勢の関係者はみな意見が一致していたという。これは「ミスに対して前向きな態度をとる航空業界でさえ、非難の衝動と完全に無縁ではなかった」例として示される。 認知的不協和の心理を内的な要素とすれば、非難は外からの要因として個人や組織にプレッシャーをかけ、失敗から学ぶ機会を奪ってしまう。なぜなら、非難や懲罰には規律をただすような効果は認められないから、ということだ。 その一例としてあげているのは、2004年にハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が行った調査である。それは、厳しい規律が一部にある病院の8つの看護チームに対する調査だ。その結果は、「懲罰志向のチームでは、たしかに看護師からのミスの報告は少なかったが、実際にはほかのチームより多くのミスを犯していた」。それに対して、「非難傾向が低いチームでは、逆の結果が出た」と言うことだ。 人間工学の専門家シドニー・デッカーは、「責任を課すことと(不当に)非難することはまったく別だ」とし、「非難すると、相手はかえって責任を果たさなくなる可能性がある。ミスの報告を避け、状況の改善のために進んで意見を出すこともしなくなる」と言っている。 著者はこのような非難行動を「脊髄反射的な犯人探し」と名づけ、それは「原因を性格的な要因に求めて状況的な要因を軽視」し、「一番単純で一番直感的な結論を出す傾向」が脳にあるためだとする。ただし、この傾向は「自分のミスになると出てこないらしい」。そしてこれは個人レベルでも集団レベルでも見られるという。 なるほど・・・人の脳は自分に都合良く出来ているわけだ・・・と納得がいった。ところで、ここで、併行して読んでいた、毎日新聞取材班による『SNS暴力-なぜ人は匿名の刃をふるうのか-』にあった内容を紹介したい。 好き嫌いなどの感情を抑制する理性の回路は前頭前野にあって、書くか書くまいかという「判断保留」の際に働くが、それは脳に高い負荷をかけるという。これについて脳科学者の茂木健一郎氏は、「脳はストレスを感じでいる時、負荷の高い行為はしたくなくなる」し、また非難することが「報酬系」を強化し、そのため繰り返してしまうのではないかとも言っている。さらに脳のミラーシステムからみても、「誰かを中傷することは、実は自分の脳も傷つける自傷行為」であること、またマイケル・サンデル教授による人気講義「JUSTICE(正義)」をあげて、「正義」は人の数だけ存在していることを考えようと勧めている。 同じく脳科学者の中野信子氏も、こうした状態のことを著書『人は、なぜ他人を許せないのか?』(アスコム)の中で「正義中毒」と名付けている。「正義中毒の状態になると、自分と異なるものをすべて悪と考え」るが、特に相手が「『わかりやすい失態』をさらしている場合、そして、いくら攻撃しても自分の立場が脅かされる心配がない状況などが重なれば、正義を振りかざす格好の機会となる」などと解説しているという。(以上『SNS暴力-なぜ人は匿名の刃をふるうのか-』毎日新聞出版 2020年より) そしてまた、責任者の追求と非難は往々にして逆効果をもたらすことになる。その悲劇的な例として著者は2007年、ロンドン北部のハリンゲイで17か月のピーターという男の子が亡くなった事件をあげる。 虐待と育児放棄の未に亡くなった15か月後に、実の母親、彼女の恋人、恋人の兄の3人が実刑判決を受けた。しかし翌日の新聞は、当時ピーターを直接担当していたソーシャルワーカーのマリア・ウォードと、地区児童安全保障委員会(LSCB)委員長のシャロン・シュースミスに非難の矛先を向けた。 その結果、2人の解雇を求める嘆願書には16万人が署名。彼女らの写真や電話番号も紙面に掲載されると、殺害の脅迫状が送られたりして自宅を離れなければならなくなった。ただ人々は、この大騒ぎでソーシャルワーカーの仕事振りが改善されるだろうと思ったし、ある識者は、「これで彼らは仕事に専念するようになる」と言ったという。 その結果どうなったか・・・。 ソーシャルワーカーの辞職急増、新規ソーシャルワーカーの激減、児童保護件数の大幅な増加、ある地域では常勤人数不足で代理業者への委託金約2億円、等々。そして、残ったソーシャルワーカーの負担は増え、一人ひとりにかけられる時間は減ったため、自分の管理する子どもに何かがないように強引に介入し始めた。「危険な信号を見逃して『魔女狩り』に遭うわけにはいかないと考えた」からだ。 そうすると、家族から引き離される子どもの数が飛躍的に増え、その結果、裁判所による保護命令が次々と出され、急増した需要に合わせるためにより質の低い家庭にも里親としての承認が与えられるようになり、本来の家庭から引き離された子どもたちの多くは心身にダメージを受けることになった。 するとメディアは、それまでとは逆に、「子どもをあやしただけで虐待疑惑!引き離されるのを恐れて逃避行を続ける母娘」といった見出しとともに、「愛する子どもを無理やり奪われる親たち」のストーリーを報道し始めたと言う。 おまけに、過剰な自己防衛が社会福祉事業のあらゆる面で見られるようになり、問題視される可能性を恐れて貴重な情報は隠蔽され、自己防衛にばかり時間が割かれ、実際の社会福祉活動はないがしろにされるに至った。そして、「こうした非難騒ぎの翌年、虐待によって死亡した児童の数は25%以上増加し、その後3年間上昇し続けた」のである。 この事件で激しい非難の的となったシャロン・シュースミスは、当時は自分だけでなく家族全員の命を絶つことまで考えたという。「家族3人とも本当に苦しんでいました。私の苦痛が娘たちの苦痛であり、娘たちの苦痛が私の苦痛でした。みんなのためにもう終わりにしたいという思いが頭をよぎりました」と。 シドニー・デッカーは名著『Just Culture(公正な文化)』でこう書いているという。 「問趨は、非難したり訴えたり裁判にかけたりすれば、相手は責任感を強く持つようになると思い込んだままでいいのか、ということだ。今のところそれで説明責任が強化されたという証拠はひとつも出ていない」 第6章は、もし私たちが「失敗から学ばない」傾向にあるなら、それをどう乗り越えるかをテーマとする。 最初にあげるのはベッカムの少年時代のエピソード。6歳のころにはごく平均的なサッカー少年だったベッカムは、毎日の練習で9歳のころには2003回というリフティングの新記録を出した。また父といっしょの公園でのフリーキックの練習は5万回を超えていただろうと言う(彼の父による)。 「私のフリーキックというと、みんなゴールが決まったところばかりイメージするようです。でも私の頭には、数え切れないほどの失敗したシュートが浮かびます」 バスケットボールのマイケル・ジョーダンもCMで、「私は9000本以上シュートを外し、ほぼ300試合で負けた。ウイニングショットを任されて外したことは26回ある」と言っているそうだ。 著者は言う。「もちろん誰でも成功に向けて努力はするが、そのプロセスに『失敗が欠かせない』と強く認識しているのは、こうした成功者であることが多い」と。 ミシガン州立大学の心理学者ジュイソン・モーザーらによって、失敗した時に脳内に起きる二つの信号の現れ方に関する実験が行われた。一つは「エラー関連陰性電位(ERN)」と言って、自分の失敗に気づいたあと50ミリ秒ほどで自動的に現れる単純な気づきの反応、もう一つは失敗の200~500ミリ秒後に生じる「エラー陽性電位(Pe)」と言う信号で、それは自分が犯した間違いに意識的に着目する反応であって、そこから学ぼうとすることを示している。 これまで、どちらの反応も強い人ほど失敗からより素早く学ぶ傾向があるという結果が知られていた。 そこでモーザーは、事前のアンケートに基づいて被験者のマインドセット(思考傾向)を「固定型」と「成長型」のふたつに識別し、グループ分けした。 「固定型」傾向の人は、「自分の知性や才能は生まれ持ったもので、ほぼ変えることはできない」ととらえる一方、「成長型」傾向の人は、「先天的なものがどうであれ、根気強く努力を続ければ、自分の資質をさらに高めて成長できる」と信じているとされる。 退屈と言っていいほどシンプルな実験を行った結果、失敗に対するグループ間の脳波の反応に劇的な違いが現れた。ERNについては、どちらのグループも同じように簡単に「間違えた」ことに気づき、同じ強さの反応が示された。しかしPeは違った。成長型のグループでは、固定型の傾向が最も強い被験者と比べれば3倍も強い反応を示したという。これは、成長型の被験者は間違いにしっかりと注意を向けていたということを表している。また、「この実験ではほかにも、Peの反応が強い被験者ほど、失敗後の正解率が上昇するという結果も出た。失敗への着目度と学習効果との密接な相関関係が窺える」と言う。 つまり、「個人でも組織でも、失敗に真正面から取り組めば成長できるが、逃げれば何も学べない。考え方の違いは脳波に如実に表れる」し、失敗から学べるかどうかの違いは、「突き詰めて言えば、失敗の受け止め方の違い」ということになる。失敗を「自分の力を伸ばす上で欠かせないもの」としてごく自然に受け止めるか、人の成功は生まれつき才能や知性によると考え、失敗を「自分に才能がない証拠」と受け止めるかと言うことだ。このことは、子どもを対象にした学習や企業組織にもあてはめて示される。 ところで逆説的だが、「成長型の人ほどあきらめる判断を合理的に下す」という。心理学者のキャロル・ドゥエックは、「成長型マインドセットの人にとって、『自分にはこの問題の解決に必要なスキルが足りない』という判断を阻むものは何もない。彼らは自分の“欠陥”を晒すことを恐れたり恥じたりすることなく、自由にあきらめることができる」と言う。成長型の人にとって、引き際を見極めてほかのことに挑戦するのも、その反対にやり抜くのもどちらも“成長”なのだ。 この章ではこの他、アメリカのウエストポイントにおける訓練における「やり抜く力」、さらに、なぜ日本に起業家が少ないのか、また数学の習熟度についての国際比較が述べられる。いずれにしても、リスクを負うことへの姿勢の違いが現れている。 終章はこれまでのまとめとして、失敗から学ぶ力を具体的に発揮する方法を考えているが、その前に人類の進化について簡潔に触れている。 歴史的に見れば、ほぼどんな社会にも、初期には神話・宗教・迷信などの形で独自の世界観が存在し、それらそのまま不可侵的に継承されてきた。これは固定型のマインドである。西洋においては、古代ギリシア時代に検証、批判を是とする理性的なものに変わった。ソクラテス、プラトン、アリストテレス、ピタゴラス、ユークリッドなどがその例である。しかし、そうした時代はキリスト教の浸透とともに終わり、長い迷信の時代に入る。1543年に解剖学者アンドレアス・ヴュサリウスが否定するまで、男性の肋骨は女性より1本少ないと信じられていた。 このような「神コンプレックス」と呼ばれる固定された世界観は現在でも見られる。全能の神のようにベテラン医師を扱う医療業界でも、無謬主義に固執する刑事司法においても、である。 一方、科学の世界では基本的に未知の真実があることを前提としているが、そのなかでは、社会科学の分野ではなお革新が促されるべきだと言う。著者は、失敗することは恥ずかしいものでも汚らわしいものでもないことを認めて、「実験や検証をする者、根気強くやり遂げようとする者、勇敢に批判を受け止めようとする者、自分の仮説を過信せず真実を見つけ出そうとする者を我々は賞賛するべき」と主張する。それは「もちろん簡単なことではないし、抵抗も受けるだろう。しかしその壁を乗り越えていくだけの価値はある」のである。問題は、モチベーションや熱意ではなく「やり方」にあるからだ。 データと有意義なフィードバックが行われることが重要なのであり、そうした「間違いを警告してくれる『信号』をシステムの中に取り入れることが肝心」であって、そのためには、「先行テスト」もひとつの手段になり得るし、本書で取り上げているRCTも強力なツールのひとつとされる。 さらにいえば、心理学者ゲイリー・クラインが提唱した「事前検死(pre-mortem)」という手法も効果的である。これは、あらかじめ「プロジェクトは失敗した」「目標は達成できなかった」という状態を想定し、「なぜうまくいかなかったのか?」を事前検証するもので、「失敗するかもしれない」と考えるのとはまったく違う。 否定的だと受け止められることを恐れず懸念事項をオープンに話し合うことによって、失敗という抽象的な概念を具体化させる。そうすると問題に対する意識の持ち方が変わると言うことだ。 これら本書に示されたまざまな手法を活用しながら「成長型マインドセットを持ち続ければ、どこまでも可能性が広がる進化のプロセスを力強く歩んでいけるだろう」と本書は結ばれているが、よりピュアーに言うなら、エゴに気づいて抑えると同時に問題に正面から向き合う覚悟を決める、それが次へのステップにつながるのだとあらためて自覚させられた。(完) (雅) |
| 森川すいめい著『その島の人たちは、ひとの話をきかない』 (青土社 2016年) |
|
『漂流老人ホームレス社会』(「月刊サティ!」2020年8/9月合併号で紹介)の著者は、「自殺希少地域」とされる5カ所を6回訪ね、そのわけを知ろうとそれぞれ一週間前後滞在した。本書はその記録である。面白いことに、その背景は地域によって異なるものや共通するものがあった。(著者のプロフィールその他については上記を参照されたい) |
| 清水将大著『二宮金次郎の言葉 ―その一生に学ぶ人の道―』 (コアラブックス 2010年) |
| コロナ以前、私の町の図書館では月に一度、「図書館+講談」として、五代目一龍斎貞花師による口演が行われていた。そのひとつに、あるとき『財政再建・農村復興 二宮尊徳』が予定され、予告とともに演題に関連する数冊の書籍が小さなテーブルにあらかじめ展示されていた。何気なく手にとって借りて読んでみたところはじめて知るとことも多く、これは紹介してみたいと思った。
最近は坐って本を読んでいる姿もあるというが、小学校の入り口に薪を背負いながら歩く二宮金次郎の像を覚えておられる方もおおぜいおられるだろう。一般的には金次郎は勤勉さの手本(注1)として、長じては篤農家、農村の指導者、そして道徳家というイメージだと思う。 注1:明治44年に刊行された「尋常小学唱歌」(第二学年用)には一番から三番まで、「手本は二宮金次郎」という歌詞が繰り返されている。 戦前の修身の教科書には、幼年から青年までの金次郎の姿だけが載せられているし(注2)、かつて読んだ伝記でも、憶えているのは農村で農民を指導する話しだけだった。本書の「まえがき」によると、金次郎はそればかりではなく、「有能な商人、銀行家、スケールの大きい実業家、藩主顔負けの政治家という顔を持っていた」と言う。しかもその上、占領軍のある少佐が、「日本が生んだ最大の民主主義者」と語ったエピソードも本書によって知ることができた。 注2:小池松次編『修身の教科書』(第4期尋常小学校修身書巻三、サンマーク出版による。 序章、終章を含めて12章からなる本書は、金次郎70年の一生を描きつつ、現代的に置きかえた抄訳や再構築した語録に解説を附して紹介している。ただここでは、その中でも基本的なところに焦点をあてて取り上げてみたい。 本書によると、実践から生まれた金次郎の考えは以下の9点である。 ①勤労、②分度(ぶんど:自分の収入に見合った水準の中での生活)、③推譲(すいじょう:分度を守って余財を捻出して家族や子孫のために蓄えたり【自譲】、広く社会や国のために譲る【他譲】、④至誠(真心)、⑤積小為大(小さな努力の積み重ね)、⑥心田開発(各人のやる気を起こさせる)、⑦一円融合(全てのものの相互の関係の尊重)、⑧仕法(農村復興や財政立て直しのやり方)、⑨報徳(金次郎の思想全般。すべてのものの特性を活かし、至誠の心をもって勤労、推譲、分度を実行すること)。 この上で、金次郎の最も強調するところは何であったか言うと、それは勤勉をともなう「実践」とされる。例えば報徳を水にたとえてこのように言っている。 「大道は水のようなもので、よく世の中を潤沢にして滞らない」。しかし神儒仏の学者が書物には通じていても世の中の役に立たないのは、それが凍ったようなものだからで、「もとは水には違いないが、潤いづらく水の用をなさない」からだと言う。つまり単なる知識は氷にすぎず、「それゆえ、報徳では実行を尊ぶ」のだと。 さらに、善行が幸福につながり悪行が禍につながることを米と稗にたとえて言う。 「米を蒔けば米が生え、稗を蒔けば稗を得るのと同じことだ。米を蒔いて米の札を立て、稗を蒔いて稗の札を立て、その生え方を調べれば、米と稗は決して入れ違っていないことがわかる」と。この説明は農民にはよくわかるものだったろう。 また推譲ということでは、「人の人たるゆえんは『推譲』にある。ここに一粒の米がある。これを食べてしまえばただの一粒だが、もし推し譲ってこれを蒔き、秋の実りを待ってから食べれば、百粒食ってもまだ余りがある。これこそ万世変わらぬ人道なのだ」。これはイエスが語ったという「一粒の麦もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし」を彷彿とさせるが、これもまた農に携わる人々には身近に理解されるものだったと思う。 そればかりではない。この推譲の道は、「富者ばかりではなく、道も譲らねばならぬ、言葉も譲らねばならぬ、功績も譲らねばならぬ。よく勤めるがよい」と言っている。これは仏教で説かれる実践の一面にそのままあてはまっていると思われる。 ここで思い出したのは、何十年も前に読んだ本にあった、後の金次郎の生き方につながるような逸話。それは、金次郎がまだ若い時に、とあるお堂で旅の僧が当時珍しかった日本語の発音で観音経を読むのを傍で聞いて感激し、200文を布施した(これは本書にもある)と言う話。正確な文言は思い出せないが、その時金次郎は、「この経は(観音にすがれと教えているのではなく)、自ら観音の行いをするように教えているのですね」と言って旅の僧を驚かせたという。 しかし施すと言ってもむやみで無原則ではない。正直で勤勉な者へは大いに援助したが、怠け者にすぐ情けをかけてはかえって滅びのもととなることを金次郎は知っていたからである。次のように言っている。 「衰えた村を復興させるには、篤実精励の良民を選んで大いにこれを表彰し、一村の模範とし、それによって放逸無頼の貧民がついに変化して、篤実精励の良民となるように導くのである。 ひとまず放逸無頼の貧民を差し置いて、離散滅亡するにまかせるのが、わが法の秘訣なのだ。なぜかといえば、彼らが改悟改心して、善良に帰するのを待ち受けて、これに地を与え屋敷を与えるのだから、恨みをいだくことはできず、また善良に帰しないわけにいかないのだ」 そして次には、分度こそが「四海の困窮を救って、あまねく苦民に施して、なお余りがあるという方法」であって、その真髄は「ただ分度を定めるという一事にある」と言う。 こうした一連の考え方を一文でまとめると、つまりは怠惰から離れて「仕法」に基づいた「勤労」をし、「分度」を定めることで「一円融合」を成し遂げる、これが「報徳」の生き方ということになる。 今日、税の無駄遣いが言われているような時、その舵取りをしている立場にある人々にぜひ通じてほしい言葉。 「国や家が貧窮に陥るのはなぜかといえば、これは分内の財を散らしてしまうからである。これを散らさないようにさえすれば、国も国家も必ず繁栄を保つことができる。 人が寒さに苦しむのは、全身の温かさを散らしてしまうからで、着物を重ねて体を覆えば、すぐに温かくなる。 これは着物が温かいのではなく、全身の温かさを散らさないからだ。もし衣類そのものが温かいのなら、質屋の蔵からは火事がでるはずだ。けれども一度でもそれで火事になったためしがないから、衣類が温かいものでないことが知れる。 分度と、国や家との関係は、ちょうどこの着物のようなものだ。 それだから国や家の衰えを興そうとするには、何よりもまず分度を立てるがよい。 分度が立ちさえすれば、分内の財が散らないから、衰えた国も起こすことができ、つぶれかけた家も立て直すことができる」 ここまで、「勤勉」「推譲」「分度」という面を紹介してきたが、本書にはそのほか「有能な商人、銀行家、スケールの大きい実業家、藩主顔負けの政治家」であった実績も数々披瀝されていて、それぞれの立場から読んでみれば、大いに参考になると思われる。 最後に、それらすべてが鋭い観察眼から来ること示すエピソードを二つあげたいと思う。(本書の著者による) 畑の草取りでは、はびこってしまった時は誰もが最も茂ったところから手を付けようとするが、金次郎の考えはまさに逆であったと言う。 「良く茂ったところを除草するには手間がかかり、日数をとられているうちに、あまり茂っていなかったところの草も伸びてしまうので、今度はそちらの草を取るのも大変になる。それよりは、繁茂したところは目をつぶって後回しにし、草の少ないところから除草していった方が効率が上がり、全体として作業がはかどるという、『観察』からくる合理的な考え方だった」 これはとくに除草に手を焼いている方々には大変良くわかる話ではないだろうか。 もう一つは農民としての面目が示されたもの。 金次郎が47歳になった天保4(1833)年は、初夏になっても気温が高くならず、稲の育ちも遅れ気味であったと言う。 「ある日金次郎は宇都宮(栃木県)の町へ出かけた途中に、ある農家で出された茄子を食べた。そして、『おやっ、今の時期の茄子にしては、種になるところが多く秋茄子の味がする。ということは、気温の上がる日が少なく、気候はすでに秋と同じなのだ。これは冷害の前ぶれだぞ』と、気づいたという。(略) 冷害にあえば、飢饉は避けることができない。二宮金次郎は急いで桜町へ帰り、『綿花の畑などを潰して、どの家も一反はすぐにヒエを植えつけよ。また、荒地や空き地、寺の境内など、耕せるところはすべて耕して、豆を蒔くのじゃ。そして、その収穫は必ず蓄えておくのだ。どの家にも一反分の年貢を免除するので、心配するな』 名主たちを集めて、こう伝えた。 『天明の大飢饉から五十年。もう、飢饉が来る頃なのだ。私はこの地方の皆を、飢えから救うために言っているのだ。一日のためらいは、3年、5年の悔いになるのだぞ。さあ、急ぐのだ』 金次郎は、昔の資料を調べて統計を取っていて、だいたい50年おきに大きな飢饉が来ることを知っていたのである。さらに、知識だけではなく、実際に、作物の育て方や、農作業をよく知っていたから、的確な判断と、正しい指導ができたのであろう」 客観的で鋭い観察眼を養うことの大切さ、そのことを肝に銘じたい。(雅) |