![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
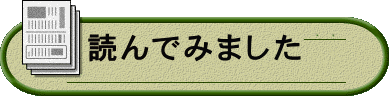
2020年7月~11月
 |
|
| 森川すいめい著『漂流老人ホームレス社会』 (朝日新聞出版 2015年) |
| 先日の毎日新聞に、『ホームレス 遠い10万円』と題して次のような記事が載った。
「新型コロナウイルス対策として国民に一律10万円を支給する『特別定額給付金』が、各自治体で申請期限を迎えつつある」が「多くのホームレスは受給できていない。二重支給を防ぐなどの理由から、住民登録が要件となっているためだ。『私たちは国民ではないのか』。当事者からは、諦めや怒りの声が上がる」と。そこで、「支援団体などは再三、総務省に支給を求め、8月4日には約100団体が共同して5000人分超の署名を提出した」が、総務省は受付期間の延長も検討していないし、住民登録を求める姿勢を貫いているそうだ。ホームレスの支援活動に取り組む上智大の下川雅嗣教授(経済学)は、「給付金が最も必要としている人に配られないのは、ある種の『切り捨て』だ」とし、10万円は路上で暮らす人にとって3~4カ月分の生活費にあたると言う。(毎日新聞2020年8月19日朝刊の記事より) 本書は、精神科医としての医療をはじめ、ホームレスの支援など多岐にわたる活動を行っている著者が、現今の日本の社会における深刻な問題の一つを鋭く描写する一冊である。1973年生まれで、プロフィールやこれまでの歩みについては、本書の終章をはじめネットにも記載されている。 ※:https://www.j-n.co.jp/kyouiku/link/michi/new_12/new_01.html:あの人に聞きたい「私の選んだ道」第12回 「本書の内容は、個人の実話に基づいていますが、実在する人物とは異なります」との断り書きがあって、著者のフィルターを通しての記述であると述べている。しかし、描かれた人々は今隣にいるかのようであり、いつどうなるかわからない話は本当に重い。またタイトルには「老人」とあるが、老人だけではない。ホームレスとなった背景にほぼ沿いながら、各章は次のように分けられている。 1章:死ななくてもよかった、2章:家族の形、3章:派遣切りの未に、4章:認知症者の行く先、5章:アルコール依存症、6章:知的障がい、7章:統合失調症、8章:希望、終章:私が野宿の人とともにいる理由。 ※「障がい」は本来「障碍」との表記が妥当と考えるが、本書に合わせて「障がい」とする(編集部) 著者は2012年、国によるホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)に委員として参加した。その結果、「問題の解決を国に期待していた気持ちは、このとき消えた。人が悪いのではない、構造が悪いのだとわかった」。そして、行政には行政にしか出来ない部分があって、それは今後も期待したいが、期待してはいけない部分は民間でやらなければならないと決めたと言う。 例えば、このようなことである。 日本国憲法は、国民は最低限度の生活をする権利を定めている。にもかかわらず、国の機能が止まる年末年始に、「ボランティアが集まって炊き出しをすると、一部の行政はその炊き出しの活動を公園から追い出す」のだ。その論理の一つに、「炊き出しがあるから“ホームレス”が来る」と言うのがある。「来るから困ると考えるのか、来るから助けられると考えるのか」、心のもちかたひとつで見える景色が違うのだ。 著者は言う。もし見える景色が違っていたなら、「答えはいつも、現場にある。現場から離れた場所で課題を設定し答えを出すことは、本当に危険だ」し、現場に行かなければ、「その間違えたことに気付くことさえできない」と。 膨大な事例とそれへの対応のうち、いくつかを取り上げて紹介していこう。 第1章は、勤続30年の会社が突然倒産し、年齢のため再就職もかなわず、兄を頼ったが鬱病になって結局そこにもいられず、野宿を重ねたあげく低体温症でようやく入院、その一週間目に亡くなったSさんの話だ。大量のアルコールが肝臓を痛めるのと同じように、過度のストレスによって脳という臓器が傷められた鬱病は、その深刻さや回復については周囲の状況が大きく影響する。このことを社会がどの程度理解し受け入れているかが問われているのだ。「自死率が最も少ない地域は、鬱病の受診率が高い」という研究もある。隠さなくても良いからである。 第2章は家族との問題によるケース。 見た目は70歳代か80歳代(実は50歳代だった)の女性Kさん。かつてスナックを開いていたが、不況で店をたたみ、脳梗塞の後遺症の夫と娘夫婦と一緒に住むようになった。するとすぐに娘の夫が金の無心を始め、貯金をすべて渡した途端に暴力が始まった。当初は娘も殴られていたが、そのうち娘も彼女を攻撃し始めた。Kさんは、「私が悪いんです。ごめんなさい」を繰り返していたが、ついにある日、夫が「このままじゃおまえが死んでしまう。これで逃げろ」と1000円札一枚を渡した。1000札は2人分一日の食費だった。 「ちゃんと説明すれば家族なのだからわかるはず、公的な目も入ったから暴力は無くなるはず」と思った職員が自宅に連絡したため、娘夫婦がすぐに役所に乗り込んできた。 「暴力などない、連れ帰る」と娘の夫は怒りをあらわにし、Kさんに向かっては、「無駄な金を使わせやがって、医療費をどうすんだ」と激しい剣幕でまくし立てた。身体が大きく声は太くて恐ろしい。「このまま帰れば激しい暴力が待っていることが容易に想像され、Kさんはじっと一点を見つめて震えていた」。 その時、福祉に精通するベテランの雅俊さんという方がこの件を見事に収めた。 雅俊さんが、「母親の面倒を見るのは大変でしょう。あなた方が『Kさんの生活の支援をしない』と言えば、母親は生活保護を受給し、面倒は行政が見ていくことになる。医療費も掛からないがどうか。もし、それでいいなら、あとは私が責任を持って行政と話を付ける。任せてほしい」と伝えると、娘夫婦は、「それならばいい」と言って、そのまま逃げるように姿を消した。娘夫婦は、「こいつの言うことを聞いておけば、親とも縁を切れるし、自分たちの金銭的な負担もない。損はない、うまい話だ」と頭の中で素早く計算したようだ、とはのちの推測である。 著者には「刑事事件にしてでも」という憤りもあったが、「あの当時は、家庭内の問題だからと、事件になる可能性は少ないと誰もがわかっていた。雅俊さんは理想よりも実を、淡々と取った」のだ。そして「『若い君たちの情熱は大事だ。それはずっと持っていてほしい。あなたたちができない部分は私がやるよ。忘れないでほしいのは、その情熱と、大事なことは実際に人が助かることだ』」と、いつも教えてくれていたそうである。 経営した会社が倒産し、借金取りから逃げるように家族を捨てた72歳のTさんは、息子が会社の社長のため生活保護は受けられないと言う。息子は、「生活保護など恥ずかしい。おまえには受けさせない」と口にし、生活は自分でやれと家にも入れてくれず、電話も掛けてくるなと言ったそうだ。 血圧が180/110と高く、倒産してからは降圧剤を飲むこともなく、治療も断った。Tさんはそれからまもなく倒れ、救急車で運ばれた時にはすでに心臓が止まっていたと、周囲の人が語っている。 第3章は、派遣先を解雇され、車いすの母親の介護をしながらの住み込みでは仕事も見つからず、ホームレス生活を続けるTさん親子。生活保護法には、申請を受ければ無条件に受理して審査を開始しなければならない原則がある。今はずいぶん改善されたと言うが、かつては、そもそも申請をしないように説得する「水際作戦」とも比喩される方法が取られていたと言う。 それまで必死で努力してきたにもかかわらず、「まだ働ける若さだろう」とか、「働けるのに働かない気持ちがある」と捉えられ、努力不足や自己責任に着せられるうえに、相談窓口では、自分たちが如何に無力であるかを証明しなければならない。「もう傷つけられたくない」と思うのが当然の心理だろう。 第4章は会話がスムーズには進まない認知症の人の例。 野宿状態の人の中には、禁煙場所でタバコを吸ったり、酒を飲んで宴会を開いている人たちがいる。治安を守る地域の警察官が目を向け声掛けするのはそのような人たちだ。話しかけられた側もそれに対する態度をとる。 一方、著者たちのような立場では弱っている人に視線が偏る。中には、助けがほしくて大げさに苦しさを訴える人や、知られたら不利益になる事実を隠す人もいる。ある福祉事務所の職員が、「また、あなたたちはだまされたのです」とか、「あなたたちの善意を利用する人たちがいるのです」と言ったことも印象に残ったそうである。 本章のケースでは、著者は先ず、「私は医学生です。脈拍が触れません。血圧が下がっていると考えられます。救急車を呼ぶべきだと思います」と話し掛ける。これは、認知症ばかりではなく、命の現場においては弱っている人に意思の確認をしてはいけない場合もあるということだ。なぜなら、「意思を持つためのエネルギーが弱っていて、たいていのことはNOと言ってしまう。拒否した方が相手との関わりが減って楽」なのだから。 さらに認知症の場合には、医師や施設によってケアの質に違いがある。上手な施設では精神薬は極力使わないので易怒性など副作用の心配も少ない。「ある医師は、『こんなものは本人のせいだ』と言って何年も大量の薬を飲ませ、説教までしていたが、薬を減らしたら、もとの穏やかな本人に戻った」そうである。 第5章はアルコール依存症。依存症になる薬物のうち酒は最も身近なものだ。薬物は一度脳が侵される二度と完治しないと言う。コントロールが出来なくなり、耐性がついて量が増え、切れると身体離脱症状が起こる。苦しさを紛らわせるために飲むことを止められず、ますます苦しくなる。 ここに記されているのは、もともと不安障害から酒に頼り、ついには仕事を失い癌になって余命幾ばくもなくなったIさんの場合だ。酒、無断離脱、暴力的な態度、パニック発作、ホームレス状態、痩せ衰え、ほとんど寝たきりというありさまだった。 もてあましていた病院から怯えた様子でホスピスに着いたIさんは、玄関で迎えたスタッフ数名に、「よく、いらっしゃいましたね」と言葉を掛けられると突然涙し、「こんな自分のために」と思ったと言う。「無価値な自分だと思っていたところを、何人ものスタッフがやさしく迎えてくれたことに、Iさんは、ふと力が抜けたようだった」。その後Iさんは食欲を回復し、薬が増えたわけでもないのになぜか痛みもほとんど無くなっていった。 アルコール依存症には薬や手術となどの治療法はない。唯一の方法は断酒を続けることのみだ。説教や強制入院ではなく、「環境と人が変わったことで、食事をたくさん食べて元気になったIさんは、酒の話をすることなく、穏やかに、数か月後に亡くなった」そうである。 第6章、Tさんは皮膚にある多数の先天性の腫瘍に対する偏見のために仕事も得られず、10代の頃から野宿生活になり、会話からも知的障がいを合併していることも覗えた。 かつては同行者が福祉事務所の相談室には同席が許されなかったため、相談者がボックスから数分程度で出てくることも少なくなく、たいていは、「生活保護は受けないということですね」と言われてお終いだったと言う。時には、「生活保護は受けません」と書かされてもいた。明らかに誘導されたにもかかわらず、福祉事務所側は本人の意思だと主張する。しかしそれでも、著者は職員に悪気があるのではなく、そういう仕組みになっていることが問題だと本書で何度も述べている。 Tさんの担当職員は特にやさしい人だったそうだ。Tさんが入院してすぐに病院に見舞いに行って、「退院したら、○○区の福祉事務所に来てくださいね」と伝えていたし、場所はわかるかと聞くと、わかるとTさんは答えたと言う。それなのにTさんは来なかった。そのことが心に引っかかっていて、「あの後どうしてここに来なかったのですか?」と訊いた。そこで、「覚えていないみたいなんですよね」と著者が言うと、いつも人をどう助けるのかを考えている担当者は一瞬でわかったようだった。 著者から見ると、Tさんが知的障がいを持つことは明らかだった。「記憶のしかた、場面の認識のしかた、声のトーン、過去の生きてきた歴史、身体の症状などからである。加えて、日付の記憶がずれていた。平成何年か?という質問には、昭和54年と答え・・・認知症を合併していることが予測された」。そして、「もしもここで、覚えていないという事実が確認されていなかったとしたら、Tさんは再びどこかに入ってどこかへ失踪したに違いなかった」と。 第7章は統合失調症の人々。見えない誰かと会話していたり、陰謀に巻き込まれて逃げていたり、ひたすら何かの儀式を続けていたりと、何か別の世界を感じながら生きている。 50歳のHさん。「いやよお、この街は俺のものなんだ」「おお。あのビルも。そのビルも。○×不動産」「ああ、おお。モデルをやっている」「おお。東大の・・・学長だったから」・・・。 会話。「『身体の具合が悪そうですけど?』『うう、おお、おお、うう、ううん、大丈夫』『足、引きずっていますけど、けがでも?』『ああ、ああ、これ、ううん、うん、うん』『病院とか、一緒に行きましょうか?』『・・・・・。いや、いい、いい。地主だから』『足は?』『あ、もう大丈夫。けっこう、けっこう。ごくろう、ごくろう』」。 「幻覚」や「妄想」のために、時として現実との区別が曖昧になる。誰にでも起こりえる病気の一つとされるが、抗精神病薬の服用で幻覚や妄想は落ち着いていくと言う。 こうした人たちとどうコミュニケーションをとればよいのか。筆者は、統合失調症だからと言って特別な方法ではなく、原則は不変なのでそれを守ればよいと言う。つまり、「コミュニケーションの原則は、聴き手の、相手を理解しょうとする行動によって成立する」のだから、自分をコントロールして先ずは自分を聴き手にするしかなく、その上で、相手に聴き手になってもらえるようにこちらの話し方や内容を考えるしかない、と言うことである。 Hさんは池袋の街の大地主としてこの土地で生きているし、また70歳女性のIさんは、「○○会」から脱会したために命を狙われ、テレビその他で監視されているように感じている。それがその人たちの現実であり世界なのだ。 そこでどうするか。それは、本人が解釈しているのとは違うものがある、その事実を具体的に明確に説明して、現実の整理を手伝うことだと言う。Hさんの場合、幻覚妄想状態のままではあるものの、必要なだけの現状の事実の理解(例えば検査を受ける必要性、たばこは病院なので吸わない規則など)のうえで入院となり、生き延びることが出来た。 これがなぜ出来たのか。それは「自分の人生の主人公は自分である」という視点を著者たちが大切にし、自身で選択したいという意思を満たすための手伝いに徹しているからだ。「どこで生きて何をして過ごしたいかは本人が決める。それができるかどうかを周囲は裁断しない」と言うことなのだ。 この考え方は統合失調症を持った人たちへのことだけではない。著者を含むグループが常に最も大切にしたいと考えている理念だと言う。著者がそれに至ったのは、社会福祉法人「浦河べてるの家」が、池袋に来てくれ、「べてぶくろ」を立ち上げてからだと言う。 「『べてぶくろ』の活動は、援助がないと生活できないのではないのかという援助側の思い込みをやめよと教えてくれた。なぜ周囲の人が、本人がどのように生きたいのかを裁断してしまうのか?と問いただされたのである。私の中の思い込みは、『べてぶくろ』によって断たれた。『べてぶくろ』の実践は、野宿の現場を見て絶望のふちにいた私の心に希望を宿してくれた」。 第8章ではまず全員がボランティアのNPO法人TENOHASI(てのはし)の経緯が語られる。 TENOHASIはThe Earth and Neighbor Of Happy space Ikebukuro(地球と隣のはっぴい空間池袋)の略。ボランティアには、路上生活を経験した人、会社員、専業主婦、年金生活者、大学生、子ども、障がいを持つ人、そういったいろいろな人々が参加し、またお互いに楽しく出会う場にもなっていて、「生きやすい国に!」を目指している。他区の職員から、池袋に行って相談するようにと促された人も来るそうだ。 本人も周囲もどうにもならないと思っていたことでも、TENOHASIと出会って、ともかくなんとかなる方法があったことが証されたと著者は言う。それは特別な技や知識で奇跡を起こしているのではなく、「誰にでもできることを実践しているだけだった」と。 相談してもどうにもならないと思えば、誰も相談には行かないだろう。ならば、支援を「届ける」しかない。「相談室」や「相談員」だけでは、本当に出会わなければならない人とはなかなか出会えないからだ。 「生活保護を申請するかと言われれば、『しない』と言う人は少なくない。・・・申し訳ないと思っているのである。それが病的になることがある。それが鬱病である」。ホームレスになった人の多くは、楽をしたいわけではなく、迷惑をかけたくないという気持ちがあると同時に、申請や集団生活などで、「もう傷つけられたくない」のである。 「自分の人生は自分で選んでいいのだという、当たり前のことを確認」し、もしそれが叶わない理由が強い落ち込みや酒であるなら、「その次の課題として一緒に考え」る。そして「私たち支援者は、本人が主人公である本人の物語の中では、主人公を支える脇役であるのだ。ボランティアスタッフだけがそうだということであってはいけない。この後出会うであろう、福祉事務所職員も、クリニックのスタッフも、地域の支援者も、本人の人生の主人公性を奪ってはいけない」のだ。 例えば、本人が住みたいところを言っても、それが出来るかどうかを周囲が勝手に判断し、施設だったり入院だったりを決めることがある。「その希望は無理だから、まずは更生施設へ」とか、「グループホームからやっていきましょう」と説得するのだ。「本人がどこに住みたいかについて、周囲は、本人の能力をジャッジ(裁断)」することは越権行為と言うべきだろう。 良い環境の施設もあるが、一部屋をベニヤ板のような薄い壁で仕切って3畳程度の広さにし、それを個室と言い張るひどいところもたくさんある。これでは集団生活を強いられているのと何ら変わりがないばかりではなく、そうした施設に入ると手元に入るお金はほとんどなくなる。「施設に食事代と称して奪われる。門限も決まっている。時間も金もプライバシーも奪われたまま管理されているのだ。しかも、それが本人のためだと確信されてしまう」。だから失踪する人が絶えないのだ。 私たちが知っていなければならないのは、今は自分は周囲の人だったとしても、「将来は、周囲によって自分の生きたい方法が制御されて施設に隔離されるかも知れない」と言うことだ。 終章では著者のこれまでの歩みを詳細に語る。そして、著者のフィルターを通しての記述であるから、「私が見た現場は現実ではあるが、事実ではないかもしれない。人を欺くために書くのではない。私が真実だと思っていることを記してはいるけれども、その中身は読む人それぞれが解釈してほしい」と述べている。 そして、総括的に次のように言う。 「『平等だということが、差別になることもある』と言った人もいた。『平等でなくてはならないのだ』、という言葉には、マジョリティにいる側の人間による、無言の圧力が含まれている。・・・マジョリティでないことは努力不足が原因なのだと感じさせられる。 ・・・平等を否定しているのではない。『みんな同じ(平等)であるべきだ』という考えを否定しているのだ。平等の名のもとに、不当に排斥されることに抗うのである。 ホームレスとは、単に家(ハウス)がない状態をいうのではない。安心して生きていく場(ホーム)がない状態をいう。みんなが平等であることを前提とする社会は、人間を、ホームレス状態に押しやる。本書には、その記録を記した」と。 「経済競争力の糧にならない人間は、ホームレスか精神科病院か刑務所に、社会は押しやっていないか。家族だけに責任を押しつけていないか。どこかの施設に入れることで安心していないか。人がなぜ生きるのかを、考える時間を失っていないか。私は単に、ただ、社会が生きやすくなったらいいと思う」。 本書はまさに、今の日本社会が隠そうとしながら抱えている問題提起の書であった。(雅) |
| 小笠原文雄著『なんとめでたいご臨終』(小学館2017年) |
| 日本在宅ホスピス協会の会長でもある著者は、1989年に内科を開院して以来1000人を超えて、なかでもひとり暮らしでは50人以上の在宅による看取りをしてきた。特にがんの場合には在宅での看取りが95%以上にのぼる。本書のカバー内側にはこうある。
「『最期まで家で暮らしたいけど・・・』 お金がない?家族に迷惑がかかる?一人暮らし? 大丈夫ですよ。安心してください。誰しも、たった一度しか死ねません。どうせなら『めでたいご臨終』してみませんか」 本書は6章で構成され、著者が関わったケースとその考えが示される。なかでも、第5章における事例は人ごととは言えない。 第1章:家なら最期まで好きなことをして過ごせる 第2章:余命宣告をくつがえす患者さんたち 第3章:一人暮らしでも、お金がなくても大丈夫 第4章:看取った直後に、家族がピース 第5章:在宅医療に失敗ってないの? 第6章:いのちの輝き いずれも背景として「在宅ホスピス緩和ケア」があり、著者それを次のように説明する。 「在宅ホスピス緩和ケアの『在宅』とは、暮らしている“処(ところ)”。『ホスピス』とは、いのちを見つめ、生き方や死に方、看取りのあり方を考えること。『緩和』とは、痛みや苦しみを和らげること。『ケア』とは、人と人とが関わり、暖かいものが生まれ、生きる希望が湧いて、力が漲ることです」 人として最期まで暮らしの中に生きている“処(ところ)”でのこうした対応によって、「生活の質」を意味するQOL(Quality of life)とともに、ADL「日常生活動作」(Activities of daily living、食事や排泄、歩行や入浴などの生活の基本的動作のこと:編集部)を向上させようとする。そしてそれが、QOD(Quality of death)「死に方の質」を左右して、著者の言う「希望死・満足死・納得死」に繋がり、「安らか・大らか・朗らか・清らか」と4つの“らか”を実現する。それが出来たなら、たとえ離別の悲しみはあっても、「遺されたご家族も同じように清らかな気持ちで送り出せることを教えてくれ」、その結果、「なんとめでたいご臨終」となるし、またそうであれば、かりに誰もそばにいない時に亡くなった場合でも、それは決して孤独死ではないのだと言う。 だれもがいずれは直面する可能性のあるこの重い課題について、著者の考え、主張をたどってみよう。 まず第1章、一級建築士の遠藤さん(男性62歳)の場合。仕事も出来なくなり副作用もあるという抗がん剤治療を断った。「がんが治るなら抗がん剤を使います。でも、たった1か月しか延命できないなら、仕事がしたい」と小笠原内科の緩和ケア外来に通院し、痛みを取って心のケアを受けつつ自宅で仕事に専念した。その傍ら、家族と過ごす時間もとても大切にし、以前から行きたかったお寺参りに夫婦で行ったり、離れて暮らす子どもたちが集まって孫と遊ぶ時間も増えたと言う。そして宣告された3か月という余命もいつの間にか過ぎ、さらに2か月後には体力が落ちて通院することが出来なくなったので在宅ホスピス緩和ケアに切り替えた。 亡くなる8日前、訪問診療に行くと遠藤さんは嬉しそうに、「先生、私が設計した家のお客さまからりんごを頂いたんだよ。妻の作るりんごジュースはとっても美味しいから、先生たちも一緒に飲もうよ」とりんごゴジュースを出してくれ、そしてりんごジユースを片手に嬉しそうな遠藤さんと、みんなで「笑顔でピース」の記念撮影をしたそうである。そして、「死ぬのは怖くないですよ。怖いのは不安があるからでしょ。不安はありません、幸せですよ。充実しているから。上手な死に方っていうのはおかしいけれど、上手な生き方っていうのかな。がんは案外、いいもんですね」と言った遠藤さんは、1か月しか延命できない抗がん剤治療ではなく、仕事を選んだ7か月間を笑顔で過ごしたのち、家族に見守られながら穏やかに旅立っていった。 抗がん剤はどのような時に必要なのか?必要でない場合とは?抗がん剤を止めるのはどういう時なのか? 多くの人はがんが見つかった時点で治療を開始する。早期発見が出来て手術で取り除ければそれが最善であろうが、手術ではどうにもできない状況になった時にはどうなのか。著者は、「抗がん剤をつかって治る見込みのある患者さんには抗がん剤は必要」としながらも、あまり効果がないと見込まれるのに抗がん剤を使うのは、むしろ苦しみにつながるのではないかと問いかける。 「手の施しようがない末期がんの人が、それでも闘い続けることが果たして幸せなのか」「勝てない相手に挑んで最期まで苦しむのなら、早いうちに気持ちを切り替えて、残りの人生を笑顔で長生きできるように在宅ホスピス緩和ケアを選択するのも一つだと思います」と。 次は伊東さん(女性70歳)のケース。 本当は入院したくない。でも最期は家族に迷惑をかけないようにと緩和ケア病棟へ入院の予約に行った。その時彼女はその病棟の先生から、「ここへ入院する時は人工肛門を作ってから来てくださいね」と言われたそうである。しかし、小笠原内科での検査では人工肛門を作っても意味がないという診断が出、その日の夜ご家族に小笠原内科へ来てもらったと言う。 説明を聞いた家族は、「先生のおっしゃることはわかるけれど、入院したほうがいいのでは・・・」と半信半疑だった。 そこで著者は、今は伊東さんの人生を左右する大事な局面だと感じ、「『入院したらお母さんの笑顔が消えてしまうんですよ。お母さんは今、とても嬉しそうでしょう。ご飯が食べられなくても、家にいるだけで幸せなんです。モルヒネの持続皮下注射やサンドスタチンという腸閉塞の特効薬を使えば、痛みも出ないし、何も心配いりませんよ』と、2時間ほどかけて説得」したと言う。 その結果、家族も“母を入院させてはいけない”という気持ちになり、翌日往診に行くと、「伊東さんの表情が今まで見たことがないほどの満面の笑みに変わって」いた。 著者はこれを次のように推測する。 「・・・私はこう思います。伊東さんは退院し、自宅で暮らすことができました。でも心のどこかで、“腸閉塞になったら入院しなくてはいけない”とか“人工肛門を作ったら緩和ケア病棟に入ろう”“家族が望むなら入院しよう”と思っていたのです。家で暮らせる幸せを感じる一方で、いつかその幸せを失うのではないかという不安を抱き、心はいつも定まっていなかったのでしょう。 しかし、“私が家で最期まで暮らすことに家族が賛成してくれた”という安心感と幸福感が、伊東さんを満面の笑みに変えたのです」と。そして、「『ところ定まれば、こころ定まる』とは、まさにこのことなんですね」と言い、「この言葉をぜひ覚えておいてもらいたいと思います」と言うのだ。 痛みとそれへの不安を解消するためにはPCA (Patient Controlled Analgesia:自己調節鎮痛法)という「魔法のお弁当箱」が使われる。これは、24時間投薬し続けることができる弁当箱サイズの医療機器で、痛みがある時にボタンを押すとモルヒネが1回分投与されて痛みが取れ、約4時間効果が持続するという。痛みが出たら何回でも本人の意思でボタンを押せることで、我慢する必要がなく、安心感が得られると同時に痛みを感じにくくさせる好循環が生み出される。 しかも、「PCAは、ボタンを一度押すと、その後15分間はどれだけ押しても投薬されないように設定できます。仮に必要以上に押してしまった場合でも、眠気が出たり、数時間眠るだけのことで、死ぬわけでは」なく、伊東さんは、「ありがとう。PCAは命綱。これさえあれば私は最期まで家で過ごせる」と何時も言っていたそうである。 第2章、大野さん(女性72歳)は退院したら5日の命と言われていた。そこで小笠原内科のスタッフが主治医をなんとか説得して退院した後、4年10か月後の小笠原内科のクリスマス会に参加、あまりにイキイキしていたので腫瘍マーカーの値を測ってみたところ正常に戻っていたと言う。 病院には患者を助けるという責任感、使命感があり、たとえいつ亡くなってもおかしくないような患者本人が退院の希望を持っていても、もし病院にいた方が長生き出来るという判断があると退院させにくいそうだ。 悪性リンパ腫で主治医から、「抗がん剤ももう限界まで使ってしまったから、もうこれ以上治療することも出来ないし、状態も落ち着いているから、今なら退院できるよ」と言われた平井さん(男性88歳)は、10年目を笑顔で暮らしている。 「いつ死ぬかわからない」と言われた鈴木さん(男性68歳)は1年もの間自宅で穏やかに過ごしたし、余命8か月と宣告されたためにがん患者の会にも「末期は入会できない」と言われた花田さん(女性64歳)は、1年以上延命して遺影を2回撮り直したという。 このように、在宅医療を選択したことにより、余命宣告を大きく超え、しかもQOLやADLを満足させつつ生を全うしたケースが多く見られるのは、「人は、ひとりでは生きていけません。最期の時もひとりではないのです。必ず誰かと関わり、お世話になったり、協力し合ったり、そういったコミュニティの中で生きています」とする著者の言葉からもよく理解できる。 たしかに、病院における医療に携わる人々の存在は安心感をもたらす。しかしその反面、患者一人ひとりにはなかなか手が回らないほど忙しいのも現実ではないだろうか。それゆえかえって孤独感を生んでそれが免疫力の低下に繋がる、そんな可能性も全くないとは言えないのではないかと思う。 1~2か月と言われた安藤さん(女性87歳)が在宅に切り換えて1年半以上経ったとき、痛み止めの薬を飲み忘れたために痛みが出たそうである。そのため、「痛い、痛い」との訴えを聞いた息子に入院を勧められて再入院したところ、1か月後に亡くなったと言う。これは「病院のほうが孤独死なのかもしれないという現実」を教えてくれたのではないかと著者は言う。 第3章では、2000年に出来た介護保険制度のおかげで、ひとり暮らしでも最期まで自宅にいられるという事例を紹介している。もちろん、病状や住居環境などの条件、また本人の望みの内容によって在宅医療にかかる金額は変わってくるが、示されている自己負担額の一覧表(本書p.116:以下同じ)によれば決して高くはない。 そのほか、訪問看護費が無料になること(p.135)や、夜間はしっかり眠って朝が来ると目覚めるという人間らしく生きるための「夜間セデーション」(p.136)、また目の不自由な河合さん(女性80歳)のケースでは、指で触れると24時間対応の介護事務所につながる「タッチパネル式テレビ電話」を導入したという。この利用料は1か月1610円、緊急出動をしてもらうと1回580円(2006年当時の金額)だそうである(p.145)。 また、THPという医療・看護・介護などの多職種が関わる際に適宜対応する実力を持ったキーパーソンと、そのために開発された情報共有アプリとしての「THP+」を使った体制によって、連携ミスが起きないようにしている(p.146)。 (THPはToral Health Planners:トータル・ヘルス・プランナーの略。医療・看護・介護などの多職種が関わる際に適宜対応する実力を持ったキーパーソン。THP+はそのために開発された情報共有アプリ。教育的在宅緩和ケアとは知っていることは教え、知らないことは教えてもらう医師の連携:編集部) 第4章は、末期がん患者にとっての1日がどれほどの重みを持つか、高木さん(女性86歳)の例。 金曜日に家族が、「先生、末期がんの姑が『家に帰りたい』と言うので、月曜日に退院させることにしました。急に悪くなって、いつ死ぬかわかりません。退院したら往診に来てもらえませんか?」と頼んできた。 「もちろん往診はするけど、急に悪くなって今にも死にそうなのに、月曜日の退院でいいの? 3日後、生きてるの? もしも亡くなったら、病院の裏玄関から出て行くっていうことだよね。そうなったら、あなたたちは後悔しない? 退院させてあげたいなら、今日の午後にでも緊急退院できるんだよ」と著者。 「えっ!? 今日、退院できるんですか? あ、でもまだ家の掃除が・・・」 「掃除なんて、ささっとすればいいし、しなくてもいいんだから」 そんなやり取りの末に、高木さんは4時間後に表玄関から緊急退院。そののち家での治療の結果、痛みが取れ、表情はどんどん穏やかになっていった。翌日の土曜日の訪問診療では高木さんは嬉しそうにして、「よく寝られたよ。嬉しいわ」と言ったそうだ。 「ありがとうございます。おばあちゃんも笑顔だったし、よかった」と家族。心の準備と覚悟ができて最期の時間を過ごしたが、日曜日には意識がなくなり、往診したところすぐにも亡くなりそうであった。 「月曜日まで入院していたら、家に帰れなかったかもしれないよ。緊急退院させてよかったね」 ところが火曜日。 「『あれ、どうしたのかなぁ。もう全員集まったんだよね』と私が聞くと、息子さんが周りを見回して言います。 『あっ、そういえば、東京のひ孫がまだ来てない』 『じゃあ、きっとひ孫を待っているんだね』」 東京から水曜日に曾孫が到着したあと、高木さんは穏やかに旅立った。そして高木さんを囲んで治療スタッフも一緒に家族みんなで笑顔でピース。このような写真は本書には何枚も掲載されている。 「その時」を見計らったようなこのような旅立ちは、まさに著者の言う「めでたいご臨終」なのだ。人の死はやり直しがきかない。もし笑顔での旅立ち看取りを望まれるなら、患者本人に合った診療所や在宅ケアの医師を選ぶことが大事だと著者は語る。 第5章では失敗した例。 残念ながら医師のスキルにも差があり、また最初から高いわけでもない。在宅医療を始めて28年になる著者自身、初めの頃には後悔することもあった。そこで、患者の願いと医師選びの参考にしてもらい、さらに在宅ホスピス緩和ケアのスキルを身につけることの大切さを後輩の医師に伝えようと、著者自身の例を挙げる。 家族に「絶対に本人に言わないで!」と懇願され、副鼻腔がんで最期まで苦しい思いを者ながら亡くなった西さん(男性59歳)には、家族への説得と告知後のフォローが出来るスキルを磨くことの重要さを教えられた。 また、廣瀬さん(女性85歳)は最期まで家にいたいという願いが家族の反対で叶わなかった。「いいところがあるから見に行こう」と、「こんなところ(グループホーム)に置き去りにされた」と悲痛な声で訴えた廣瀬さんは、おそらく、そのためにタコツボ症候群となってしまって無念の最期になってしまったのではないか。(※個別の事例であって、グループホーム自体が悪いというわけではない:著者) また、ご主人が入院することになった古川さん(女性72歳)本人は、車椅子を使いながらもヘルパーに頼んで買い出しも料理も出来ていた。しかし、離れて暮らしていた息子は心配して、「ひとり暮らしなんてダメだ。父が入院している間、母にも入院してもらう」と言う。著者は、「ひとり暮らしでも大丈夫ですよ。お母さんは足が悪いだけだし、何も心配いりませんよ。お母さんが『家がいい』と言っているのだから、家にいさせてあげたらいかがですか?」と説得した。 その時は「わかりました」と言ったので、納得してもらえたと思ったが、なんとその夜、息子は何の連絡もせずに入院させてしまった。おそらく息子は、「小笠原先生の話はわかったけど、自分の意見とは違う。入院させたほうがいい」と思ったのだろうと著者は推測している。 古川さんは入院して2日後に亡くなった。おそらくタコツボ症候群であった。 「患者さんとご家族の意見が対立した時、ご家族に対し、患者さんの想いはしっかりと伝えますが、いくら主治医でも『家にいさせるように』と強制はできません。 しかし、14年間も古川さんの主治医をしていた私は、その性格をわかっていました。あの時、息子さんに納得してもらえるスキルがあれば・・・と後悔するのと同時に、私以上に母親の性格を知っていた息子さんだからこそ、気の弱い母親のひとり暮らしを心配したのかもしれないと、胸が張り裂けるような思いがしました」 そしてその後は、患者だけでなく、ご家族も後悔しないように、説明する時には患者さんの性格を踏まえ、過去の事例もお話ししながら1時間でも2時間でも粘り強く説得するようになったと言う。そして、 「この事例は、子どもが考える最善の選択が、必ずしも親にとって最善ではないこと、それを大切な人の死をもって気づくのでは遅いということを教えてくれました。これは親子だけに限った話ではないと思います。なぜなら、死が迫っていない人には、死ぬ人の気持ちがわからない。自分がもうすぐ死ぬと思っている人は、残りの人生が決まると覚悟した上で一つひとつの選択をしている。家族は、患者がそれだけの重みを感じながら選択しているということを知るべきだろう」と言う。 医療従事者は患者のために最善と思う医療・ケアを選択する。それは在宅ケアでも同じだが、松尾さん(女性80歳)の場合は優しさが裏目に出てしまった事例だ。 ALSでは、最終的に呼吸が出来なくなった時には、自然の流れに任せて死を受け入れるか、人工呼吸器をつけて延命するか、選択を迫られることになる。彼女は前者の選択をしていたが、旅立ちの時が近づいてきたその時、駆けつけた息子さんが救急車を呼んでしまったそうである。そのため彼女は1年間も人工呼吸器を付けたまま病院で亡くなった。 人工呼吸器をつけている患者の多くは、苦しさのあまり呼吸器を外そうとする。そのため多くの病院では、筆談の時以外は苦肉の策として患者さんの手を縛ることがある。著者が救急搬送の報告を受けて病院へ行くと、彼女は文字盤を使いながら、「は・ず・し・て」と涙ながらに訴えるだけだったと言う。 このことから著者は、「何かあったら救急車を呼ぶ」という発想が日本の常識になっていることを痛感したという。 また、退院時に医師や看護師は、「何かあったら、すぐ病院に来てね」と言うが、それは患者さんを安心させるために言っている場合も多く、「本当に入院が必要な時だけ来てね」というのが真意であって、安易に救急車を呼んでしまうと苦しい延命治療をされたり、最期まで家にいたいという願いが叶わなくなったりと、地獄の苦しみを味わいかねないという。 助かる人はもちろん助けるべきである。しかし、末期がん、老衰、認知症で自分の意思を表明出来ないなど、たとえ助からないとわかっていても最期まで苦しい延命治療をされてしまうことが多い。こういう悲劇に遭わないためには、ACP(Advance Care Planning:アドバンス・ケア・プランニング)といって、患者や家族がTHPや医師、訪問看護師、ケアマネージャーなどを交えて、「延命治療をするかしないか」「救急車を呼ぶか呼ばないか」など、予め決めておくことが必要となる。もし意思決定能力がなくなっても、自分の想いを語ったり書き残していれば、それは尊重されるべきなのだ。さらに、 「日本の救急車が無料であるがゆえに起こる悲劇もお伝えします。近年、軽傷でも救急車を呼んでしまう人が急増し、本当に緊急を要する人が利用できなくなるという事態が起きています。その結果、助かるはずの人が助からなかったり、状態がひどくなったりするのです。救急車をタクシー代わりに使うなどもってのほかです。本当に必要な人が必要な時にだけ利用することで、こういったことが起こらないように願っています」 (毎日新聞2020年1月11日朝刊によると、2019年1~11月に全国の警察が対応した110番通報は829万9775件で、うち18.4%が緊急性のない内容だったという。前年同期の19.2%と比べ、やや改善したが、「免許更新の方法を教えて」「子どもが言うことを聞かないので警察官が叱って」「「家の中にゴキブリがいる」など相談や警察対応が不要な内容もあった:編集部) 第6章では、教育的在宅緩和ケアという、小笠原内科のスタッフと遠距離のサポート医師とで行われる遠距離の在宅緩和ケアを紹介している。この章には、35歳2児の母が見せた最期まで生き抜く姿のほか、朗らかに生きて笑顔で旅立っていった亡くなった方々、そして遺族に生まれた温かな想いが描かれている。 見送る側にとっても見送られる側にとっても実感できるような「希望死・満足死・納得死」のための小笠原内科が考案したシステムは次の5本柱である。 ① THPケアシステム・・・多職種が連携できるような体制 ② THP+・・・患者に関わるすべての人が情報共有できるアプリ ③ 連隔診療・・・いつでもどこでも診察できるテレビ電話 ④ 退院調整・・・退院希望の患者に合う在宅医を探し、退院させること ⑤ 教育的在宅緩和ケア・・・医師同士が教え合うこと 小笠原内科は、100km離れたケースも含め、岐阜県を中心に88例の教育的在宅緩和ケアを行なってきた。在宅ホスピス緩和ケアのできる医師が増えることは、それだけ多くの地域で多くの人が笑顔になれるということだ。「笑う門には福来たる、そんな在宅ホスピス緩和ケアが望まれ」ている。 「あとがき」での著者の言葉。 「“最期までここで暮らしたい”という願いが叶い、自然の摂理の中で『希望死・満足死・納得死』ができた時、ご遺族は離別の悲しみで涙を浮かべながらも、笑顔でお別れをします。そんな場面に立ち会うと、『おやおや、みんなピースしているねぇ。じやあ私も笑顔で旅立とうか』という亡くなった方の声が聞こえるような気がします。 『ご愁傷さま』ではなく『笑顔でピース』。今の日本の常識では考えられないかもしれませんが、『笑顔で死ねる、笑顔で看取れる』としたら、なんとめでたいご臨終でしょう」 最後に、本文では書ききれなかった本書に掲載の情報、データを紹介したい。 ・お別れの日に向けて ~安らかな看取りのために~ のパンフ・・・p.28~29 ・モルヒネの使い方で知るべきこと・・・p.80 ・あくび体操・・・p.108 ・園部さん(男性79歳)の場合の自己負担額(2ケース)の比較・・・p.116 ・上村さん(女性82歳)の場合の自己負担額・・・p.153 ・抗がん剤を使うかどうかを見極めるコツ・・・p.194~195 ・旅立ちの日が近づいたサイン・・・p.196 ・教育的在宅緩和ケアなら遠距離でも大丈夫の組織図・・・p.251 ・著者が徳島県から送ったTHP+・・・p.275 ・森さん(男性76歳)が旅立たれた直後に家族が書いたTHP+・・・p.276 ・鎌倉にいた著者がテレビ電話で350km離れた柏原さん(女性91歳)の遠隔診療・・・p.293 ・THPケアシステムで患者を支える(連携・共同・協調+介入)の組織図・・・p.311 機会があればぜひ一読されたらと思う。 |