![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
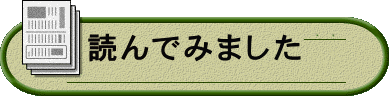
2020年1月~6月
|
| 福岡正信著『自然農法 わら一本の革命』(春秋社 1983年) |
|
「有機農業」という言葉が注目を浴び始めて久しい。しかし、日本における有機農業の普及率はいまだ0.3~0.4%と言われており、1%にも満たない。農薬も化学肥料も、使わないに越したことはないと誰もがわかっていながら、なぜやめられないのか。半世紀近く前に書かれた本書が問題の核心をついている(本書の初版は柏樹社 1975年)。 |
| 菅野美代子著『超孤独死社会』(毎日新聞出版 2019年) |
| 今日この国の現実を読者に突きつける。著者は出版社の編集者を経たフリーライター。想像も避けたいような描写から始まる生々しいありさまにまず圧倒される。著者はどのようにして現場に立っていたのだろうか。これまでは無縁であっても、これからは誰でもがこのような状況にいつ直面するかわからない。この深刻な現実について血の通った洞察を示してくれたことに敬意を表したい。
本書は、孤独死した本人、ゴミ屋敷、遺族、サポートする人々、そして特殊清掃業者にまさに“接した”レポートである。特殊清掃が手がけるのは、ゴミ屋敷、猫屋敷、火事現場、自殺現場、また技術のあるものは災害復旧など多岐にわたるそうだが、近年は孤独死が圧倒的で、「手がける案件の10件中8件が孤独死」だと言う業者もいるそうだ。 次のような記事(2018年5月14日付毎日新聞)が紹介される。 「5000社以上が加入している特殊清掃の業界団体である『事件現場特殊清掃センター』によると、民間資格である『事件現場特殊清掃士』の認定制度の施行が始まった2013年から、その数は5年間で15倍に膨らんで」いて、その背景には、家族、親族関係の希薄化があり、孤独死の増加に比例して特殊清掃の需要増によって新規参入業者が相次いでいると言う。 著者は現場の取材を続けるうちに、孤独死の場合には、そこに「故人の生きづらさが刻印されている」こと、そしてその背景には「社会的孤立の問題が根深く関わっている」ことに気づいていく。 孤立し、人生に行き詰まり、セルフネグレクトに陥る事情は何か。取材からわかってきたのは、人間関係が良好でありながらたまたま発見の遅れるのはきわめて稀れであって、「ある者は恋愛関係でもがき苦しみ、そしてある者は虐待などで親子関係が絶たれ、ある者は会社でのパワーハラスメントで心が折れ」、そして結果として、「周囲から取り残されて緩やかな自殺へとただ、ひた走るしかなかった」のであると。そして、「私な壮絶な現場の臭気に圧倒されながらも、遺品の数々から生前の彼らの姿がありありと目に浮かぶようになった」。 そして著者は、「その日初めて存在を知った彼、彼女らの抱えた苦しみを考えると、一晩中眠ることが」出来ずに、「私は、彼らが亡くなった孤独死の現場をたどるだけでなく、遺族や大家などその周囲の関係者に話を聞くことで、彼らの歩んできた軌跡をたどりたいと思った」。そして、同じ現場を共にする特殊清掃人たちに励まされ、「遺族さえ立ち入ることのできない凄まじい腐臭の漂う部屋で、最後の“後始末”をする特殊清掃人の温かさ」を知って、彼らの物語も描きたいと思うようになったと言う。 「年間約3万人と言われる孤独死だが、現実はその数倍は起こっているという業者もいる」ほどで、その現場から見えてくるのは、「やがては訪れる日本の未来」であり、「こうも言う。『こうなる前に、どうにかならなかったのだろうか』と。変な話に聞こえるかもしれないが、本書の取材に協力してくれた特殊清掃人たちは、内心では自分たちのような仕事のない社会が望ましいと感じている。私もそう思う」。 著者が語る本書のテーマは、「特殊清掃のリアルにとことんまで迫ることだ。それは、特殊清掃人たちの生き様や苦悩にもクローズアップしながら、私にとっての生と死、そして現代日本が抱える孤立の問題に向き合うこと」であった。そしてこうも言う。「死別や別居、離婚などで、私たちはいずれ、おひとり様になる。(略)特殊清掃の世界を知るということは、きっと、私や本書の読者であるあなたの未来を知るということなのだ。だから、たとえ目をそむけたくなる場面があっても最後まで希望を捨てずにお付き合いいただきたい。最後の1行まで、あなたの救済の書となることを願って」と。 始めの紹介が長くなったが、本書では第1章から第5章までさまざまなケースを、著者の言葉通りリアルにそしてとことん迫っていく。そして最後にはなぜか崇高ささえ感じられるほどであった。 第1章:「異常気象の夏は特殊清掃のプチバトル」 2018年夏の猛暑、高温注意情報が連日流れるまっただ中、一階に住む80代夫婦が営む二階の単身者用のアパートの一室で孤独死があった。借り主は心臓発作で亡くなった65歳の男性。発見したのは最後の勤務先である近所の生鮮食品の卸売会社の店長。当日出勤して来ないのを心配して大家の主人と二人で部屋に入ると、すでに冷たくなっていた遺体が発見された。部屋にはゴミが鴨居に届くほど積もっていて奥の部屋には立っては入れず、匍匐前進していったという。エアコンはどこにもなかった。 34年間、懇意だった大家によると、ゴミ屋敷になったのは4、5年前、それまで大家が分別していたゴミを自分でするように注意したのがきっかけではなかったかと言う。妻から臭いの話があったり、ベランダに出したゴミの袋が近所に飛んでいく苦情が来るよ、と話したそうだが、その時は、「わかりました、すみません」とは言うものの、直る形跡はなかった。家賃6万5千円は毎月手渡しだったが、34年間遅れたことは一度もなかった。著者によると、孤独死する人は人付き合いの面では困難を抱えていることが多くとも、家賃の支払いなどはきちんとしている人が多いように感じると言う。 この件の担当者である上東という清掃人についても、著者は他の章と同様紹介していく。彼は特殊清掃だけではなく、遺品整理や生前整理も行っている。楽しかった子供時代の想い出を持つ団地育ちで、30歳の時に仲間3人で廃品回収業を立ち上げた。ところが半年後に仲間の一人に肺がんが見つかり、お金がないと命すら守れない現実を突きつけられて、治療費を捻出するためにかなりあこぎなやり方をしたと言う。その仲間が亡くなったあと三日三晩泣きはらしたが、それでも心が痛んでもう限界だと言う時に、知り合いに勧められ遺品整理業に転向した。 ゴミ屋敷の遺品は掃除しなければ整理できない。そのため、転向してからは、特殊清掃が必要な孤独死の物件も手がけることが増えていき、本格的に特殊清掃にも乗り出していった。そして、日本初の遺品整理のフランチャイズということですぐにメディアにも注目され、テレビなどにも頻繁に出るようになったが、現場では、孤立し、心に苦しみを抱き、片づける以前に問題を抱えている人が圧倒的に多いということに気づいていった。しかし、メディアが求めるのはあくまでゴミや遺品の効率的な片づけ方で、彼が伝えたい心の部分には誰も目を向けようとしなかったと言う。それもあってメディアに出ても発信することが出来ず、ジレンマを抱えて次第に心が疲弊していくようになった。 メディアが求めるものと自分の思いとの乖離に悩んだ彼は、円形脱毛症になったり自律神経をやられたりしたあげく、苦しみ、辛さから逃げ出すために最終的に山にこもることで自分を取り戻した。そして、今はひとつひとつの現場を大切にして、遺族の中に自らも身を置き、寄り添うように時間をかけて作業を行っている。現場では遺族に敬語を使わないと言う。その理由は、何を捨てて何を残して欲しいのか、真意をくみ取るには余計な壁は取っ払ったほうがいいと考えているから。彼は次のように言っている。 「生きづらい人には、僕はすどく共感するの。孤独死した人は、みんな恐らく根は良い人なんだと思う。人を騙したりとかは絶対できない人。だから、同時に自分に嘘がつけなくてすごく苦しくなってしまう。悩んでそれが物凄いストレスになっちゃう。自分はこれでいいのかという、罪悪感を抱えているの。ずるくないから悩むんだよね。きっと世渡りは上手じゃない。ただ、その分、人に正直だと思うし、自分に正直でありたいと思っている。でも、社会を優先させなきゃいけなかったり、人を立てなきゃいけないところがあったりするでしょ。それに矛盾を感じてしまって、自分を許せてない人じゃないかなって思うよ」 「特殊清掃をやっていてきついのは、その人の内面がわかっちゃうこと。ペットボトルひとつからでも、その人の苦しみが見えちゃうんだよね」 たしかに、遺族と話し合いながら遺品整理するのは金銭面では非効率的だし時間もかかるが、彼は、「これまでたどってきた人生から、そんな生きづらい人の気持ちが痛いほどにわかる。そこに共感できる優しく温かな人柄を持ち合わせている。だから特殊清掃という仕事に携わっているのだろう」と著者は結ぶ。 第1章にはこのほか、ゴミに埋もれた部屋を掃除したいとのマンモス団地に住む70代の女性。この人はテレビ取材とその放送をきっかけにしてご近所との付き合いが生まれ、上東の仕事をキャンセルした。また、アパートで孤独死した77歳の男性の場合は、部屋は整然と整理され、床にはゴミ一つ落ちていなかった、まさに清貧を地でいったような生活がうかがえた。畳の上でなくなった彼のようなケースは珍しいと言う。彼は、最後まで誰にも迷惑を掛けず、恨まれることもなく、しかも十分な遺産を遺族に残していた。 猛暑の夏に死後一日で発見されながら、「人が歩んできた生き方は、ここまでも部屋に如実に現れるのか――。同じ死でも、こうも違うのかと思い知らされる」。 最初の件で、主のいない部屋で経を上げたあと、僧侶が語った。 「この方をもし生前に知っていたら、どうしてたんだろうってよく思うんです。一緒になって片づけようって言えたのかというと、話しかけても拒絶されるだろうと思って言えなかったかもしれない。関わらないでくれって人に、どうやって心を聞かせるのか。こちらも何をしてあげるのが正解なのかっていつも考えてしまうんですよ」 僧にもその答えは見つかっていない。 第2章から第5章も、深刻な描写が続くが、スペースの関係からここではやむなく簡潔に紹介せざるを得ない。 第2章:「燃え尽きて、セルフネグレクト」では、20年ぶりに会った別人のようになった兄(55歳)のことから始まる。会って数カ月後、連日の猛暑で兄は不詳の病死をした。警察署では一目でいいから兄の姿を見たいと懇願したが、警察官は、絶対に辞めたほうがいいといって首を縦に振らなかったと言う。 特殊清掃人の塩田氏の話。遺族らの行き場のない感情や憎しみが、特殊清掃業者に向けられることも少なくないそうだ。 「普段は何の交流もないのに、孤独死した時だけ責任を取ってくれと言うのは、意味がわからない」と。 第3章:「孤独死社会をサポートする人々」では、先ずは警察官である。警察官は最初に遺体を運び出す。もと警察官の菅原氏は、一番辛かったのは飢えによるもので、孤独死自体は止めようがなく、これから急増するだろう、そして引き取り拒否も増えるだろうと見通している。そしてそのつけは行政にまわるが、そのうち行政も音を上げるだろうと彼は内心では感じていると言う。 孤独死は、火葬はしたものの行き場のない「漂流遺骨」という形になって遺ることがある。 「3万円で遺骨を引き取る『終の棲家なき遺骨を救う会』(東京都新宿区)には、押しつけられた遺骨をどうすればいいかという親族からの相談がひっきりなしに電話やメールで寄せられる。その数は、月に100件を超えるという」 「顔も知らない親族が孤独死し、さらに遺骨を押しっけられた。できるだけ安く簡単に済ませたい――。相談内容は、突然の出来事に慌てふためいた親族の困惑が目に見えるようなものばかりだ」 このほか、猫屋敷を売却して仏壇の水を取り替える不動産会社社長。家族から密接には接触したくないと思われている人たちの受け皿となって、その家族の代わりに高齢者を手助けしている人々(“レンタル家族”と称している)。地元で孤立している人たちの支援に向けた「さえずりの会」を立ち上げた、親族の孤独死を経て自らがボランティアで回っている人。そこには孤立状態から困難に陥った人の相談がひっきりなしに届く。 第4章:「家族がいてもゴミ屋敷に向かう」では、地元の高齢者向け病院に22年間介護福祉士として働いていた10歳離れた実の姉53歳が失跡した事件から。2年以上経過しても未だに行方がわかっていない。おそらくゴミ屋敷化しているのを親族に知られたためだと言う。 ゴミ屋敷になったきっかけは同じ病院に勤める男性との失恋ではないかと妹は推測している。過食によって肥満になり、また自己啓発セミナー、宗教にもはまっていた時期もあった。姉はまじめであると同時に、生きるのが下手で、自己主張が苦手であった。家族も今はもうどうすることも出来ずにいる。 第5章:「なんで触ったらあかんの?僕のおばあちゃんやもん!」は、行列の出来る関西の遺品整理・特殊清掃業者、横尾氏の話である。 祖母の孤独死を経験したときに、何もかもが母親の肩に掛かり、その結果膠原病が悪化して入院を余儀なくされた。 「おばあちゃんが亡くなって、母親は膠原病でしょ。葬儀やなんかをこなせる体力はない。だけど、親父は昭和の親父やから一つも動けへん。おばあちゃんの荷物は多くて、本当に片づけが大変やったんです。バックヤードの女性が一番割を食うんですわ。人一人死んだら、それからがほんま大変や。片づけるのも母親一人では、でけへん。ただ単に家の中の物をぽんと出す仕事じゃなくて、家族に寄り添った整理人が絶対必要になってくるって、確信したんです。今思えば、全部おばあちゃんが導いてくれたんやわ」 高校時代ラグビーに明け暮れた彼はそこで大手遺品整理会社に転職を決意し、輝かしい営業成績を収めて大阪支店長まで上り詰めた。 しかし、そこは彼が夢見ていた遺族に寄り添うような会社ではなかった。まだ遺品整理という言葉が世に出たばかりの頃で、いくらでも高額な金額をふっかけることが出来たのだ。しかし彼は、逡巡して苦しむ。「俺が追い求めたいのは、こんな世界じゃない」と。 「ある案件が100万円で成約したことを社長に電話すると、『お前、そんなんやから大阪の売り上げが悪いねん。150万円とか200万円とか、ようやらんのか!』と怒鳴られた。 たまたまその声を聞いてしまったお客の男性は、驚いた様子で首を振った。 『横尾さん、あんたはええ人や。だけど、そんな会社におったらあかん。あんたには悪いけどキャンセルするわ』 横尾は、泣きながら社長に電話して抗議した。 『俺がいつ会社に迷惑かけたんか。俺が会社を軽視したことなんてないわ。俺は常に胸張って仕事しとるやないか。こんな会社辞めたるわ!』 悔しくて、涙が止まらなかった。必ず自分が目指していた遺品整理を実現してやる。みんなが笑顔になれる、そんな存在に絶対なってみせる。そう決意して、会社に辞表を叩きつけた」 彼は2008年、会社を辞めるとすぐに大阪の堺市で遺品整理、特殊清掃業を立ち上げた。当時、需要が最も多かったのは、生活保護受給者の部屋の整理だったと言う。そこで、前に働いていた会社の約半額という破格に設定し、その金額はすぐに話題になった。彼は同時に、部屋の整理の価格を抑える代わりに家電を買い取り、利益を上げるという仕組みと作った。たとえ1件当たりの利益は少なくとも、時間をやり繰りし、手がける件数も増やした。 「確かに遺品整理のノウハウは前の会社に教えてもらった。しかし、会社は人の心に寄り添うという最も大切なことを置き去りにしていた。そのことに対する反発が原動力となり、メモリーズは関西で随一の遺品整理、特殊清掃業者として名を馳せるまでになった」のである。 「近年増え続ける特殊清掃業者の中には、遺族が慌てふためくことを逆手に取って、ボッタクリのような金額をふっかける業者も多い。横尾はそんな業者に憤る。『10万円、20万円っていったって、庶民には大金や。特殊清掃で100万円とか取ってどうすんの。お天道様はちゃんと見とるんや』」 ある現場では、「2Kの部屋の上までゴミ袋が山のように積み重なっていた。(略)案件を紹介した社会福祉協議会によると、他社の見積もりは50万円だという。 『横尾さん、どうか助けてやってくれや』 (略)どんなに安く見積もっても、40~50万円はかかるはどのゴミの量だった。しかし、どう見てもこの親子には支払い能力がない。 もうこの金、返ってけえへんでもええわ。人助けや。俺にこの現場を見させたら、俺そんなの絶対やってまうやん。俺品祉整理から始まったんや。おっちゃんが、やったるわ。だから安心して任しとき。 横尾は、月々2万円の5回払いで、10万円でゴミ屋敷の片づけを引き受けることにした。しかし、そのお金ですら、返ってこなくていいと思った。 『坊や、よう、俺と出会ったな。助けたるわ。おっちゃんは、スーパーマンやからな』 横尾は、心の中でそうつぶやき、懸命に部屋のゴミを片づけた。部屋のゴミがすべて撤去されると、みるみるうちに男の子の顔は、明るくなっていった。少年の母親は泣いて喜び、毎月2万円を手に横尾に返しに来た。横尾は、まさに、少年にとってスーパーマンになったのだ」 引用が多くなってしまったが、その中身へのアプローチには欠かせなかったからである。次に、一般的な事情として触れられていたものとあげておこう。 先ず料金である。特殊清掃の費用は遺体の腐敗が進めば進むほどかさむことになり、数百万円というケースもざらにある。そして、相続放棄をした場合を除いては、負担を強いられるのは血縁関係にある遺族だが、最悪、後払いであることをいいことに費用を払わずにそのまま逃げるケースもあると言う。そうでなくとも、賃貸の場合、多額の掃除費用をめぐって遺族と大家がトラブルになることも多く、特殊清掃業者がその板挟みになるケースが多い。 また、孤独死の場合4件中3件が男性で、そのほとんどが離婚をして家庭崩壊となった男性だとする業者もいるそうだ。さらに、男性は女性に比べてゴミ屋敷よりも趣味に傾倒したモノ屋敷へと傾倒しやすいと言う。 ニッセイ基礎研究所が2014年に出した「長寿時代の孤立予防に関する総合研究~孤立死3万人時代を迎えて~」でのアンケートをもとにした著者の概算によると、日本では「約1000万人がさまざまな緑から絶たれ、孤立していると推測される」とし、「特に2019年現在の30代から40代後半に至っては、10人に3人が独身であり、きょうだいも少なく、一人暮らしをしていて、孤立しやすい状態にある」と言う。 最後に著者は、「おわりに 孤独死に解決策はあるか」において、孤独死を取材するに至った経緯を述べながらこう感じたと言う。 「問題は1人でなくなることではなく、そのもっと前の段階にあるということだった」 「一人一人にはそれぞれ誇ることのできる人生があり、そして物語があるということだった」 「この方法なら孤独死は防げるという解答などない」 「運命の歯車が狂い始め、どうしようもなくなった時、果たして私たちに何ができるのか――」 「だからこそ私は、彼ら、彼女らの人生を知って欲しいと思った」 さらに最後に、著者は次善であることを承知の上でとして、実務的な対策としていくつかを挙げている。 それらは、「AIやITを利用した見守り」「郵便局での対面での見守り」「レンタル家族で無縁者をサポート」「行政の取り組み」「支え合いマップ」「「セカンド小学校」「孤独死保険」「御用聞き」などである。 しかし、そもそも生きづらさを抱えて人たちは、「こうしたネットワークや仕組みにたどりつき難」く、その前に「きっと心を閉ざし、八方ふさがりになって力尽きてしまう」のが現状でもある。そして結局は故人ごとに異なるし、アプローチが難しい」というのが現実ではあるが、しかし、この見えない渦に「巻き込まれ、もがきながらも、あきらめないその姿にこそ、希望がある気がした」と結んでいる。 本書の示すものについてどのように捉えるか。おそらく避けて通れないこの問題について知るきっかけとなることを願って紹介した。(雅) |
| 中野信子、鳥山正博著『ブラックマーケティング -賢い人でも、脳は簡単にだまされる-』(KADOKAWA 2019年) |
| 今日までのマーケティング理論は、「自分で意思決定が出来る消費者」が前提となっていた。しかし、現実には、その前提から外れている購買行動も多く、そうした現象を扱わずに「『正しいこと』だけを述べる“規範の学”」を、本書では「よい子のマーケティング」と呼んでいる。そもそも購買行動には個人差があり、一人の人間でも時と場合によって異なった行動をとるからだ。
本書はそのような、「標準から外れた少数派の消費者や、モラルから逸脱した手法」を取り上げ、これまであえて対象としてこなかった現象について、売り手の側の戦略と消費者側の心の癖や行動との関連は如何なるものかを論じている。読んで後には、これから先何かを買いたいと思った時に、かなり客観的な判断が出来るのではないかという心境にさえなった。 中野氏は脳科学者、鳥山氏は経営学者ならびにコンサルタントとして、ともに著名である。本書は取り上げられたテーマをめぐる対話をもととして整理されており、それぞれの専門からの知見がわかりやすく、しかも自身あるいは見聞きした経験からけっこう心当たりのある事例をあげながら解説している。 構成は中野氏による序章と鳥山氏による終章に加えて5つの章から構成される。序章によると、「第1章から第3章では、ヒトの行動を左右する神経伝達物質を手掛かりに、脳のメカニズムを検証」し、「第4章では『操られやすい』という脳の脆弱さを明らかに」し、第5章では、「最新の遺伝子研究の知見とあわせて、脳の男女差や地域差、『国民性』に踏み込んで」いく。また「要点」と示された文章それ自体に赤線が引かれており、理解に便宜が図られていることも本書を特徴付けている。ここではそれらを参考にしながら、それぞれの章で興味をもった点をあげていこうと思う。 第1章、「焦りをかきたて判断力を奪う商法にご用心 ―セロトニン×不安を煽るマーケティング―」では、先ず、「いくら稼いでいるか」よりも「周囲と比べてどれだけ稼いでいるか」のほうが幸福感につながりやすいというイギリスの研究をあげる。さらに、常に幸福感を求め続けることが、「生活に困らないだけの十分な収入がありながら、怪しい儲け話に乗って大金を騙し取られてしまう」事件が後を絶たない理由ではないかと言う。 また、CMなどによって困りごとを作り出して不安を煽ることで「ニーズ」から「ウォンツ(欲しい)」に顕在化させるやり方を「点検商法」と言う。これは将来の不安を武器に手遅れの恐怖を喚起させるもので、「霊感商法」や「開運商法」と相似する。これらは「最初から“焦り”や“不安”を感じやすい人」をターゲットにすることで、「その気」にさせることも容易であって、そのような詐欺まがいに会ってしまう例もよく聞く話である。 第2章、「『ハマリたがる脳』を刺激する罠の数々 ―ドーパミン×依存させるマーケティング―」では、パチンコに熱中してわが子を車の中に放置してしまうほどのドーパミンの快楽の恐ろしさから始められる。カナダにおけるラットを使った研究によって、ドーパミンによる依存形成による欲求は、生物の基本的な生理的欲求(空腹、渇き、発情期の異性が近くにいるなど)よりも強いことが明らかにされたと言う。 また、ギャンブルは、「消費者は損をしたら学習し、同じ商品やサービスには二度と手を出さない」という従来のマーケティングの前提とは相容れない。これはヒトばかりではなく、サルやハトによる実験からもわかっていて、つまりは「『出るか、出ないか、わからない』という状況がドーパミンの動態を変化させ、出るまでやめられなくなるという習性が、一定数の固体には備わっている」と言えるそうである。 さらにはソーシャルゲームに付随する「もったいない」と「みっともない」という消費者心理が巧みに利用され、それに対して依存性が高じていく過程の解析、テレビ通販番組で年間4000万円もの開封されていない商品が家の中に山積みになっている知り合いの女性の例などが述べられる。テレビの通販番組では、司会者の使ったフレーズおよび商品の特徴のアピール点とを、電話の鳴った回数と結びつけながらリアルタイムで進行役に指示しているそうだ。 参考までに、本書に挙げられている依存症の国際基準を列挙する。 ① 対象への強烈な欲求・脅迫感がある ② 禁断症状がある ③ 依存対象に接する量や時間などのコントロールが出来ない ④ 依存対象に接する頻度や量が増えていく ⑤ 依存のために仕事や通常の娯楽などを無視または制限する ⑥ 心や体に悪いことを知っていても続けている である。 そして、「これら6項目のうち、過去1年以内に3つ以上を繰り返し経験したかもしくは1か月以上にわたって3つ以上の症状が同時に続いた場合、専門的な治療が必要な依存症と診断」される。 第3章、「理性を麻痺させ『欲しい』と思わせる仕掛け ―オキシトシン×愛情マーケティング―」では、なるほどと思わせられたのが、女性のイメージが強いオキシトシン男性(例えば任侠の世界の)にも多い可能性があると言うこと、また分泌量が多い人は「妬み」の感情を抱きやすくなるということであった。これは「仲間の絆」や「愛情の裏返し」とも言えるが、その反面、仲間以外に対する「排外性も強くなるという傾向がある」とされ、確かにその通りだと納得させられた。 オキシトシンには不安やストレスを軽減させ、痛みを緩和したり免疫力を高める効果があるが、マーケッティングに関係する重要なポイントはそれが人間関係に影響を及ぼすことである。例えば、オキシトシンがたくさん出ると初対面でも恐怖を感じず、積極的にコミュニケーションを取れるようになり、またそれによって得られた情報も強く海馬に記憶されるそうである。 しかし、その愛情の深さを逆手にとっての詐欺師の暗躍もまた現実なのだ。中野氏は著書『シャーデンフロイデ』のなかで、「詐欺事件は愛情と信頼に基づいた性善説的な社会基盤が形成されている国に多発するのではないか」と洞察しているそうである。 この章にはこのほか、「新製品普及会」の頭文字をとったSF商法という悪質な催眠商法、押し売り、マルチ、内集団バイアスを応用した商法などが挙げられる。握手券、投票券などを一部の熱狂的フアンの「消費者余剰」に結びつけるやり方は、「承認」よりも「好きな相手に影響を及ぼしたい」という「関与」の(充足感)の方が快感が大きいことを示している。また、返報性の原理に通じる『後妻業』(直木賞作家黒川博行氏の作品)や、フェイスブックの「いいね!」のやりとり、出会い系アプリの闇なども論じられる。 このように、自らが選んだという意識(自己効力感)、そしてその選択は正しかったと思いたい消費者の心理を伴いつつ、「他者からの愛を欲している限り、ヒトの脳は、『だまされるリスク』から逃れることはない」とも言う。オキシトシンは自分自身が癒される環境にいるならば分泌が促され、それはまた周囲に伝播していく愛と絆のホルモンであることは間違いない。しかし、愛情を食い物にする手口が世の中にあふれている限り、これからはその「働きなどへの正しい理解は、一般の人にとっても必要な時代になっている」のではないかと言っている。 第4章、「五感を使って他者を操る手法とは ―前頭葉機能×刷り込みマーケティング―」では、前頭葉と消費の関係を述べる。 「賢い買い物」をする時には前頭前野が非常に重要な働きをするのだが、その働きを低下させることで購買に向かわせるというやり方を取り上げる。たとえば、倫理的消費と呼ぶ社会貢献を打ち出した商品を好んで買う行為は、冷静で合理的な判断よりも情動が決め手となることがあるが、それを悪用した手口の典型が便乗商法である。東日本大震災でも同様の例が多々見られた。 ストーリー・マーケティングと言う言葉があって、商品に何らかの物語をつけると売り上げが伸びると言う。本書では、「力をあわせて・・・」などのコピーとともに家族の写真とを表示したトマト、無農薬栽培をアピールする曲がったキュウリ、ツイッターで告白することでピンチを乗り切った例などがあげられている。自分では理性を働かせて購買したつもりでも、実は何らかの情報に“流されて”判断している場合がけっこうある。 また例えば、負荷の高い自由な絵より塗り絵の方が脳は怠けることが出来るのだが、自分で色を決めることで自己効力感も満足できる。しかし、青い空、緑の草原、黄色いキリン、赤いりんごなど、ほとんどは同じような色使いになる。この効果を応用した仕掛けをプライミング(呼び水、事前刺激)と言うが、これと同様に、買い物客の五感を刺激して誘導する工夫はいろいろな場面で見られるようだ。 例えば、水着売り場にココナッツオイルやトリピカルフルーツの香り、高級なワイン売り場に流れるクラシック、高級ブランド店と量産店の照明の違い、等々。「ヒトの脳が下す判断や評価は絶対的なものではなく、いろいろな要素によって“揺らぐ”ものなのだ。 このほか、嫌でも耳に入って連想を引き起こす「イヤーワーム」現象、速い思考と遅い思考の相違、ストレスを感じずに選べる選択肢の数は5~9個、二者択一というやりかたで断られにくくする「デートの誘い方」、「これさえあれば」と思わせるミラーニューロンの働き、Iメッセージが相手を感動させる、「普及学」と「見せびらかしの消費」などが取り上げられているのが面白い。 日本は他者の意見を気にする社会とはよく言われるが、おどろいたのは、口コミの影響が圧倒的に顕著なのだそうだ。筆者(私)はツイッターとは無縁であって、「つぶやく」ようなこともさっぱり思い浮かばないけれど、「地球上で毎日つぶやかれている言語の約4分の1は日本語」だそうだ。びっくりした。 このこととも関連していると思われるが、レビューの数や星の数でどんどん他者の意見が可視化されることで、結局、「サイバー空間では自分だけの判断よりも、多くの他人が下した評価のほうが重要な尺度として機能している」と言うことには思い当たる。 さらに関連しては、SNSの闇と名付けてその依存性の例に、アメリカミシガン大学の研究チームによる論文、「フェイスブックを利用する頻度が高くなるほど幸福度が低下する」をあげる。そして、「幸福度が下がるほどフェイスブックを見ずに入られなくなるという悪循環が、SNS依存症に拍車をかけているかも」知れないと言う。 この章の最後に、ネット社会の「メシウマ」というスラングを取り上げる。これは「他人の不幸で今日もメシがうまい」という言葉から来ているらしい。「ヒトの脳には他者の痛みに共感する回路があるだけでなく、もともと他人の痛みに快感を覚える回路が備わっている」とされる。その例を、ネットなどで人をバッシングすることにハマっている状態をあげる。これは、“正義”執行している快感によって前頭前野の理性の領域に麻痺が起こっているのであって、ヒトのなかにすでにそのような悪魔的な性質が棲んでいるということなのだ。 第5章、「だまされやすさは遺伝子で決まる? ─遺伝子に操られる脳」では、まず市場における日米の消費者行動の違いがどのようなものかが語られる。たとえば、少々傷があっても売れる(アメリカ市場)か、少々高くても傷一つない方が売れる(日本市場)という具合である。そしてそういった国民性はどこから来ているのかと。 結論的には、脳科学によって説明される。ただし、生得的な遺伝子配列だけではなく、その現れ方の違いによるものも大きく、「遺伝子の働きは『生まれ』だけでなく、『育ち』にも影響を受け、脳の“個体差”は」遺伝子の発現を制御・伝達システムに拠っているというものである。これを示すラットの仔を使ったストレス耐性の実験が紹介されている。 それによると、仔をよく舐める母親とよく舐めない母親の仔を取り替えることで、舐めない仔のストレス耐性が高まったと言う。「遺伝ではなく、舐められるという後天的な要素によって変化が起きた」ということである。しかも、「後天的に獲得した気質が一見、次の世代に引き継がれるように」見えることから、環境や風土と文化や国民性との関係にもそうしたことを考慮に入れることが必要ではないかとしている。 さらに、セロトニントランスポーター(セロトニンを回収して再利用するたんぱく質)の量によって遺伝子の型があり、「不安を感じやすい」「緊張しやすい」「不公平感を抱きやすい」日本人に多い型と、「不安を感じにくく」「緊張しにくく」しかも「やや楽観的すぎる」アメリカ型という傾向が双方の市場の違いの要因である可能性も指摘している。また、南欧の人々にみられる冒険心と情熱、マーケットで男女別や年齢別は最近ではアテにならいこと、右脳人間・左脳人間、あるいは男脳・女脳と現象的な男女差と個体差、等々、ここでは詳細に触れないが興味を惹かれる話題が提供されている。 最後に日本人の文化と風土に触れる。世界の陸地面積のわずか0.2%に過ぎない日本で、世界の災害被害総額(どのような換算方法かは不明)の約2割、つまり5分の1を占めているそうである。そうした自然環境の圧力に生き延びてきた子孫が今の日本人であって、そこには集団の意思を尊重する助け合いがあったとされる。これは、畑作に比べて集団に合わせることが重要な稲作中心の村落共同体におけるしきたりも大いに影響していると考えられる。 日本人にはCOMTというドーパミン分解酵素の活性が高いタイプの人が多いと言う。それによって欧米人に比べて「自分で決めた」という快感が生まれにくく、そのため「他者が決めた方向性やルールに従う傾向が強くなる」とされる。このような自然および文化的な環境圧力に適応した遺伝子が優位な個体が生き延びることで、最初はその率がわずかであっても、何代も続くことで大きな割合を占めるようになった。 ただ、新規なものや開拓など、リスクを負ってもチャレンジする遺伝子もまったく消えたわけではない。なぜなら、日本には稲作に適さない土地も多いし、また日本のメーカーはアメリカよりも新商品を活発に作っているからである。またイグノーベル賞では、イギリスやアメリカとともにトップを争っているそうである。 つまりは、プレッシャーのない状態が、持てる能力を発揮するためにはいかに大切かと言うことになる。最後に日本の教育機関、ことに大学におけるシラバス(講義計画)のあり方をはじめ数々の問題点を指摘しているが、まったく同感である。 中野氏は第一に主張したいこととして、「いかなるルールを設計する時も」、それが「人々にどんな行動を奨励することになり、結果的にどんな秩序を生み出してしまうかをもっと考えるべきだ」と述べる。 以上読んできて、人の心の弱点の背景や意味を知ることが、自らをより客観視した行動の後押しになるのではないかと感じた。実生活における購買行動を再考するためには最適である。(雅) |
| 斎藤明美著『高峰秀子の流儀』(新潮社 2010年) |
| かつて『高峰秀子の言葉』(新潮社
2014年)を取り上げた(月刊サティ!2014年6月号)ことがあり、同じく養女の斎藤明美が著したものである。本書はそれより4年前、2007年から2008年の2年間、「婦人画報」の連載をまとめたもので、高峰秀子の生前に出版されたもので、少々重なる部分もあるかと思うが、あえて再び取り上げることにした。 著者はもと「週刊文春」の記者で作家、2009年に松山善三・高峰秀子夫妻の養女となった。情報誌ネットと言うサイトの「ふれあいコラム」には、週刊誌の記者として高峰秀子に寄稿やインタビューのお願いをしたのが「松山と高峰と親しくなったきっかけ」となったとある。3年越しに高峰に月刊誌の連載を願っていてようやく実現した頃、彼女の母が難病で余命を宣告され、兄弟もいないために週刊誌の仕事をしながら3日おきに郷里の高知と東京を往復する生活を続けていたという。そして次のように語る。 「その時、高峰が本当に心配してくれて、母が死んだ時は、絶望した私を、それこそ深い穴から助け上げてくれるように、毎日、毎日、家に呼んで手作りの温かいご飯を食べさせてくれたんです。それを松山もまた優しく受け入れてくれて……。ですから二人は、おおげさでなく、私の命の恩人なんです。 養女になるなど夢にも思っていませんでしたし、二人がそのことを私に告げた時には、まさに驚天動地でした」 『高峰秀子の言葉』を取り上げたあと、高峰自身が著した、『わたしの渡世日記』を読んで、生い立ちから女優として歩んできた道のり、養母のすさまじい行状、それを反面教師とする姿を知り、これがまさに「カルマ」なのかと思った。彼女はそのほかにも数々の著作をなしているが、5歳の頃から小学校にも満足に通えなかった環境のもとで、よくもそこまでなし得たのかと感心するばかりであり、人の可能性や心がけというものの力を改めて感じさせられた。 今回紹介する中にも、夫の松山善三氏に聞いたこんなエピソードが載っている。 彼女は新婚の頃、やたらと新聞や雑誌をひっくり返して何かを探していたそうである。不思議に思った彼が「何をしてるの?」と尋ねると、「字を探してるの」と答えた。 「夫は驚いた。31歳の新妻は辞書の引き方を知らず、読めない字がある時は、別の媒体でその同じ字を探して、読み方を知ろうとしていたのだ」と。そして、「とうちゃんが、中学時代に使ってた辞書をくれたの。それで引き方を教えてくれたよ」「引き算も教えてくれたの。横から一借りてって。割り算と掛け算も教えてくれた」と言ったそうである。 著者はその時、「私は何だか涙が出そうになった」として、「高峰さんが可哀想なような、可愛らしいような、そして健気なような・・・」、そしてまさに、「松山善三という人は、高峰秀子に“安寧”を与えた。彼女が望んでも手に入れることができなかった心の安らぎを」と思ったそうである。 本書は、「高峰秀子という知性」からはじまり、「動じない」「求めない」「期待しない」「振り返らない」「迷わない」「甘えない」「変わらない」「結婚」「怠らない」「27歳のパリ その足跡を訪ねて」「媚びない」「おごらない」「こだわらない」など、魅力的な見出しがならぶ。本文は著者の文章とともに日付の付いたできごとが交互に配され、いずれも高峰秀子という人間を際立たせてくれるが、ここではその一部しか紹介できないので、もし興味を持たれたらぜひ一読されることをお勧めしたい。 「動じない」のなかでは、4歳の時に養母・志げに「かあさん」と言えと責め立てられ、半べそをかきながら「かあさん」と呼んだけれど、呼ばせた相手を「これは怪しの者だな」と感じ、「ふーん、人間ってこういうものなのか」と思ったそうだ。 「だが、もし高峰秀子が凡庸な子供なら、ここまでは思わなかっただろう。・・・世の中、わからないほうが幸せという事象がいくらもある。だが高峰秀子は『気の毒』にも、既に4歳にして物事の真偽を見極める目を持っていた。ために彼女は、それ以後、用心を手放さない子供になり、やがて、おいそれとは人に心をゆだねない、隙のない人間に成長していくのである」 「求めない」で典型的なのは、著者が成瀬巳喜雄監督生誕100年についてインタビューを求めた時に言った、「興味ない」「成瀬さんがいいと思って、私もいいと思った。それでいいんだよ」という言葉だ。つまり、高峰秀子は、「人間生活の根本とも言える対人関係にさえ何も求め」ないし、「明らかに彼女は自分自身を“他者”として捉えて」いることが分かる。著者は、これは女優としてはあり得ない精神構造ではないか、と捉えている。 何億を稼ぎ続けても、大半は養母に吸い上げられ、結婚する時には貯金が6万5千円しかなかったし、夫婦で合わせて100本を超える映画トロフィーは捨ててしまった。そして言った。「あんなもの、いつまでもとっておいてどうするんです。重みで棚がしなってきちゃった」。 「高峰秀子にとって、金や名誉は『あんなもの』であり、『そんなもの』でしかない。 著者は「愚痴」と「昔話」と「説教」が年寄りの三種の神器だと考える。もちろん、歳を取らなくてもそんな人はたくさんいて、20年間、1200人ほどの著名人に著者がインタビューしてきたなかで、自身の過去を語る時に自慢の匂いがない人は非常に少なかったと言う。とりわけ俳優、なかでも女優が夢心地の顔になる、つまり自己陶酔だが、見ていて興ざめしたそうだ。高峰にはこれが全くないという。「振り返らない」のである。 田舎にいる著者の父が半分ボケ(著者は意図的に「ボケ」と言う言葉を使っている)て、側に誰かがいるとのべつまくなしに50年も60年も昔の話をすると言う。自慢話から、繰り言、恨み、悪態等々。著者は見ていて哀れだと思う反面、一方では「父らしい老方」だと納得もする。「父はボケる前から自己管理能力のない人だったからだ。そしてそんな父を見ていて、私は思った。人は、その生きたように老いるのだ、と」。 また、自伝というのは自身を語るインタビューと同じだが、その人がどれだけ客観性を持って己を直視できるか、それが一目瞭然でわかると言う。先にも触れた『わたしの渡世日記』について、著者は、「おそらく自伝と呼べるもので、この作品ほど自己を客体化した作品はない」と評している。 結婚した時の夫との格差について、著者が「夫が劣等感を抱かないようにとか、そういうことは考えましたか?」と訊ねた時、「朝から晩まで考えてましたね」ときっぱりと言ったそうだ。そして、 「結婚した当時はお手伝いさんが三人いたんだけど、例えば食事の時、おかず持ってくるんだって、私のほうに先に出すんだもん。習慣って、ちょっとやそっとじゃ直らないからね。それで魚の切り身なんか、私のほうが大きいの。だからそういうことをやめさせたり、御用開きさんに『うちは今日から松山です。高峰じゃありません』って言ったり。でもいっくら口が酸っぱくなるほど言っても『高峰さん、こんちは』なんて来るから、しまいに、全部とっ換えちゃったの。魚屋、八百屋、酒屋・・・御用聞きさん全部」 そして著者はこう付け加える。「普通の妻にはない、“高峰秀子”ゆえの特殊事情とはいえ、ここまで実行した高峰さんを、私は天晴れだと思う」と。 高峰の一つ一つの動作が実に丁寧であることは前回も紹介した。「怠らない」では、「神経が全てに行き渡って」いるので、「どこかにけつまずいた、ぶつかった、何かを壊したということが全くない。つい“うっかり”ということが皆無の、驚異の人」なのだと言うことをあらためて付け加えておきたい。 高峰秀子は普通じゃない。著者はそのどう普通じゃないのかをその出会いからずっと考えてきたし、また読者にも一緒に考えて欲しいというのだが、自身でもいまだ確たる答えはないと言う。しかしそれでも、著者が20代の頃に感じた“3種類の人間”に当てはめて推し量ってみようとする。それは、 ①何もわからない人 ②わかっているが実践できない人 ③わかっていて、なおかつ実践できる人 著者の経験では②が一番多く、同時に一番不幸だと言う。その理由は、「わかっていて実践できないのだから、挫折感や自己嫌悪を感じる。そして、実践できないということは『わかっている』ことにはならないのではないかという恐怖にさいなまれる。幸せなのは①と③だ。ただし中身は正反対であり、③に入るのは至難だ。 高峰秀子は明らかに③の人である」。では、なにが「わかる」「わからない」のか。「それはたぶん、人としての理想だ。言ってみれば、人としてどうあるのが麗しいか。本当の幸福とは何かということ」ではないか、「高峰秀子は、それを知っている。そして実践できる。そこが普通じゃない、というのが私の結論である」と結んでいる。 「おかげさまで、いよいよ私の連載も最終回です」となり、松山氏が「おめでとう。無事に最終回、よかったね」と笑顔で言ってくれた時、高峰さんが言ったそうだ。 「“こだわらない”って、もうやった?」 これまで内容にも一切の制限はおろか、何一つ注文をつけなかった、「その高峰さんが、初めて自分から、“こだわらない”というタイトルはもう使ったかと聞いたのだ。・・・“こだわらない”というテーマが高峰さんの信条の中でもよほど重要なものに違いないと推察した。 このところメディアなので、「こだわる」という言葉が「こだわりの○○」と言うように、まるでプラスの意味のように使われることがあるが、連載の担当者が言うように、本来はネガティブな意味である。このように意味が取り違えられたりするのを耳にすると、いかに「言葉は変わる」ものとはいえ釈然としないのはやはり「歳のせい・・・?」。 で、いきなり高蜂さんが話し出した。 『私は、心の中にノートを持ってるの。そのノートにね、いろんなことをゴタゴタ書きこみたくないの。いつも真っ白にしておきたいの』 これは前回も紹介しているが、これについて著者はこう付け加える。 「もし私たちが日常のあらゆる出来事に対して『こだわらず』、それを実行し続けることができたら、どれほど毎日が心安らかなことだろう」と。 最後に、『高峰秀子の言葉』を前回取り上げようとしたきっかけとなったもので、やむなくカットしたエピソードを一つ。 高峰が70代初めの頃、いつも行く麻布十番の魚屋へ、その晩のおかずを買いに行った。(普通、女優は、少なくとも“大女優を呼ばれる人はそんなことをしないそうだ) 「高峰が魚を選んでいると、店の主人が言った、 『お客さん、よくみえるけど、近所にお住まいですか?』 高峰は応えた、 『ええ。そこの麻布永坂に住んでます』 すると店主が、いいこと教えてあげるとでも言わんばかりに、 『あそこには女優の高峰秀子さんが住んでるんですよ。知ってました?』 その時高峰、少しも慌てず、ニッと小さく笑うと、と言っても私は現場にいたわけではない。恐らく高峰のことだからそんな表情をしただろうと想像するのだ。 こう応えた、 『私、その成れの果てです』 ・・・驚いたのは魚屋の主人で、アングリと口を開けたまま。 なぜこの言葉が私のお気に入りかと言えば、いかにも“高峰秀子らしい”からだ。 高峰でなければ絶対に言えない一言だからだ」 客観視の見本のような話に思えた。(雅) |