![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
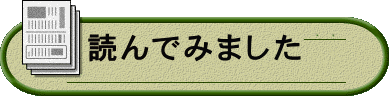
2019年7月~12月
 |
|
| 高橋三千綱著『作家がガンになって試みたこと』(岩波書店 2018年) |
| 作家による闘病記には違いないが、そこから想像されるものとはかなり違っていた。で、本書をここで取り上げるかどうかについては少し躊躇したけれども、こんな考え方もあるのかということ、そして、文筆家である著者の文章は「さすが読ませるなぁ!」と言う感想を持ったことから、あえて紹介することにした。いわゆる闘病記とはひと味もふた味も違っていて、著者自身の環境や状況に負うところも多いし、自分にはとうてい当て嵌まらず出来そうにもないとは言え、ものの見方を広げる意味では読んでみて痛快でもありまた衝撃的でもあった。 記録は血糖値の数値が境界線よりもはるかに高くなったことから始まる。つまり糖尿病。早々と3ページ目にはこんな文が出てくる。「担当の老医者はどこかの病院をお払い箱になったような頼りない人だったが、それでも酒の飲み過ぎだとかカロリー制限を死守せよなどと、くどくどと説教をすることを忘れなかった。・・・」と。そして、検査入院で血糖値が320mg/dLを超え(基準値は70~109)、γ(ガンマ)-GDPの上限値は79U/Lであるのに2010年2月にはなんと3954。「それは検査の間違いである」と主張した結果、1カ月後には4026。それを見て先生は、「死んでいる人の数値ですよ」と青ざめたという。 その後、肝硬変、三度にわたる食道静脈瘤の手術、食道ガンの手術、肝性脳症での入院、そして、「こんどは胃がんが見つかりました」と告げられる。作家というと、イメージの一部には無頼派というものがあって、著者自身はそう自称しているが、それも酒が原因の肝硬変となればここで不飲酒云々といっても始まりそうもない。 ただ言えることは、著者は本書で読む限りではあるけれど、あくまで楽天的なのだ。次々と病の経験をしながらも自分でもさまざまに調べ、また書名にあるようにいろいろと試みるのである。そしてその中には「そういうものか!」とトンと手を叩きなるものや痛快なものもけっこう多い。 「毎日インシュリンを注射して断酒しないと、四カ月で死ぬ」(2010年4月の時点)と告げられた高名な肝臓病の医師に手紙をしたためる。 「告知は医者のつとめであるかもしれないが、それにショックを受けてありもしなかったガン細胞ができてしまうことがあります。私はあなたの傲慢さに憤りを覚えます。『死ぬ』と患者に告げて、青ざめている相手を見て愉快ですか。同じ言葉を告げられたら先生はどう反応されますか。冷徹さは必要でしょうがそれだけでは患者は救えません。先生は毎日百人の患者を前にうんざりされているかもしれませんが、患者にとっては命を救ってくれる人は、I先生ひとりなのです」 数日後に先生からは詫び状が届いたそうだが、その時にはI医師にかかることを断念していた著者は、「『よし、こういうときこその楽天家だ。まず、禁酒する。家族を安心させて仕事する。新しい三千綱を発見しよう』。そうほざいた私は、意地を見せてその後半年間は完全に禁酒した」そうである。 もちろんきちんとした診断も受け、治療もおこなっているのだけれど、本書を読み進めると、そうしたことよりも、全編にちりばめられている著者による健康、病気、医者に対する考え方、信念といったものが強く印象に残る。つまりそれは著者の人生そのものに対する姿勢と通じるようだ。 曰く、「・・・それに肉、総菜を食べない人はタンパク質不足で死ぬ。表立って語られることはないが、ガン患者の死因のほとんどは、ガン細胞ではなく栄養失調だと専門医は知っている」 「ひとつだけ決めていたのは、たとえ胃ガンであろうが手術は断るつもりでいたことだ。・・・何故か。胃ガンの手術をされてしまえば半年で死ぬ」 「実は私は病気を重ねる内に、医者の言いつけを守ると人生が台無しになると喝破するようになっていた」 どちらかと言えば、医者から言われたことはよく聞く方の私からすれば、これなどまさに「本当かよ・・・!」である。そして、食べたいものを食べ、静脈瘤出血の恐れがあるにもかかわらず、ゴルフのティーショットでは欲を出して力一杯振ってしまうのを、本人は「若い証拠」だと見なし、T大学病院の医者については「バカの壁」と言ったそうである。 こうして紹介していけばきりがなさそうだが、もう少し書き出してみよう。7カ月に及ぶ戦いに一応のピリオドを打つことになって、「楽天家は運を呼ぶ、そう思った」時に考えたのは、「病気で死んだ人の内、病院の担当医師に殺される患者の割合は20%は下るまいと言うことだ。原因は誤診と、無責任で無神経な医者から与えられるストレスである」と。 「早期発見であれ、それが真性ガンであれば、すでに臓器転移しているのである」「手術をしないからこそ、数年間は安穏に過ごせるのだ」「医者の言うまま手術をしたら、手術後の人生が台無しになる。・・・ではどうするか。『愛に生きよう』。おまえは馬鹿か。もう少し人生を暗く考えることができないのか」 ビタミンB1はブドウ糖をエネルギーに変換するが、不足すると疲れたりだるくなる。特に、「脳は不足するとひどいことになり、はっきり言うとバカになる。糖尿病のため、カロリー制限ばかり医者からいわれていた私はある時期、忠実に米食も少なくし、肉も野菜も控えていたら相当バカになった」そうである。 胃にガンが二つ出来ていると宣告されてから2年たったある日、著者の娘が母に、「『自分の身体なのに、あんなにいい加減にしていていいの』と尋ねたそうである。母の答えは『いいの』で終わったそうで、さすがあっぱれ自称無頼派作家の妻である」となった。 ガン細胞一個の大きさは0.01ミリ。「本物のガンが1センチに成長するまで150カ月かかると言われている」。通常、医者が告知するのは、「ガン細胞が1センチの大きさになってからで、それは10億個のガン細胞になる。もしそれが真性ガンであれば、発見されたときは、すでに他の臓器に転移しているはず」なのだそうだ。 はたして65歳の時に言われた二つの胃ガンは、いつの間にか消えてしまったそうである。それは、もともと人間に備わっている免疫力(免疫細胞療法ではない:編集部)をアップさせることによってであると明言し、その真髄は「ほったらかし療法」にあると。その論理は、「なぜ、病気になるか。それはストレスのせいである。ではなぜストレスが溜まるのか。それは、無理をするからである。無理をしさえしなければ、人にはガン細胞はうまれない」のだと宣言する。 著者は「フィクションを書く作家であるが、信じた医師が書かれたことはしっかり理解している」という。自らが納得できる治療法を求め続け、再生医療、成体幹細胞、樹状細胞ワクチン、免疫細胞療法、iPS細胞等々についての考えを示すとともに、最後に「期待される患者像」、そして「免疫力で蘇る」として自分が信ずる「ほったらかし療法」の「秘伝」を明かしている。仏教の戒からみると「ン?」というのもいくつかあるが、ストレスをなくす方法として納得できるものもある。仲間とか食のこととならんで、なかにはいわゆる「願望実現」の瞑想に似ているものもあったりする。 いずれにしても、「本当?こんな考え方も『有り』なの!」という点から本書を紹介することにした。最後に「無名の担当者へのお礼の言葉」として著者は次のように記している。 「人生はたいしたことはないけれど、なにごともあっさりと愛してみよう、と考え方を変えてみることで、美しく見えてくることがあると思う」。なんとなくだが、ウペッカーにほんのりと近づいているように見えた。(雅) |
| 『方丈記』(詠嘆的無常観)から『徒然草』(自覚的無常観)へ ~芥川龍之介と夏目漱石に触れつつ~ |
| およそ100年を前後し生きた鴨長明と吉田兼好。
彼らが生きた鎌倉時代、「飢饉」「火事」「台風」「地震」などが立て続けに起こり、その惨状が凄まじい。「わびしれたるものども、歩くかと見れば、すなはち倒れ伏しぬ。築地のつら、道のほとり、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず。くさき香世界に満ちて・・・。母の命尽きたるを知らずして、いとけなき子の、なほ乳を吸ひつつ、臥せるなどありけり」。大火事においては、都の半分近くが灰燼となり、数百人が一夜にして死んだ。「吹き切られたる焔、飛ぶが如くして、一、二町を越えつつ移りゆく。煙にむせびて倒れ伏し、或いは焔にまぐれて忽ちに死ぬ」。 またこの時代は宮廷王朝が滅び武家社会へと移りゆく大動乱時代でもあり、人心は闇に沈んだ。当時の人々の様子を『二條河原落書』に見ると、「このごろ都にはやるもの、夜盗、強盗、生首、成らず者、にせ綸旨(偽文書)、早馬、虚騒動、還俗・・・」という叙述が続く。 次々と起こる大災害、人心の乱れ。目の当たりに、まさに人の世の無常、苦を突きつけられた長明と兼好。彼らはその実感を吐露する。 「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて久しくとどまるためしなし。」(長明) 「人はただ、無常の身に迫りぬる事を心にひしと掛けて、つかの間も忘るまじきなり」(兼好) そうした無常な世においては「人の営み、皆愚かなる中に、宝を費やし心を悩まず事は、すぐれてあぢきなけてぞ侍る」(長明) 「人はおのれをつづまやしやかにし、奢りを退けて財を持たず、世を貪らんぞいみじかるべき」(兼好)など「捨」の心も自ずと生じていったようだ。 やがて長明は小さな方丈の草庵へと籠居していく。一方、兼好は特に定めて常住することなく、いくつかの寺院を渡っていく。二人は出家の心持ちをそれぞれ次のように述べている。 「いづれの所を占めて、いかなるわざ得てか、しばしもこの身を宿し、たまゆら心を休むべき」「今、方丈の草の庵、よく我が心にかなへり。故に万物を豊にして、憂れはしき事、さらになし。」(長明) 一方、「実の大事は、たけき河のみぎり流るるが如し。しばしもとどこほらず、ただちに行ひゆくものなり。されば、真俗(出世間・俗世間)につけて、必ず果たし遂げんと思はん事は、機嫌をいふべからず。とかくのよひもなく、足を踏み止むまじきなり」(兼好) 長明は出家草庵生活に没入し、兼好は必ずしもそこに留まらない。 ここより、さらに両者を対比していくが、ここで『方丈記』が影響を与えたと言われる芥川龍之介に触れてみる。 実は、芥川龍之介は『方丈記』の相当な愛読者だった。龍之介の母が「いつもポケットに入れている本、何だえ、それは?」と尋ねると「これですか?これは『方丈記』ですよ。僕などよりもちょっと偉かった人が書いた本ですよ」。小説『羅生門』の冒頭など、『方丈記』「養和の飢饉」の描写然としている。龍之介は、長明から描法はじめ思想においてもかなり影響を受けていたようだ。その龍之介は、とてつもない厭世状態からくる神経症の渦中、自殺したことは知られる通り。 自殺に関して、原始仏教では、「嫌悪や不満は人を自己破壊へ導く病気」(『沙門果経』サンガ文庫のスマナサーラ長老より)と捉えている。龍之介はその最たるところへ自らを追いやった。思うに、龍之介が傾倒する長明が何かしらその背中を押してしまったことも少々あろうかと。 長明は、その生涯を収めるべく、方丈庵で隠遁生活に入った。そこで『方丈記』を著わすが、そこで、厭世気分に見舞われた、なすすべもない姿が垣間見られる。「今、草庵を愛するも、閑寂に著するも、さばかりなるべし(そうなるべくしてなったものだ)」。このくだりは、元の俗世間に戻ることはないという意思表示。それは精進故ではなく、草庵への執着からに他ならない。この草庵において「要なきこと(世の中のあれやこれや不要なこと)を述べて、あたら時を過ごしたり」と『方丈記』を結んでいる。そこでは、無常を傍観し嘆くだけの不満げな遁世者の姿が見えてくる。そんな長明の有り様は龍之介の厭世感をひたすら鬱積していくだけだっただろう。 一方、兼好も出家し草庵に入った。しかしながら、次のように語る、「世をそむける草の庵には、閑かに水石をもてあそびて・・・いとはかなし。閑かなる山の奥、無常の敵競ひ来たざらんや(死がやって来ないことあろうか)。死に臨めること、軍の陣に進めるにおなじ(死に直面していることは、武士が戦陣に進んでいるのと同じである)」。長明とは草庵中の思いが大きく異なる。すなわち、草庵は生死の戦いの前線だと。 「世は定めなきこそ、いみじけれ。」(兼好)という言葉に、無常を腹に落とし込む凜とした姿を見てしまう。「人、死を憎まば、生を愛すべし」。無常の認識に徹する時、生きる尊さが照射されてくる。さらに「一日の命、万金よりも重し」と語る。原始仏教では「人は成長すべきである、とは仏教の基本的なスタンス。成長の頂点は解脱に達すること。」(『沙門果経』サンガ文庫のスマナサーラ長老より)と言う。兼好は、この尊い一日一時を、仏道に生きることを唱える。 兼好は出家に際して、「吾が生既に蹉陀たり(起こるべきして起こった苦あり)。諸縁(世俗の縁)を放下(捨て去る)すべき時なり」と、迷いない言葉を吐く。「おなじ心ならん人、さる人あるまじ」の語りは、ブッダの「一人犀の角のごとく歩め」の体だ。 夏目漱石に触れたい。漱石も『方丈記』を読み、親友の正岡子規に書簡を送っている。「此の頃は何となく浮き世がいやになり、どう考えても直してもいやでいやで立ち切れず、人生は夢幻の如しといふ位な事は疾から存じて居ります。“知らず、生まれ死ぬる人、何方より来たりて何方へ去る”と長明の言は記憶すれど、悟りの実は迹方なし(悟りの実相はない)」と。長明の言を借りて、世の儚さ無常を嘆く漱石がある。この後、漱石は『三四郎』『それから』『門』と三部作を著す。そして、この物語は、主人公が最後に仏門を叩いていくところで終わる。無常、苦の認識は、いかなる時代でも仏道へと向かうのか。そうして、『明暗』へ、「則天去私」へ展開。これは、因果の流れに身を処す仏道の「全託」のあり方ではないか。この姿が、兼好に重なってくる。 「命は瞬間、瞬間消えていゆく」(ブッダ)。兼好は、無常を自覚し、仏道を歩み、その生き様を因果の流れに委ねていく。長明のように、無常の詠嘆に留まらない。兼好は、無常を冷徹に自覚する。そして「瞬間」を生き抜き、その因果を受け、次の「瞬間」を生き抜き、次のその因果を受け切っていく。無常から遁世せずに、無常にうろたえずに、「瞬間瞬間」立ち向かう。あとはあるがまま、とのメッセージを発しているようだ。「一時の懈怠、即ち一生の懈怠となる」。「人はただ、無常の身に迫りぬる事を心にひしとかけて、つかのまも忘るまじきなり。さらば、などかこの世の濁りも薄く、仏道をつとむる心もまめやかならざらん(真剣にならないことがあろうか)」(兼好) とはありながら、肩肘張らず、軽やかにもあれ、楽しめとも言っている。「人事(いろいろなこと)多かる中に、道を楽しぶ気味深きはなし(仏道精進を楽しむような味わい深いものはない)。この実の大事なり」。無常であるこの世だからこそ仏道を楽しめ、とは逆説的だが、まさにそうだろう。スマナサーラ長老もよく言うことだ。世の無常はネガティブに見える。ところが、認知を変え、ポジティブに見ればそう見えてくる。どちらがいいか。兼好の次の言葉で締めくくりたい。 「折節の移り変るこそ、ものごとにあはれなれ」「万の事も、始終(生滅)こそをかしけれ」 「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」。(Y.T.) |
| 池田清彦著『環境問題のウソ』筑摩書房 2005年 |
| ダイオキシンは本当に危険なのか、外来種は悪玉なのか、今の自然保護のありかたは? 著者は一つ一つにデータをあげながら疑問を呈し、この社会がそれらの問題点を取り上げる姿勢に間違いはないかと鋭く指摘する。なかでも、地球温暖化の主要因ははたしてCO2なのか、CO2を削減しさえすれば温暖化にブレーキが掛かるのか、それには明確にNOを突きつける。 去る9019年9月23日、ニューヨークで行われた「国連気候行動サミット」でグレタ・トゥーンベリさんは訴えた。「・・・人々は困窮し、死に瀕している。すべての生態系が崩壊し始め、私たちは大規模な絶滅を前にしています。それなのにあなたたちは、お金と永続的な経済成長という『おとぎ話』ばかりを語っている」(「毎日新聞朝刊」2019/9/25より)。国連本部の総会ホールは静まりかえったという。 世界の自動車販売台数が年間9000万台を越えていたり(2018年)、生活のための膨大なエネルギー利用が大気に影響しないはずはないだろうと素朴ながらそう思うし、自分の住む地域(東京)でも子供の頃と近頃の冬の寒さの差は確かに実感される。しかし、それをただちにCO2に起因する「地球温暖化」というグローバルな観点に結びつけることが、疑問の余地がないほど絶対的に正しいのだろうか。 先の新聞には同時に、「学校で気候変動を教えること自体は問題ない。だが、(温暖化を警告する科学者とそれに懐疑的な科学者の)両方がいることを教えるべきだ」とする研究者の意見も載せている。地球温暖化がCO2の排出の増大によって起こされているという見解が異常気象と関連づけて常識のようになっているが、はたしてそうなのか。著者は、「温暖化脅威論は地球規模のマインドコントロール」(薬師院仁志による)という意見に賛意を示し、温暖化のCO2原因論にデータを示しながら反証する。 どのような見解を持つにしても、硬直した見方は何ごとによらず望ましいことではないと思う。たとえ多くの人が言っていることであっても、出来るだけ幅の広い情報をもとに自分なりに考え、客観的な視点を持とうと努めることはとても大切なことではないか。この問題を含めて著者は、冒頭であげた4つのテーマについて徹底的にデータに基づいた考察を行っていて、少なくとも本書を読んだ後では、これまで特になにも疑うことなく「そうなのか」と思っていたことが、単に無批判的に取り入れていたに過ぎなかったのではではないか、ということを改めて感じさせられた。 著者は1947年生まれの早稲田大学名誉教授、専門は生物学、「帯には多分野にわたって評論家活動を行っている」とある。10年以上前に出版されたもので、還暦目前に執筆されたものだが、その主張はきわめて歯切れが良い。ここでは4つのテーマのうち、第1章に絞って紹介することにしたい。 第1章の流れはこうである。まず、「地球温暖化は本当なのか」として、都市の気温と田舎の気温の推移からみると、地球規模の温暖化(グローバル・ウォーミング)ではなく局地的な温暖化(ローカル・ウォーミング)ではないかと言う。地球規模の温暖化という点では最も有名なデータとしてGISS(NASA・ゴダード宇宙研究所)の数値があるが、そもそもそのデータの取り方(アメリカやヨーロッパに偏っていて海の上はほとんどない)にも問題があって、その信憑性に疑問が呈される。そして、地球をよりくまなく測っている衛星のデータからは、「地球の気温がうなぎ登り上がっているという巷に流れている言説は、それほど信用できるものではなさそう」だと言う。 また、20世紀に都市部の局地的な温暖化が起きていたのは確かだとしても、それがCO2の排出の増加によるものかどうかはまったく不明であり、「温暖化は昔もあった」として、木の年輪測定から昔も今と同じくらい暖かい時代もあり、あり寒い時代もあったことを明らかにしている。なかでも興味を引かれるのは、中世温暖期と言って10世紀から12世紀はかなり暖かかったらしく、10世紀にノルマン人に発見されたグリーンランドは「当時は草や木が生えて綠におおわれており、そこからグリーンランドの名前がついたという」し、いくつもの農場さえあったのだが、「16世紀までには絶滅したとのこと」で、それ以後、雪と氷の世界になったと推測している。 17世紀は気温の極小期で、ヨーロッパではアルプスの氷河が前進し、日本で1780年代には両国川や浅草川が結氷したという記述も古文書に残っているそうである。著者の近くの高尾山に元禄時代に生えたブナの大木があるそうだけれども、今は暖かすぎて若いブナが育たなく、自然には更新されないと言う。 いずれにしても、15世紀の温暖現象はCO2の人為的な排出によるものではなかったことは確かなので、もし現在の温暖化(や1970年頃の寒冷化)が、「よし事実だとしても、自然のサイクルの枠内に収まる現象と考えてはいけない理由はない」とする。 また、水温によって水を構成する分子の微妙な違いから、サンゴの殻を分析することでその時代の水温を推定することができる。それによると、気温の変動パターンが陸上のそれとは一致せず、地表表面の温度を決める要因は複雑であって単純ではないことを挙げている。さらに、地表の気温が変化するとそれが熱伝導で地下深くまで伝わることから、グリーンランドの氷に穴をあけて壁の温度を調べた研究があり、その結果、17世紀は現在より1度ほど低く、10世紀は1度以上高かったことが分かり、古文書の記録と良く一致していると言う。 あるいは、8000年前から5000年前のエジプトや黄河流域で古代文明が生じた時期は、「ヒプシサーマル期と呼ばれ、昔から暖かかった時期としてよく知られている」し、青森県の三内丸山遺跡で縄文期に栗を栽培していたのもこの時期である。私も、この縄文期の気候は、かつて学校で「縄文海進」として、貝塚などの遺跡が内陸にあることなどにとても興味をもったことを思い出す。 さらに長いスパンで見ると、「ここ数百万年単位で見るならば、地球は寒冷化している」が、そういったなかでも温度は「4万年と2万年の周期で変動し、「100万年以降はこれに加え10万年周期が出現している」という。さらに遡れば、恐竜の栄えた中生代白亜紀の平均気温は今よりも6度も高かったことが知られている。 そして、CO2の濃度のデータを見ると、その上昇と気温の上昇が相関している1880年頃から1940年頃まで(もちろん相関=因果関係とは言い切れない)と、その濃度が急激に増大し1940年から70年までに地球の平均気温が0.2度下降したのとはまったく矛盾している。ちなみに、1940年頃まで全世界の年間炭素排出量はせいぜい10億トンだったものが、70年には40億トンとなっていた。 このほか、温暖化は水蒸気、CO2、メタン、オゾン、フロンガス、N2O(亜酸化窒素)などの温室効果ガスによるが、温暖化への貢献ではこのうち水蒸気が最大で90%を占めている。それに加えて、地表から出て行こうとする熱の95%以上はすでに存在する温室効果ガスによってブロックされて地表方面に再放射されているという。「という意味は、温室効果はあと数%で飽和に達し、温室効果ガスがどんなに増えてもそれ以上は温暖化しないということだ」として、「気候の変動はCO2 の人為的排出が始まる前からあったわけだから、他に原因があると考える方がはるかに合理的だ」と結論づけている。 そしてその原因は、太陽の活動がおおよそ11年周期で変動することにあって、その間、可視光の放射は0.1%くらい、紫外線では1%、X線では100倍ほども変化するという。アメリカのライドによる黒点数と北半球の平均気温が相関するという論文もあり、「1989年に発表した気象庁のレポートには『地球全域の平均海面水温の長期変動は、太陽黒点数の長期変化とよく似ている』と書かれ」ていて、過去120年あまりの変動グラフによると、「太陽黒点数が増加した時には水温が上がり、減少した時には水温が下がっていることがよくわかる」。 また、17世紀半ばから18世紀前半までの70年間の寒かった時期には黒点がほとんど消えてしまっているし、10年から14年と変動する黒点数の増減幅を変数として使うとさらに気温変化との相関を示していると言う。つまり結論として著者が最も強調しているのは、太陽の活動こそが気温変化に大きな影響を与えているのであり、CO2の影響はあくまでマイナーに止まる(下線は編集部)ということ、そして、莫大なコストを使ってそれを規制するのは、「健康のためと称して高価な薬を投与してコレステロール値をほんのわずかさげているようなものかもしれない」と結論づける。 この章の最後には「温暖化で何が起こるか」として、気温そのものの上昇よりもそれがもたらすさまざまな作用として懸念されている海面上昇、異常気象、健康被害、農業への影響があげられている。 海面上昇については、過去30年の日本の各地での海の水位は、東日本では数㎝下がり、西日本では数㎝上がっているという。また、「世界的に見てもここ数十年の海面上昇はほとんどない」。IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の予測では、今後100年間に9~88㎝海面が上昇すると言うが、「9㎝ならば別に大したことはないし、88㎝も上昇したら、京都議定書程度のCO2の排出規制じゃ焼け石に水」であり、明日から、CO2の人為的排出は一切しなければ多少の効果があるかもしれないが、それでは海面の変動よりも先に人類の文明が終わることになる。 また、異常気象については、IPCC1996年の報告書に「全体として、20世紀を通じて異常気象、すなわち気象可変性が増加したという証拠はない」となっているそうで、むしろ森林の伐採などによる影響によって洪水などが起きているのである。つまり、「要するに異常気象がどんどんひどくなるなんていう話は、いかなる科学的根拠もないインチキ話なのである」と。 健康被害について、環境庁のマンガに、「マラリアなど熱帯のだけの病気が日本にもやってくるかもしれないのだ」と書いてあるそうだが、これも温暖化とは関係ない。日本でも昔はマラリアがあった(平清盛の死因がマラリアによる高熱だったという説があり、『源氏物語』でも光源氏が瘧〔オコリ、ギャク:マラリアの一種〕にかかって苦しんだという:編集部)し、小氷期でさえヨーロッパやイギリスからマラリアはなくならなかったそうで、20世紀初頭にはアメリカでも蔓延していたと言う。また、エイズ、鳥インフルエンザなどのさまざまな伝染病もグローバリゼーションが急速に進んだためであって、つまりは衛生環境次第なのである。 農業についても、それは、温暖化とCO2濃度の上昇とによって、熱帯から寒帯における国々への影響はさまざまであり、特に熱帯地域で高温に強い品種の改良がなされれば、世界全体の穀物生産量への影響はむしろプラスになるのではないかと言う。 最後にCO2削減のコストについて論じ、炭素排出量の制限ばかりに目を向けた「京都議定書が完璧に実行されたとしても、100年後の気温上昇をほんの6年ほど遅らせることができるだけ」であり、むしろそれを太陽光や風力など、代替燃料の相対的なコストをなるべく早く化石燃料以下にすることや、「途上国の様々なインフラ整備に使った方がずっと効率よく温暖化対策を実現できる」はずと提言する。 そして著者が「独断的」とする予想では、「地球の温度は直線的に上昇するなんてことはなくて、あと十数年か数十年かしたら下降するに違いないと思う。そうなったら政府もマスコミも地球温暖化論などはすっかり忘れて、氷河期が来る、と言って騒ぐんだろうな」と言うことになる。 このあと、冒頭にあげたダイオキシンについて、外来種問題、そして自然保護についても同様のスタンスで鋭くかつ諧謔的に論じている。 著者には本書の他にも多くの著作があり、その一部を紹介すると、『ほんとうのエネルギー問題』(KKベストセラーズ 2008年:エネルギー)、『新しい環境問題の教科書』(新潮文庫 2010年:温暖化問題と洞爺湖サミット、生物多様性、人口と環境問題)、『ほんとうの環境白書』(角川学芸出版 2013年:原発、エネルギー、温暖化、感染症、自然保護、など)、『この世はウソでできている』(新潮社 2013年:「健康のため」「安全のため」「環境のため」というウソ)等々。 とくに、『この世は・・・』では、「言語を統一しようとすることは、当然ながら、一種の他者コントロールである」とか、誤報をきっかけとした「ダイオキシン法」の成立などをはじめとする民主主義を始めとするこの世の仕組み、健康や安全をめぐる科学を装った言説などに続いて、なぜ現代人はウソを信じやすいのかについて述べていて、心したいと思う。 確かに、私たちが今話題とされる環境問題について関心を持つのはとても大切なことだと思うが、いわゆる流布されている話しをそのまま受け入れて自分の意見とするのではなく、一度は「はたしてそうなのか?」と考えてみることが大切だと思う。そのような意味で、視野を広げてくれ既成の概念を再考させてくれる一冊であった。(雅) |