![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
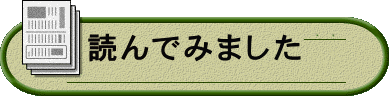
2019年1月~6月

|
| 『宿命の戦記 ―笹川洋平、ハンセン病制圧の記録―』高山文彦著 (小学館 2017年) |
| 「すごい人がいるな!」と思わせた本書は、地球規模でハンセン病の征圧に全力を注いでいる日本財団会長笹川陽平氏の活動に、足かけ7年間20カ国で密着取材した大部の記録である。1年の3分の1を海外活動に充てている笹川氏の差別撤廃の運動は、「国連総会決議に結実し、各国に提示するガイドラインも承認された。彼がいなければ、各国のハンセン病対策と差別の緩和は100年遅れただろう」と著者は述べている。氏は2001年にWHOから、国連大使と同級の立場と権限を有するハンセン病制圧大使に任命された。 すでに知られているように、ハンセン病は癩菌によって生じる病気であり、伝染率のきわめて低い伝染病で、1981年に3種類の薬を同時に処方する多剤併用療法MDTが開発され、現在ではほぼ完璧に治癒可能になっている。1995年から99年までの5年間、日本財団がこの治療薬を無償提供し、200年以降はMDTを作っているスイスの製薬会社ノバルティスが無償提供を引き継いでいる。 しかしながら、ハンセン病それ自体では死の原因とはならないが、侵された患者は姿形、外見が著しく崩れていく。そのため日本では業病とされたり、キリスト教世界では神の罰といった差別を受けてきた長い歴史がある。 笹川陽平と日本財団は、1974年からハンセン病制圧運動に本格的に乗り出している。彼を動かしているのは何か。それは差別に対する怒りであり、差別との戦いであると言う。 「僕がこうして世界各地を回ってハンセン病の撲滅、差別の撤廃を訴えているのは、(中略)父が受けた差別を晴らしてやりたい、と言う思いがつよいからなんです」。彼の父笹川良一は、右翼の大物、A級戦犯(正確にはA級戦犯容疑者であって無罪放免された)、博打の胴元をやってその金で慈善事業・・・という具合にマスコミからこぞってレッテルを貼られていた。 彼は父に名誉毀損で訴えましょうと何度も言ったという。「そのたびにあの人は言うんだ。おまえ、なに言ってんだ。書くやつらだってメシ食って、女房子どもを育てなきゃならないんだぞ、てね」。良一氏には自分が差別されている意識はなかったという。彼は、父に対するレッテル貼りがいかに虚妄であったかを明らかにするために、東大の伊藤隆氏に依頼して7年掛けて父の資料を整理していった。誤ったレッテルで差別された父を正しく理解して欲しい、彼の事業はこの情念から出発している。それが、「するどい感性に裏打ちされた実感豊かな行動となり、(中略)力強いメッセージ性を帯びるであろう」と著者は記している。 笹川氏のブログ(2017年2月8日)によれば、「記録に残っている1982年から2016年までの34年間に訪問した国・地域は119カ国、海外出張回数は466回、滞在日数は2954日、面談した国王・大統領・首相は181人を数える」という。本書の著者が本書でレポートした国、地域名を列挙すれば、インド、エジプト、マラウイ共和国、中央アフリカ共和国、ブラジル、ロシア、キリバス共和国、バチカン市国、そして中央アジア、西ヨーロッパ各国である。 行く先々では、直接患者に触れ、抱き合い、時には優しく激励し、また時にはそこでの為政者、担当者に対して厳しい言葉をかけている。 エジプトでは、テレビ局のインタビューで、「人類はたくさんの過ちを犯してきました。わけてもレプロシーの問題は、人類史にとって大きな籠の歴史です。人間として認めてこなかった。こんなことがあっていいのか」。そして老人の手をなぜながら、「この人の手はあたたかいし、血が通っています。こうして握っていても、病気は決してうつりません。まして、神様の罰だなんて信じたり言ったりすることは大きな間違いであると、テレビを見ているみなさんによく知っていただきたいのです」。そして、「社会は治った人を受け入れて欲しい」と。 成功例がある。インドのチャティスガール州ライプールでのコロニーでは、優秀なりーダーによって立派な成功例が生まれている。 「回復者代表のボイ氏が、その隣から顔を出して、 『ここのコロニーは、じつはたいへん素晴らしいところなんです。お医者さんがふたり生まれています。IBMでソフトエンジニアをやっている人もいます。博士もでています』 『へえ、そうなの』 『それだけじゃないですよ』と、運転手氏が付け加えた。 『外の町から健康な若い女の子がやってきて、尊敬するコロニーの若い男の子と結婚しました』 『へえ、そんなことがあるの!』陽平の声は絶叫に近かった」。 インドでは、ダリット(自分たちの呼び名。マラティ語で「砕かれた者」「虐げられた者」という意味。アウトカースト)に属せられた若者が、どんなカーストにも属さない職業のIT技術者を目指すのは当然なのだ。 もちろん成功例ばかりではない。むしろこちらの方が多く、より深刻である。訪問先で元、現罹患者のインタビューが行われているが、その一つ、ブラジルアマゾンの奥地でその人たちが受けてきた扱いは、「収容所(このように彼女は言い換えた)の生活は、動物と変わらぬような」ものであった。これらり類する事例はとても膨大で、本書のあらゆる所に取り上げられており、とてもここで紹介し切れるものではない。 「制圧」とされるのは、1991年にWHOが示した、「国民1万人当たりの患者数が1人を下回った状態」を指していて、これを達成すると拡大を押さえ沈静化できるとされている。しかし、国全体のデータはそうであっても、州や地方によってその数字は大きく異なっているのが普通であるし、また調査が進んでいないために低く出ている場合もざらである。表に出ない患者数はまだまだ多く、毎年新しく患者も発見され続けている。調査と正確な情報がいかに重要性か、本諸で繰り返し強調されているのもそのためである。 ハンセン病対策には、国や地方組織の対応が肝心であり、またそれに熱意を持つ人々がいるかどうかに大きく左右される。消極的な政府要人もいれば、その反対に積極的に取り組む為政者、そして献身的な医師、看護師、その他たくさんの人々がさまざまな人間模様を見せている。 最後に、高山氏によって書かれた補遺は、この病に対する日本の歴史をめぐって詳細な考察がなされており、それだけでも一読する価値がある。また、家族関係者の国に対する集団訴訟に関しては、ものの見方のバランスという点から考えさせられた。 大部にも関わらず中身が非常に濃く、かつ多様で幅広く大量の情報が含まれている本書は、やや無謀とは思いつつあえて紹介したいと思った。なぜなら、もし自分であったら、家族であったら、知人であったらどうか、そして、無差別平等の厳しさについて考えさせられる一冊だったからである。(雅) |
| フランス・ドゥ・ヴァール『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』 (紀伊國屋書店 2017年) |
| 一度読んでそのままという本が多い中で、本書は繰り返し読んでみたいと思うほどとても密度が濃いものであった。翻訳者による解説によれば、本書は、人間と動物の心の働きを科学によって解明するきわめて新しい「進化認知学」の入門書ということだが、そのバラエティの豊富さには驚かされる。
「人間の認知は動物の認知の一種」であること、これが本書の一貫した主張であり、その裏付けになる実験、観察に対して適切な解釈を、また論拠となる諸文献も正しく提示されている。もし人間が持つ理性や意識が他の動物たちに微塵もなく、それらの根拠を知る足掛かりが人間以外の自然界に全く無いとしたら、それは、「人間の心を空白の進化空間に宙ぶらりんの状態に置き去りにすること」に他ならない。著者が自分の研究所を、ミッシング・リングに引っかけて「リヴィング・リンクス・センター」と名付けている理由もそこにある。 著者はエモリー大学心理学部教授、ヤーキーズ国立霊長類研究センターの当該センター所長、ユトレヒト大学特別教授で、数々の著作があり、チンパンジーやボノボの研究者として広く知られている。本書で扱われているのは霊長類からはじまり、ゾウ、犬、猫、カラス、オウム、タコ、イルカ、等々、多岐にわたり、それも行動によるだけではなく、はてはfMRI(機能的磁気共鳴画像法)による犬の脳領域の機能までを紹介している。 著者が本書で言いたいことは、(1)動物の認知には唯一の形態などはないこと、(2)ある種に備わった認知能力は一般にその種が生き延びるに必要なだけ発達すること、(3)従って、認知能力の格付けなどは意味がなく、技能は灌木状に特殊化していると想定すべきこと(思考に言語は必要としない)、(5)なので、人間と非人間という分け方は相応しくないし、それは程度の問題であること、等である。 ところで、動物の視点から見えるものを「ウンヴェルト(環世界)」と言うが、それは、生き物の、自己を中心とする主観的、断片的な世界なのである。したがって、私たちが見ている自然は、「私たちの探求方法に対してあらわになっている自然に過ぎない」(ヴェルナー・ハイゼルベルク)のであって、それは、認知の仕方が種によって異なるということを表している。 著者によれば、認知とは、「感覚入力を環境についての知識に変えるという心的変換と、その知識の柔軟な応用」と定義される。その内容は、紫外線を知覚し、匂いの世界で生き、触角を頼りにする、超音波で位置を知る、などなどきわめて多様である。ミツバチは尻振りダンスで遠くの食物のありかを教え、ハイイロホシガラスが秋に何平方キロの何百カ所に2万個以上蓄えておいた松の実の大半を冬と春の間に見つける力、それに沿った定義である。 特に根拠はないけれども、私は長い間、アダムとイブが食べた「知恵の実」というのは、「時間の発見」のことではないかと思ってきた。過去や未来の発見がいかにも人間にふさわしいし、動物は「今の瞬間」に生きているのだと。しかし、5年計画を立てたりする犬や猫はいないだろうけれども、近未来を考えて過去の経験をエピソード記憶(いつ、どこで、なにを)として現在に生かすチンパンジーの観察には驚きであった。そして、「霊長類や鳥類が未来を指向する証拠の蓄積があり」、人間だけが心的時間旅行をするのではない多くの事例が提示されている。 もちろん種によって持っている能力は異なっている。本書で挙げられている動物の特性をできる限り列挙してみよう。 自己認識、道具使用、推量、模倣、計画、喧嘩、遊び、嫉妬、出し抜き、欺き、仲直り、駆け引き、相互理解、利他行動、共感、連携、三者関係の認識、分割支配戦略、協力、仲裁、共同作業、分かち合い、等々である。 さらに、先を考え、情動を抑制し、自制して欲求の充足を先延ばしし、欲望制御の時の転移行動を行う。事前の知識から洞察力のある解決策を探る。問題の把握と解決策を思いつく。論理的繋がりを探す。道具とその組み合わせが閃く。道具セットを使って別の道具を作る。移動時間を計算する。メタ認知をする。政治的戦略を用いる。体勢に順応する。仲間を救う。苦しむ仲間を慰める。行動の結果を検討し、他者の視点を獲得する。不公平を嫌う(チンパンジーは相棒より少ない報酬しかもらえない時だけでなく、多くもらった時も異議を表明する)、等々、目白押しに興味深い知見が挙げられる。 これを見ると、まさに人間も動物の一種であって、人間の認知だけが特別だなどと言えるものではないようだ。「上は神や天使、人間に始まり、他の哺乳動物、鳥類、魚類、昆虫類へと徐々に下がって、一番下の軟体動物に行き着く」という上等、下等という「自然の階梯」に沿って認知能力の序列付けは何の意味も無い。私たちは、動物にどんな知能があるのかを問う前に、「その可能性を阻もうとする気持ちを克服しなければならない。したがって、本書の核をなす問いは『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか?』となる」というわけである。 有名な事例として、幸島でニホンザルの芋洗いが広まっていく過程から知られた学習と世代間に受け継がれる社会的伝統など、かつては人間、あるいは少なくともヒト科の動物だけのものと思われていた能力が、実は広く行き渡っているのである。「認知の波紋は類人猿からサルへ、イルカへ、ゾウへ、犬へと広がり、鳥類や爬虫類、魚類も呑み込み、ときには無脊椎動物にまで及ぶ。この歴史的進展を捉えるにあたって、ヒト科の動物を頂点に頂く尺度を念頭に置いてはならない。私の見るところでは、むしろそれは果てしなく拡大を続ける可能性の宝庫」であると、本書で著者は熱く記す。 このほかにも、人間の言語、年齢、性別についてゾウの認知、大人のオスのオランウータンの行き先についての12時間前の告知、イルカの「シグネチャー・ホイッスル」(個体ごとに特有の抑揚の付いた高音)は名前と見なされること、思考は言語を必要としないこと、大きい集団で暮らす霊長類ほど一般に脳が大きいこと、頭足類の神経系はむしろインターネットに近いこと、霊長類は自分を取り巻く社会的世界を理解していること、自己認識はタマネギのように一層ずつ積み重ねながら発達していくこと、鳥類の脳は以前考えられていたよりも哺乳類と相似であること等々、きりが無いほどだ。 最後に著者は、「不連続制よりも連続性は人間と霊長類の比較ばかりではなく他の哺乳類や鳥類にも及ぶ」と言い、「動物の認知の研究をしていると、他の種に対する尊敬の念が深まるだけでなく、私たち自身の知的複雑さを過大に評価するべきではないことも教えられる」とし、「真の共感は、自己に焦点を合わせたものではなく、他の種をありのままのかたちで評価しなければならない」と結んでいる。 本書で示されたエピソード一つを取り上げても、それぞれの専門分野で一冊の分量ほどになるのではないかと思われるほどの内容であった。(雅) |
| トーマス・ギロビッチ、リー・ロス著『その部屋のなかで最も賢い人』 (青土社 2019年) |
| 著者のトーマス・ギロビッチはコーネル大学の、リー・ロスはスタンフォード大学のそれぞれ心理学教授。40年にわたる、主に社会心理学と判断・意志決定の分野における研究による本書は、人と社会の心理と行動をさまざまなデータによって明らかにすることを主眼としている。そこには、実に多くの実験や報告の実例が示されており、これまで漠然としていたものに鮮明さを与えてくれる格好の書としてここに紹介したい。
もともと書物に傍線を引くのは好まないのだけれど、本書を読み進めるとおもわずそのことを忘れてしまうような箇所が頻繁に出てくる。そこで、傍線の代わりに付箋に短いメモを書いて貼ってみたが、今度はそのために本の上部が飾りのようになってしまう結果となった。 本書は2部構成になっている。その内容は、「訳者あとがき」で簡潔にまとめられているので、先ずはそれを引用する。 「・・・たとえば本書の第1章では、『自分よりゆっくり車を走らせているやつはバカで、自分より速いやつはイカレてると思ったことはないか?』と読者に問いかけ、私たち人間には、自分は物事をあるがままに客観的にとらえていると思い込む傾向(「素朴な現実主義」)があると指摘する。そのために、正しく認識をしているのは自分の方ほうであり、他の人々の認識か間違っていると決めつけてしまうというのだ。(中略) 本書の前半(第1章から第5章)では、このような客観性という幻想や、選択肢の提示のしかた(オプトイン方式、オプトアウト方式)【注:編集部】が行動にいかに大きな影響を与えるか、行動が感情に影響を与える仕組み(行動の優位性)、イデオロギーや先入観のために物事を歪んで見ていること(偏り/バイアス)など、人間の認識と行動に見られる基本的なパターンを紹介していく。後半(第6章から第9章)では、こうした原則をふまえて、個人や社会が直面する問題(人生における幸福感、成績不振、国家間の対立、気候変動問題)に、どうすれば賢く対処できるかを説いていく」。 私が特に興味を持ったのは前半、第1部であった。 第1章「客観性の幻想」であげられた例には次のようなものがある。「食べものが『辛すぎる』とか『まったく味気かない』とか言うときには、自分の味蕾や、子どもの頃に食べた物、自分の育った文化にある料理についてではなく、その食べものについての意見を言っていると思っている。そして、他の人の意見が異なると、・・・あなたは、この人の好みがこんなに変なのはなぜだろうと不思議に思う」。 これと同じことが、部屋の設定温度、音楽のボリュームなど、「あり得るなあ・・」と思われる例が示され、それらについて、「変わっているのは自分の方だと結論づける事例を思いつくこともできるだろう」が、それは「ただの例外にすぎない」ということだという。なんとなく納得させられたような気になる。 つまり、私たちには「世界に存在する物を感じ取った内容を、主観的な解釈ではなく客観的な解釈であるとして扱う傾向が」あって、それが「人間のあらゆる種類の愚かさの根源」となっているという。そして、「私たちが見ている色は、私たちが知覚する物体の『そこに』あるのではなく、そこにある物と、私たちの感覚システムの働きとのあいだの、相互作用の産物」だということは、まさに認知について言われていることにほかならない。 この章の後半では、こうした見方をさまざまな実験によって検証している。例えば、どこかの単語1つを聞こえずらくしてある文章を聞かせた時には、無意識のうちにその文脈に沿った単語をそこに埋めてしまうということなどである。つまり、人は、示された感覚信号の隙間をそれと気づかずに埋めてしまうのだ。 あるいは、何かの行為をした人が、「私のような立場に置かれて、そうしたシナリオを突きつけられた人なら誰でも、まったく同じことをしたでしょう」という発言をしたとすれば、それは、「他の人たちと自分の見解や行動の選択が同じものになる程度を過剰に見積もっている」のであって、著者はそれを「素朴な現実主義」と名付けている。 メッセージボード(例えば「ジョーの店で食事しよう」と書かれた)を提げてキャンパス内を歩き、出会った人たちの反応を記録するように依頼した実験では、その実験に参加することに合意したか、あるいは断った直後に、他の学生がどうするかの割合を推定し、合意する人と断る人の性格を推定してもらった。その結果は、依頼に合意した学生は合意する人の方が拒否よりも多いと推定し、そうした対応からは個人的な性格はあまりうかがえないと回答したが、断った学生はその逆であった。 また、60年代の音楽と80年代の音楽のどちらかが好きな人の場合、いっそう多くの人が自分と同じ年代の音楽を好むだろうと考えるし、政治的な題材に対しても同じことが働いているという。 このほかにも本章では、いくつかの実験と他のデータ、例えば選挙における客観性とバイアスの関係、自身の個人的な経験の判断に対する影響、討論における客観性、等々、さまざまな素朴な現実主義があげられている。そのうえで著者は、「自分と異なる見解を持つ人は、まったく異なる判断の対象に反応しているのかもしれないと認識できないことから、誤解が深まり、対立が長引く恐れが生じる」と述べ、そしてそこで重要なのは、「少なくとも、事実と解釈についての意見の相違と、価値観や好みについての意見の相違を区別」することが重要であると主張する。 第2章の「状況の押しと引き」では、通りに面した庭の芝生に「『安全運転』と書かれた看板を立ててもらえませんか」という頼みに対する反応の実験に始まる数々の事例によって、「人は状況による微妙な影響をもっと受けやすい」ことがわかり、第3章「ゲームの名前」でも、フランクリン・D・ルーズベルトの署名した法律をとっかかりに、「人がどのようにその状況を解釈するか。(略)すなわち、自身の経験や価値観や目標という観点から見て、さらには関係していそうな社会規範に照らして、状況が自分にとってどのような意味をもつかということ」が重要であるかを論じている。 そして第4章「行動の優越」においては、心の行動の心に対する影響について述べているが、これは、私たちの日常生活のみならず仏教を学ぶうえで大いに参考になると思われる。ここで示された実験のうち二三の例をあげれば、「ペンを噛んで『微笑み』の表情を作らせ、またある実験では、ペソを唇にはさみ微笑みを作らないようにさせた。行動のしかたによってもたらされた手掛かりが感じ方に影響するという考えと合致して、微笑みなから漫画を見た学生たちは、しかめつらに近い表情で漫画を見た学生たちよりも、その漫画をはるかにおもしろいと感じた」という。 また、地球温暖化による脅威については、「質問をしている部屋の温度に変化をつけた。特別に暖かくした部屋で質問された人は、寒い部屋で質問された人よりも、地球温暖化ははるかに深刻な問題であると考えると回答した。実際のところ、暖かい部屋にいて、政治的には保守派あると自認している人たちが、寒い部屋にいて、リベラル派であると自認している人と同じくらい、地球温暖化への懸念を表明した。さらに、被験者たちに地位の高い人や低い人、権力を持つ人と持たない人と関連した姿勢を取らせた時には、テストステロンの濃度とストレスホルモンのコルチゾール濃度の上がり方と下がり方に差が出た。 これを就職の模擬面接に応用した実験では、「面接の前にパワーの強い人の姿勢をまねていた被験者たちは、パワーの弱い人の姿勢をまねた被験者たちよりも、面接において強い印象を残し、仕事を与えるのにいっそうふさわしいと評価された」ということだ。 このように、行動が信念に影響を与えることが示されている一方、また、「ひとたび特定の信念と一致するようなやり方で行動すれば、その信念を指示する気持ちが」涌いてくるという。さらにそれが快楽の体験と関連する脳の領域とも結びついていることが示される。 「被験者たちに少量のワインが与えられた。一部の被験者には、そのワインはボトルで90ドルすると告げられ、残りの被験者には10ドルすると告げられた。高い値段のワインを飲んでいると思っている被験者のほうがワインをより高く評価したということを知っても、みなさんは驚かないだろう。この実験からは、こうした評価だけでなく、fMRIの記録が、被験者が値段の高いワインを飲んでいると思っているときに、快楽の体験と関連する脳の領域において活動が活発になっていることを示していた、ということもわかった」。 第5章「鍵穴、レンズ、フィルター」では、日常生活に見られる判断の間違いは、正しい答えを出すよりも、誤った答えが直観的に簡単に見つかるためであるという。やや長いので、ここでは一つの実験だけ紹介する。 「被験者は、次のような人物について書かれた文を読んだ。 リンダは33歳の独身で率直な話し方をするとても聡明な人だ。学生時代には哲学を専攻し、差別や刑事司法の問題に深い関心をもち、反核デモに参加したこともある』 被験者はそれから、リンダがその後の人生において、さまざまな活動や職業に従事した可能性がどれくらいあるかを答えさせられた。とりわけ、次のような活動や職業に就いた可能性の順位を付けるように求められた。小学校の教師、精神障害者のためのソーシャルワーカー、女性有権者同盟のメンバー、フェミニスト運動の活動家、銀行の出納係、保険外交員、フェミニスト運動を行う銀行の出納係。 回答において目立った点は、ほとんどの被験者が、リンダは単に「銀行の出納係」であるよりも『フェミニスト運動を行う』銀行の出納係である可能性が高いと考えたことだった。リンダは、銀行の出納係について私たちがもつイメージにはしっくりしないように感じられるが、フェミニストの銀行出納係としてのイメージなら容易にわいてくる。フェミニスト運動についてリンダが関心をもっていることを考慮に加えれば(彼女の明らかな政治的傾向についてわかっていることからすれば、その可能性が高いようだ)、この組み合わせはもっとしっくりくる。 だが、ほんの少し考えてみれば、それは正しいはずがないことに気がつく。『銀行の出納係でフェミニストの運動を行う』人は誰でも必ず銀行の出納係であり、したがって、前者のほうが後者よりも可能性が高いということはありえない!」これは論理学の基本である。二つの事象の結びつき(銀行の出納係でなおかつフェミニスト運動を行っている)が、構成要素単体のどちらかひとつ(銀行の出納係、フェミニスト運動を行っている)よりも可能性が高いことはありえない。 しかし、この問題について論理的に検討した後でさえ、間違った回答がなおも正しく感じられる。そのうえ正しい解答はそれほど難しいものではなく、間違った(そして直観的な)解答はあまりに簡単だ。ちょうど、著名な古生物学者のスティーヴン・ジェイ・グールドが語ったように。『私はこの例が特に好きだ。三番めの陳述[フェミニストの銀行出納係]がもっともありそうにないことはわかっているのに、頭のなかにいる小さなホムンクルスが、ずっと飛び跳ねながら私に向かって叫んでいる――『でもただの銀行の出納係であるはずないぞ、説明の文を読んでみろ』」。 そして、「賢い人はどのような段階を踏んで、関係するすべての情報を確実に手に入れるのかさらに、賢い人はどうやってペースを緩め、迫ってくる直感を無視すべき時を見極めるのか。賢明さの重要な要素は、まさに、いつ直感を信じ、いつ用心深くあるべきかをしることなのだ」と結んでいる。 このほか、まさに仏教の「見」の見本となるようなもの、正しい評価を下すための事例、予言の自己成就の例、等々、スペースがいくらあっても紹介しきれないほど内容が膨大で、かつ興味深い。 第2部では、個人や社会が直面する重要な問題について述べているが、ここでは簡単に紹介するにとどめる。第6章は、人間の幸福を心理学的にどう捉えるか、第7章は自分の欲求と意見の異なる人々の欲求との対立について、第8章は教育における難題、第9章は、気候変動というさらに大きな難題について論じている。 おおかたの本は図書館から借りて読んでいるけれど、本書だけは例外的に購入してしまった。なぜかというと、内容的なことに加えて繰り返し読むことで新しい発見がありそうに感じたからである。今回は引用があまりに多くなってしまったが、それは、解説を加えるより直接的に面白さが伝わると考えたためである。人の行動とその心理について興味を持たれる方、あるいはそのことを話題として取り上げる機会のある方々にはぜひお勧めしたい一冊であった。(雅) 【注】多くはインターネットと関連するかたちで使われているが、ここでは、オプトイン(opt in)とは、自らの意志で参加を表明すること、オプトアウト(opt out)とは、参加をやめることを表明しない限り同意している、と言う意味で使われている。(編集部) |
| 近藤恒夫著『薬物依存を越えて -回復と再生へのプログラム-』 (海拓社 2000年) |
| 最近も有名人が逮捕されて、薬物依存症について再び世間の注目が集まっている。
「わかっちゃいるけど、止められない」依存症について強い関心を抱いている。私自身、お酒とタバコの依存を止めたいと心底願いつつ、全く自分の意思でコントロールできない苦しさを15年間経験したからだ。 『薬物依存を越えて』の著者近藤恒夫氏は覚醒剤依存症に陥った一人だ。壮絶な覚醒剤の依存症から抜け出し、薬物依存症者の回復施設ダルクを日本で創設した。 著者は秋田県に生まれた。後に離婚して家を出ることとなった母は、武家出身の厳格な祖母とずっと険悪な間柄だった。著者が5歳の時に、精神的に追い詰められた母に喉もとに出刃包丁を突きつけられた経験をする。 高校生になると競馬や競輪などのギャンブルにのめり込んでいた。大学入学時に預けた預託金ほしさに勝手に大学を中退し、預託金20万円をギャンブルにつぎ込んでしまう。社会人になると仕事や女性にものめり込んだ。 覚醒剤を勧められて、いつでも止められると思い気軽に始めてしまう。短期間のうちに尋常ではない勢いで覚醒剤のとりこになってしまった。覚醒剤を覚えた3カ月後には、トイレに行くのもおっくうになり台所で用を足すほどの状態となってしまう。当然、仕事もクビになった。次に、兄の会社の仕事を手伝うが、会社のお金を覚醒剤購入のために使い込み、倒産に追い込んだ。 薬物依存に気づいた家族から再三にわたって覚醒剤を止めるように言われたが、「こいつらがいるから覚醒剤が自由に使えない」と感じ、「家族を殺したい」とまで思うこともあった。著書の中では・・・ 「おふくろが夜寝るときには、必ずサイフと預金通帳を腹巻に入れていた。通帳を見つけられたら、覚醒剤を買うために使われてしまうと思っていたのだろう。また、夜になると台所の包丁が全部どこかに片づけられてなくなっていた。私がシャブで狂って包丁を振り回すのではないかと、不安と恐怖の毎日を送っていたのだと思う」・・・と当時の状況が語られている。 犯罪も犯しかねないギリギリのところで、「薬物依存は病気だから」と家族に説得されて病院に入院する。初めての一時帰宅で自宅に隠していた覚醒剤をネクタイの後ろに隠し、睾丸の下に注射器をガムテープで貼り付けて病院に持ち込み、病院のトイレで隠れて打つ。このあたりから、覚醒剤を止めたくても止められない自分に気づき、薬物依存症に陥ってしまった自分に違和感を感じるようになる。刑事が逮捕しにきた時でさえ、連行される前にもう一本シャブを打ちたいと考えていた。 著者の人生を振り返ると、ギャンブル、仕事、女性、薬物・・と常に「何か」にのめり込んで生きてきた。この状態を理解する上で重要と思われたのは、著者が語る幼少期の経験だ。 「(生まれた)娘を見ていると、自分の幼年期のつらい思い出が浮かんできた。母に出刃包丁を喉に突きつけられた母子心中未遂事件や、祖母と母の不仲から「明日、どうなるのか」という不安だらけの日々が思い出された」 このように子どもの頃から非常に強いストレスにさらされ続けていた。何かに依存してのめり込んでいる間だけは、幼少期に受けた「死ぬかもしれない」というトラウマやダメな自分を責め続ける自分自身から逃避できた。少しでも楽になる瞬間を得るためならば自滅の道と分かりながらもその道を選択せざるを得ないのが依存症なのだと思う。 こうして警察に逮捕・勾留され、受けた裁判で「私は、シャブをやめるために今日までさまざまな努力をしてきたが、すべて無駄でした。もう、もう・・・疲れました。私のいまの希望は、刑務所に入ることです」と陳述した。取り繕いの無い本心に裁判官が著者の更生を信じてくれた。ここから、徐々に回復への道筋がついてくる。 執行猶予がつき、出所した後、AA(名もなきアルコール依存症者の集まり)ミーティングに参加した。「覚醒剤をやりたくなる気持ち」を仲間の前で正直にしゃべったら、法廷で自分の「ありのままの気持ち」を素直に話した時のような軽い気持ちになった。 その後、入院中に知り合ったロイ神父(アルコール依存症経験者)の仕事(アルコール依存症者の回復のためのリハビリ活動)を手伝っているうちに、薬物依存者の回復施設を設立したいと思うようになる。当時は「薬物依存の回復などありえない」という考えが主流で周囲から猛反対されたのだが、次第に薬物依存者が著者のまわりに集まり、NA(名もなき薬物依存者の集まり)ミーティングが開かれるまでになった。 活動は徐々に大きくなり、著者は日本で初めて薬物依存者の更生施設=ダルクを創設した。その後、ダルクは全国各地へと広がった。ダルクの活動は、アメリカのAA(アルコール依存症者の自助グループ)から生み出された12ステップというプログラムを基にしたミーティングから成る。 「ミーティングは、いわば便秘を治す下剤のようなものだ。薬物依存者の心の奥深くに沈殿した恨みの感情を外に出し、自分を好きになれる感情(自尊感情=セルフエスティーム)を生み出してくれるのだ」と著者が述べている通り、活動の核を成している。 ダルクの唯一の決まりは一日3回のミーティングに参加することだけだ。依存症は「関係性の病」「孤独感がもたらす病」とも言う。依存症は病気ということで、医師のもと治療を受けても、「支配」と「依存」の関係に陥りやすいと著者は言う。支配者が「クスリ」から「医師」に変わっただけになる危険性が高いため、医療だけの回復は難しいのだそうだ。ダルクのミーティングで「同じ目線の仲間」と苦しみや心の痛みを共有することが回復の大きな足がかりとなる。 ミーティングの鉄則は、「言いっ放し、聞きっ放し」である。これは、参加者が何を言っても反発されないで受け入れられているという安心感を得る土壌となる。参加者はそうした守られた環境の中で自分の気持ちや経験した出来事を素直に仲間に話すことができる。気持ちや経験を言語化することにより、自分の中の混乱した記憶や感情などが整理され、心が落ち着いて物事の本質が見えてくる。同時に自分の話を仲間が共感して聞いてくれたという深い満足感を得ることもできる。ミーティングは、疎外感や孤独感などで傷ついた依存症者の心を癒し、混乱した気持ちを整理してくれるのだ。「回復の95%は仲間の話を聞くことによる」とロイ神父が述べている所以である。 ミーティングの理念となる12ステップの最初に、「われわれは薬物依存に対して無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた」という言葉がくる。ずっと意思が弱いからお酒とタバコが止められないと思っていた私は、この言葉にとても衝撃を受けた。著者自身、一年間ミーティングに通っても何も改善点が見られなく、何年やってもダメかもしれない、というあきらめのような気持ちが生じてやっと自分の無力を認めることができたという。その時から薬物を止め続ける苦しさが軽減したそうだ。 自分の意思でポジティブに「クスリを止めたい」と心に念じれば念じるほど、その反動として「クスリをやりたい」というネガティブな願望が心に焼き付けられることになるのだと思う。自分の無力を自覚してあきらめの境地になった時、ポジティブ・ネガティブの思いが湧かないのでやりたい気持ちが軽減されるのではないかと感じた。ただ、この境地に至るまでに人はどれほどの苦しみを体験しなければならないのだろう、と私自身の経験を顧みて思った。 アルコール依存症は別名「否認の病」と言われている。依存症者はなかなか自分が依存症であるという事実が認められない。依存症からの回復には自己客観視が重要な第一歩なのである。<自分の無力を認めた状態>というのはまさに「ありのままの自分を客観視」できている状態と言える。これは、ヴィパッサナー瞑想の<捨>の心に通じるものだと感じた。 また、仲間の話を聞くことは、他者の苦しみや痛みに共感する<悲>の心を育む。また、仲間に対する信頼が高まり、仲間との友情や絆が生まれてくると、孤独な薬物依存者だった心の中に<慈>の心が育まれる。 ダルクにつながっても回復できるのは3割だと著者は言う。なぜ、重度の依存症だった著者がその3割という回復の狭き門をくぐることができたのか。著者は、依存症に苦しむ仲間の回復のためにダルクという組織の設立・運営に奔走した。そこには、同じ依存症に苦しむ仲間が回復していく姿を嬉しく感じる<喜>の心が働いていた。 人が幸福に生きるためには「慈悲喜捨」の心が大切であるが、依存症からの回復にもこれらの心所が重要な要素となっていた。活動の核となっているミーティングでは、「私は」という主語で自分の気持ちを言葉で表現する。それは、自分の心に気づく(=サティ)ことであり、心を随観することでもある。人前で話しをすることは、自分の経験や気持ちを言語化(=ラベリング)する訓練にもなっていた。依存症からの回復プログラムがヴィパッサナー瞑想修行と重なった。 私自身お酒とタバコを止められたのは、体調の悪さに加え、受診した人間ドッグで肝臓の数値の悪さが判明したことがきっかけだ。「このままでは死んでしまうかもしれない」と恐怖した時から、アルコールとタバコをピタリと止めることができた。しかしその後、今度は砂糖依存症になってしまった。就寝前の甘い物が止めたくても止められないのだ。「自分の無力」が腹に落とし込まれるまであとどれほど遠い道のりを歩まねばならないのか考えると気が遠くなる。 幸い私には法友という仲間がいる。共に仏教を拠りどころとしてあきらめずに歩んでいきたい。(N) |
素晴らしく、小気味好い本だと思う。
著者の黒川伊保子さんは、大学を卒業してから、35年間もAI(人工知能)研究に没頭してこられた。1980年代の世界のAI研究において、世界の最先端の空気を吸ってきたのだと思う。そして、AIの研究をするために、人間の脳の機能を追求していって、「人間とは何か」という本質的な問題を考えてきた。AIと脳科学の観点からの英雄像が面白い。
今後、世の中は、AIの世の中になり、変化のスピードはますます速くなり、先が読めない時代になり、激変する。その時に向けて、その時代を生き抜く若者に宛てたメッセージである。黒川さんは、堂々と世間を渡っていく「英雄」であれと言っている。そのためには、「失敗」が重要であること、「孤高」が脳の熟成に必要不可欠であることを、脳科学を使って説明したいというのが、本書を書く目的なのだ。
そして成人や老人にとっても極めて面白いと思う。本来は、若者向けに書かれたのだと思うが、この考えは、いつの年齢になっても適用可能である。
圧巻は、第1章の「失敗の章」である。この章は、この本の半分を占めている。失敗することが、どれだけ人を成長させるのかということを、AIや脳の観点から説明している。その説明が、人を納得させる。私も、もっと早くこの本に巡り合いたかったなと密かに思っている。黒川さんは、「日本ほど失敗にビビる国もありません。失敗が、才能のある人をこの世から抹殺してしまう国です。だからこそこの本を書いたのです」と述べている。最近は、失敗の研究などで、失敗についてたくさんの本が書かれる時代になった。それだけ社会が失敗を認める時代になってきたのだと思う。
AIの学習過程では、人の脳神経回路を模したニューラルネットワークに、たくさんのパターンを入力していくことによって、学習させていく。その際、失敗事例も入力として与えないと、概念構成が完成しないそうだ。人の脳も同様で、失敗体験こそが、センスの良さを決める。失敗しない脳は、未完成であり脆弱なのだそうだ。ただ、同じ失敗を漫然と繰り返すのはダメ脳で、失敗に胸を痛めない人は脳が学習に失敗する。例えば、失敗を他人のせいにしたり、自分のショックを回避するのは、せっかく痛い思いをしたのに、脳神経回路が書き換わらず脳が成長しない。これは、いかにももったいない。失敗を自分に受け入れることが重要なんです。
これは、地橋先生のダンマトークでよく出てくる受容することだと思う。若いうちの失敗は宝物である。
「孤高の章」では、「孤高」の時間を持つことを強調している。黒川さんは、脳は「孤高」の時間を持たないと世界観が創れない、誰とでも共感していると自分にしかできないものに出会えないし道が拓けない、と言っている。まさかどうでもいいことに「いいね!」を押していないでしょうね、と辛辣である。私は、この言葉にハッとした。そういえば、「いいね!」を押しまくっていた。
もうひとつ、脳科学的な観点から面白いことを書いている。右脳と左脳の連携についてである。
右脳は潜在意識の領域を担当し、イメージを創生し世界観を構築する。それに対して、左脳は顕在意識と直結して、言葉や数字を操り、現実的な問題解決を行う。右脳と左脳を連携する脳梁を通る信号の量が多いと、感じたことがどんどん言葉になる。そして臨機応変にこの世の中を泳いでいける。しかし、脳内に豊かな世界観を創り上げるには、左右脳連携を寸断して、右脳や左脳のすみずみまで信号を行きわたらせる必要がある。
英雄脳とは、脳梁を寸断し豊かな世界観を持ちながら、必要なときに、右脳と左脳がすばやく連携するハイブリッド型の脳だと説明している。一般的には、前者は男脳、後者は女脳なので、黒川さん流に言うと、そのどちらの特性も兼ね備えた人を英雄というのだろう。
最終章の「餞(はなむけ)の章」も素晴らしい内容だ。餞は、遠くへ旅立つ者へのメッセージです。そのメッセージ、「上質の異質になれ」という言葉は、胸に響く。
「おわりに」を読んで、わかったのであるが、この本は、始め、若者のために書かれたのであるが、それを百戦錬磨の大人にも知って欲しいということで、トーンを変えて書き直したのが本書である。
黒川さんは、常に闘っている人なんだ。女性ですが男脳の人。黒川さんは、大学を卒業して、コンピュータ関係の会社に入社している。その会社は、競争が激しく厳しい会社であり、そこで競争を勝ち取ってきた黒川さんは、相当に優秀だったのだと思う。でも、黒川さんだって、常に進軍ラッパが鳴っている状態ではなかったと思う。落ち込んでいたり、挫折したりしたことがあったと思うが、そこから這い上がってきたところに強さがあるのだろう。
この本の英雄のモデルは、黒川さん自身だと思った。黒川さんは、英雄としてこの世の中を生きてきた。胸を張って高らかに宣言しているように感じる。こういう人生は、これで素晴らしいと思う。「英雄の書」は、強者の論理の本なのである。
ここまで書いたところで、弱者の側からの意見も言っておきたいと思う。これからの人生を歩む若者を鼓舞するのにはいいが、もうすでに人生の大半が経過して自分が敗者だと思っている人には、ちょっとつらいかもしれない。
昔、私の職場で、研究室の上司が、ある時(かなり歳をとってから)、自分は今まで一流の人間だと思っていたが、今になって二流の人間であることがわかった、と言ったのをある人から聞いた。それを聞いて、すごく寂しくなった。その人は、東大の電気出で、会社の中では、超エリートであった。私も、横で見ていて、一流ではないことは、常々わかっていたのであるが、その人は、終始、強気だった。そんな人が、研究所生活の終盤で、つくづくそう思ったということは、憐れに感じてならない。その人は、そんなことが心の重荷になっていたのか、定年退職してすぐにこの世を去ってしまった。晩年は、悲しい人生だったんだと思う。私は、今でも、そのことが、時々、思い出される。
この世の中には、多くの敗者と、それを上回る非常に多くの普通の人と、少数の英雄がいるのだと思う。
私は、アップル社のスティーブ・ジョブズの生い立ちや伝記は、いろいろな機会に目にしてきた。ジョブズの創った製品は素晴らしいし、天才だと思うが、人間的に素晴らしいかどうかは疑問である。ジョブズは、英雄になるために、どんなに多くの人たちを踏み台にしてきたのか。ビジネスにおいても、自分の信じる道に猛進するため、多くの人や会社を切り捨ててきた。ジョブズの成功の陰には、そのような人たちが大勢いることを知っておくべきだ。
英雄を目指すのか、人間的に評価されることを目指すのか、どっちをとるべきか?それは、人それぞれだろう。我々修行者としては、ケースバイケースで考えて、判断することが必要だと思う。英雄的な行為を為すべきか、為さない方がいいのか、その場面に遭遇したとき葛藤が生じ、その人自身が試されているのだと思う。行動に移す時に、エゴがあるかどうかを常に自分に問うていきたい。
そんなことを言ったら、英雄なんて生まれないかもしれない。人のことなんかかまわず邁進しないと、革新的なことはできないというのもある程度はそうだろう。でも、黒川さんのような人は、レアである。世の中には、挫折から這い上がることのできない人たちのなんと多いことか。特に、「自尊の章」を読んでいる時に、そんなことを考えてしまった。
本当は、「弱者の書」とか「普通の人の書」のような本が必要だと思う。普通の人がどんなに素晴らしいかを、誰かが書いてくれるといいなぁと思う。そんな弱者の視点を持ちながら、この「英雄の書」読んでみることが、ヴィパッサナー瞑想者には必要なのではないだろうか。仏教の「捨(ウペッカー)」の立場からは、強者も弱者も、成功した英雄も挫折して落ちこぼれていった凡人も、一個の人間として等価なのではないか。残酷でエゴイスティックな英雄と、名もなく貧しく心が浄らかな一兵卒に、果たして優劣が付けられるのだろうか。
頭の回転が速くマルチな才能の持ち主と、誰にでも分け隔てなく優しい心のきれいな人は、どちらが先に人格完成者になり、苦しみに終止符を打つことができるのだろうか・・・。
「智慧」も「慈悲」も体得しなければ、真の「捨」を完成できないような気がするが、この本には脳を創っていくための、素晴らしいアイデアがたくさん詰まっている。智慧を育てていくためにも一読に値する良書だと思った。(N.N.)