![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
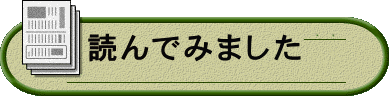
2018年7月~12月
|
パール・バック著『母よ嘆くなかれ』(1993年、法政大学出版局) |
| ノーベル文学賞の受賞者で『大地』などの名作によって世界中に名の知られているパール・バックに知力にハンディキャップのある娘さんがいたことを知ったのは友人からのメールに添付されていたサイトの情報からだった。
そのサイトに紹介されていた本の抜粋に、私の目は射抜かれたのだ。それは、次の文章だった。 「もしわたしの子どもが死んでくれたら、どんなにいいかと、わたしは心の中で何べんも叫んだものでした!このような経験のない人たちにとっては、これは恐るべきことのように聞こえるにちがいありません。でも同じ経験をもっている人たちには、おそらくこれはなにも衝撃を与えるようなことではないのです。わたしは娘に死が訪れることを、喜んで迎えたでしょうし、今でもやはりその気持ちに変わりはないのです。もしそうであれば、娘は永遠に安全であるからです」 私は、30年近く前に、心臓に重度の障害のある子どもを産んだことがある。 健康に生まれたと信じていたわが子が明日をも知れぬ命だと知った時、私はあまりのショックから混乱状態に陥った。 そしてその時に、「なぜこの私がこんなひどい目に会わなければならないのか?私にはこんな子どもは育てられない。親としての情が移ってからこの子に死なれたら私は生きてはいけないだろう。まだ何もわからない生後間もないうちに死んでほしい」という思いが心を去来したのだった。 結局、次男は生後4カ月目に手術を受けて、術後感染のため命を落とすことになったのだが、その時に自分が心の中で思ったことが息子に伝わり、そのために親に迷惑をかけたくないと思って死んでしまったような気がした。そしてそれからの私は、たとえ心の中であっても、わが子に死んでほしいと願った最低の母親だという自責の念に苛まされることになった。 私が地橋先生の瞑想会にたどり着き、そこで特に心の反応系に重きをおいた修行を積み重ねてきたのも、このような経緯による。 自分が次男の命を奪ったという罪悪感を手放せない限り、私は死ぬに死ねないという思いがあったからである。そして、ヴィパッサナー瞑想の明確な修行システムの中で、自分なりに必死で鍛練を繰り返した甲斐があって、ようやくその課題を克服できつつあると実感されてきた今日この頃、私の目に飛び込んできたのがこのパール・バックの言葉であった。 「私だけじゃ、なかったんだ!パール・バックのような偉大な女性さえ、自分の子どもに死んでほしいと思ったことがあるんだ!」 パール・バックの赤裸々な告白の言葉は、私には次男からの赦しのメッセージのように感じられ、思わず涙がこぼれたのだった。この本をすぐに取り寄せて、貪るように読むことになったのはいうまでもない。 パール・バックの子どもは、身体的にはとても健康に生まれたように見えたのだが、3歳になっても言葉を話すことができなかった。外見的には、まったく問題のないどころか、むしろ飛び抜けた美しさを持つわが子が、ひょっとしたら何か発育上の問題を抱えているのかもしれないという疑念は日に日に大きくなり、彼女はその原因の解明のため、娘と一緒に名医を求めて世界中を探し回ることになる。それは、長く悲しい旅の始まりだった。 当時(1920年代)の医療水準は、現在ほどは発達していなかったせいもあり、どこに行ってもはっきりとした病名もわからず、それゆえに治療法の手がかりさえつかめないままに、途方に暮れるしかなかった。しかも、どの医者も診断の最後には、「回復の希望はないことはないと思いますので、諦めることなく養育を続けてください」というようなことを言う。この言葉に残されたわずかな希望を胸に、彼女は厳しさを増す経済事情の中、なりふり構わず各地をたずね歩く破目になったのだ。 しかし、その苦悩の旅も、ある冬の日に終わりを迎えることになる。それは、ミネソタ州のある病院で、これまでと何も変わらない曖昧な診断結果を知らされた後、診察室を出てホールの方へ歩いて行った時に起こった出来事だ。その病院に勤務していた別のドイツ人の医師が部屋から出てきて、彼女に助言を与えたのだった。パール・バックにとっては、「生きている限り、感謝しなくてはならない一瞬が、幸運にも訪れたの」である。 私にはこのくだりが、本の中では最も印象に残ったところでもあるので、その部分を詳しく書き出したい。 「『わたしの話すことをお聞きください』と、そのお医者さんは、命令するように、こういわれました。『奥さん、このお嬢さんは決して治りません。空頼みはおやめになることです。あなたが望みを捨て、真実を受けいれるのが最善なのです。でなければ、あなたは生命をすりへらし、家族のお金を使い果たしてしまうでしょう。お嬢さんは決してよくならないのです。おわかりですか。わたしにはわかるのです。わたしはこれまでにこのような子どもを何人も何人もみてきました。アメリカ人はみな甘すぎるのです。しかし、わたしは甘くはありません。あなたがどうすればよいかがわかるためには、苛酷なほうがよいのです。 この子どもさんは、あなたの全生涯を通し、あなたの重荷になるはずです。その負担に耐える準備をなさってください。この子どもさんは決してちゃんと話せるようにはならないでしょう。決して読み書きができるようにはならないでしょう。よくて4歳程度以上には成長しないと思います。奥さん、準備をなさってください。とくに、お嬢さんにあなたのすべてを吸い取ってしまうようなことをさせてはなりません。お嬢さんが幸福に暮らせるところを探してください。そしてそこにお子さんを託して、あなたはあなたの生活をなさってください。わたしはあなたのために本当のことを申しあげているのです』」 一見しただけでは、残酷きわまりないこの助言が、パール・バックには絶望から希望への大転換となった。パール・バックはその時の自分の内面の変化を次のように表現している。 「わたしはそのときのわたしの感情を筆で表すことはできません。同じような瞬間を通ってきたことのある人には、語らずともわかっていただけるでしょうし、またその経験のない人には、たとえどんなことばを使ってみても、わかっていただけないことですから。それを表現する道があるとすれば、ただそのとき、わたしの心は絶望して血を流している、そんな感じであったと、申しあげるより他ありません。 娘は広いところに出たのがうれしかったのでしょう。跳んだり、踊ったりしていました。そして涙にゆがんだわたしの顔を見て、大きな声を立てて笑うのでした」 「これはすべて遠い昔に起こったことでしたが、しかし、わたしが生きている限り、わたしはことが終わったなどと思うことはできないのです。あのときのことは、今でもわたしのもとにとどまったままなのです。 わたしはもちろん、あの小柄なドイツ人がわたしにいってくださったことばによって、すべて諦めたわけではなかったのです。 でも、あのとき以来、わたしの心の奥底では、あのお医者さんのいわれたことは正しかったのであり、もはや望みはないのだ、ということがわかっていたのです。 あの最後の審判が下ったときにわたしはそれを受け入れることができました。すでにわたしは無意識のうちにそれを認めていたからです。 わたしは、娘を連れて、また中国の家に帰ったのです。 お名前も存じ上げないあのお医者さんにたいするわたしの感謝の気持ちは決して消え去ることはないでしょう。あのお医者さんは、わたしの傷を深く切開しましたが、その手際は鮮やかで、しかもすみやかでした。わたしは一瞬のうちに、避けることのできない真実に直接顔を合わせることになったのでした」 なぜこの場面が私の心に最も響いたかというと、それこそがヴィパッサナー瞑想の本質だと直感されたからである。 私たち人間の生きる苦しみとは、二元対立の価値観に翻弄されることからくると私には思われる。次男の心臓の疾患がわかった時の私のネガティブな反応も、源をたどっていけばそこにぶち当たるのだ。 進化の頂点と考えられている人間の脳は、思考やイメージという概念を発生させることで、この世の真理の探求の有力な手段を獲得したことと引き換えに、世界を善と悪、優れたものと劣ったもの、重要なものとどうでもいいものというように、自分が勝手につくり出した価値判断軸という妄想の基点に振り回されることを運命付けられることとなった。(これは地橋先生の持論でもある) そして、自分の知能に誇りを感じている者ほど、そのエゴの持つ極端性に心が引き裂かれることになる。なぜなら、二元対立という矛盾のバランスをとるために、自分がプライドを置いている対象と真逆の存在に必ず斬られるからだ。 パール・バックの場合も、知的なものをことのほか重んじる家系に生まれ、たぐい稀なる人並み外れた文才に恵まれたゆえに、正反対の現象に襲撃されたかのようであった。 自分自身の明晰な頭脳に多大な満足感を覚えていたパール・バックにとって、知能の発育が遅れたわが子の存在は、最初は地獄のような苦しみをもたらしたが、ドイツ人医師の言葉によって、その逃れることのできない運命を受け入れるしかないと腹を括った時に、地獄から天国への転換が始まったのだと思われる。そしてこれもまた二元論のエゴの性質ゆえに発生していたものなのだ。 後になって、自分の子どもに知能の発育に問題があると知った時の激しい苦悩の理由を、パール・バックはこのように分析している。 「わたしの家族はみな、愚かなことや、のろまなことを黙って見ていられないたちでした。しかもわたしはとくに、自分よりも感受性のとぼしい人にたいして我慢できない、というわたしの家族の癖をすっかり身につけていました。そのわたしのところに自分でもどうしても理由のわからないハンディキャップを受けた娘が授けられたのです」 私の場合もパール・バックとまったく同じだった。 人一倍、虚栄心が強くて、この自分には健康で優秀な子どもが与えられるのは当然だと考えていたのだ。そして、その子の能力を伸ばして、社会的に立派だと認められるように育てるのが自分の役目であり幸せなのだと信じて疑わなかった。それがどれほど傲慢な考え方であったのか、ヴィパッサナー瞑想の精神を受け入れることができた今ならはっきりわかる。 自己中心的な二元論の価値判断軸を肯定している限り、私たちは生きる苦しみからは決して解放されないということも。 ヴィパッサナー瞑想では、「捨(ウペッカー)」の心が何より大切だとされる。「捨」とは「平等性」と訳されることが多い。これは、百パーセントの希望は、百パーセントの絶望からしか転換されないということを教えてくれているのではないだろうか。 だからこそ、無慈悲にも感じられるドイツ人医師の絶望的な宣告は、わが子の状況が何も変わらないままで、暗闇から希望の光を呼び込むきっかけとなったのだ。 知能に障害のあるわが子の存在を完全に受容し、自分が死んだ後にも子どもが安全に幸福に生きていける施設を見つけたパール・バックは、そこの生活に娘が馴染み、家に帰ってきても間もなくその施設に戻りたがるようになったことに気づいて、ようやく子どもとの長い闘いに終止符が打たれたことを知る。 しかし、それはわが子との闘いではなく、自分自身のプライドとエゴ妄想に対する一人相撲に他ならなかったことを理解するのである。私には、この心の変容の過程が、まさにヴィパッサナー的だと感じられたのだ。 パール・バックは自分の思い込みが根本的に間違っていたことに気づいた時のことを次のように記している。 「わたしは、この歩んで行かねばならない最も悲しみに満ちた行路を歩んでいる間に、人の精神はすべて尊敬に値することを知りました。人はすべて人間として平等であること、また人はみな人間として同じ権利をもっていることをはっきりと教えてくれたのは、他ならぬわたしの娘でした。どんな人でも、人間である限り他の人より劣っていると考えてはなりません。また、すべての人はこの世の中で、安心できる自分の居場所と安全を保証されなくてはなりません。わたしはこのような体験をしなければ、決してこのことを学ばなかったでしょう。もしわたしがこのことを学ぶ機会を得られなかったならば、わたしはきっと自分より能力の低い人に我慢できない、あの傲慢な態度をもちつづけていたにちがいありません。娘はわたしに『自分を低くすること』を教えてくれたのです」 「娘はまた、知能が人間のすべてではないことも教えてくれました。娘はわたしにはっきり話すことができなかったのですが、その意思を通じさせる道はありました。娘の性格にはきちんと一貫したものがありました。彼女にはすべての嘘がはっきりわかるようで、どんな嘘でも決して許しませんでした。娘の精神はあくまでも純粋だったのです」 「親は、自分の子どもの生命は決して無駄ではない、たとえ限られた範囲内であっても、人類全体にたいして重大な価値をもっている、ということを知れば、慰められるはずです。わたしたちは、喜びからと同様に悲しみからも、健康からと同様に病気からも、また利益からと同様に不利益(ハンディキャップ)からも、おそらく後者のほうから、より多くのことを学ぶことができるのです。 人の魂は、十分に満たされた状態から最高水準に達することは滅多にありません。むしろ逆に、奪われれば奪われるほど、最高水準にむかっていくものなのです」 人生のほとんどすべてであった茨の道を歩き通した果てに、パール・バックが得た洞察も、エゴレスの心しか救いはないということであった。エゴレスとは百パーセントの平等性という意味である。 私には、それは、プライドだけでなく、何かがあるという存在妄想ですらも徹底的に否定すること、そしてそうだからこそ、完全なる平等性とは思考やイメージによっては決して伝えることは不可能で自分自身の修行によって覚るしかないということだと解釈された。そして、これこそが、ヴィパッサナー瞑想の本質に通じていると思われるのだ。 『母よ嘆くなかれ』のこの本に出会ったことで、次男が姿を変えて、もう一度私のもとに現れてくれたような錯覚を覚えた。自分の傲慢さをなくすため、これまで一所懸命に修行を続けてきた私の努力を認めてくれたかのように。 「お母さん、もう十分だよ。ありがとう」 そう語りかける息子の声が、パール・バックの文章の行間から聞こえてくるような気がした。その声に向かって「・・生まれてきてくれて、ありがとう」と呟くと、感謝と喜びの涙が溢れ出て、一瞬、目の前が真っ白になった・・・。(K.U.) |
|
映画『ゲッベルスと私』を観て |
|
先日、岩波ホールで『ゲッベルスと私』というドキュメンタリー映画を観た。 |
|
『あなたの脳のはなし』デイヴィット・イーグルマン著(早川書房 2017年) |
||
| 学校では色や光の三原色、そして波長の違いによって色の違いが生まれると学ぶ。その時はその先は無かった。しかし、実は、「外部世界に色は存在しない」「私たちは何百万という波長の組み合わせを区別できるが、そのうちのどれかが色になるのは、私たちの頭の中だけのことだ。色は波長の解釈で有り、内部にしか存在しない」のだという。また、「私たちに見えるのは、生物学的に限定された、現実の一部でしかない」ということ、ダニ、コウモリをはじめとして、「生物が感知できるのは生態系の一部」であり、「実際に存在する客観的現実そのものを経験している生物はいない」。
著者はスタンフォード大学の神経科学者。本書は、情報を受け取った脳による認識、理解、決断の、行動という「プロセスの大部分は意識に上らず、本人も気づかないうちに終わっている。本書は、このような脳と意識や意思決定のことが歯切れよく語られてく」(「訳者あとがき」による)。 このように、わたしたちの行動、信念、偏見もすべて、「意識的にアクセスすることができない、脳内のネットワークによって、決定される」のではあるが、しかし、脳は自らそのネットワークを書き換えることができる。それは脳の最も強力な特徴のひとつであって、良くも悪くも脳の回路に刻み込むことで考えたり意識することなしに実行されるようになる。まさに「反応系」の書き換えに希望を置くところの所以である。そしてついには、「新しいスキルは意識のおよばないところに沈む」ことになる。 これは、脳は前頭葉抑制の状態になること、そしてその状態は「心中のおしゃべりによって気を散らされることがなくてはじめて、実現できる」し、「意識は傍観者になっているのがベストである場合が多い」。これはあらゆる修練と言われるものにあてはまることであり、ヴィパッサナー瞑想の訓練にも重なる。 また、興味深い指摘は、共感が人類の進化の上で培われてきた有益なスキルだと言うことである。「私にあなたは必要か~」の章では、正常な脳の機能には周囲の社会ネットワークが欠かせないとする。「あなたは他人が苦しむのを見るとき、それは彼らの問題であって自分のことではないと、自分に言い聞かせようとするかもしれない――が、脳の奥深くのニューロンには、その差がわからない」「他人の痛みを感じるこの生来の能力は、私たちが自分の立場を離れて相手の身になれる理由のひとつである。しかし、そもそもなぜ私たちにはこの能力があるのか、(中略)人が感じていることをうまく把握できたほうが、人が次にやることを正確に予測できる」。 その他、「時間的な差のある複数の情報を同時に感じるために、私たちは過去に生きることになる」ことや、決定に関する神経のネットワークは「自我消耗」と呼ぶ心理学者が呼ぶところの生物学的なニーズにしたがっていること、アイオワ州の小さな町の教師が教室で子どもたちに「他者視点の取得」と「ルール体系は恣意的」なことを体験させ、「自分自身の意見を持つ力を与えた」こと、さらには、最終章「私たちは何ものになるのか?」では、これからのテクノロジーの進歩の方向を予見するなど、興味は尽きない。 最後に、「人類の明るい未来を望むなら、人間の脳がどうやって相互作用するかを研究し続ける必要がある――その危険と機会の両方を。なぜなら、私たちの脳の配線に刻み込まれた真実を避けることはできないから。私たちは互いに互いを必要としているのだ」と結ぶ。今まで学んできたことをさらにいろいろな面から補ってくれる一冊であった。(雅) |
||
|