![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
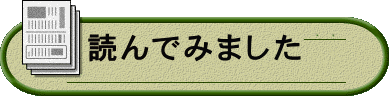
2018年1月~6月
| 住野よる著 『また、同じ夢を見ていた』 (双葉社 2016) |
| 主人公は、なっちゃんという十歳の女の子です。自分のことを「かしこい」と公言し、もっとかしこくなりたいと思っています。なっちゃんの口ぐせは「人生とは・・・」。漫画の『ピーナッツ』が大好きだからです。スヌーピーの相棒のチャーリーはこう言います。「人生はアイスクリームみたいなものさ、なめてかかることを学ばないとね」。だからなっちゃんは、「人生ってリレーの第一走者みたいなものよ」と言ったりします。「自分が動き出さなきゃ何も始まらない」のです。 教室でなっちゃんは、桐生くんというクラスメイトとペアになり、「幸せとは何か」という課題に取り組みます。桐生くんは絵を描くのが好きなのですが、級友にばかにされたため絵のことをひた隠しにしています。なっちゃんは、不当な言いがかりをはね返さない桐生くんを歯がゆく思っています。弱いものいじめをする「ばかな男子」もゆるせません。 ある日、桐生くんのお父さんが万引きをしてつかまり、桐生くんは学校に来なくなりました。正義感に燃える「かしこい」なっちゃんは、いくじなしで「弱っちい」桐生くんのために、クラスで代理戦争をしてしまいます。その結果、桐生くんからは「小柳さん(なっちゃんのこと)が一番きらいだ」といわれ、教室では無視といういじめにあうはめになりました。 なっちゃんには、変わった友だちが三人います。自傷行為をする高校生の南さん、人間関係がうまくいかず行き詰っている若い女性、人生の山や河を越え今はおだやかに暮らしている「おばあちゃん」です。なっちゃんは三人から人生のヒントをもらい、幸せについて考えを深めていきます。 自分は敵ではなく味方であると伝えるため、なっちゃんは桐生くんに会いに行きました。息子を傷つける者は入れないぞと物語の門番のように立ちはだかったのは、桐生くんのお母さんです。なっちゃんは、相手に受け容れてもらうにはありのままを正直に言う以外にない、と心に決めます。これは「不妄語」の実践にほかなりませんが、なかなかできることではありません。 お母さんの信頼を得たなっちゃんは、ドアを挟んで桐生くんと向き合います。話していくうち、最大公約数的な幸せがあるわけではない、その人その人の幸せがあり、相手の考えを認めた上で理解しあい、思いあうことが大切だと気づいていきます。なっちゃんは考えに考えに考えてこうした結論に至りましたが、これが智慧でなくて何でしょう。それまではかしこい自分が正しく、ばかな相手が間違っていると思っていたのです。なっちゃんは粘りづよく考えました。考えるのをやめたり、やけになったり、諦めたりしたら、智慧が現れるはずがありません。ずっといた暗闇(無明)、そこを出た時広がった未体験の風景。おそらく闇の中でさまざまな気づきがあり、それは無意識のヴィパッサナー瞑想になっていて、「認知の書き換え」が起こったのだと思います。 年上の友だちは「また、同じ夢を見ていた」と言います。それぞれが自分の子ども時代の夢を見ていたのですが、夢の中の子どもはなっちゃんにそっくりです。なっちゃんはやがて、南さんみたいな高校生になり、人間関係に悩む若い女性になり、数々の試練をのりこえて「おばあちゃん」みたいな晩年に至るかもしれません。でも、人生は書き替えられるのです。 この小説の作者は原始仏教を知っていたのでしょうか。それはわかりませんが、なっちゃんはこう言います、「人生とはダイエットみたいなものね」と。「むちむちじゃ、ちゃんと楽しめないのよ、ファッションもジョークも」。確かに、ムチムチ(肥満)で無知無知では楽しめませんね。(桐葉) |
| 東城百合子著『家庭でできる自然療法 -誰でもできる食事と手当法-』 (あなたと健康社 2002) |
よい瞑想をするために、みなさん体調には気を付けていらっしゃることでしょう。特に食事は、その内容、量、摂取する時間などでさまざまに意識の透明度に影響します。たとえ瞑想者でなくても、現代を生きる私たちにとって、何を、どのくらい、どのように食べればよいのかは、非常に大きな関心事です。多種多様の健康情報と次々に流行る食材。情報の海の中で何をどう選べばよいのか、はっきりと分かるためには時間が足りなさ過ぎるようです。 この著者は戦後の若い頃、重度の結核にかかり死の床にありました。化学療法と栄養をつけよとの医師の指示で肉や魚、卵など努めて摂った結果、容体は悪くなる一方でした。そんな時、食養法を学んだ兄の友人である医師に教えられ、玄米菜食の自然の食物と自然の手当法を施すことで、みるみるうちに回復しました。 何が起きたのでしょう。著者は言います。自然がもたらす生命力豊かな食物を、感謝の気持ちで頂いたこと。料理も手当ても自ら手を動かし工夫することで少しずつ元気になり、希望に繋がっていったこと。それが病から立ち直らせ、自然の偉大さへのとめどもない感謝の思いから、以来70年近くを病に悩める人々のために草の根の健康運動に捧げ、90歳を超えた今も自然の教えを伝え続けています。 私もこの瞑想に出会う以前、一年近く著者の料理教室に通い、教えられた自然食を実践しました。実感として分かったことは、今までは食べ物を〝物”として見ていたんだな、ということでした。栄養素がどうのとか、あれがいい、これがいいなどと、自分の都合でしか見ていませんでした。この世がエネルギーの出し入れの世界だとしたら、当然私たちは自分の身体の血肉となる食べもののエネルギーを取り込んでいるのです。瞑想の境地を言葉を尽くして説明したところで実際に体験しないと分からないように、ここはやってみないと分からない部分です。ですから著者は、実践と工夫を強く訴えます。 しかしそうすると、食生活に〝こだわり”が生じがちです。肉はだめ、野菜は無農薬じゃないと、子どもにそんな添加物まみれのお菓子なんてとんでもないわと言って差し出されたものを邪険に断る・・・。そのような自己中心的態度が神経を詰まらせ、病気や人間関係の崩壊などの不幸を招くと著者は言います。そんなときも手本にするのは自然です。自然は完全に〝調和”のとれた世界です。その姿から、自分の身勝手さを省み、気づくことで取るべき道が見えてくるのだと。 それを聞いて私が思い浮かべたのは、セイタカアワダチソウという外来の多年草です。背丈が高く、秋に黄色い鮮やかな花をつけて勢いよく群生する姿を見かける方も多いと思います。この草は根から周囲の植物の成長を抑制する化学物質を出しているそうです。ですから在来の植物を駆逐して、大繁殖するのです。 しかし数年経つと、その毒が自分たち自身を衰退させ、背丈は低くなり、そこに在来の植物が再び育ち出します。周囲に混じり合い存在し続けるセイタカアワダチソウの姿に、自然の調和を見出すことができるのです。 (ちなみにセイタカアワダチソウを乾燥させ入浴剤にすると、アトピーのかゆみに効果があります。長男は軽度でしたので、これでほとんど治りました。この本に詳しく載っています) この瞑想を始めた当初、先生がありとあらゆる修行の末にこれが唯一最高の道と確信されたというお話を聞いて、おかげで私は回り道をしなくて済むんだという有難い気持ちでいました。しかし、仏教の実践の究極は、慈しみの精神を養うことだと知りました。エゴを乗り越えるためには誤った認知を変えて反応系を整え、優しい心を育てていかなければならない。そのために色々な観点が必要だと感じています。 寒い冬に地中に向かって伸びる根菜類に、夏の暑い日差しを受けて色づき、成長する野菜たち。アスファルトの片隅にあってさえその根をしっかりと大地に根差して伸びてゆくタンポポやヨモギなどの野草。その力を頂いて生きていくことができるありがたさを思って涙するという著者に、深い慈しみの心を学ぶことができると思うのです。(M.N.) |
| 「心のなかの独り言 内言の科学」(日経サイエンス、2018年1月号)を読んで | ||||
| 私は日経サイエンスという雑誌をほとんど毎月買って読んでいるのだが、最新号(2018年1月号)に掲載されている「心のなかの独り言 内言の科学」を読んで驚いた。なぜならその論文は、地橋先生の指導されている瞑想法の有効性を科学的に裏付ける内容であったからだ。 先生の瞑想法では、初心者はまず歩く瞑想のやり方をマスターするように促される。 歩く瞑想のやり方は、中心対象を足の裏に定め、その一点の感覚に意識を集中させる。感覚を十分に感じたら、次に間をしっかり取ってから「離れた」「進んだ」「着」「圧」などというようにラベリングをする。そしてそのラベリングは、過去形であること、または漢字などを使用する圧縮型であることが特徴だ。 私はこの瞑想法が、先生が体得されたブッダの教えであるヴィパッサナー瞑想の真髄を凝縮した暗号のようなものであるという直感があった。そして、その暗号を理論的な観点から読み解くには、科学の力を借りる必要があるのではないかとも考えていた。 本来は理系音痴の私が、日経サイエンスを購読しているのもそのためであり、今までにも先生の瞑想法の理解につながる数多くの論文に出会うことができている。それらの論文は、物理学や数学、化学や生物学、そして脳科学や心理学など多岐にわたるもので、その数が増えるにつれて仏教の本質がこの世のあらゆる現象に投影されていることを次第に確信するようになっていた。 今回の論文「内言の科学」もその一つであり、内言のメカニズムを科学的に追求することで、サティの瞑想にはなぜラベリング(内言)が必要なのかの理由の解明につながる画期的な内容のものである。 私は、内言を扱った科学が存在すること自体知らなかったのだが、1920年代から1930年代にかけてピアジェやヴィゴツキーという心理学の大家が内言についての説を打ち立てており、この論文の著者である英ダラム大学のファニーハフ教授は、特にヴィゴツキーの考え方に強く影響を受けたそうだ。 この論文によると、ヴィゴツキーの内言についての説は、「他者の行動を調整するために用いた言葉を、他者ではなく自分の行動を制御するために用いる」手段であること、また「大人が行っている声にならない独り言は、子供として発達していたころに他者と交わした会話を内面化したバージョン」という特徴がある。 私はこの部分を読んで、ヴィゴツキーの説は、自分の外側にあると見なしている世界と自分の内側の世界すなわち脳内は、実は同時かつ時系列的にまったく同じ構造のものであると言いたいのではないかと直感した。 ファニーハフ教授も、人間が他者に対して発話している時と自分自身の頭の中でダイアローグを行っている時では、脳の使い方に共通点があるだろうという推定に基づいて機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)を使って実験を試みている。 そしてその実験結果は、ファニーハフ教授らの仮説を見事に裏付けるものとなった。 日経サイエンスの論文には、ファニーハフ教授らが行った複数の実験結果を脳の図でまとめてあるのだが、この図が実にわかりやすい。 簡単にそれについて解説すると、実験①では、内言がモノローグ(独白)型かダイアローグ(対話)型かによって脳内で発火する部分の違いがあるかを調べる。 結果は、モノローグの内言では「通常の発話の際に活性化する標準的な言語システムが動員される」のに対して、ダイアローグの内言では「他者の考えを推測するのに関与しているとされる脳領域と部分的に重なっている」ことが明らかになった。 また、実験②では、被験者に特定の言葉を頭のなかでつぶやくように依頼した場合と、自発的に行った場合の内言で、脳内の活動を比較する。 結果は、要請されたケースでは「脳の標準的な言語システムの一部であるブローカ野が活性化した」のに対して、自発的なケースでは「より後方に位置する側頭葉の一部領域が活性化した」という結果を得られた。 このことを表した脳の図で見比べると、違いは明確だ。 実験①のモノローグ型と実験②の要請された場合の脳の発火の状態は一カ所に集中する一元論的であるのに対し、実験①のダイアローグ型と実験②の自発的な場合の発火の状態は分散型の二元論的になっているのが一目瞭然である。 これは、私にはまるで、数直線の縦軸と横軸の広がり(サティの瞑想)と数直線の中心であるゼロの焦点(サマタ瞑想)のように感じられた。 また、ヴィゴツキーは内言と私的発話は他者へ向けられた発話に比べ省略が多いと指摘しているそうだが、このことを検証するためファニーハフ教授らが行ったアンケート結果をまとめたものも非常に興味深い。それによると、内言には次の4つの大きな特徴があるそうだ。 ①基本的にはダイアローグであること ②表現が圧縮される傾向があること ③他人の声が組み込まれるのには限度があること ④自分の行動を評価あるいは動機づけする役割があること この4つの特徴は、仏教の根幹とされている四聖諦(苦・集・滅・道)の解釈に通じるものがあるのではないだろうか。 この内言についての論文から見えてきたことを、ヴィパッサナー瞑想の理論に結びつけて私なりに解釈すると以下のようになる。 二元論(多様性)で成っていると思い込んでいる外界の現象―それは自分の体の感覚でもあるのだが―を、ヴィゴツキーの説のように内言(ラベリング)によって脳内に取り込んでいくと、ダイアローグ型の内言から次第にモノローグ型の内言へと移行していく傾向がある。 それは、地橋先生が講座の初回に教えてくださる認知のプロセスを逆方向にたどっていくようなもので、だからこそ、自発的な(能動的な)内言から要請(受動的な)された内言に移るのである。 そしてそれが、最初はラベリング(二元論)が必要不可欠であり、次第にラベリングが圧縮されていく(一元論)傾向にあることも説明できる。 また、二元論から一元論に変化するということは、二元論が過去の妄想であると捨てられるという意味になり、それが過去形のラベリングでなければならない理由であろう。 認知のプロセスを逆方向に進むということは、因果関係の逆転を暗示しているとも言え、これが物理学ではニュートリノが光速を超えたと一時的に騒がれていた現象を説明するものではないのか。 そして、先生の瞑想法では、最後はラベリングのない瞑想、つまり「サティの自動化」の状態になるという。 このことは、一旦確立された認知のプロセスを逆向きにどんどん進んでいけば、鳥が卵の殻を突き破って外に羽ばたくように、いつかは認知のプロセス自体の枠を超えて真実を直観することが可能となる。それが、私には、この世のありのままを瞑想によって洞察する智慧の発現のように思えるのだ。 (ちなみに、幼児が私的発話を繰り返すのは、「他者の視点に立てず聞き手に合わせた話ができないことの反映である」とするピアジェの説は、ヴィゴツキーの説とベクトルの方向が逆向きの認知のプロセスを確立するまでの過程を指していると考えられる) 数学でも物理学でも、難問とされているのは皆このことを言っているだけのような気がしてならない。 なぜなら、人が外界を知覚する手段は脳を通すしかやりようがないから。自分の外界は左脳(二元論)と右脳(一元論)から成る脳構造の反映であるのなら、脳も外界の反映であるといっていいだろう。 そしてその外界と内界を別のものとして分けているのは何かというと、自分が存在するという錯覚なのだ。 脳の構造でいうと、左脳と右脳をつなげる脳梁があるという錯覚とも言えるかもしれない。養老孟司さんが「バカの壁」と呼んでいるのも自我という妄想への執着に他ならない。この「バカの壁」を完全に取り去るとどうなるか。それが仏教の「涅槃」に当たるもので、それがわかれば「涅槃」という概念だけでなく何もかも元々存在しなかったことが明らかになるのではないか、と私は勝手に妄想している。 ファニーハフ教授らによる内言の4つの特徴もまた、突き詰めるとこのような意味になると私には感じられる。 以上、できる限りわかりやすい表現を使って、この論文から読み解くことができる先生の瞑想法の解釈を試みたが、やはり、思考を用いて自分の理解した内容を人に伝えることには限度があることを痛感している。 このことも、ブッダの教えの真髄はパパンチャ(概念)を超越したものであるからなのだ。だからこそ、パパンチャ(概念)への執着がきっぱりと絶ち切られなければ真実は悟られることは不可能でありそれが自灯明の意味ではないかと愚考している。 地橋先生が、なぜ実践を重視されているかというと、ブッダの教えの実践方法であるヴィパッサナー瞑想は、概念や思考をもてあそんでいる限りその入口にすら立てないのだと知り尽くされているからである。なぜ、そのことを確信を持って断言できるのかというと、地橋先生ご自身が厳しい修行時代を経て、仏道の本質は煩悩を滅尽させていくことであり、それは取りも直さず思考や妄想で何を考えようが、クズでしかないと痛感されたからだということが、先生の下で8年間修行させていただいた私には感じられるからである。 先生は、二十年以上に渡って、ご自分が体得されたことをなんとか私たちに伝えようと、一生懸命に瞑想を教え、ダンマトークをなされてきた。私もまた、先生がどのような状況でもまったく動じない姿も目の当たりにしてきた。妄想を一蹴する迅速さの故だろうかと想像している。 私自身、この世の真実を知りたいという欲求の根源には、生きる苦しみから解き放たれたいという原動力があった。何をやっても、永遠の幸せに行き着くことができない虚しさと苦しさ。でも、幸せはないと諦めなければ苦しみも決してなくならないと身をもって知ることができた。 それは生存本能を諦めるということと同じくらい困難なことなのだが、それがなされたら、生存本能こそ貪瞋痴だと心底納得されるのではないかと憧れている。生存本能を言い換えると、言葉(概念)ということになるのではないだろうか。 この論文は、内言がこの世のすべてであり、その正体を暴くことが真の安らぎに通じる道であることを教えてくれた。 ファニーハフ教授も論文の最後のところで、「内言の科学を正しく追求していけば、これら人間の認知のすべての側面を言語的思考から解明できそうだ」と言っている。 このような価値ある素晴らしい科学の論文に出会えたことは何よりの喜びである。 地橋先生の代表作である『ブッダの瞑想法 ヴィパッサナー瞑想の理論と実践』の本のタイトルに「実践」だけでなく「理論」も明記されている理由は、私のように瞑想の実践が苦手な者でも、ヴィパッサナー瞑想を信じて、諦めることなく修行を続けていけば、必ずパパンチャ(概念)を超える次元に達することができるという意味なのだと思いたい。 パパンチャが超越された次元とは、すなわち無のことだが、いったん存在の妄想の罠にからめとられたら、量子論でいうところの波と粒子の矛盾のように、一番シンプルなことを理解するのが、認知的かつ情動的に一番困難になってしまうのだ。 先生の瞑想会で、信頼できる家族や法友の方々に支えられながら修行を続けてこられた私は、すでに100%幸せであったのだと生きとし生けるものすべてに、心から感謝がわき上がってくるのを感じていた。(K.U) |
||||
|
|
『ダイアモンド博士の“ヒトの秘密”「動物のコトバ、ヒトの言語」』を観て |
| 2018/1/17にNHKで放映された『ダイアモンド博士の“ヒトの秘密”「動物のコトバ、ヒトの言語」』を観た。この番組は、『若い読者のための第三のチンパンジー』(ジャレド・ダイアモンド著)をベースにしながら野外講義という形をとったもので、今回の内容はその本の第6章にあたる。
人間がどのようにして複雑な言語を獲得したかは、非常に興味深いテーマである。この課題に対する回答は、動物の鳴き声やアフリカなどの原住民のコトバから推定されるという。 では、単純な言語は、どのように獲得されたのであろうか。 ベルベットモンキーやプレーリードッグは、言葉を使って、敵の襲撃を仲間に知らせることができる。敵によって鳴き声を変えるのである。その点では、これらの動物は名詞を使い分けてはいる。しかしその言語は単純であり、複雑な表現はできない。 ではヒトの言語はどう発達したのであろうか。それを考えるに当たって、博士はこの人間社会で単純な言語を使う民族を探すために各地を調査して回ったそうである。 パプアニューギニアの人々(フォーレ族)は、石の道具を使い、文字はなかった。フォーレ族の使っている言語(フォーレ語)を調べると、場所を示す動詞があり、主語が人間かどうかで違う動詞を使っており、英語より複雑だった。 この調査でわかったことは、人間の社会においては単純な言葉で生活している民族はいないということであった。どの民族も、複雑な言語を駆使している。 とはいえ、人間社会で単純な言語を使う環境はあった。異なる言葉を使う商人同士が、交易のために使った単純な言語(これをピジン語と呼ぶ)がそれであった。この言語は、商売のための言語であり日常生活の言語ではない。 ヒトの言語が、どうやって複雑で洗練されたものになったかという疑問を解くヒントは、ピジン語で育った子供たちの言葉に見つかった。昔、インドやハワイの農園には、いろいろな国(例えば、フィリピン、日本)の移民が集まってきていた。それらの移民たちは、仕事ではピジン語を使っていた。 ピジン語は仕事をするには十分であったが、普段の生活には物足りない。彼らの子供は、両親のピジン語を聞いて育っていったが、言いたいことが充分に表現できない。ピジン語では満足できなかった子供たちは、自分たちで複雑な言語を作り始める。それをクレオール語と呼ぶ。 クレオール語は、各地のピジン語を使っていた家庭で自然発生的に生まれた。このようにして、単純な言語から複雑な言語へと進化していったと考えられる。 人間が、なぜ複雑な言語を獲得することができるのかというと、人の脳に備わった遺伝的なプログラムから生まれたのだという考えがある。 代名詞や副詞も、我々の遺伝子のプログラムに由来する可能性がある。この考えは「普遍文法」と言い、言語学者ノーム・チョムスキーが提唱した。人は生れながらにして、あらゆる言語に適用可能な文法を持っているという考えである。 脳の発達に伴って言語も進化してきたという訳である。高度な言語は、人間のような複雑な脳を持ったものにしか与えられていない。そして、そのような脳をもっていれば、文法を持つ言語を持つようになるのは必然だと言っているのである。クモが巣の作り方を生得的に知っていたり、また鳥は教わらなくても空を飛ぶのと同じように、人間も生まれながらに言語の使い方を知っているというのだ。人間は、特別な存在なのかもしれない。 ここで重要なのは、人間が言語に文法を持ったことだ。人間以外に言語に文法を持った動物は見つかっていない。それほど、文法を持つということは、画期的であった。 文法は、単語に順番を設けて手順を示す。文法をもう少し科学的に分析すると、文法によって、単語と単語との間の関係を表現できる。もう少し深く考えると、空間的な関係や時間的な関係(現在のことなのか、過去なのか、過去分詞的なことなのか)を表現することが可能だ。そして、言語に文法を持つことにより、思考の概念空間が一挙に拡大した。これにより、妄想する能力も飛躍的になったが、空間的な関係や時間的な関係により、自分自身を対象化して観るという「気づき」が生じてきた。この自分自身を観るという「気づき」は、メタ認知と呼ばれているもので、ヴィパッサナー瞑想の核心部である。 動物の言葉の単語には、順番を操作するルールがない。すなわち、人間の言語のような文法を持たない。動物には気づき自体はあるのだが、人間のようなメタ認知的な気づきはないように思われる。言語にとっては、文法を持つことがメタ認知的な気づきを得るための必須条件ではないかという気がする。 では、メタ認知的な「気づき」は、大脳皮質のみに局在するのかと言うと、それだけではないと思う。人間が気づけるのは、身体という存在があるからである。気づきを得るためには、身体を通して、人間の周囲の空間である外界に働きかけができる(出力する)ことが重要である。 出力することによって、環境に働きかけることができる。そうすると、その働きかけに対するリアクションが返ってくる。そのリアクションが新たな気づきとなっていく。そして、気づきの連鎖がもたらされる。入力だけだったら、そのような気づきの連鎖はない。そして、時間的な要素も加味し、それらが渾然一体となって気づきを補完していく。 人間が外界に働きかけができるのは、身体を持っているからこそ可能となる。だから、身体を持つことにより、瞑想もできるし、気づきの極みである「智慧の発現」につながっていくのである。 このように、メタ認知的な「気づき」は、言語に文法が備わったことと、身体が存在するということによって得られた。 人間は、抽象化する能力によって、主観的にも客観的にも、この現象世界を見ることが可能になった。しかし我々人間は、全てを概念化して思索するという枠の外には出られない。しかし、それに気づいているということは、その枠の外に出られる可能性を示唆しているのではないだろうか。 人間の言語に文法が備わったのは、画期的なことだった。さらに、今、この素晴らしい言語を停止させることによって、次のステップに進むことができるのではないか。それが、サティの瞑想であり、言語を介することなく、直接知覚による気づきによって、全てが概念化されてしまう思考の枠の外に出て、現象世界を対象化して認識する可能性が開けたのではないだろうか。 その偉業が修行現場でなされた時、一切の人生苦は無明(貪・瞋・痴)という名の妄想から生じていると認識できるのではないかと妄想している。 言語による気づきと違って、サティの瞑想では、事象の本質を直接知覚する衝撃とともに、世界が180度ひっくり返るような認知の転換がもたらされるのだろう。真理の究極を究めていく最終章は、サティの瞑想の実践に徹するしかないのではないかと夢想しながら、今日もまた瞑想修行を続けようと思う。(N.N.) |