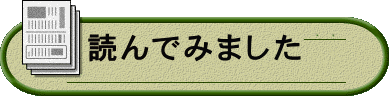新聞の書評欄で池谷裕二さんの新刊『パパは脳研究者』を知り、さっそく買って読んでみた。
この本は、脳研究者の池谷さんが、ご自身の娘さんの誕生から4歳になるまでの成長を通して考えたこと感じたことなどを記録した育児日記のようなもので、この夏、初孫が生まれたばかりの私にとっては、まさにうってつけの本である。
0歳0ヶ月から4歳までといえば、何もできない「モノ」としてこの世に現れた存在が、人間という生命の進化の頂点の原型にまでのぼり詰める過程でもあり、それはまるで、宇宙の始まりから生命の誕生を経て人間という種の繁栄に至るまでの全宇宙史の縮図のようなものと言っていいだろう。
つまり、人間の赤ちゃんの成長には、存在とは何かについての究極の問いに対する答えが隠されているような気がするのだ。それを、第一級の脳研究者である池谷さんの目を通してわかりやすく語られるということで、否応なく期待が高まる。そして、読み進めるにしたがって、私の期待をはるかに超えたレベルの内容であることに驚嘆の連続状態となった。
一例を挙げよう。
赤ちゃんは0歳3ヶ月頃に空間把握能力が芽生えるという。そして、0歳6ヶ月頃には時間の観念ができてくる。人間としての完成は、自分とは何かを知ることである。
それには、存在のすべてを認知するためにメンタルローテーション(空間把握)とメンタルトラベリング(時間把握)を自由自在に駆使する能力が必要である。その上で、高度な抽象化能力である自己客観視の力が完成するのだから。それゆえに、人間の赤ちゃんの最初期の発達のプロセスの本質をとらえることは、この世の構造の根源に迫ることと同じであると私は考える。
目に見える空間と見えない時間は、ある意味、右脳(イメージ)と左脳(思考)の関係に似ている。また、これを物理学の量子論に当てはめてみれば、粒子と波にたとえられないだろうか。あるいは、数学の概念を使えば、0(ゼロ)を意味する∞(無限大)と1/∞(無限小)の関係のようなものではないのか。
仏教は、この世は無であり、存在が有ると考える方が人間の脳が見せる勝手な思い込み(妄想)だと説く。何もないはずの無を0(ゼロ)と解釈することによって、ありとあらゆる妄想が発生しているだけなのだと。それを池谷さんは、この本の終わりの方のコラムで次のように記している。
<「脳」が知ることができる情報は、生まれてこのかた、ビビビ信号のみです。私たちは、ビビビ以外の信号を、一度も感じたことがないのです。ビビビ世界こそが、私たちの全てです。だから、ビビビ世界以外に「現実の世界」などという仮定を、脳の外部に設定することは無意味です。あるかないかもわからない「世界」なのですから。>
<脳のビビビ信号が「現実の世界」の情報を運んでいると仮定することは無謀です。「宇宙人の音楽」が単なる仮定にすぎないように、脳にとって「現実の世界」は、ただの仮想でしかありません。いわば幻覚です。脳にとって唯一確実なことは「私」とはビビビが綾をなす大海に浮かんだ存在だということだけです。それは「意味」を伴わない抽象世界。いや、意味という概念すら無効な、ビビビのみの純世界です。>
<脳は確信犯です。幻覚を、幻覚だと感じさせないよう、私たちに巧みに演出してみせる詐欺師です。そして、私たちは、それが幻覚にすぎないことを、心のどこかで薄々知りながらも、あえて疑うことを避け、「この世界」の虚構にどっぷりと浸かり、人生を堪能しています。>
脳研究の第一人者である池谷さんには、ビビビ信号の矛盾がはっきりと見えているのだ。
ビビビ信号とは、空間と時間、粒子と波、∞と1/∞のような両極端の相反する組み合わせが同時に存在するという本来はあり得ない状態なのである。このような矛盾を認めることは不可能なはずなのに、現実の実感からこの世を肯定せざるを得ない。私にはそれが、学問の世界の限界であると感じられる。
しかるに、ヴィパッサナー瞑想の修行を続けているうちに、その限界を打ち破るものこそがこの瞑想ではないかと確信するようになった。心の汚れとは、存在という妄想に執着する心に他ならない。執着がわずかにでもある限り、思考の枠組の外には出られないだろう。だが、ヴィパッサナー瞑想の修行を完成した者には、ビビビ信号の意味するものが直観されるにちがいない。
『パパは脳研究者』の本には、父親としての池谷さんの娘への愛情が随所に散りばめられているが、私にはそれを超えた真実への情熱も感じられた。ご自分の研究成果のすべてとその限界を伝え、そこから次の発見へと繋げてほしいという研究者としての真摯な願いが込められているように思えるのだ。
人間の脳の限界を超えることのできる唯一の手段であるヴィパッサナー瞑想。それを求めてやまない本のように、私には受け取られた。
一見すると育児書のようなタイトルの本だが、そう思って読むと、池谷さんからの心地よい裏切りに打ちのめされるにちがいない。脳研究のすべてがわかりやすくまとめられた珠玉の一冊として、また学問から瞑想への橋渡しとして、多くの人にこの本を強く薦めたい。(KU)
|
![]() 月刊サティ!
月刊サティ!