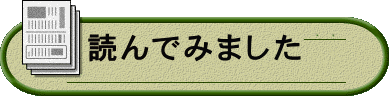|
『外来種は本当に悪者か?』フレッド・ピアス著(草思社2016年)
日本には古来おびただしい数の動植物が持ち込まれてきた。近ごろテレビでよく取り上げられるのは、飼育目的で持ち込まれた動物が野生化し、それが元々の生態系を乱すばかりではなく、在来種を絶滅の危機にさらしたり、農産物にまで被害をもたらしたりという情報である。本書は、そうした次元を越えて、はたして「生態系は安定が基本で、変化は異常」という思い込みは誤りであると、島という閉じた空間から、湾や湖、都市の荒廃地に至るまで、じつにさまざまな事例を駆使して考察し主張する。
知る限りではあるけれども、カスタマーレビューの多くは「☆」の数の分布(AMAZONによる)がどちらかに偏っているけれど、本書は現時点で21件が「☆」五つ(10件)と一つ(6件)とに分かれ、二~四つは計5件しかない。そのような意味から、紹介するかどうか少々迷ったが、評価が分かれた「悪者か?」どうか、の部分には触れずに、これまで疑問も持たずにいたことを再認識させてくれ、なるほど「無常」とはこういうことでもあるのだと気づかせてくれた部分についてのみ記してみたい。
これまで学校で極相林と言うことを教わった時、それはもうこれ以上変化しない安定したものとして覚え、理解したように思う。しかし少し考えてみれば、それでも気候や自然災害によって影響を受け、変化していくであろうことは容易に推測できる。したがって、現在では極相と言えども、より適切には動的な平衡状態にあるという視点から森林の姿を理解するようになってきている。
本書ではもう一歩進んで、生き物同士の接触、侵入とそれが及ぼす影響について検討していく。そしてそれは、「他種類の生き物がいる成熟した生態系は『飽和』していて、もう入る余地がない」のではなく、「外来種がたくさんいる環境には、在来種も多」く、「自然を乱すという概念がそもそもない」ので、「生き物の出入りも激し」く、「『在来』『外来』の区別もほとんど意味がなくなりつつある」という結論に至る。つまり、「ダイナミズムと変化こそ自然本来の姿なのだ」との主張、これが本書のバックボーンとなっている。
「無常」のことわりはこの世のすべてに当てはまる。絶滅していくもの、絶滅を食い止めようとするもの、どちらも包含したまま濁流のように変滅していくのが残酷な無常の真理ではないか、と「無常=苦」の理解に思いを新たにした。このことを忘れずに、本書をきっかけにして自己の「ダイナミズムと変化」にも期待しよう。(雅)
|
![]() 月刊サティ!
月刊サティ!