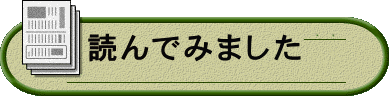猫とならんでぺットの双璧をなしている犬は、人類が最初に順化(家畜化)した動物であるといわれています。その始まりは、人の集落に残飯をあさりに来た多少警戒心の薄かったオオカミの縄張りを守る本能が、そのまま集落周辺の夜警につながった、つまり番犬として役に立ったという持ちつ持たれつの関係から、次第にパートナーとして認められていったという推論もあるようです。
この本の著者は、そんな犬と人との関係がどのように築かれ、それが両者にとってどんな意味があったのかを考察した結果、「愛情、親しみ、友情を感じる私たちの能力は、イヌのおかげで発達したのではないだろうか」と、つまり犬との交流の産物ではないかと考えるに至りました。
題名からは少し大げさな印象も受けますが、納得するかどうかはともかく、「なるほど!」という話も多く展開されており、利他や慈悲の心が人間に共通して存在することの一つの見方、そしてその心を育てることがごく自然であることが説得力を持って述べられています。
さらに著者は、飼い犬ベンジーとの交流をきっかけに、犬には「異種の動物と心を通わせる、生得的な性質」が備わっており、ほかの動物を区別しないばかりか、人間に対してもまったく偏見がないので、犬は、「平等な世界に生きている。私たちよりもよほど進歩的な考えのもち主ではないか」とまで考え、その背景として、犬の先祖とされる狼の一種ハイイロオオカミの習性、そして、犬と人とは究極のネオテニー(neoteny:幼形成熟)であることに注目して説明していきます。
アシュレィ・モンタギュー(アメリカの人類学者)は次のように述べているそうです。
「幼い子供が愛清を求めるのは非常に重要なことで、その欲求が満たされてこそ健全な人間に成長する。愛されたいという欲求だけでなく、愛したいという欲求は、健全さをひどくゆがめようとする力が社会にいかに多くとも、ともに人間の最も強い欲求として人生の終わりまで失われない。これは明らかにネオテニーの特徴である」(本書より引用)
そうであれば、犬と人とが互いに惹かれあうのも不思議ではないですし、その結果として、「人が犬に思いやりを伝え、犬は伝え返す。自然界ではまれに見る博愛の循環」が実現されたということでしょう。そして、返される保証が一つもなくても、「見返りを求めることなく愛せるのは犬のほうだ。それが犬の愛の本質」なのだと述べ、人が種の壁を越えて愛情を広げるという画期的な一歩は、人の力のみで踏み出されたのでなない、と結んでいます。
いずれにしても、人間は傲慢であってはいけないし、すべての生命に対して謙虚でなくてはならないと思います。また犬のみならず、他の生物と人間との関係への思いがけない視点を開かせてくれる好例として紹介する次第です。(雅)
|
![]() 月刊サティ!
月刊サティ!