![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
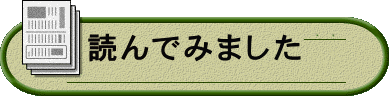
2016年1月号~6/7月合併号
著者は「風化仏教徒」を自称する 1937年生まれの精神科医。扉にフツーの人がフツーに死んでいくための終活の書とあり、原発事故、原爆被爆者、多くの患者の死、自らの心筋梗塞、そして対談を通して「死」に関する考察を進めていく。
母の入院を通して、それまで「自分はそこそこいい医者だと思っていた、その矜持が砕け散った」こと、世間では家で看取られるのが好ましいと見られているけれど、それは「大勢の親兄弟、親戚、友人、近隣の支え」という前提があってのことで、今の日本では負担が個に負わされ、頑張りだけでは保てない現実。また、旧知の末期ガンの看護師と奥さんの介護の姿勢から、最後まで正気を失わずに自己決定していく死も楽ではない、「人間は弱い。人を助けたり、助けられたりして生きてきている。死の時だけ例外になるのは不自然」なことだと気づく。
また、「死は肉体の生滅であるが、それだけではない。誰でもこの世に影響を与えていく、その影響が、長いか短いかの違いだけである」として、その影響は、個人だけでなく社会にとって新しい世界をつくり出していくための契機でもあり、決して「喪失」ではないと言う。そこには「死の豊穣さ」とも言うべきものがあり、「毎年、遡上する鮭が、産卵を終えて死んでいく。それをみていると、死と豊穣は、ぴたっとくる『組み合わせ』だとわかる」と言う。
さらに対談からは「何を遺したら安心して死ねるだろう」という課題が浮かび上がる。財産や名前でないのはもちろん、人材でもない。そして、「DNA―子どもや孫―もそんな気がする。子どもを遺して安心ならヒトは有史以来、こんなに死にこだわってこなかったはずである。『生のリレー』の短い区間を担った、ということがそんなに安心とは思えないのである」に至って、生命の基本的な本能の一つにまで疑問を投げかける。
「最期に向けての対話」というテーマのもと、結局、人間の生き方に行き着く。「ヒトは知能は高いが『賢くはない』と言わざるを得ない」のは、欲に執着しすぎると争いと破滅があることを知りながら止められないからであり、「・・・福島県を除けば、なにごともなかったかのような日常がもどってきている」のは、通常の生活では便利で優れた機能である「忘却」のマイナス面が表れていることを指摘する。
本書は瞑想修行に直接的なヒントになるようなものではないが、どのページも背景に奥行きのある内容が含まれている。自分に当てはめて考えてみることで、「あるがままに観る」ことを支える土台を固める助けとなると思う。(雅)
『キレイゴトぬきの農業論』久松達央著(新著選書、2013)
『新・観光立国論』デービッド・アトキンソン著(東洋経済新報社、2015)
前者は有機農業を営む脱サラ農業者が著者。茨城で総勢6名のスタッフとともに約 3haの畑で多種類の野菜を育て、個人や飲食店に直接販売している。
有機=美味で安全、農家=清貧な弱者、農業=体力が必要、は全部勘違いだと言う。有機農法は、生き物の仕組みと多様性を生かしながら「健康な野菜を育てる」ための手段。農薬を使わないことで野菜たちを篩にかけ、健康な個体を残すのもその一つだ。要は、「その植物がもっている形質を発揮できるように導く」こと。教育にも通じる考えだ。
農業には自由度があるからこそ、お仕着せの常識とは訣別したい。しかし、長く続けていくためには、自分の適性を客観的に判断し、論理的、合理的に考えることが大切だという。
例えば、男が田植機に乗り女性が苗を運ぶ風景、よく考えれば合理的ではない。相対的に非力な女性が機械操作に回り、力仕事は男性が担当する。著者の農園の芋掘りは、一番小柄な女性がトラクターに乗り、男たちが後から芋を拾っていく。こういう地味だが小さな合理化の積み重ねが全体の生産性を向上させると言う。これは、自分の状況を客観的に把握し、柔軟な思考から生まれた結果だ。自己客観視と平等という視点の重要さ、そこから生まれる斬新かつ合理的な発想、その面白さを教えられた。
後者の著者は25年間日本に滞在する元ゴールドマン・サックスアナリスト。裏千家の茶名「宗真」を持つ。
「気候」「自然」「文化」「食事」の4つの基本条件に抜群に恵まれた日本への観光客数が、世界26位と低いのはなぜか。観光産業は全世界GDPの9%を占めているのに対し、日本は0.4%と低いのはなぜか。データを基にした分析から始まる。最近日本を自讃するテレビ番組が目に付くが、日本の美点だという「気配り」「マナー」「サービス」「正確な鉄道時刻」「治安」は、あった方が良いが、必ずしも外国観光客の増加には繋がらないことが指摘される。
また珍しさだけのものや世界遺産登録を目指す動機にも違和感を覚えると言う。それらを主たる目的として日本を訪れるのはほんの一部だけ。大部分はそうではないのだ。
なかでも、東京オリンピック招致でも話題になった「おもてなし」が、まったくの独りよがりからの視点であることを一章を割いて詳しく論じている。そこには、「きっと喜ぶはず」「郷に入らば郷に従え」という自己中心の視点を離れられない発想を感じるという。
後半に展開される提言とともに、二冊とも、漠然と抱いていた今までの思い込みを覆す。視点、思考を柔軟にしてくれた。(雅)
『がんばれば、幸せになれるよ』山崎敏子著(小学館、2002)
「おかあさん、もしナオが死んでも暗くなっちゃダメだよ。明るく元気に生きなきゃダメだよ。わかった?」
5歳でユーイング肉腫という小児癌を発病、9歳で亡くなった直也君の遺した言葉を元に母が綴ったもの。4回に及ぶ手術によって腫瘍を取っても取っても再発してしまう。親の動揺に「手術しないってことは死んじゃうってことじゃん。だからナオは手術するよ。だってやってみなくちゃわからないじゃないか」。
「代われるものなら代わってあげたい」と言うと、そのたびに「ダメだよ」とかぶりを振り、「ナオでいいんだよ。ナオじゃなきゃ耐えられない、お母さんじゃ無理だよ」ときっぱり。親が子に育てられていく。
いつのまにか母にいろいろ注意をするようにもなっていた。「はいはい」と聞いていたら、「おかあさん、すぐ忘れちゃうから、書きなよ」と言われてノートにメモをするようになった。人に頼まない、自分でやる。一度言ったら何回も同じことを聞かない。お母さんは勇気がない、勇気が大事。人のことも考える。仕事をしてくれているんだからお父さんを大事にする。いきなり怒らないで口でまずやさしく説明する。自分がイライラしているからといって子供に当たらない。物を大切にする。おかあさん同士でおしゃべりばかりしないでナオの話も聞く。子供に言っていることが自分でできていない。人の話は目を見て聞く・・・。そして「本当に子供が好きなら子供がいやがることはしない。それが本当に好きだってことだ」と。
これらはすべて母のことを思ってのことだった。なぜなら、「もしナオが死んだら、おかあさんはダメな人間になりそうだから、今のうちから、おかあさんの弱いところ、いけないところを直してもらいたい」と、いつもそう言っていたという。「ナオはね、今死ねないんだよ。お母さんの心の準備ができていないから」。
「ナオは力は弱いけど心は強い。体が強くても、心が弱いのはダメだ。ナオ、体はこんなだけど、病気には勝っているからね」。病気と闘うことで精神的にこれほど強く、これほど成長した。ご主人も、言葉もない様子で、「おれたちの子供だって思える?」とつぶやいたほどだったと言う。
なぜこの親なのか、なぜこの子なのか。ぜひ一読を勧めたい一冊だった。(雅)
「残酷すぎる真実」第10回(月刊『波』2015年12月号、新潮社より)
出版社が発行する小冊子。昨年 12月号にとても興味のわく小論『残酷すぎる真実』第10回(著者橘玲)が載っていたので紹介したい。
今回も特にタイトルは掲げられておらず、先ず経営者や海外駐在大使、あるいは政権アドバイザーなどの立場を去った女性たちの話題から始まる。
2003年、ニューヨークタイムズの記者リサ・ベルキンがこの現象をオプトアウト(自らの意志で仕事から身を引く)と名付けたが、その時、「男と女は生まれながらにしてちがっている」と述べたことで、大きな反響を巻き起こしたという。
「モビールをベッドの上から吊し、同時に若い女性が赤ちゃんに笑いかける」と、男の子はモビールを、女の子は女性の顔を見ようとする。アメリカの心理学者レナード・サックスは、幼児教育で「沢山の色を使って表情豊かに人物を描く」よう指導されたADHD(注意欠陥・多動性障害)の男の子たちが、先生の指導を無視してロケットや自動車を描きなぐるのは、男の子に「欠陥」があるのではなく、眼の構造が女の子と違うのだと20年ほど前に指摘した。
網膜には棹状体 (かんじょうたい)に反応する M細胞(小細胞)と、錐状体 (すいじょうたい)とつながる P細胞(小細胞)があり、「棹状体からの情報はM細胞を通して大脳皮質の物の動きの分析を司る部位に送られ、錐状体からの情報はP細胞を通じて質感と色の分析を司る部位へ送られる」。そして男性の網膜にはM細胞が厚く分布し、女性の網膜は P細胞で占められている。この違いが、親や教師が「男の子らしい」「女の子らしい」絵を描くように指導しなくても、描く絵の色の違いや描き方、描く対象の好みが別れる理由なのだと述べる。
また、左脳に卒中を起こした男性の言語性IQは平均で20%低下するが、右脳の場合には低下はほとんど見られないのに対し、女性ではそれぞれ 9%、11%低下するという。これらは胎児の段階からの性ホルモンの影響とみられ、その結果、男性の「空間把握や数学的推論」「システム化」に対し、女性は「言語の流暢性」と「共感」に秀でているとされる。
このほか、イスラエルのキブツでの男女一切区別なしの教育結果における性別役割分業の傾向、男女の職業選択と満足度、給与に反映させる自分の価値の見積もり方、これらから、「最新の遺伝学や脳科学の知見は、男と女では生まれつき『幸福の優先順位』が異なることを示唆している」と結論づけている。
わずか6ページの紙幅のなかにも凝縮された内容があり、かなり刺激的で脳科学的な知識を補完するものであった。テーマは毎回違うが、今後もまた楽しみな連載だと思う。(雅)
『「平穏死」のすすめ』石飛幸三著(講談社、2010)
『日本人の死に時』久坂部羊(幻冬舎
、2007)
前者は特別養護老人ホームの配置医が著者。
現在、多くの医師は、自然死の姿がどのようなものかを知る機会が無い。自身もホームの配置医になって初めて知ったと言う。病気を治すことばかりを教える今の医学教育と医療は違うのだと著者は強調する。認知症、誤飲性肺炎、胃瘻手術、延命医療、ターミナルケア等々、「口から食べられなくなったらどうしますか」というテーマは重い。
「最後は水だけ与える、そうすれば精神が落ち着き自然に戻る」という三宅島の言い伝え。胃瘻は「食べられないこと=死」という前提を崩した。しかし、それが逆流して肺炎を起こしかえって苦しみを増すことも。本当に死に向かう人のためになるのか、家族は苦悩し迷う。「我々は何か間違えているのではないでしょうか」。
著者は特養ホームでの看取りを通して人間らしい穏やかな死に方があることを知るが、また、そこが平穏な最後を迎えたいという基本的な欲求を完結できるシステムになっていないことも痛感する。ある特養の施設長がオランダのホームを視察した時、認知症の老人の口を開けてスプーンを入れようとしたところ、現地のワーカーから「あなたは何て恐ろしいことをするのか。この人は食べたくないのに。あなたは老人の自己決定を侵害している」とどなりつけられたと言う。後から届いた手紙には「私たちは、食事は並べるが、無理に食べさせたり、チューブを入れたりしない。そのままでも安らかに死ねる」とあった。
後者は、特に“老”に焦点を当てたもの、著者は訪問診療を行っている医師である。
何歳まで生きれば“ほどほどに”生きたことになるのか。命を延ばすことを目的にしてきた医療の結果、日本人の平均寿命は世界のトップクラスとなった。しかしそのために健康寿命との差は広がり、平均で男6.1年、女7.6年の寝たきり生活を送るという。アンチエイジングがもてはやされる一方、巷に溢れる健康情報にはあまりに嘘が多い。仕事がら接してきた多くの老人にとって長生きはどのような意味があったのか、医師としての無力感や迷い、今も分からないとの切実な思いを語っている。
この時代に本来の老人医療はどうあるべきか。私たちはどう上手に受け入れ満足な死を得られるか。著者は欲望にはきりがないと悟って、老人力の代わりに無頓着力、満足力、感謝力をつけることを勧める。老病死の事実をしっかり知ることが大事だと思う。“老”を自覚する人はもとより、まだ先の話と思っている方にもぜひ一読を勧めたい。題名から来るイメージとは裏腹に読後感は明るい。(雅)