![]() 月刊サティ!
月刊サティ!
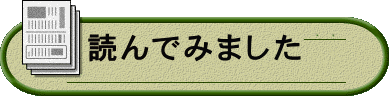
2014年1月号~6月号
血縁関係の無い二人、遺伝情報(ヒトゲノム )が 99.5%一致しているのに見た目が全く違うのはなぜか。それは遺伝子スイッチが入る順序やパターンの違いによるもので、外部からの刺激や変化の総称としての環境がそれに影響を与えるそうです。ですから、「親は、子どもの個性や方向性、つまり遺伝情報を充分意識しつつ、必要な遺伝外情報を教えることが大切」と著者は言います。学習、訓練の大切さや子への接し方などの主張は私たちが学んでいることと通じていて、スーッと胸に入ってきます。
ところが、遺伝子は利己的なものだという先入観に対して、第4章「ゆずり合い、助け合う利他の心」では、「遺伝子は、利己的でありながらも、利他的な特徴をも獲得」していったとあり、一月のQ&Aの解説の通りでした。そして「利己と利他とは・・・実のところ表裏一体」であり「『利他』とは、自分を後回しにして他人の役に立つように生きることですが、実はそうすることで自分も生かされる」ことになるという訳なのです。
子育てというのはやり直しのきかない難しいものですが、要は親の心構えの部分がとても大きいと思います。夢中(と言うより霧中)で過ごしてしまった当時ですが、早く出会っておきたかった一冊でした。(雅)
高峰秀子がサラッと口にした言葉を養女の斎藤明美が綴ったエッセー集。短い言葉の中に高峰の鋭い感性と人間への洞察がありありと見えてくる。
30の言葉はどれも興味あるものばかりだが、なかでも「忙しい時ほど余裕を持たなきゃいけないよ」の項をぜひ紹介したい。ある時夫の松山善三が台所仕事をする高峰の姿を見やりながら、「かあちゃんはノロいけど、速いんだよね」と言ったという。
「矛盾した言い方だ。だが高峰の動作をきわめて的確に表している。高峰は一つ一つの動作が実に丁寧な人だった。だから椅子にかけたまま遠くのゴミ箱に紙くずを投げ入れたりという類の動作は絶対にしなかった。それがどんな些細な動作でも、その一つの動作だけを最初から最後まできちんと行った」
まさに、日常生活のサティのようだ。“ながら○○”をしない。大いに反省させられた。
また「いつも心のノートを真っ白にしておきたいの」。高峰は白が好きだったという。汚れが生じればすぐに分かって掃除が出来るから汚れは目立つ方がいい。心の汚れも同じこと、そうやって自分の心のノートを真っ白に保ってきたに違いないと著者は言う。
その他に「苦労は、磨き粉みたいなもんだね」「食べる時は一所懸命食べるといいよ」「私は、イヤなことは心の中で握りつぶす」などなど。こうした洞察や感性は本人が持って生まれたものとともに、否応なくエゴを統べざるを得なかった末の人間観察、自己理解によるものだと思う。自分の心構え次第で人はどんなものからも学べるということを改めて感じた。(雅)
『単純な脳、複雑な「私」』池谷裕二著(講談社、2009)
脳科学者である著者の出身高校での双方向の授業をまとめたもので、脳とは、心とは、私とは、という生徒とのやりとりは臨場感いっぱいです。
ボリュームと内容の多様さからサラッと「読みました」とはいかないのですが、あえて紹介しようと思ったのは、瞑想の理解に側面からのヒントがあちこちに出ていると思われるからです。例えば、脳について考える時の作法として重要にもかかわらず忘れ易いことの一つが「心を外から眺めること」などは、ヴィパッサナー瞑想と通じるところです。
また、他者の存在を意識するようになった進化の過程で「自己観察力」が生まれ、「自己観察して自己理解に至るというプロセスは・・・進化的にはコストは低い。こうして僕らは、自分を知るために、一度、外から自分を眺める必要が生じてしまった」のだそうです。そして、トレーニングによって、意志が生まれる脳のゆらぎそのものを「直接、意識的に変えることができるかも知れない」とは、まさに反応系の修行に通じる印象でした。このほかにも、心について理解の幅が広がるような話題がいっぱい。とくに第一章「脳は私のことをホントに理解しているのか」、第二章「脳は空から心を眺めている」は、私たちの瞑想の裏打ちとして納得のいくもので、内容のある一冊でした。(雅)
『母がしんどい』田房永子著(新人物往来社、2012)
これは新企画の時に先生が例に挙げた一冊 (コミック)である。試しにカスタマーレビューを見てみると、出るわ出るわ、母との深刻な話が次々と書かれていた。早速図書館から借りて読んでみた。
『続々母原病』 (久徳重盛著サンマーク出版)にもさまざまなタイプが出ていたが、よく病気になったりグレたりしなかったと、逆に感心するほどだ。過干渉の弊害などどこ吹く風、身勝手な感情の赴くままに娘に向かう母親のエネルギーが凄まじい。一人娘のためそれをまともに食らいながら自分の気持ちをはっきり言えず、自分が悪いのだと思って無理に我慢していくもどかしさ。理解してくれていると思っていた父もそうではなかった・・・。
ついに精神科へ。これが良かった。「あなたはとんでもない親からとんでもない育てられ方をしたんです」「子どもが幸せになればなるほど『私のおかげ』って恩を着せる人達だからね」「お母さんいくつ?」「60歳です」「残念!あと二十年は生きちゃいますねぇ~ハハハ」「(えーっ、親のことそんなふうに思っていいんだ)」。「親に会わなければいいだけ。もうここには来なくて大丈夫」。治療は何もなかった。
かつてダンマトークで、人間関係について「どうしても駄目なら緊急避難的に逃げ出すしかない」(そのあとカルマの話が続いたけれど )と聞いた覚えがあるが、それは本当だ。
著者の結論は、「結局自分のことは自分で責任を持つしかないんだ」という平凡、しかしあたりまえの真実だった。(雅)
『ここは私の居場所じゃない~境界性人格障害からの回復~』レイチェル・レイランド著(星和書店、2007)
境界性人格障害( BPD)と診断された30代の女性レイチェルが、精神科医による精神分析的治療を受けて回復していくまでの実話である。
「女性はなべて弱く、人を巧みに操り、感情的過ぎ、劣る者」という女性像をもつ厳しい父親によって彼女の女性性は否定され、母は夫の女性像に沿うかのように全面的に父に頼り切っていた。その結果彼女は、「忌むべき女性」である事実を受け入れられず男性のように振る舞い続け、心は宙づり状態になっていた。そしてその心の歪みを“拒食症”と“抑圧”によって何とかバランスを取ろうとするが、それがうまくいかなくなりそうになると“脅しや攻撃”に出るというパターンを繰り返してきた。
そんな彼女が精神科の病院に入院することになった日、担当医のパジェット先生にこう言う。「ここは私の居場所じゃない!」と。
それは、私には、「世界のどこにも自分の居場所がない!」という悲痛な叫び声として響いた。
彼女の心の中には、強烈な人間不信、屈辱感、無価値感、自己非難が渦巻いていた。しかし、そのような激しい心の疼きから生じるどんなひどい言動も、パジェット先生は、いわば父親として“ありのままに”受け止め、レイチェルの心に問い続けることによって、癒し育んでいった。
4年にわたる治療の間、先生との間に繰り広げられたもの、それはまさに彼女の心を育み直す営みそのものだった。
ついに、最後の面接を迎えたとき、彼女が先生に手渡した贈り物に添えた手書きのカードには、こう書かれていた。
「かつては暗闇が立ちこめていたのに、今ではそこに美が見えます。私たちはともに石炭を掘り起こし、それがダイヤモンドであることを明らかにしました。新しい人生の幕開け。新たな春は不思議さに満ち、決してその輝きが失われることはないでしょう。あなたの心の娘レイチェルより」
最後の面接を終えて帰宅した彼女は、茫然としながらも、家族が先に向かったレストランに出かけ、そこで家族を見つけてこう言う。
「・・・私の居場所はここだったのよね。家族みんなと一緒・・・」
この実話は、気づきへのアプローチこそ異なるが、生きていく上で“あるがまま”を認め、受け入れることがいかに大切かを教えてくれる。そしてまた、“心を育み直す”ことは出来るのだと言う。今「苦」の中にいる人への貴重な贈り物である。(清水啓子)
『やなせたかし明日をひらく言葉』やなせたかし著(PHP研究所、2012)
1月5日のNHKスペシャルで、アンパンマンの生みの親、やなせたかしさんの特集がありました。私はこの番組で、やなせさんの来し方とその人生観に深い感銘を受け、『やなせたかし明日をひらく言葉』を読んでみました。この本は右ページにやなせさんの著書からの言葉、左ページにエッセーを綴ったものです。
悪人や怪獣を倒すだけのヒーローに疑問を持ち、「本人も傷つくんだけれど、それによって人を助ける」世界で最も弱いヒーロー、アンパンマンを生み出したやなせさん。その哲学の核心とも言える、生きる目的は「人を喜ばせること」だという言葉に出会った時、私は体が震えるような感動を覚えました。なぜなら、それこそが真の幸せへの道、私たちは本来周りの人々を幸せにせずにはいられないのだということに気づいたからです。
未熟児で生まれたこと、5歳の時の父との死別、伯父の家に引き取られ育てられた心の葛藤、中国での戦争経験、漫画家になってから続いた長く不遇の時代、体が弱くて病気との闘いの日々など、文字通り試練の連続の人生を送ってきたやなせさんは、一時は自殺未遂をするほどの辛酸をなめながらも、人の真の幸せは自分の真の幸せに通じるという信念をとことん実践した方だと思います。
「大震災から三日後、あるラジオ番組に『アンパンマンのマーチを流してください』と言うリクエストがあり、さっそく放送したところ、子供たちがラジオに合わせて大コーラスを始めた」のも心から頷けます。その日からラジオ局は連日この歌を流しました。「幼児は世の中で最も冷酷な批評家」なのです。やなせたかしさんのような清らかな心の持ち主の方は、すべての過去を乗り越えて今の瞬間に生きることができるのだと感じました。私はその無私の心に深く打たれるとともに、その生き方を見習って、自分も周りの方々も幸せにするためにクーサラを続けていきたいと思いました。(U&I )
日本全国で処分される犬と猫は年間約18万頭。1日あたり500頭近くが殺されている。そんなかわいそうな姿など見たくない。そう思う方も多いだろう。確かに本作には、目をそむけたくなるような現実も映し出される。しかし、その姿に涙しながらも、観終えた後は不思議と、救いようのない不快な重さや暗さに引きずられない。公開から5年を経た今でもその問題提起の切り口の鋭さから、全国の動物愛護団体、市民団体等による上映会が各地で行われている。
朝日カルチャーの『ブッダの瞑想法』で知り合った法友が主催する松戸の自主上映会にボランティアとして参加した。映画の内容もさることながら、動物の『命』に対して関心を寄せる、来場者の真摯な眼差しが印象的だった。(T.O.)
次回、5月 24日 (土)に上映予定。 http//inochi-shiawase.jimdo.com/
『動的平衡』福岡伸一著(木楽舎、2009)
生命現象とは何か。それは「動的な平衡状態にあるシステム」、これが著者の結論である。この結論に至るまで、著者は記憶から始まって脳の考察を経、生命維持にとっての食べ物とは何か、飢餓と肥満とはどのように関係しているのか、そしてついには細胞から細菌、ウイルス、プリオンというミクロの世界にまで焦点を当て、ミトコンドリアに行き着く。途中、「消化とは、食べ物情報の解体」であることから、「○○○ゲンを食べ物として外部から沢山取り入れても衰えがちな肌の張りは取り戻せない」とか。がっくりである。
それはさておき、著者の眼目はそこではない。
ルドルフ・シュタイナーのマウスを使った実験を証として、生命は外界と隔てられた実体としての存在などではなく、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかないこと、さらに端的に言えば、これも一時的に形作られているだけの容れ物のなかを分子が通り過ぎる流れそのものであると結論づける。つまり「その流れの中で、私たち身体は変わりつつ、かろうじて一定の状態を保っている、その流れ自体が『生きている』ということなのである」と言う。
著者は分子生物学者だが、はからずも仏教の無常という真理を生命科学の面から証明(照明)していて、実にすっきりと得心できる。また、終盤にライアル・ワトソンの著書から象と豚の意識に触れているところなど、それだけでも実に感動的であった。 (雅)
『みぞれふる空』米本浩二著(文藝春秋 、2013)
「脊髄小脳変性症と家族の 2000日」という副題の、病気の妻と二人の娘たちと著者との現在進行形の介護・闘病の記録。この病気は、主に小脳の萎縮で歩行困難、手の震え、言語障害、嚥下障害を引き起こす難病で、原因不明で根本的な治療法はなく、緩慢にしかも確実に進んでいくと言う。
毎日新聞記者として単身赴任中(現在は終了)に妻が発病、不用意な医者の言葉に傷つき、思春期・反抗期の娘たちに妻とともに苛立ち、また妻からの言葉の奔流に及び腰になる著者。懸命に現実に立ち向かいながらも、言いたいことを胸にしまって右往左往しているあるがままの姿は、まさに鏡を見ているような感じさえした。
悲惨な状況を何とかしようと、藁にも縋る気持ちで漢方や気功にも活路を開こうとする。
「可能性があれば何でもアリだ。駄目なら撤退すればよい。原因不明で病気になったなら、原因不明で治ることもあり得る、と考えるのが人情だろう」と。
しかし、「歩けなくなったら、這えばいい」と介護やリハビリの専門家にあっさり言われ、「『歩けなくなったら、もうおしまいだ』と思ってきた長年の霧が晴れる心地がした」と言う。
今出来ることを力いっぱいと受け入れた覚悟のすがすがしさがこの本を貫いている感じさえする。「歩けなくなることは終着駅ではなかった。むしろ始発だ。どこまで駅があるか分からないが、もうおしまいと言われるまで旅を続けるしかない」の言葉に、深く共感を覚えた。(雅)
![]() 前ページへ
前ページへ
![]() 『月刊サティ!』トップページへ
『月刊サティ!』トップページへ
![]() ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ
ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ