
| 2023年11月号 | Monthly sati! November 2023 |
| 今月の内容 |
| |
【お知らせ】
※近刊される地橋先生の新しい単行本が現在最終的な段階に入っておりますので巻頭ダンマトークは少しの間お休みさせていただきます。
|
『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |

![]()
![]()
![]()
|
『小説家の瞑想修行』 榎本 憲男 |
|
★二十代から映画の仕事に従事してきましたが、50歳になったことを転機として、あてもなく会社を辞めました。辞めるきっかけとなったのは、すでに45歳ころから自分の頭の中はガラクタだらけだと自覚するようになっていて、さらに、売り上げを追い求める映画作りやマーケティングリサーチなどが嫌にもなり、すこし落ち着いて自分を見つめ直したい、もうすこし落ち着いて本を読み、映画を観たくなったからだ、といえばずいぶん格好をつけているようですが、そういう面がなかったとは言えないと思います。 |
![]()
|
(承前) |
| (1)意識的なことよりも、なんとなく感じていることや無意識に思っていることの方が強く出力され、業を作っていくものだ。 無自覚な思考パターンに、気をつけなければならない。 無くて七癖の常同的振る舞いの自覚化から、人生の流れが変わっていく・・・。 気づきの瞑想をする。 サティを入れる・・・。 (2)過去に作った善業や不善業によって、日々経験する事象はほぼ定まっている。 最悪の事態も超ラッキーなことも、起きることは決定的に起きてしまうのだ。 それに逆らう自由も、受け容れる自由もある。 古い業が新しい業によって微調整されていく瞬間だ。 サティを入れて見送るという選択・・・。 (3)日常生活では、顕微鏡モードの厳密なサティから肉眼モードに変換しなければならない。 眼耳鼻舌身意の情報の中身を理解しながら、「見ている」「聞いている」「考えている」と自分を俯瞰していくのだ。 今、自分は何をしているのかに気づこうとすればよい。 自覚の維持を心がけるマインドフルネス・・・。 (4)次々と水面に拡がっていく波紋のように、優しさから優しさが手渡され伝えられていく。 だが、愚かな善意と智慧なき優しさは、人を真の幸福にみちびかない。 現状を正確に把握し、何が本当に相手のためになるのか熟慮されるべきではないか。 明晰な智慧と優しさが連動する慈しみの瞑想・・・。 (5)1年後には、記憶の40%は当てにならなくなり、感情の記憶になると60%は食い違ってしまうという。 そもそも今の瞬間をあるがままに見ることが至難の業なのに、その不正確な記憶がさらに変容してしまうのだ。 生きてきた証しは記憶しかないのに・・・、人生とは、何なのだろう。 (6)思考の流れが止まり、静かになった心の内奥に耳を澄ませ、どうしてもやりたいと感じることはやってみるしかないだろう。 痛い思いをしなければ骨身に沁みないし、失ってみて初めて値打ちに気づくものだ。 学ぶべきことを学ぶなら、自ら蒔いた種を刈り取る苦しい人生にも意味がある・・・。 (7)何のデータも入れなければ、優秀な演算機能を持つパソコンも空箱同然になってしまう。 学ばない、考察しない、情報を集めない、練習もしないし、修行もしない。 ただ心を空っぽにして、静かにしているだけで洞察の智慧が閃くだろうか。 現実逃避の瞑想、虚しい空っぽ、無意味な静けさ・・・。 (8)習練すべき技能が修められ、必要な情報が十分に集められているならば、余計な準備や計画で頭をいっぱいにしない方がよい。 その瞬間、即興で閃くものにはムダがない。 脳内に用意されたものを意識的に具現化するタスクは、今の瞬間にブレーキをかけるだろう。 心を空っぽにして、静かにしていること・・・。 |
![]()
| PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会編 『PTSDの日本兵の家族の思いと願い』(あけび書房 2023) |
9月29日付の毎日新聞夕刊に<阿倍氏国葬1年佐高信さんと検証>という記事が載り、本文の中にとても気になる次のような文章があった。 |
![]()
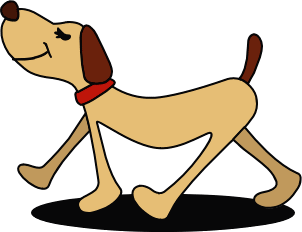 文化を散歩してみよう 文化を散歩してみよう |
| 第11回:韓国文化に触れて(2) |
| はじめから言い訳で恐縮ですが、この欄でエピソードを取り上げているうちにいろいろ思い出してしまい、話題があちこち飛んでとりとめのない印象になりました。ご了承ください。 2)ペンパルのお宅で ソウルではペンパルのお宅に滞在させていただきました。今では考えられませんが、当時は迷惑かどうかなどは全く考えもしませんでした。 ソウルに着いた当日、案内書に載っていた『バンドーホテル(半島ホテル)』のコーヒーショップで友人と一緒にやってきたペンパルと待ち合わせました。どうやって場所と時間を連絡したのか今ではすっかり忘れてしまっています。ともかくタクシーでお宅に向ったのですが、その時の市内の高速道路は今は取り払われていて(9月号)、清渓川という昔の川筋に流れを復活させ、ススキがあったりトンボが飛んでいたりの散歩道になっています。 タクシーで思い出したのが、何年も後になりますが前に述べた同僚と訪韓した時のこと。私は車のことはさっぱりですが、その時のソウルのタクシー(普通の)はみんな同じ形に見えました。現代自動車製のポニーとかいう車種だったようで、エンジンは三菱のものをモデルにしていると聞きました。ただタイヤが見た目にも減っているのにけっこうスピードを出したりしていたので、同僚と一緒に「大丈夫か?」と話したことを思い出します。今となってはそんな時代もあったのだなあという感じですが。 Nam(南、以下漢字で表示しますが読み方は“Nam”です)さんというペンパル(以下:彼女、)のお宅はソウルも東寄りの清涼里というところにありました。どこで高速道路を下りたのか覚えていないのですが、おそらく清涼里駅から続く広い道だったと思います。もしソウル駅が東京駅にあたるとすれば、清涼里駅は上野駅に符合するような感じで、たたずまいもそんな雰囲気を受けました。後に大きなロータリーに変貌する駅前はまだ未舗装で大きく開かれ、彼女のお宅の近くまでそこから広い道が続いています。あまり自動車も通らず、どちらかというとのんびりした感じでした。なぜそんなことを覚えているかというと、私の街にも環状7号線が開通する以前に雰囲気がよく似たところがあったからです。 私の街には、かつて軍用道路のために整備された広い道が常磐線の北側まできていて、長い間そのままになっていました。そこは線路で行き止まりになっていますから車もめったに入ってこないので、未舗装でただのだだっ広い場所だったという印象しか残ってはいません。昭和40年代の中頃、常磐線が高架になると環状7号線の工事も進み、街並みはすっかり様変わりしてしまい、今では四六時中車の絶えることがなくなっています。 で、清涼里から彼女の家までの道の様子がちょうどそんな感じだったというわけです。 彼女のお宅は2階建ての縦割り住宅でした。日本で縦割り住宅といえば一般的に2世帯らしいのですが、そうではなく、何軒もが一続きになっているようでした。ただその建物はおそらく日本が統治していた時代のものではなかったかと思われます。なぜなら、滞在中に使わせてもらった2階の部屋が畳敷きだったからです。戦後に建てられたものなら畳敷きなどあり得ませんから。 彼女の下には二人の弟と一人の妹。お母さんは多分当時40代ではなかったでしょうか、日本語は聞くのは多分OKですが話す方は少し苦手にみえました。お父さんとはもう普通に日本語で話しました。彼女や弟(高校生)との会話は片言の英語や、こちらの怪しげな発音の韓国語単語を断片的に並べただけです。もちろん私はまだハングルを読むのもたどたどしくて、国民学校(日本では小学校)2年のもう一人の弟にも及びません。そこで、外に出たときにはできるだけ看板を読むようにしたりの訓練です。ただ、高校生の弟がとても察しが良くて、「Iさんが言うのはこういう意味だ」と回りに説明してくれたりしましたので、実に助かりました。 私は高校生の頃からテープレコーダー(もちろんオープンリール)で、親戚の集りや近所の人が家にお茶を飲みに来たときなどの会話を面白がって録音をしていた時期がありました。また受験生時代にそれで英語を勉強したこともあり、その時に小型のレコーダーをプレゼントに持っていって、ついでに彼女に練習帳にあった韓国語会話を吹き込んでもらったりしました。 2000年を過ぎてから、かつて録音したテープには貴重な故人(祖父や祖母、叔父叔母、父母、近所の人など)の声などが入っていますので、それをCDにコピーし直そうと考え、ためしに一部を業者に委託してみたことがあります。業者からの回答は、テープ自体が古くなってブツブツ切れてしまうので到底出来ませんということで、がっかりしました。 もうひとつ凝っていたのが「スライド」と「8ミリ」です。「8ミリ」は別として、スライドでは汽車や電車、近所の雪景色、花、神社の神輿などなど、自分では「けっこうセンスある」と思いながら撮っていました。 余計なことですが、第2回で触れたカリフォルニアでの派米農業実習生に応募し、合格を目指して力んで農業の勉強を始めたきっかけは、先輩の帰国報告会で見たスライドの雄大なアメリカの景観でした。それほど強烈なインパクトがあって、やる気が俄然高まったものです。もっとも、5万円(当時)の保証金で1年間アメリカ生活を経験出来るというのも大きな魅力だったので、なおさらですが・・・。 で、スライド映写機まで持って行って、これまで自分で撮り溜めたスライドを見せたりしました。 私:Do you want to go to Japan? 彼女:ネー(韓国語で「はい」) 多分社交辞令でしょうけれど。 ちょっとエピソードです。 100円から文通が始まり、韓国語(のはずの)手紙を彼女の友だちが真っ赤に添削してくれたことは第3回で述べました。今とは違い大学書林の『朝鮮語入門』くらいしかほとんど教材もない時代で、それも「韓国」語ではなく「朝鮮」語です。それで例の在日の同級生が私が韓国へ行く前に、『イムジン河』(北朝鮮の楽曲、当時日本でも流行っていた)をとりあげて、「Iさん、この歌ソウルの町の真ん中で歌ってごらん、捕まるよ」と言ったりしたついでに、「『朝鮮語』勉強してる?」と聞いたので、「No、No、『韓国語、韓国語!』」と言ったら、「その調子、その調子!」と苦笑いしたものです。 とはいえ、教科書だけでは、文章の仕組みはなんとかわかっても、口の開け方の図を見てそのようにやってみたところで、あたりまえですが発音が正しいかどうかはまったくわかりません。テープなどの教材や韓国語教室もほとんどないころです。それでも、どこでどう探したのか覚えていませんが、お茶の水にある韓国YMCAで韓国語を教えているのを知り1年ほど通いました。先生は東大大学院への留学生で、国民学校1年生の教科書を使って「カナタラ」(あいうえおに相当)から始め、まがりなりにもなんとか慣れていきました。 そのあと、縁あって日暮里にある韓国協会の牧師さんから日本に保育の研修に来ている方たちを紹介してもらったところ、なんと私の学科の留学生がその人たちと知りあいだったということもあり、けっこうグループで時間を過ごしたりしたものです。で、あるとき2週間韓国に行ってきたら、「Iさん急に韓国語うまくなったね」と言われて少しはうれしく、また「やっぱり言葉は中に入るのが一番だな」と思ったり。 もとの話しに戻ります。 はじめての韓国訪問にスライド映写機やテープレコーダー、もちろんカメラも、それもあちこち回り道してよくもまあ持っていったと今となっては思います。 お土産にしたのはテープレコーダーのほかに、洋酒(あの頃はとにかくジョニ黒)とタバコ(多分マイルドセブン)です。洋酒は容量にリミットがあったり、日本製タバコは禁止だったと後で知りました。でも、なぜか税関では何ごともなく、またお父さんは知ってか知らずかお構いなしで、タバコを近所に配ったりしていたようです。 で、こちらへのお土産はというと、一族の長老らしい方から青磁の花瓶、パジチョゴリ・チマチョゴリ、螺鈿の飯台でした。青磁の花瓶は残念ながら割れてしまい、パジチョゴリ・チマチョゴリはボロボロになってしまいましたが、螺鈿の膳はいまでも別の目的に使っています。いずれ食事の話題が出たらまた触れようと思います。 実は、ペンパル時代に日本人形を彼女に航空便で送ったことがありますが、当時は(今はわかりませんが)日本文化を彷彿させるようなものに対する規制があって返送されてしまいました。そんなこともあって土産ものには少し神経を使いました。 そんな時代ですから、もちろん日本の歌謡曲などはもっての外だったはずです。ですが、先ほど述べた練習のために吹き込んでもらうついでに、興味に任せて会話や私の親へのメッセージを録音したりしていたら、彼女は西田佐知子の「アカシヤの雨がやむとき」を唱ってくれました。私はそういう歌謡曲などは疎いのですが「えー!」と思いました。そんな疎さの証明みたいなものですが、それからほぼ20年後、7月号で触れた通訳をしている女性が「恋人よ」を唱ったのを聞いた時も、歌手が誰かも知らなかったし、おまけに名前も「ごりん」と読んだくらいで、まったく・・・。もっともカラオケが入るようになるとそこでは日本の歌謡曲もあって、細川たかしの「北酒場」などもありましたけど・・・。 いずれにしてもいろいろ規制したところで隙間はどこかにあるようです。 ※韓国ではカラオケ店をノレバンと言います。ノレは「うた」、バンは房の漢字読みで部屋のこと。喫茶店はタバン(茶房)と言います。ついでですが、韓国語では漢字の読み方は原則ひとつですが、「茶」は珍しく読み方に「タ」と「チャ」のふたつがあります。 ところで、日本にも東・西・南・北という一字姓があります。そのため“Nam”さんは悪名高い創氏改名政策でも改名せずに済み、日本人からは「みなみさん。みなみさん」と呼ばれてとても親しくされていたそうです。それどころか、お父さんが日本のことを「内地では・・・」と言われたのにはちょっとびっくりしました。(※韓国の姓名については別に取り上げたいのですが、以前先生の著書を韓国語に翻訳された南さんはルーツを同じくする一族です) で、お父さんと日本語で話をしているのが聞こえた近所の人から、南さんの家には日本人が来ているのか、それとも在日韓国人が来ているのかと訊かれたりしたそうです。そして、お母さんのお姉さんや旦那さん、つまりおじさんやおばさん、従姉妹たち(金ヌナ(第7回)やその弟たち)を始め、親戚の人たちがとっかえひっかえ尋ねてきた(見に来た?)り、賑やかでとても楽しい経験でした。 そんなこんなで、毎年夏になると夏休みを利用して訪韓することが続きました。とくに記憶に残るのは、8月15日、南さん宅でテレビを見ながら「今年もまた8月15日は韓国だった」という年がけっこうあったことです。そして暑い夏のこと、あっちで昼寝こっちで昼寝、私もラフな格好で・・・。それがまったく不自然ではありませんでした。 ただ朝晩、というより朝はけっこう湿度が低いためか清々しく、朝鮮という名前が「朝の鮮やかな国」を意味すると自負しているのももっともだと思いました。(※李成桂が建国した朝鮮の国名については歴史的な話があり、この欄のテーマではないので触れません) このような、遠慮というものをすっかりどこかに置いてきたようなおつきあいが、私の韓国の印象のベースになっています。ただ、その後いろいろな人と知り合っていきましたので、どこの国でもさまざまなのは同じだな、と思うようになりましたが。(つづく)(M.I.) |
スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ著、奈倉有里訳
|
| ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ 『月刊サティ!』トップページへ |