
| 2023年10月号 | Monthly sati! October 2023 |
| 今月の内容 |
| |
| |
巻頭ダンマトーク:今月は休載いたします |
| ダンマ写真 | |
| |
Web会だより ー私の瞑想体験- :私の「聞法」と「実践」 |
| ダンマの言葉 :『四人の友(慈・悲・喜・捨)』・・・3 | |
| |
今日のひと言 :選 |
| |
読んでみました :ロバート・モンロー著『究極の旅』日本教文社 1995) |
| |
文化を散歩してみよう :韓国文化に触れて(1) |
| ちょっと紹介を! :猪木寬至著『アントニオ猪木自伝』(新潮社 2000) |
【お知らせ】
※近刊される地橋先生の新しい単行本が現在最終的な段階に入っておりますので巻頭ダンマトークは少しの間お休みさせていただきます。
|
『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |


![]()
|
私の「聞法」と「実践」 H.M. |
| ヴィパッサナー瞑想に取り組む皆様のご参考になればと思い筆を取りました。コロナ流行にかまけて中断していた瞑想を再開した経緯と、その前後半年余の自分の心や日常生活がどう変わってきたかにつき記します。
<瞑想との最初の出会い> 私はいわゆる社会人になって以来何度か転職をしましたが、自分がやりたいことにチャレンジできる環境には恵まれていたとの実感があります。一方で、人生を共にする人との死別も経験し、また、仕事において責任が年々重くなり、昼夜を分かたずメールに追われるなど多忙な日々を送って来たため、厄年にさしかかる8年前あたり から不眠等の心身の不調に見舞われるようになりました。 そんな不調を解消したいとウェブで運動の機会として体幹トレーニングのスタジオをみつけ通い始めました。同時期に大乗仏教の僧侶でインドでヴィパッサナーの修行もされた方が都内の区民センターで瞑想会を開かれているのを知り、参加したのが瞑想との出会いとなりました。 瞑想会では坐りの瞑想が中心で合宿にも参加し、心身の観察のようなことができてきたと自分なりに実感がわいていました。しかし6年前の転職の後、特に余暇の時間が取れない日常となり、指導者も転居するなど瞑想習慣がおろそかになってきたところでコロナ禍が発生、2年ほど前からは瞑想会そのものが開かれない状況となり、次第に瞑想から遠ざかるようになってしまいました。 <コロナ禍の中でのプロジェクト> 2020年の初め、観光船でのコロナ感染のニュースが大きく報道されていたころ、会社では社運を賭けたプロジェクトが実を結ぼうとしていました。世界的にコロナの不安が急速に広まりつつあるころで本当にそれを実行してよいか議論があり、感染状況や経済活動への影響を日々追いかけながら、最後の一歩を踏み出すことに躊躇がありました。 ある日、上司の並々ならぬプロジェクト完遂の覚悟に触れ、自分の中で「ここまで来たらやろう」という声がしたような気がしました。覚悟が決まりプロジェクトを船出させる決断をしましたが、そこには「自分の意思」による発信という積極的な意識はなく、誰かに背中を押されたような感覚でした。 今にして思えばそれは、自分がこうしたい、という小さなエゴを越えた大義であって、世間で言う「スーパーエゴ」のようなものだったかもしれません。しかしながら結局それもエゴの一つではなかったかと思っています。なぜなら、プロジェクト完遂までの一つ一つのプロセスを進めていく課程で、課題それぞれは小さくてもミスなくきっちりやり遂げよう、やるのは「自分だ」というエゴがいつの間にか心の中に広がっていったからです。 プロジェクトを実行していく上では、もちろん考え方やスタンスの違う人々とも接していかなければなりません。そうすると、たとえば他社との統合の局面では、仕事の進め方や考え方について両社で意見や視点が違ったりします。そうすると、「そちらのやり方は自分たちと違う」ということだけではなく、「間違っている」というような評価から軋轢も生じてきます。 何気ないそういう小さなすれ違いを繰り返すうち、「自分」という意識に伴って否応なく怒りの芽が生まれてきてしまいました。そのうえ、その怒りの芽が表面にも浮かび出してきて悩みが増大する中で引き続き睡眠時間が短い日々が続き、結果仕事の効率も下がっていきました。そしてついにはそうした状態を周囲からも指摘されるようにもなり、行き着いたのは自身のありようについて早急に対応を迫られるというところでした。 <気づきと変化> そのような状況に煩悶していたなか、再度瞑想の機会がないかなぁとウェブで探しているうち「これは!」と感じたのが朝カルの地橋先生の講座でした。そこで、サティの再履修を一からするつもりですぐに申し込み(今もリピート中)、併せて1day合宿にも参加しました。 地橋先生の著書は、これまで渉猟してきた仏教関係の本のなかの一冊でしかありませんでした。しかし講座では、「ダンマトーク」で三毒・四聖諦・五蓋から因果論、慈悲の瞑想などが基本から丁寧に説かれ、さらに理論と明確に結びつけられた実践がわかりやすく指導されていました。 私の場合ですが、特に坐りの瞑想の前段階の修行として行われる歩く瞑想にはかなりのフィット感がありました。おそらく先に述べたように3年程体幹トレーニングをしてきたこともあって体の感覚を捉えやすく、坐る瞑想より歩く瞑想のほうが妄想や思考が入りにくいように感じられました。 ダンマ(トーク)の学びと並行してサティの実践を日常生活でも意識していくうちに、具体的な変化という手応えも自覚されるようになってきました。その「成果」は次のようなもので、この先も深めていきたいと思っているものです。 第一に、怒りの発生時点の感覚に意識してサティを入れるようになってくると、日常の仕事などの場面で「誰が(した、しない、よい、よくない)」という主語を意識して思考することがなくなり、単に「事象」だけを観られるようになったことです。その結果、あくまでも「事態の解決」という目的に絞った会話が習慣化するようになりました。 そうすると、それまでは叱責を恐れて内心硬くなっていた様子の部下の心も打ちとけてきていろいろ話を聞けるようになり、それとともに周囲からも良いアイデアが出るようになってきました。こうして、「心理的安全性」がもたらされた結果、良いコミュニケーションから良いアイデアへ、そしてそれが再び心に安定をもたらすという好循環を生むという大きな変化がありました。 今後は、仕事上だけではなく、日常生活での身近な人や環境でも同様に対応できるようになりたいと思っています。 第二は、特に会社における儀礼的な付き合いや、若いころにしていたような空腹でもない中での食べ歩き飲み歩きのような生活習慣などにおいて、それらは本当に今の年齢・状況の自分に必要なのかどうかを客観的に観られるようになったことです。 本当に自分の心と体に問いかけて必要であればそのまま続けるとしても、不要だなと感じれば手放していく、断捨離のような決断が自然に出来るようになったことです。それによって心に余裕が生まれ、気持ちが楽になってきました。 聞法と実践という双方を大切にされる地橋先生や参加される皆さんとの出会い、共に学ぶ機会は、煩悩や執着を毎日ただ落としていけばいいという安心のもとで仏・法・僧への信(サッダー)を揺るぎないものにしてくれました。これからまたいろいろな苦の原因と向き合っていくなかで、将来独り練修していくこととなっても聞法と修練に励めるよう、一回一回のセッション、合宿の機会を大切にしていきたいと思っています。 |
![]()
|
(承前) |
![]()
![]()
| ロバート・モンロー著『究極の旅』(日本教文社 1995) |
| 本書は、精神の旅であり、探索の旅路である。
著者が自分とは何かを探索して、その答えを得た旅を記述している。 著者は、体外離脱活動を経て、結局「自分がどこから来たのか、どのようにここへ来て人間になったのか、なぜここにいて、最終的にはどのようなスケジュールで、どこへ去って行くのか」を知ることができた。 本書で「向こう側」すなわち物質界の境界線の彼方にある意識の領域(これを精神世界と呼ぶことにする)を、地図に記そうと試みている。著者は、精神世界の地図制作者である。その地図は、著者が体外離脱をし、その世界を探索することによって作られる。 著者は、ある時、偶然に体外離脱できるようになった。そして、体外離脱がこうやれば確実にできるということを見出した。この体外離脱を使って、精神世界への探検に乗り出す。 この精神世界の探索で、知的生命体に出会う。彼はインスペックと呼ばれ、著者が体外離脱をした後、精神世界の中のいつもの待ち合わせ場所で会う。そしてインスペックの助けにより、いろいろな世界を探検する。このインスペックは、著者の教育係も務めているのだ。 探求していろいろなことを学んだ。地球の生命系は、我々の住むところであるが、時空に支配されている。著者は、地球の生命系が時空全体を包括しているMフィールドと呼ばれる非物質的なエネルギー場を発見した。Mフィールドには各種の生命体が集まっており、さまざまな思念が放射されている。すべての生命体は、コミュニケーションのためにMフィールドを利用している。その思考を捉えるには、テレビのチャンネルを切り替えて、番組を見るように、その思考にチャンネルを合わせれば良い。総じて動物は、人間よりもM放射に敏感である。 Mフィールドのうち、無秩序な人間の思考の波のHバンドがある。 精神世界のHバンドノイズには、思考が飛び交っている。地球のあらゆる生物、とくに人間から発するコントロールされていない思念波のピークである。 著者は、Hバンドの思考は耐えられないくらいの雑音だと言っている。ただ、その思考にチャンネルを合わせなければ、その思考に翻弄されることはない。ただし、それには訓練が必要である。 著者は、Mフィールドを超えて、さらに先の精神世界を探索する。 例えば、あるとき精神世界の中で記憶の層にアクセスすることができた。そこでは自分のいかなる過去にもアクセスでき、さまざまなものが学ばれた。なぜ過去にそのようなことをしたのかの理由もわかった。 そして、さらなる向こうの私にたどり着く。そこで、もうひとりの自分と話すことによって、過去のさまざまな出来事の意味を教えられ、それらの経験がいかに貴重だったかが深く理解されるのである。 著者が故郷に帰りたいと言うと、インスペックは、瞬時に故郷に連れて行ってくれた。心を故郷に向ければ、そこに瞬間移動できるのだ。だが故郷に帰還してはみたものの、そこには目新しいものは何もなかった。そして、それゆえに自分は故郷を抜け出してきたのではなかったかと、著者は思いがけず思い出していた。 変化のない故郷はつまらない。それに比べて、地球は四六時中学ぶことばかりである。変化や新しい知識が絶えず押し寄せてくる。 インスペックは、面白いことを言っている。 人間としての記憶や経験が大事で、人間でなくなったときにそれらが大きな価値を持つらしい。だから、人間としての経験を卒業してきた者は、他の場所で非常に敬われるらしい。それにしても、「人間を卒業する」って何?と思ってしまう。 この「人間を卒業する」という言葉を、私は他でも聞いたことがある。史上最大の霊能者と言われるエドガー・ケーシーも同じ「人間を卒業する」ということを言っているのだ。 地球の生命系を見ると、競争ということが「生存する」ということから来ている。生命にとって、生存欲は一番強い欲求である。地球の生命系は、食物連鎖による弱肉強食のシステムなのである。地球の生命系は、さまざまな欠点もあるが、素晴らしい教育機関である。この機関によって私たちは、おのおののやり方でエネルギーについて幅広く理解し、それを制御し取り扱うすべを覚えていく。 以前にスマナサーラ長老が、天界に再生するよりも人間界に再生するのが一番難しい、と説法されていたのを思い出した。人間に生まれるのは奇跡のようなものである。天界では厳しい修行はできず、人間に生まれるからこそドゥッカ(苦)を体験し、無常の真理を目の当たりにする修行ができるのだ。だから人間界に生まれた幸運に感謝しなければならない。 後でわかるのであるが、驚くべきことに、インスペックは、未来のモンロー自身だったのである。すなわち未来の自分が、まだ、知識を得ていない状態の自分を教育しているという不可思議な構造なのだ。この精神世界では、過去、現在、未来に一瞬で行けるし、時間的のみならず、空間的にも一瞬にしてどこにでも行けるのである。 あるときインスペックから、新しい方向を目指す時が来たことを告げられる。もう、たくさんのことを学んだ。ただ「基本」という、モンローにとって必須の知識が残っていると知らされる。著者は、その「基本」を求めて、さらなる探求を続けることになるのである。しかし、もうインスペックの力は借りられず、一人で探求しなければならない。 この「基本」とは何かが、この本のクライマックスである。これを求めて、著者は、今度はひとりで探索を開始する。そして最終的に、著者は自分でこの「基本」を探し当てたというより、より高い知的生命体から教えられることになる。自分は全体の部分であり、その部分がいろいろな経験を積んで知識を得てきた。今度は、部分が全体に戻るのだと。そのために、他のいろいろな部分を集めて、一緒に旅立つのだという。その旅立ちの時は3500年だということだ。 著者のこのような経験が信じられるものかどうかは、読者の判断にお任せする。 著者は、この旅で得た精神世界の構造についての知識や体験から、だれでも同じものが検証できるように配慮して、ヘミシングを考案しGatewayプログラムを作った。これにより、あの驚くべき精神世界がだれにでも体験できる可能性が開かれたのである。(N.N.) |
![]()
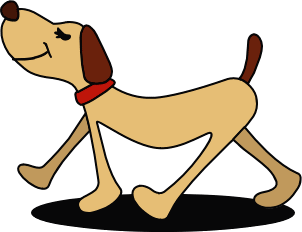 文化を散歩してみよう 文化を散歩してみよう |
| 第10回:韓国文化に触れて(1) |
| これまで韓国関係の話しを対象にしてきたこの欄も今回でちょうど10回目になりました。だからどうというわけでもありませんが、一つのテーマに即していくのは少々難しくなってきたように思います。そこで、とりあえず「韓国文化に触れて」ということにすれば「何でもありか!」と、頭に浮かびましたので、特に掘り下げた考察などもせず(出来ない)、思いつくままお話しすることにしました(もっともこれまでもそうでしたが)。なので、あちこち飛んだりするかと思いますがご承知ください。
○初めての韓国で 1)雪岳山へ あまり興味のある話にはならないかも知れませんが、今回は第1回でスルーした初めて韓国に行った時のソウル到着までの話しを記してみたいと思います。 第1回でも触れましたが、1969年の8月(夏休み)に初めて下関から船で韓国を訪れました。なぜ飛行機を使わなかったのか、今はもうすっかり忘れてしまいましたがおそらく慶州から雪岳山に行こうとしたのではないでしょうか(ひとごとのようです)。また、ことによると単純に船の方が安いと思ったのかも知れませんが、下関までの旅費とかそこでの一泊代も含めて今考えれば割高だったかも知れません。もちろん、船旅にロマンを求めたり、連絡船だけしかなかったかつての時代の旅をなぞろうとしたわけでもないのは確かです。 余談ですが、当時東京では100円はもう硬貨がほとんどだったのに、下関ではまだ板垣退助が使われていて、場所によってこんなにも違うのかと、なにかめずらしいものを見たような、日本は広いなあと感じたりしました。おそらく過渡期だったのでしょう。なぜこんなことを覚えているかというとパチンコ屋に行ったからです。負けましたけれど。 そのころはまだフェリーではなく(関釜フェリーは1970年6月から)、当時もっていた三つ折りのガイドブックには「関釜連絡船」と載っていた記憶があります。ただ検索してもその年に就航していた船の記録に接することが出来ませんでした。そのガイドブックは残念ながら今は手元に無いので確かめることも出来ません。とっておけばよかったと今になって反省しています。 600トン(これも記憶です)の船で夕刻6時に出港し、船中で東京農大の学生や、多分どこかの大学の女子学生らしい人と知り合って、話をしながらの一泊でした。 朝鮮史を研究しているという農大の学生は、そのころ韓国に大学と関係がある農場があってそこを訪ねる予定だそうです。当時の私はただ「海外」に行ってみたいだけで、「朝鮮史」とか「韓国文化」にとくに興味を持っていたわけではなく、ただ「そうですか」と聞き流した程度でした。また女性は「〇〇栞」さん(苗字は覚えていますが略します)と言う名前で、名刺をいただいたかしたと思います。でなければ今覚えているはずがありませんので。ただその時は「栞」の読み方を(聞いたはずなのに)忘れてしまい、帰国後にモヤモヤを解消するため辞典で調べました。で、「しおり」とわかって「ふーん、女性に『しおり』か・・・」と、今考えれば大変失礼ですが、そんなことも心に浮かびました。なにせ、そのころの女性の名前はほとんど「子」が付いていたものですから。ともかく彼女のおかげで漢字の読み方を一つしっかり覚えることができました。 未明の3時ころに到着し、入国手続きまで港の外に数時間待機です。船の名義は正式には何だったのでしょう、今でも気になります。 ちなみに、1970年(2度目の訪韓)も下関からでしたが、その時は正式に「関釜フェリー」になっていて、船も違っていました。その船では見送りの人々との間に五色のテープが出航まで何本も渡され、その風景を写真に撮ったりしましたが、今ではそんな時代もあったのかと懐かしく思い出します。 ところがその2回目の時、釜山で下船する際に団体客が優先されて一般乗客が後回しになってしまいました。団体客はおびただしい数で奥から次々と出てきます。一般乗客(仕事か商売か、韓国人の人たちが大部分)の方が明らかに少ないのに、「なんでそっちが先なんだ!」という声も聞こえ、「まだいるのか!」とイライラしながら待っていたのを今でも覚えています。それがどんな団体かというと、見た目にも欧米人が混じっていたりしている某宗教団体の信者だと思われました。帰国後、写真週刊誌(多分“Focus”)で集団結婚式の写真を見ましたので。 もとの話しに戻ります。 入国手続きを終え、はじめて朝鮮半島の土を踏みました。その時頭に浮かんだのは、「この土地が陸続きでヨーロッパまで続いているんだなあ」と、なぜかユーラシア大陸を思い浮かべて感無量でした。とにかく海外への憧れが強い時期でした。 で、その日のうちに慶州に行こうとタクシーで釜山(プサン)駅に行きました。「プサン」という発音は通じたようです。で、駅の切符窓口で「キョンジュ(慶州)」と言ったのですがなぜか無反応。そうしたら、後ろにいた女性が通訳(?)してくれて、3回目にやっと買えました。こちらはちゃんと発音したつもりでも最初の2回は通じなかったようです。ともかく「キョンジュ」一つでも難しいものです。 汽車には無事に乗ることが出来、青空の広がる慶州に着いたのが午後3時頃。そうしたらガイドをして生活しているらしい日本語を話すおじさんが寄って来て、今日中に全部見られる(夏なので日が長い)からとしきりに勧誘されました。ちょっと警戒心もありましたが、こちらもウロウロするよりはましかと考えて応じました。ガイド料にいくら払ったか忘れましたが、当時は1ドル360円、韓国通貨では270ウォンの時代、何か目減りしたような気分で情けない思いでした。 慶州は新羅の古都ですが当時はまだ一帯が観光整備以前の素朴な様子でした。なんとなくですが雰囲気としては日本で言えば飛鳥のあたりに似ているように感じます。当時はまだ飛鳥に行ったことはなかったので、「今思うと」ということですが。 今は世界遺産になっている「石窟庵と仏国寺」や曲水の宴がひらかれた鮑石亭の曲粋渠なども見学することが出来ました。現在は石窟庵の石仏は保全のためにガラス越しにしか見られないのですが、まだ直接見ることが出来る時代でした。 そのあと、頭の中にユースホテル=安いというのがあって特に予約もしないで行ったのですが、無事に宿泊することが出来ました。ただ、そこでの夕食の時、小学生ぐらい(3~4年生に見える)の男の子と(おそらく)父親が食堂で食べていました。今はそんなことはないでしょうが当時のこと、ハエが数匹飛んでいたのです。 私はかつて八ヶ岳の麓の「経営伝習農場」で派米実習のために団体訓練をしたことがあります。その食堂の近くに牛舎や豚舎があって、そこでは二重の網戸にしてもハエを防ぎきることが出来ません。そこでの食事の時に飛び交うハエに比べればどうと言うこともない数です。 ところがその子はとても横柄な口調で、「なんとかしろよ!」と数回も言ったのです。驚くと同時に「末恐ろしいガキだ。このまま大きくなったらどうなるんだ」と。父親がどんな立場の人なのかわからないけれど観光客のようにも見えないし、こんなところでこんな小さいのが威張り腐ってと、ちょっと暗澹とした気分になりました。 食後、ボーイが「風呂」(が沸いた:多分)と言いに来たので石けんとタオルを持って向かったところ、なんと水でした。 「なんだ、まだ水じゃないか!」とあきれて部屋に帰りそのまま寝てしまったのですが、あとで韓国では夏は洗面器などのお湯で体を拭くだけだと知りました。湿気が少ないのでそれでいいのだそうです。ちなみに銭湯文化は統治時代に日本が持ち込んだものです。 余談ですが、1999年12月に縁あってヨルダンからイスラエル、エジプトへ行ったことがあります。ご存じのように乾燥地帯です。もちろんホテルに泊まったのでシャワーを浴びましたが、そのことではなく、長袖のワイシャツの袖口が全然汚れないのです。砂や埃は払えばきれいに落ちてしまうし、皮膚もさらさらしていて全く気持ち悪くなりません。「これでは風呂はいらないな」と感じました。日本では風呂に入らないと「さっぱりしない感ありあり」ですが、ところによっては「風呂への欲求」度が低い、あるいは起きてこない文化もあるようです。 翌日慶州を出発、雪岳山(ソラクサン)を目指しました。 汽車は4座席対面のボックスでしたので、慶州に観光にきていてソウルに帰る女子学生(らしい)や、赤ちゃんをつれた軍人さん夫婦と話し(とりあえず英語で)ながらで、けっこう楽しい時間でした。栄州(ヨンジュ)という駅からは連結を分離してソウルと江陵(カンヌン)方面に別れます。そうしたら、今度は高橋さんという日本人の中年の男の人が話しかけてきました。変な英語でしゃべっているのを聞いていたらしく、「あなた日本人ですか?」「日本人なら、ちょっとお願いがあるのです」と。 その人が言うには、朝鮮戦争の時に北から逃げてきて、江陵(カンヌン)で結婚(多分韓国女性と)して今は漁師をしているのだとか。大阪に親類がいるので言づてをしてほしいとたのまれました。内容は忘れましたが帰国してから電話をかけて消息などを伝えたことを覚えています。 終点の江陵に着いたのが夜中の11時過ぎ、もし高橋さんに会わなかったら泊まる場所にも困ったはず、助かりました。高橋さんに世話してもらった旅館に泊まっていたところ、江陵は北朝鮮にも近いので、不審者が泊まっていないか警察の臨検(当時のことです)があって、「そういうところに来ているのだな」と改めて思いました。 翌日は「冬のソナタ」の舞台にもなった、今では有数の観光地となっている雪岳山の麓の束草(ソクチョー)にバスで向かいます。始発点で複数あるバスの内なんとか束草行きをみつけ、「ナヌンカンダ(私は行く)」と言ったら変な顔をされました(多分、発音は簡単なのでシチュエーションが変だったのでしょう)。その時近くに日本語が分かるおじさんがいて、お決まりの「どこから来たの」「どこへ行くの」などちょっと日本語で話しをしていたところ、その会話の中で私が「やっぱ」と言ったらそれが「?」だったようなのです。すると隣にいた同じくらいの歳の人が「やはり」と言うことだとその人に説明したのです。こっちのぞんざい語を丁寧語に翻訳してくれた方に敬意を感じました。 なんとか無事に束草の旅館に着きましたが、そこでの出来事は第1回に述べたとおりです。 余談ですが、いまは北朝鮮の領域に属している半島東側に金剛山という名峰(太白山脈に属する)があります。山水画に見られるような峰々で今は行われていませんが、一時期韓国からも金剛山観光ツアーが実施されたこともあります。その金剛山に連なる山々が南へ走って日本海に没し、海から切り立って聳えているいくつもの岩山を「海金剛」と呼んでいます。 翌日のことです。雪岳山では観光客が革靴でも登れる3ルート(当時)があり、その海側のルートをたどる途中でその海金剛の景色を眺めることが出来ました。足元から下方には松の木が海に張り出し、海には岩山、そこに雲が流れてくると見えなくなり、またサーッと見渡せる。まるで画を見ているような気分でした。 それはさておき、無謀にもその3ルートを1日でクリアーしたために汗びっしょりになってしまいました。すでに何日も風呂に入っていません。次の日、束草からバスで江陵に帰ってきて、たまらないので銭湯はないかと訊くと、あるというので旅館の子供に案内されて行ったところ工事中。あとで夏の間は休業だと知りましたが、前に述べたのがその理由です。 どうしようかと思いましたが、到着直前にバスから浅い小さな川で子どもたちが裸で水浴びをしているのを見ていました。そこで、一応はと思って用意していた海水パンツを履き、タオルと石けんを持ってそこに向いました。川の中で体を洗って水浴びする、おそらく二度とない良い経験をしました。 そのあと江陵からはYS11でソウルに向いました。ご存じのようにYS11は戦後国産初と話題になった双発の飛行機で、その数年前には同型のものが同じ航路でハイジャックされています。 帰国後のことです。在日韓国人の同級生に、「Iさん、予約も何もしないで行ったの!!!」と驚かれました。今では外国旅行に限らず、そんな行き当たりばったりで出かけることは考えられませんが、とにかく若かったということでしょう、怖いもの知らずとはよく言ったものです。(つづく)(M.I.) |
猪木寛至著『アントニオ猪木自伝』新潮社2000
|
| ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ 『月刊サティ!』トップページへ |