
| 2023年9月号 | Monthly sati! September 2023 |
| 今月の内容 |
| |
【お知らせ】
※近刊される地橋先生の新しい単行本が現在最終的な段階に入っておりますので巻頭ダンマトークは少しの間お休みさせていただきます。
|
『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
  |
| |
![]()
|
『瞑想を続けていたら人生が好転した話』 永井 陽一朗 |
|
私は発達障害(自閉スペクトラム症)です。20歳の時から強い被害妄想に襲われるようになりました。現実との区別はついていましたが、妄想の臨場感が強く、荒唐無稽な妄想であってもリアリティーが感じられるのでした。
18歳で高校を卒業してからニートの期間と派遣の仕事の期間を繰り返していましたが、仕事は長続きしませんでした。妄想が強く、メンタルの調子は悪く、生活は不規則でした。 20代前半の頃、元々、生き方や人生に関する哲学に興味があった私は仏教に興味を持ち、お寺に座禅を組みに行きました。週1で2カ月くらいの間通いましたが、怠けてしまって長続きしませんでした。 仏教に関する書籍も読みましたが、学者の書いたものは難解で私には理解することが出来ませんでした。スマナサーラ長老の本も何冊か読みましたがこちらの理解力が及ばず、やはり分かったという感覚は生まれませんでした。 ヴィパッサナー瞑想のやり方も本やDVDで学びましたが、当時は、少し試みただけで終わってしまいました。ただその後も、仏教について理解したいという思いは続き、それはまるで執着のような感じでしたが、そうかと言って勉強するわけでもなく、メンタルの調子は悪いままで妄想も強く、ニートと派遣の仕事とを繰り返していました。 しかし、転機が訪れます。 41歳の3月のある日、私はふと、「十二縁起、理解出来なくてもいいかあ」と、それまで抱えていた十二縁起を理解したいという執着を手放しました。そしてなんとなく十二縁起についてAmazonで検索してみると、『ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想入門』という本を見つけました。 レビューには十二縁起についての分かりやすい説明も書かれていて、「この本に書かれている十二縁起の解説なら理解出来る!」と思い、早速、購入し、読んでみたところ、書かれていることは7割くらいは理解することが出来ました。 私は7割くらいの理解で満足でした。長年、理論的な理解を得たいと執着していましたが、その執着を手放したら、理論的な理解を得ることが出来たのです。禅の言葉に「放てば手に満てり」という言葉があるそうです。 本を読んだ後、ゴエンカ氏の10日間のヴィパッサナー瞑想の合宿に申し込みましたが、メンタルの調子が悪く、通院していることを理由に断られました。 41歳の12月に「True Nature Meditation」という瞑想教室があることを知って1日通い、それからマインドフルネス瞑想を行うようになりました。 さらに瞑想を学べるところはないか探したところ、「マインドフルネスサロンMelon」という瞑想スタジオを見つけ、41歳の3月26日から毎日通い始めました。またそのころグリーンヒルのホームページをみつけ、その年の6月か7月にはグリーンヒルの初心者講習会に参加し、それから毎月の1day合宿に参加するようにもなりました。 41歳の12月に瞑想を始めてから、人間関係に大きな変化がありました。良い縁がたくさんあり、嫌いな人から離れることが出来たのです。またMelonやグリーンヒルの方たちと仲良くなり、良い人間関係を築くことが出来、グリーンヒルでは親友が出来ました。 さらに42歳の12月に新しく働き始めた職場には嫌な人が1人もいませんでした。2カ月しか働けませんでしたが、その後3月から始めた仕事の職場にも嫌な人は1人もいませんでした。その職場も5月で辞めましたが、すぐに別の仕事を見つけ、寮に入り、大嫌いな父親と離れることが出来ました。念願の自立を果たすことも出来ました。今のところその職場でも問題となるような人間関係は皆無で、人との関わりが劇的に良くなったことを日々実感しています。 私のそれまでの人生はあまり生きがいが感じられないものでしたが、瞑想を始めてからはこのように人生に大きな変化がありました。 妄想に囚われることや、父親に対するわだかまりもいずれ乗り越えなければならないと思っています。 |
  Y.U.さん提供 |
|||
このページの先頭へ |
|||
|
|||
| |
|||
![]()
| (承前) 心は本来、慈しみを常に感じるようにはできていないので訓練される必要があります。心はもともと愛と憎しみの両方を持っています。悪意、拒絶、怒り、恐れとともに愛も持っているのです。しかし日常生活のなかでは、なんらかの策を講じて憎しみを減少させ愛を増大させようとしないかぎり、慈しみが心に作り出す安らかな感覚は体験できません。 愛――他者に対する無条件の愛――を自分の心に持つことは心に安心感をもたらします。そうなると、ものごとにどう対処したら良いかが分かりますし、自分自身を信頼できるようになります。何の恐れも持たずに完全に自分を信頼できます。たとえわずかでも心の平安を損なう憎しみや怒りの反応が起きないように、自分自身を訓練できることも分かってきます。こうしたことが心に慈しみを育てることによって得られる第一の、そして最も重要な成果なのです。 慈しみの心がもっとも育まれるのは、まったく愛されそうにない人と対する時です。そういう時にこそ私たちの感情と知性を本当に変えることができます。そのような時には、私たちは変化せざるを得ないのです。 たいがいの人には、慈しみの心をもって対するのが難しい人がいます。でも私たちはそういう人がいることに感謝すべきです。とはいえ、あとで振り返って感謝するのは簡単なのですが、実際にそういう人に面と向うとありとあらゆる否定的な感情が湧き起こってきてしまいます。嫌悪、憎しみ、それらの感情に対する正当化や合理化、怒りなどが湧き起こります。こうしたすべての否定的な感情が起こる時こそ慈しみを実践する時です。まさに絶好の機会と言えます。 そのような機会を持ちながら活用しないとすれば、それはまったく残念なことです。もし愛することが難しいと思われる人が今はいないのなら、すべての人を慈しみの対象にしましょう。相手が誰であろうと何をしていようと、何を信じていようと、すべての生き物は私たちが慈しみを身につけるための状況を提供してくれます。彼らが何を言おうと、あなたに興味があろうとなかろうと、彼ら自身が慈しみを持っていようといまいと、それは問題ではありません。どうでもよいことです。 唯一重要なのは自分の心であり、ただそのことだけを心に留めておけば良いのです。 「私の心が慈しみに満ちて、すべてをあるがままに受け入れ、心から怒りと憤りをなくすことができたなら、ダンマ(法)の道への大きな一歩を踏み出したことになるだろう」 私たちはダンマを理解し、自分のものにし、それによって生きなければなりません。 他者に対する反応を変えるべく、自らに働きかける機会は誰にでもあります。 誰もが四六時中人に会っていますが意見の違う人は必ずいるものです。そういう時、固く口を閉ざして何も言わないようにしたからといって慈しみを育てることにはなりません。そんな態度が作り出すものは、せいぜい憤りや抑圧や心配、あるいは無関心でしょう。そのようなものでは慈しみを育てる助けになりませんし、心を浄化することにもなりません。真心をもって相手に応対できるという確信が持てるようになってこそ、自分への信頼感と安心という大きな成果が心のなかにもたらされるのです。 ブッダは「慈しみによって得られる十一の利点」について語っています。はじめの三つは「幸福な眠り、悪夢を見ないこと、幸福な目覚め」です。寝つきが悪いとすれば、それは、慈しみの心が欠けているからだと言ってもよいでしょう。 不眠の問題は睡眠薬では解決しません。慈しみによって解決するのです。慈しみの心があれば潜在意識は不快な働きをしなくなり、不吉な夢や悪夢も見なくなります。すべての衆生に対する慈しみの心があれば、前夜眠りについた時と同じ気分で翌朝も目覚めることができます。 夜にバランスシートを作るのも役立ちます。心の中で作るだけでもかまいませんが、気が向いたら実際に書いてみるのもよいでしょう。バランスシートの一方に「今日、他人に対し、何回ぐらい慈しみの心を抱いたか」を書き込みます。もう片方の欄には「他人と関わった時、どれほどしばしば怒りや苦痛、憤り、拒絶、恐れ、不安を抱いたか」を書き込みます。それぞれを合計してみてマイナスの方が多ければ、その状態を変える解決策を考えましょう。すぐれた商店主はみんな一日の終わりにバランスシートをつけ、商品が客に受け入れられていないことが分かれば必ず改善策を講じるはずです。 このようなことは一つの技術です。生まれつきの性格的欠点や能力の問題ではありません。すべての煩悩がなくなるまで自分自身を何度も変えてゆくための技術なのです。私たちがその技術に取り組むのは、他の人々がとても愛すべき人たちだからではありません。彼らはそんな人たちではありません。もし彼らが愛すべき人たちなら、天上の世界を歩き回っているはずです。この人間界には落ちて来ないでしょう。ここは31ある宇宙界の中で下から5番目の世界なのです。全部で31ある段階の下から5番目にいる私たちは、そこで何を期待すべきでしょうか。 この世界にはたくさんの学ぶべきことがあり、それこそたちがここにいる目的です。この世界は大人のための継続的な学習クラスであり、人間界全体はそのために形作られているのです。私たちがこの世界にいるのは、快適さを見つけるためでも、金持ちや裕福になったり物を所有したりするためでもありません。有名になるためでも世界を変えるためでもありません。たしかに人々は様々な考え方を持っています。しかし厳密に言えば、人生は大人のための学習クラスであり、心を発達させ育てることが最上の課題なのです。それ以上に重要な課題はありません。 私たちの心は美しいバラが雑草に取り囲まれている庭のようなものです。何よりも、雑草があると栄養が雑草に奪われてしまい、バラは育ちません。私たちか花や香りを楽しむこともできなくなります。ついには雑草がバラを枯らすことになるでしょう。同じことが私たちの心の中でも起こります。バラの茂みにあたるものは、私たちの心の中で育ちつつある慈しみです。雑草を刈り取り、花が見えて香りをかげるようにしておかなかったり、雑草を適当な長さに切り取らずに伸び放題にしたりしておくと、最後には雑草が慈しみをすべて枯らしてしまいます。その雑草とは怒りとそれにまつわるすべての感情のことです。 ほとんどの人は自分を愛してくれる誰かを求めています。自分を愛してくれる人がほんの少しいて、愛をお返しする人もいるでしょう。しかし不運にも誰からも愛されない人もいます。そういう人たちは恨みや憤りを抱くようになります。しかし実は、まったく逆の態度をとるほうがうまくゆくのです。もし自分から愛そうとすれば、周囲には数え切れない程その対象になる人々がいます。なぜなら、すべての人は愛されたがっているからです。 誰かが自分を愛しているからといって、自分が他者を慈しんでいることにはなりません。慈しみを施す人自身は慈しみを感じていますが、私たちのほうでは何も感じていません。自分のことを愛すべき人だと見てくれたことについて、ただありがたく思っているだけです。そのような思いもエゴを支え、エゴを肥大させることになります。逆に、誰かを慈しむことはエゴを小さくする方向へと私たちの心を向かわせます。私たちは他者に慈しみを施せば施すほどより多くの人々を慈しめるようになり、自分自身もいっそう慈しみ深くなれるのです。 私たちの心が何を生み出すにせよ、生み出しただけの分量のそのものを自分自身の中に持つことになります。これはとても単純な方程式なのですが、ほとんどの人はそんなふうには理解していません。誰もが、自分を愛してくれるより多くの人を求めて探し回っています。しかしそれはうまく行きません。自分を愛してくれる人を増やそうとするのは愚かなことですが、人生において数多くの愚かな行ないをして来たのが私たち人間です。 いま述べたことは、ブッダが説いた十一の利点の一つである「人間にも人間でない者にも愛される」という言葉に合致します。私たちが他者を慈しめばその他者は私たちに関心を持ちます。私たちを愛してくれる人々は大勢いるのです。私たちが他者を慈しむのは、私たちが何かを与えたいためでも、彼らが愛情を必要としているからでも、彼らが慈しみに値するからでもありません。私たちが他者を慈しむことができるのはひたすら慈しみを施すように心が訓練されてきたからなのです。 それはちょうど計算練習のようなものです。いくつかの数字が目の前に示されればあなたはそれらを「足す」ことができます。合計を知りたいならそれぞれの数を「足す」以外にやるべきことはありません。あなたの心も同じように訓練されてきました。つまり、心が訓練されていれば何が起ころうとも慈しみを施せるようになるというわけです。 「天人(デーヴァ)が人を護る」という言葉があります。天人とはより高い世界の存在で、守護天使です。他者を慈しむ人は護られているのです。ところが人々はしばしば、「もし誰かがあなたに意地悪をした時に慈しみをもって応えたら、相手はあなたを弱い人間だと思い、あなたを好きなように利用するのではありませんか」と反論します。 たしかに人々はそうしたがる傾向があるので、それは大いにありうることです。しかし彼らがそうするなら、彼らは自分たちにとって悪いカルマを作っていることになるのです。慈しみの心をもった人は決してその慈しみを失いません。自分の心の中にある慈しみがどうして失われたりするでしょうか。 もし誰かがあなたを利用したとしたら、それは、あなたの心がすでに訓練されているかどうかを知る機会です。心に怒りを抱いていないかどうか、あなたが相手の人を本当に大切に思い、慈しみをもって応えられるかどうかを知る機会なのです。それはまた、私たちがなすべきことをしているかどうかを確かめる機会でもあります。もちろん、慈しみには他人の権利に配慮することも含まれています。つまり、他人を利用する人には慈しみが欠けていることになります。 慈しみをもって対応すると弱さを見せることになるのではないかと私たちは恐れがちです。しかし、そのような弱さがあると考えるのは誤りです。なぜなら、慈しみは私たちに弱さではなく、強さを与えるものだからです。慈しみの感情だけを抱いている人には懸念がなく安心感に包まれており、何ごとも彼らを動揺させないのでいつでも安らいでいます。慈しみは心を強くするのであり、弱めはしません。しかし激しい感情と結びついた慈しみ――これも「慈しみ」だと誤解されることがよくあるのですが――は、相手への依存心を生み心を弱くしてしまいます。慈しみが単独の感情として心のなかにあり、それによって心が育成されるならば、心は岩のように強くなります。ある人が護られるのはその人自身の心の清浄さによって護られるのです。 「速やかに集中できる」ということも「慈しみの十一の利点」の一つです。瞑想の修行を自らへの慈悲の心をもって始めるのはそのためです。心は「寛容さ(布施)、戒を守ること、慈しみ」の三つの基礎がなければ集中することができません。これらは、瞑想の三本柱であり、それによって瞑想修行は支えられます。 「慈しみ」という感情は集中するために絶対に不可欠なものです。それは心に平安と静寂を作り出すからです。もしも慈しみの心が欠けていると思われるなら、瞑想の前に「慈悲の瞑想」をすることが慈しみの心を養うことを助けるでしょう。(つづく) アヤ・ケーマ尼『Behg Nobody,Goig Nowhere」を参考にまとめました。(編集部) |
![]()
![]()
| 町田明広編『幕末維新史への招待』(山川出版社 2023) |
| もう60年以上も前になる。中学入学時の担任(英語担当)が、「僕たちは明治維新によって『天下太平になった』と教わったんだ」と、憤りを感じさせる口調で語ったことを覚えている。そして「天下太平になった」などとは嘘だったと。
その先生はのちに外国語大学で教官(退職後名誉教授)となり、最終講義では太陰暦から太陽暦への改暦、つまり明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日となったことについて言及した。つまり明治5年の12月は2日間だけになり、政府は当年12月の役人の給与を払わないで済ませたこと、さらに、旧暦では翌明治6年が閏月のある年回りだったので(つまり13カ月あるはずだった)、新暦を採用して2カ月にして、結局給与支出を計2カ月分節約する意図だったことを強調した、それも批判的に。私にはそれらはやむを得ないとも思えるけれど、先生にとっては感情的に受け入れがたかったのかも知れない。 一般的な話としては、前者を否定する形で成立した政権は前の時代を低く、当代を高く評価するだろう。文明開化へ舵を切った明治時代についても同様、明治維新を勝者の側から描けば、江戸時代をことさら未開な、あるいは暗黒社会に位置づけようとしたことは不思議ではない。ただそれは措くとしても、とくに昭和の初期のいわゆる軍国主義によって白紙状態の子どもたちへ刷り込まれた歴史教育は、なかなか消し去りがたいものだったと思う。 たとえば、昭和19年12月16日、神奈川県大船町小坂国民学校の初等科6年男組での大日本教育会の指導のもとでの授業は、B29の飛来を防ぐ方法を問うものだったという。(以下、若林宣著『B-29の昭和史』ちくま新書2023より) いろいろなアイデアの中に3人、「特攻隊のやうに体当りで落します」と答えた児童がいた。授業の主旨は撃墜する方法ではなかったので、教師は「体当りする人は日本人として最も立派な方々ですが、(略)体当りをしてくれなくとも、勝てるやうなことを考へることが大切でせう」と言ったという。しかしそこで著者はこう述べる。 「この授業内容が公に出版されたということは、特攻を称揚する世の中であったと同時に、教育目的を外さない教師もまた求められてもいたことをも示している。ただしその教育目的は、戦争遂行という国策におおきく左右されていたのであるが」 また「体当り」と答えた児童に対しては、 「児童自身はそのとき意識しなかったであろうが、報道や教育に影響された結果として、大なり小なり身を挺して戦うことを目分の胸に刻み込み、あるいは優等生的であろうとすればするほど、おそらくそのように答えたであろう。『体当り』と答えたのは軍国教育の成果でもあるから、授業の目的に沿わない回答であっても、戦時下の教師としては頭ごなしに否定できないのである。『日本人として最も立派な方々ですが』という言葉が、そのことを表している」 1931年生まれの私の中一の担任の先生は、このような、少年のころに戦争、敗戦による社会の混乱を経験しつつ黒塗りされた教科書を使った世代だった。昨日まで「鬼畜米英」と言っていたその同じ大人の口から、今日になると「平和こそは!」と言う言葉を聞くという一夜にしてひっくり返った価値観。そうした背景があって、明治維新や明治時代に対する否定的な思いがあるように見受けられた。 戦後生まれの私の場合、そのような価値観の混乱を経験しているわけでもなく問題意識もなかった。教科書そのまま、他の教科と同じように受験に出そうな所に線を引いて学んだだけ。なので、ラジオで五代目古今亭今輔の落語(『おばあさん三代姿』:フルバージョンで)に出てくるおばあさんが、明治の御代を「治まる明(めえ)※」と嘆いているのを聞いても、「そんなものか」と思っただけだった。ただその後には、いろいろ興味をもって読んだ(小説だけではなく)ものから仕入れた雑駁な知識からも、その時代にはさまざまな事情が複雑に絡み合っていることだけはわかってきた。 ※この言葉の出所は「上からは明治だなどと読むけれど治まる明(めえ)と下からは読む」と江戸っ子が読んだ狂歌による(地橋先生より)。 もちろん、歴史に対する普遍的で完璧な評価などはもとより存在しない。国と国との間では当然のこと、たとえ文化的に同じ社会に属する人の間でも見られるとおり。ただたとえそうではあっても、少なくとも客観的に信頼性のある資料を求めたり、あるいは個人的に少々頭を柔らかくしておくことは十分に意味のあることと思える。広い視野を持とう、頭を柔らかくしよう、というのはこの欄のモットーでもあるので、今回はいささかそのための材料となるのではと思い、本書を紹介することにした。 「はじめに」において編者は、最近の幕末維新史の研究や歴史教育をめぐって警鐘を鳴らすと同時に、本書の主旨として、「『時代を変えた英雄たち』という視点ではなく、朝廷・幕府などの諸勢力や当時の社会情勢について、総合的な視点からこの時代を描き出すことに」重点を置いていることを述べる。そして「序章」では、「一般常識とは大きく異なる『研究の現在』地点を、読者のみなさんにわかりやすく説明することを目的」にしているという。「なるほど面白そうだ」と思った。 本書は22名の執筆者それぞれが担当する幕末・維新を、さまざまな角度からの現在における研究に基づいて記述している。内容の筋道としては、幕末明治に対する「一般常識」のようなものがどのように出来てきたのか、はたしてそれは事実かどうか、そして、それ以外の見方はないのかについてである。 一例をあげれば、「幕末とは「『尊皇攘夷』派と『公武合体』派の政争」と言われているが、事実はそう単純化できるものではないという。実際にはかなり錯綜していたことを裏付ける事実が資料をもとに浮き彫りにされている。 テーマ別には21の章とコラムから成っている。各章は簡潔にしかもたいへんわかりやすい。またそれぞれの章末に、より深く知ろうとする読者のために適切な参考文献があげられているのも親切だと思う。しかし、ここでそれらすべてを取り上げることは無理なので、とくに興味を惹かれたところだけに絞ることにした。ということで、すべての章のタイトルと執筆者の一覧は本稿の終わりに記している。 また本稿では、今回は特に本書で引用された文献からのものも記した。なので、すでに「もう知っていた」というようなものがあるかもしれないがご了承願いたい。 先ず一つ目は坂本龍馬のアイデアだとされている「亀山社中」と「船中八策」。実は両方とも存在しなかったそうなのだ。小説ではさんざん読まされてきたのに。 編者は本人の著書『薩長同盟論』(人文書院、2018)や『新説坂本龍馬』(集英社インターナショナル新書、2019)のなかで、亀山社中が存在しないことや、龍馬は薩長同盟の成立の一翼は担ったけれど、それは決して彼一人の功績ではないことを論じたと言う。さらに、「船中八策は知野文哉著『「坂本龍馬」の誕生』(人文書院、2013)によって、存在自体が否定され、大政奉還も龍馬の手柄とはいいがたい。つまり、龍馬は過大評価されているといえよう」と書いている(「序章」)。 そして、『竜馬がゆく』で肥大化した虚像をつくり出したのが司馬遼太郎であり、それはまさに当時、明治維新百年という世の中の機運にそったものだったとしている。 二つ目目はいわゆる「鎖国」についてである。 日本史の教科書には江戸時代の日本は鎖国しており、例外的にオランダと中国との交易があったと記述されていた(今の教科書ではどう書かれているか知らない)。つまり「江戸時代=鎖国」という概念が条件反射的に出てくる。ただ、近年には、対外的な交わりがあったことから、「鎖国」と言うにはあたらないという論調もあり、「なるほど、それはそうだな」とは思っていた。 本書ではそのあたりを明確に論じ、17世紀には『鎖国』という概念が自体が存在していなかったと断言している。その論旨をまとめると次のようである。 1)大学頭林復斎が編纂した『通航一覧』(1853年頃に完成)に外国が4分され認識され対応していること。その4分とは、①国交を持つ「通信の国」(朝鮮王国と琉球王国)。国交を持たないが、②例外的に商売関係を有する「通商の国」(中国とオランダ)、③指導が必要な地と「撫育」の地(蝦夷地)、④そしてまったく関係を持たない「異国」の4つである。 2)ロシアから遣日使節レザノフの来航(1804年)を機に、対外関係を上記①と②に限定することが確認されたが、その際の議論のなかで「『鎖国』という言葉・概念が使用された形跡は認められない」。 3)そもそも教科書などで「鎖国令」と呼ばれている1633、34、35,36、39年の5つの下知(内容は本稿では省略)は「ポルトガル・スペインを念頭に置き、あくまでカトリック禁教を狙い」としている。しかも33~36年のものは長崎奉行に対するものであり、39年のものは「島原・天草一揆」(1637)を契機に全国の大名に申し渡したものである。 そしていずれのものにも「貿易の統制を意図した内容は含まれていなかった」うえに、「『鎖国令』という法例は存在しない」のであって、なぜそれらをまとめて「鎖国令」と呼ぶのかというと「この時期から『鎖国』がはじまった」とする後世のまなざしが込められているのである」としている。 では、いつ「鎖国」という言葉が誕生したのかというと、「長崎の蘭学者志筑忠雄がケンペルの日本の対外関係に関する論文」を訳したことによるという。ここではその詳細ないきさつは省くが、志筑は蘭語再版(1733)を底本とし、付録第6編「日本帝国にとって、今のまま自国民に外国とのいかなる交易をもさせないことが有益か否かの論」を訳出した際、「原題が長いことから、志筑は本文中の表現を参考に『鎖国論』(1801)と題し、これを契機に『鎖国』という新しい日本語が誕生した」ということだ。 そして江戸時代を「鎖国」とする「見解が定着していくのは、日本の帝国主義が強力に推進されだした明治20年代以降」で、「国家が国民に植えつけることを望んだ」結果とされる。1904年の第一期国定歴史教科書『小学日本歴史』には「家光期の対外政策は『外国の事情にうとくなりて、世界の進歩におくれた』」と「「西洋に後れを取った要因」として描かれている。そうした見解は、1907年に施行された歴史教科の義務教育化によって国民に浸透するとともに、このネガティブな見方は第七期『くにのあゆみ』(1946)まで踏襲されたという。まさに本稿の最初に述べたような結果をもたらしてきたわけである。 本書はこの「鎖国」という捉え方を次のように述べている。これは重要であると思う。(下線は本稿筆者) 「従来近世の問題としてのみ語られがちであった『鎖国』とは、じつは近世を『他者』とみなし訣別する近代日本のまなざしであり、西洋的近代化を志向した近代日本人のメンタリティにほかならない」と。 三つ目は最初に触れたように幕末の争いが単純に「尊皇」と「佐幕」とは区別できないこと。その一つの裏付けが孝明天皇の振る舞いなのだという。 ◎目次と執筆者 大島明秀(熊本県立大学文学部教授)、刑部芳則(日本大学商学部教授)、金澤裕之(防衛大学校防衛学教育学群准教授)、久住真也(大東文化大学文学部教授)、久保田哲(武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部教授)、後藤敦史(京都橘大学文学部准教授)、佐藤雄介(学習院大学文学部准教授)、篠崎佑太(宮内庁書陵部宮内公文書館研究員)、清水唯一朗(慶應義塾大学総合政策学部教授兼大学院政策・メディア研究科委員)、須田努(明治大学情報コミュニケーション学部教授)、田口由香(長崎大学教育学部准教授)、竹本知行(安田女子大学現代ビジネス学部教授)、友田昌宏(東京経済大学史料室嘱託)、奈良勝司(広島大学大学院人間社会科学研究科教授)、福元啓介(株式会社島津興業尚古集成館主任・学芸員)、藤田英昭(徳川林政史研究所研究員)、益満まを(京都外国語大学非常勤講師)、町田明広・編者(神田外語大学教授、日本研究所所長)、光平有希(国際日本文化研究センター総合情報発信室助教)、宮間純一(中央大学文学部教授)、森田朋子(中部大学人文学部教授)、山田裕輝(福 井市立郷土歴史博物館主査・学芸員) |
![]()
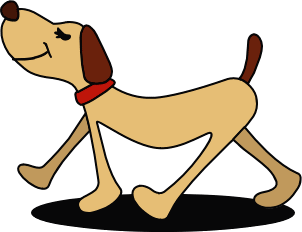 文化を散歩してみよう 文化を散歩してみよう |
| 第9回:プライドそして人と人との間(6) |
|
|
メルヴィン・モース、ポール・ペリー著、木原悦子訳
|
| ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ 『月刊サティ!』トップページへ |