
| 2023年2月号 | Monthly sati! February 2023 |
| 今月の内容 |
| |
【お知らせ】
※近刊される地橋先生の新しい単行本が現在最終的な段階に入っておりますので巻頭ダンマトークは少しの間お休みさせていただきます。
|
『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |

![]()
|
『脳内映画館からの脱出(New New Chinema Paradise)』(4) |
|
★瞑想に出会ったのに(3) Refugee from
Asura's world (瞑想難民になる) |
 地橋先生提供 |
|||
このページの先頭へ |
|||
|
|||
| |
|||
![]()
|
『段階的に進めるブッダの修行法』(3) 2.「持戒」 |
![]()
![]()
| ショーン・エリス+ペニー・ジューノ著『オオカミの群れと暮らした男』(後) (築地書館 2012年) |
| (承前)
著者は再びアイダホに向かった。それは放たれたのではない本当の野生の狼の群れに入るためだった。こうして彼は今まで人間に出会ったこともない狼とともに2年の間暮らすことになる。 そのころになると、暗闇での視力を除けば五感が研ぎ澄まされ、「松の葉が落ちても聞こえたし、私の周りにはいろいろな動物がいて彼らは自分たちの世界を動きまわっている私を観察していたのだが、私は私で彼らが動くのを見なくても彼らの匂いを嗅ぎ取れた」という。それでも狼だけは、見ることも聞くことも匂いを嗅ぐこともなかった。 しかし森林に入って4か月目、ついに小道の先約150mほどのところを一匹の黒い狼が横切るのを見る。そのあとしばらくは姿を捉えることが出来なかったが、やがて辛抱強く待つうちそれが若いオスであること、5匹の仲間(のちに4匹となり、また子どもも生まれる)がいること、またそのオスが調査役であることがわかってくる。 それからは厳しい経験を経て次第に彼らに受け入れられていった著者、実はその期間の経験が本書の真骨頂と言えるのだが、それを斑のように紹介するとかえって趣旨を損ねかねないので、ここでは象徴的な一つのエピソードだけを取り上げることにしたい。 ある時どうしても水が飲みたくなった著者が谷間に向かっていつもの道を下りはじめると、若いオスが彼に飛びかかってきた。 「私はショックで一瞬息が止まり、動くこともできず、そこに寝たままだった。これは全く彼らしくなかったが、彼は本気だった」「何が起きているのか、彼をこんなに怒らせることを何かしたか、私は思いつかなかった。彼は私を殺す前に群れの他の仲間が帰ってくるのを待つつもりかなと思い始めた。私の命は風前の灯だ、あんなに頑迷を通したため自分で蒔いた種だと観念した」 ところが夕闇が濃くなり始めると、突然「攻撃的態度が消え、彼は再び落ち着きと静けさを取り戻し、(略)私の顔と口をあちこち、まるで私に謝っているかのように、舐め始めた」。そのあと谷間への道を「ついてきなさい」と言うように歩き出し、巣穴区域から7~80メートル離れたところで立ち止まり、「地面が爪でひっかかれた跡の匂いを嗅いだ。私が下を見ると、そこに今まで見たこともない、匂いも全く違ったクマのどでかいフンが落ちていた。地面には深いひっかき跡と周りの樹木の皮にいくつもの溝があった」。 「突如、すべてがはっきりしてきた。若いオスは私を殺そうとしたのではないのだ。それどころか、私が4、5分前にこの道を通っていたら、クマに襲われただろう。この狼は私を確実な死から救い、同時にクマが巣穴とチビたちの存在に気付かないように守ったのだ。私は彼に命を救われた」。 著者はそののち、難しかった人間世界への適応を経て戻った世界で狼の子育てと繁殖プログラムに関わっていく。知見を込めたその一つが、テープで遠吠えを流して谷の向こうにライバルの群れがいると思わせ、メスに子どもを産ませようとするものだ。 同時に著者は母を思うようになる。それは狼が次世代の仲間を育てるのを共同の仕事としていることからだった。母が外に出て仕事をしたのは家に食べ物を運んでくるため、そのために「子どもの養育を彼女が最も信頼できる家族のメンバーに」託したのだと。またそれ故に、年配者が歳月を経て培った忍耐と英知を学ぶことで、著者の幼年期は「はるかに豊かなものになった」と受け止めるようになった。 そしてまた、犬についてもいろいろなことが語られる。 例えば狼の群れの中では一番知能が高く意志決定の役割をするアルファ、しつけ係・用心棒・ボディガードとしてのベータ、そうした違いが犬の訓練にも大いに関連しているという。犬のしつけの問題は、ほとんどがそうした狼と犬の類似点を理解していないことから起きる。狼と犬のDNAの違いはわずか0.2パーセント、彼らの本能は基本的に狼と同じなのだ。 例えば、アルファの子を家に持ち帰ったらどうなるか。アルファは「覚えが早く、訓練しやすいのでいつの日か、時が来たと思ったら彼は群れのリーダーになろうとする。そして彼はその日を待ちながら、この飼い主にはもはや群れをリードする能力がないと示す弱みの兆候を探」す。だから、「飼い主はいつも彼より一歩先んじていないと、あんなにかわいくて素直だった犬がわがままなヤツに変身し、飼い主が何を言っても言うことを聞かなくなるだろう」と。 ベータの場合は群れのメンバーの規律を守り、取り締まり、外部からの脅威に対処するのが彼の役割。しかし、何を脅威と思うかが飼い主とは違うかも知れないから、彼が示す攻撃性を飼い主の視点では理解できないこともある。さらには、家の中でも群れの規則とみなすことを徹底させ始めるかも知れない。もし彼がソファーに坐ったりしてはいけないと躾けられたりしていたら、人間の子どもに対してもそれを当てはめてしまうかも知れない。犬の錯覚は危険を呼ぶ場合もあるのだ。 また品質管理の役を持つテスター犬は、「毎日飼い主をせかせてその能力を試し、飼い主が双方にとって意思決定するに適した人間であるかどうかを確認する」から、とてもやっかいでうるさい存在になりそうだという。 そして中位から下位の犬は、「当然ながら神経質で疑い深い。群れにおける彼らの役割は危険の見張り」で、「ときたま少々の餌を与えればそれ以上は要求せず、彼らはそれで満足」するからいいペットになる。しかしただ一つ問題があって、「吠えすぎること」と「恐怖による攻撃」が現れるかも知れないそうだ。 しかし著者は、「オオカミの群れでは役に立つが人間社会では困る全ての特性が矯正できるように、犬の問題も矯正できる」と述べ、「成長した犬を再教育するためには、彼が生後の数か月に口にした食事を与えてみることだ」と述べている。 また食べ物についても面白い。狼の場合、その内容が群れの性格を完全に変えてしまうほどだとも言う。例えば、アルファのメスが我が子を他のメンバーに紹介する前に、そのメンバーに与える餌を「年取った牛とかまだ母の乳を吸っている子牛(その胃の中のミルク成分が誰に対しても心を落ち着かせ鎮める働きをする)に限定」して彼らのエネルギーレベルが下がったことを確認するという。それは「群れのメンバーは、ほとんど体だけ大きくなった子オオカミみたいに、おとなしく優しく寛大な性格になる」からだ。 つまり食の内容次第で「攻撃や闘争は消え、彼らは誰に対しても寛大になる。そんな彼らを見ていると、オオカミが人間の子どもにわが子同様に乳を与え育てたという神話や伝説は信じられなくもない」と著者は言っているが、これは狼や犬に限らず他の動物、もちろん人についても当てはまるのではないだろうか。 最後に著者は夢を語る。 一つは長期的な計画の元で、「オオカミが森林を閥歩すれば自然環境にとって、ひいては人類のためになるということを証明すること」。そのために「オオカミの居住スペースを持った敷地を買い――理想的には一匹のオオカミに対し1エーカー(約4000㎡)の自然林――そこで教育研究センターを経営」することだ。 そして、ネズパース族を支援すること。つまり、何人かをイギリスに呼び、彼らが土地を管理できると証明する機会を与え、「いつの日か、かつては彼らのものであったものの一部でも取り返せればいいと思っている」。 また、子どもたちに、「土地をいかに尊敬して使用するか、自然の賢さをいかに学ぶか、汚染された川を植物や岩や動物を使って飲めるような清らかな流れにいかにして変えるか」を示すこと。 それからもう一つ。不適切な犬を買い、誤解することにより幾多の悲劇が起きていることから、「犬の訓練コースで、生涯の友である彼らを人々に理解してもらうこと」。 この稿の最後に著者の次の言葉を紹介したい。 「私が住んでいた、そして仲間として属していると感じていたオオカミの世界は、きわめて単純でバランスが取れていた。ごまかしや、悪意や、根拠のない残酷さのない世界だった。何かがなされるには必ず誰でもが理解できる理由があった。それはときに手荒く攻撃的で、自分のものに対しては争うが、彼らはその本性の片面として優しさと思いやりをも持ち合わせ、私が実際に見て経験したように、仲間を大いなる愛情で手厚く面倒をみた。 彼らにとっては家族という単位の安全を守り養うことが最も重要なことだが、この世界を共生している生物に対しては尊敬の念を持っていた。彼らは遊びではなく食うために殺生するが、決して食べられる以上の殺しはしない。 れと対照的に、人間はあらゆることを当たり前のことと考えている。人間は貪欲で、利己的で、人間しか大事な種はいないかのようにこの地上を略奪している。だから私たちの社会に危険と思いやりのなさが蔓延している。飛行場で出発を待つ間、両親が子どもたちと口論し、何でもないことで子どもを折檻しているのを目撃した。私は叫びたかった、『止めろ。子どもとは楽しめ。授かりものに感謝しろ』と」 ここでは本書の枠組みの、それもわずか一部を紹介したに過ぎない。例えば、一時は著者と行動を共にした相棒のこと、あるいは狼との緊張感のあるやりとり等々、やむなく見送ったものも多くある。数ある動物に関する書籍のなかでも、本書は良い意味で群を抜いて異色さを放っている。「認識が改められた」というような平凡な言葉ではなく、「人は狼の崇高さに及ばないのではないか」というレベルの印象さえ受けた一冊だった。(雅) |
![]()
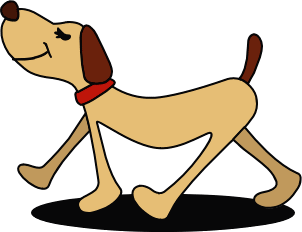 文化を散歩してみよう 文化を散歩してみよう |
| 第2回:「田」という字をめぐって
前回は異文化に接する時のこちらのありかたや、言葉のやりとりの場面から垣間見えるものについての話題でした。今回は、日本と韓国じ漢字を使っていても指す意味が違う一つの例として、「田」という漢字を取り上げてみたいと思います。 |
 |
ちょっと紹介を! |
|
|