
| 2021年7月号 | Monthly sati! July 2021 |
| 今月の内容 |
| |
| |
巻頭ダンマトーク:『動画の瞑想と静止画の瞑想』 |
| |
ダンマ写真 |
| |
Web会だより:『心と向き合って -赦し、懺悔、そして慈悲の修行へ-』(1) |
| |
ダンマの言葉 |
| |
今日のひと言:選 |
| |
特別掲載:『アビダンマの解説と手引き』 (2) |
| |
読んでみました: 内田樹著『日本辺境論』(新潮社 2009年) |
| 『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
![]()
| 巻頭ダンマトーク『動画の瞑想と静止画の瞑想』 地橋秀雄 |
| 「我思う、ゆえに我あり」と言ったのは、フランスの哲学者ルネ・デカルトでした。 有名な言葉ですが、ヴィパッサナー瞑想の立場からは、「妄想を止めなさい、すると無我が体験されますよ」ということになります。 思考を止めるのは至難の業です。考えごとモードから脱することができなければ、デカルトのように、エゴがある、自我が在る、と感じてしまうのは当然かもしれません。 仏教では、「我=エゴ」はイリュージョン(幻影)であり、妄想に過ぎないと見ています。エゴ感覚や自我感覚は実在するものではなく、偽の印象であり、思考のプロセスから生じてくる錯覚なのだとする「無我論」が説かれているのです。 *思考を止める どれほど衰弱し意識が朦朧としても、人間の思考や妄想が止まらないのは驚くべきことです。たえず微弱なイメージや妄念が生じては滅し、止めどもなく連想が流れ続けるものです。その思考の流れを止めるには、特別な訓練や修行が必要になります。 思考を停止させる伝統的な方法の筆頭は、一点集中型のサマタ瞑想でしょう。同じ言葉を繰り返し唱えたり、単一のイメージに心を釘付けにして、瞑想対象と一体化するサマーディを目指していくやり方です。 思考や概念モードというのは、言葉が次の言葉に繋がり、イメージとイメージが次々と連鎖していく状態です。この連続状態にならなければ、思考が止まっていると理解してよいのです。 では、思考が止まれば、自動的に「洞察の智慧」が閃くのでしょうか。残念ながら、思考が止まるだけでは、ダンマ(法:真実の状態:あるがままの存在)の本質を直観する智慧は生じません。妄想をまったくしないカブト虫やムール貝に智慧が生じないのと同じです。思考が止まりっぱなしなら、おバカだということになります。朝から晩まで雑念が止まらず、妄想で自滅しかかっている人類だからこそ、思考を止めることに意味があるのです。 明晰な意識状態を保ちながら完全に思考を停止させることができるのはサマーディの手柄ですが、これでは仕事は半分です。 後の半分は、智慧です。事実をあるがままに観る技法であるサティが、気づき→観察→洞察と成長し、ついに悟りの智慧として完成するのは、サマーディの力に助けられるからだと言ってよいでしょう。 サマーディの完成はすべての瞑想者の目指すところですが、サティの精度を桁はずれに高めるためにこそサマーディはあるのだと理解すべきです。これはヴィパッサナー瞑想の最重要ポイントなので、マハーシ・システムの修行現場に即してもう少し説明してみましょう。 *サマーディの分水嶺 心を一点に集中させ、釘付けにしていくのがサマーディの特性です。例えば、座る瞑想の最中にサマーディが高まってくると、意識の対象はただ「膨らみ・縮み」や「盛り上がり・凹み」だけになっていくでしょう。お腹の感覚が微妙に変化し推移していくのがリアルに知覚され、認知され、また生起してくるものが知覚され、認知されていく・・・。こうして、経験する一瞬と確認する一瞬が間断なく連続していくのが、サティの瞑想の基本型です。 サマーディは、注意を一点に注ぎ続ける能力です。したがって定力が未熟な段階では、意識が中心対象から逸れて音や雑念に反応してしまうでしょう。たとえ心がさ迷い出ても思考モードに陥らず、必ず気づいて中心対象に戻すことができれば、瞑想修行としては結構です。サティは安定しています。しかしあちらこちらに注意が逸れてばかりいては、中心対象の観察の精度が上がらず、洞察の智慧など到底生じません。 このように、ヴィパッサナー瞑想が進むのはサマーディの成長にかかっているのですが、ここはキワドイところでもあります。ヴィパッサナー瞑想の瞬間定(カニカ・サマーディ)になるか、サマタ瞑想のサマーディに埋没するかは紙一重だからです。 *ニミッタの一里塚 サマーディが高まってくると、光や色彩や文様などさまざまな視覚イメージが出現してくることがあります。音や匂いの場合もありますが、いずれも「相」(ニミッタ)と呼ばれる脳内現象で、実在するものではありません。サマーディがさらに高まれば、「ニミッタ」の鮮明度もいや増すので、初めてこの現象を体験すると、多くの人がのめり込んでサティを忘れてしまうものです。 ニミッタ(相)は心が仮作したものであり、法ではありません。概念やイメージに集中していくのはサマタ瞑想の特徴で、妄想に集中しているのと同じことです。現実から遊離しますが、集中の極みであるサマーディの完成を目指していく修行です。 サマーディの定力を養うことは、「戒→定→慧」の「定」の修行であり、ヴィパッサナー瞑想の完成に必要不可欠なので、そのように心得て取り組むべきです。 *サマーディの罠 問題は、正しくヴィパッサナー瞑想を修行していたのに、サティとサマーディのバランスが崩れて、いつの間にかサマタ瞑想に脱線してしまうことです。サマーディが対象と合一するまでに深まると、正しく知覚し認知した一瞬の現実感覚が、一枚の静止画像のように掴んだまま手放せなくなってしまうのです。これが、ヴィパッサナー瞑想者がサマタ瞑想のサマーディに埋没していく瞬間です。 例えば、歩く瞑想の足の感覚や座る瞑想のお腹の感覚を正しく実感していたのに、次の瞬間、新しい感覚を実感せずに、脳内の歩行イメージや「膨らみ・縮み」のイメージに集中してしまうのです。法と概念がすり替わる一瞬です。 ヴィパッサナー瞑想で正しく捉えた実感も、一瞬にして過去のものとなり、10年前の記憶イメージと同じものになっていくのは、無常の宿命と言うべきでしょうか。法として実在していたものが、法ではなくなるのです。心が作り出した静止画像を、ただ眼を閉じて思い出しているのと変わらないのだから、直ちにサティを入れて現在の瞬間に回帰しなければならない・・・。 矢つぎ早に生起してくる対象を、強烈な集中で次々と認知していく瞬間定だけが、存在の本質を直観する洞察力につながります。そしてその持続に耐え抜くことこそ涅槃に到る唯一の道なのです。 *崩壊していく現実・・・ 高速疾走する車のナンバー・プレートを視認できる人はいないでしょう。しかるに、極度に集中を高め、サマーディという名の明晰な視力を得た者には、ナンバーが視認できる可能性があります。サティの気づく力と、サマーディの禅定力が連動してくると、洞察の智慧が閃く所以です。 だが、諸刃の剣のように、同じサマーディの力が瞑想者を一枚の静止画像のなかに没入させ、瞬滅する法の観察から脱落させもします。静止画像は猛烈なスピードでコマ送りされている映画の一コマにしかすぎません。この世に執着できる現実などどこにもないのに、一瞬の静止画にしがみつき握りしめようとするのは、変滅する無常の真理のただ中で、欲望や怒りの執着を手放さない愚か者と同じなのです・・・。 |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |
![]()
|
『心と向き合って -赦し、懺悔、そして慈悲の修行へ-』 (1) 匿名希望 |
| 私がヴィパッサナー瞑想に出会ったのは10年ほど前になります。当時、合宿へ参加したり、地橋先生の指導を受けたりした後に環境が整い始め、そのため苦が少なくなってくるとモチベーションも下がりだし、数年の間仏教から離れてしまいました。
そのうち、無常に変化していく人生の中で再び苦が生じ始め、やはりもう一度仏教を学びたい、今度はやめずに続けたいと思うようになりました。そこで、朝カルに通うというルールを自身に課し、今度は真剣に修行に取り組もうと決心をしました。以下はそのレポートです。 赦しの瞑想に取り組む |
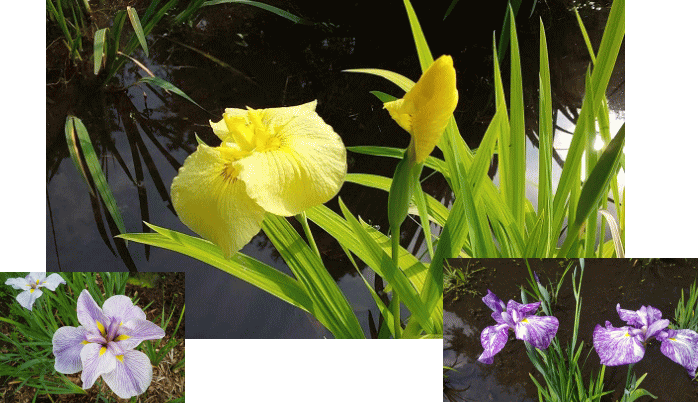 (Y.U.さん提供) |
|||
このページの先頭へ |
|||
| 『月刊サティ!』 トップページへ |
|||
| |
|||
![]()
|
「月刊サティ!」2006年3月号、4月号に、アチャン・リー・ダンマダーロ師による「みんなのダンマ」が掲載されました。これは、「パーリ戒経」中にある仏教徒が自らを善き人間に鍛える実戦の指針で、6つの項目に分けられています。今月は5回目です。 五番目の指針pantañca sayanāsanam (パンタンチャ サヤナーサナム 淋しいところにひとり臥し、坐し)とは、でしゃばりになるな、ということです。どんなところに住むのであれ、静かに、平穏にいなさい。集団の他の人と深くかかわったり、一緒に騒ぎ立てたりしてはいけません。本当に仕方がないとき以外は、問題に巻き込まれないようにしなさい。 |
![]()
![]()
| 特別掲載:『アビダンマの解説と手引き』 (2) |
|
(承前) 第5節 イマーニ ドゥヴェー ピ パティガサンパユッターニ ナーマ 9、ドーマナッサ(精神的な苦しみ)を伴い、パティガ(嫌悪)が付随する、アサンカーリカ(駆り立てるものがない)チッタ 第5節へのガイド 第6節 第6節へのガイド |
![]()
| 内田樹著『日本辺境論』(新潮社、2009年) |
| 本書についてはすでに多くの紹介や感想文などが出されているので、屋上屋を重ねるようになってしまうが、「このような見方もあるのか!」と思ったこと、それから、これまで漠然としていたものを改めて理解するのによい事例が出されていることもあり、あえてここに取り上げてみた。
著者は神戸女学院大学名誉教授(2018年現在)で幾多の著作もあり、ここで改めて紹介するまでもないと思う。本書は、Ⅰ:日本人は辺境人である、Ⅱ:辺境人の「学び」は効率がいい、Ⅲ:「機」の思想、Ⅳ:辺境人は日本語とともに、の4部から構成されている。 Ⅰは、辺境とは中華文明に対しての意味であるということから説明される。Ⅱ~Ⅳもそれぞれ興味深いが、私にとって最も印象的であり、「なるほど!」と思わせたのはこのⅠであった。 ここで語られるのは、中華に対して日本という辺境に住む人々は、新しいもの、すぐれたもの、学ぶべきものを外の世界に求め、「外来の知識の輸入と消化吸収に忙し」く、それを模倣し加工し改良するのは得意とするが、その結果、他国との比較でしか自分たちを語れなくなるという心情を作り出したということについてである。 ある意味でそれは劣等感覚でもあって、ことさら意識しなくても、「日の本」という国名を名乗ること自体が<中華に対しての東の辺境である>という心情の表れだとする。そしてそれが、著者が言うところの「辺境人」の心の癖、パターンであって、例えば、漢字を「真名」とし、そこから作り出した表音文字を「仮名」と称するのもそのひとつとされる。 古代における例として、「日出ずる所の天子・・・」云々は、うがった見方とは言いながら、著者は、「辺境」という立場を知らなかったふりをした、いわば逆手に取ったのではないかと推測している。また、中国への皇室の遷座という秀吉の誇大妄想も、まさにこの辺境という思考パターンそのものではないかという点は、なるほど十分あり得るのではないかと思わされる。 実は本書を読みながら少々思いついたことがある。ここであえてそれらをあげてみたい。 先ず、信長はどうだったかということが浮かんだ。おそらく辺境思考のパターンからみると異端者ではなかったか。では光秀はどうだったか?あるいは自らを「新皇」と名乗った平将門は・・・?当時の権力から見れば確かに「地方」ではあったが、しかし当時の「板東」の人々がその地を「地方」と考えていたかどうか。 さらに考えていくと、辺境に位置するという感覚は、自覚の有無にかかわらず、それに対する反動も呼び起こしたのではないかとも思う。そのひとつがいわゆる「国学」で、そしてその感覚が極端に展開すると、日本が世界の文明の中心であったという偽書とか、あげくは漢字渡来以前に日本独自の「古代文字」があったという妄想までをも膨らませたのではないか。こんな連想が次々と浮かんだ。 また、こんなことも思い出された。 日清戦争の契機となった1894年に朝鮮半島で起きた農民戦争、いわゆる「東学党の乱」。30~40万人が命を失ったと言われている。この「東学」という名称は西洋の学問に対して称えられたものであって、韓国ではこれは、「単なる農民反乱の域を超え、農民が主体となって侵略軍である日本軍と戦ったものなので、現在では甲午農民戦争と言われる」という。(井上勝生著『明治日本の植民地支配-北海道から朝鮮へ-』岩波現代全書011、2013年より)。 井上勝生氏は当該書のなかで、「韓国の民主化運動では、東学と東学農民戟争の歴史の生きた記憶が人々を強く励ました」として、次のようなエピソードを紹介している。 「1998年10月、来日した金大中大統領が、日本の国会演説で、アジアの人権思想として朝鮮の東学をあげたのが、韓国での東学の高い評価をよく示している。金大統領は、アジアには自前の近代民主主義思想が生まれなかったという従来の考え方を真っ向から批判した。 『アジアにも西欧に劣らない人権思想と国民主権の思想があり、そのような伝統もありました』 孟子と釈迦の思想には、人間の尊厳性と平等が述べられており、『韓国にもそのような伝統があります』と断って東学を紹介した。 東学という民族宗教の創始者たちは『人すなわち天なり(人乃天)』『人に仕えるに天の如くせよ(事人如天)』と教えています。こうした人権と国民主権の思想だけにとどまらず、それを裏付ける多くの制度もありました。ただ、近代民主主義 の制度を西欧が先に発見しただけであります』と」 『日本辺境論』に戻ると、このような辺境思考のパターンは現代にも脈々と流れていると言う。それは他国との比較でしか自国を語れないというところにも現れる。 たとえば、オバマ大統領の就任演説にはアメリカ建国の意義が見事に語られているのに比べ、その感想を求められた当時の日本の総理大臣は、「世界の一位と二位の経済大国が協力していくことが必要だ」というコメントを出したという。つまり、その時総理の頭に浮かんだのは、世界におけるランキング表だったということになる。この違いはどこから来るのか。それは自ら主体性を自覚しているか否かによると著者は言う。 また先の敗戦について述べた日本軍の中枢にいた軍人たちの行動も、まさにこの思考パターンに沿ったものであったことを論証する。開戦に自分は反対だったと言葉では言うが、その意見をあくまで主張することはしない。あげく、「お前の気持ちがわかる」というような空気に染め上げられた結果として開戦に至ったのだと。つまりは外部からの干渉によってはじめて自分の行動を起こす。このような行動パターンは、個人レベル社会的レベルを問わず、それによって「被害者意識」から免れなくなってしまうと言うことだ。 しかし、辺境にあるのはマイナスばかりではなく、プラスの部分も持っている。それはⅡで検討される日本人の「学びたがり屋」という分析、そしてⅣに述べられる日本語の特殊性についてである。 Ⅱの「辺境人の『学び』は効率がいい」では、司馬遼太郎の小説で現在外国語で読めるのは3点しかないという例をあげ、「自国民を共扼している思考や感情の型から完全に自由な人間などいません」と言う。これは、思想や感覚はなかなかその国民以外には感知されにくいということであって、もちろん日本だけではないのだが。 ただそのなかでも日本は、「われわれはこういう国だという名乗りから始まった国ではない」し、「日本人とはしかじかのものであるということについての国民的合意」もない。したがって、もちろん国旗も、国歌も、国号もなぜそれが選ばれたのか、それが決定された確固たる理由も意識されていないだけではなく、そもそも語られる必要性からして全く認められていないわけで、「そうなっているからそうなのだ」というほどの既成事実のようなものになっていることを語る。 何を言いたいかというと、はっきりした目標や理念を柱として自分の意見やものごとを成り立たせているのではなく、何ごとについてもすべては他者との関係如何で自分の立ち位置が決まってくると言うわけだ。だから、「つねに他に規範を求めなければ、おのれの立つべき位置を決めることができない」し、自分が何を欲しているのかについても、他者のそれを「模倣することでしか知ることができない」のだと言い、それを著者は「虎の威を借る狐」に譬えている。 ここで私が思い出したのは、伊丹十三と佐々木孝次(もと専修大学教授)との対談における次のような言葉だ。 「佐々木:・・・日本人というのは相手が何もいわない限りどこまでも無秩序になるけれども、一旦相手に、これはどういうことか、と問い詰められると、それはこういう秩序に従ってこうやってると答えられない。しかし、われわれが無秩序だといっても、僕は、根本的に自己肯定的な、快の原則に従っていると思う。 伊丹:つまりわれわれは自我というものを一貫して変わらぬもの、という方向に鍛えてこなかったわけでしょうね。日本人の唯一の一貫性というのは「相手との関係がすべて」ということでしょうが、相手との関係というものは当然クルクル変わるわけだから、日本人の一貫性はクルクル変わること、という奇妙なことになっちゃう。 佐々木:すべては相手の出方次第。個人から国家まで、これはもう戦前から戦後まで一貫してるんで・・・」(『伊丹十三選集』第1巻「日本人よ!」岩波書店 2019年、より) しかし、実はこうしたことは悪いことばかりではなく、学びの意欲と方法という面ではそのよい面が働くと著者は言う。それが師弟関係であって、その関係は「本源的遅れを前提にしないとうまく機能しない」し、「その欠点は同時に、外来の知見に対する無防備なまでの開放性という形で代償されている」とも言っている。 さらここでは、大学での講義の要点を記したいわゆるシラバスや研究論文発表の形式などについても、ネガティブな見解を述べる。それは、学ぶと言うことの本来のありかたについてである。もしあるものごとの意味や有用性についてはまだ不明であっても、それを学ぶことがいつかは重要な役割を果たすことがあるだろうと、「先駆的に確信する」ことから始まる、それが学ぶと言うことではないかというふうに。そして、今日のあらかじめ要点を伝える講義のやりかたと、本来の意味での「学ぶ」ということの二つは相容れないのではないかと主張する。このことは、今日の高等教育で「教養」が軽視されつつあることと通底するものがあると思われる。 Ⅲの「機」の思想。ここではまず、自分の無知と未熟とを自覚しながら己を超越した外部を構想できるのが宗教的寛容であるとされる。たしかに日本ほど宗教に寛容な文化は思いあたらない。神前結婚というやりかたもキリスト教のそれをまねて明治以降に考え出されたそうだし、神道、仏教、儒教、キリスト教その他の新興宗教等々、ともかくも共存が出来ているのは、一面では「いいかげん」に見えても、言い換えれば「良い加減」であるのかも知れない。しかし著者はこの宗教性を、「絶対的な信」という成立を妨げるものとしても捉えている。 著者は次に「機」という概念を論じる。「自分のことを考えていると、そこに隙が出る」が、対象に心を止めることなく反応するその「完全な自由を成就した状態」が、澤庵禅師の言うところの「石火之機」なのだと言う。この部分は武道とは縁のなかった私には実感として理解しづらかった。(ちなみに本書の著者は武道家でもある) ただ、「天下無敵」という真の意味は「敵を作らないこと」というところはなるほどと思えたし、またこのことから、「老いや病や痛みを私の外部にあって私を攻撃するものととらえず、私の一部であり、つねに私とともに生きるものと考える」というのは、「あるがまま」「受け入れ」を基とするヴィパッサナーの認識の仕方と完全に重なっていると感じられた。 さらに第Ⅲ部では、例えばある作業に供される専門の用具が身近にない時、手元にあるものを工夫したり加工したりして使用することや、いつか何かの役に立つかもしれないというような知のありかたを、学ぶ力と関連させて論じている。 IVの「辺境人は日本語と共に」で印象に残った論点をあげれば、「ぼく」「私」「おれ」「自分」等々の第一人称を相手との関係性によって使い分けるニュアンスは、外国語(特に英語)には翻訳で出来ないこと。さらに、「代名詞の選択によって書き手と読み手の間の関係が設定され」、それは、「発信者受信者のどちらが上位者か」を決定するという特徴があるということなどである。 |