
| 2021年6月号 | Monthly sati! June 2021 |
| 今月の内容 |
| |
| |
特別掲載:『アビダンマの解説と手引き』 (1) |
| |
ダンマ写真 |
| |
Web会だより:『仏教聖地巡礼 インド・ネパール七大聖地の仏跡巡り』(7) |
| |
ダンマの言葉 |
| |
今日のひと言:選 |
| |
読んでみました:頭木弘樹、NHK<ラジオ深夜便>取材班著『絶望名言』 |
| 『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
![]()
| 特別掲載:『アビダンマの解説と手引き』 ( PART 1 ) |
| 2019年4月より、“Learn Buddhist Scriptures”として「アビダンマの解説と手引き」が“DHAMMA BLOG”のなかで公開されています。これは、アビダンマ(論)の入門書である「アビダンマッタサンガハ」の解説書、“Comprehensive Manual of Abhidhamma”(Bikkhu
Bodhi監修)が、影山幸雄、中村洋子、島田真理子の3氏によって日本語訳されているもので、ダンマ普及の一助となるようにとの格別のご厚意により、「月刊サティ!」にも掲載させていただくことになりました。厚く御礼申し上げます。
掲載にあたってのレイアウト等は、一部を除いて元のかたちに沿っています。また、今月号では巻頭で掲載させていただきますが、次号からは「特別コーナー」で連載いたします。 なお、すでに公開済みのホームページは現在一時停止されておりますが、再開され次第アドレスを掲載いたします。 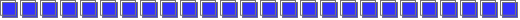
訳者からのメッセージ 第1章 チッタについての概要 第1節へのガイド 第2節へのガイド 究極の真理が物事の根本的な要素であることは明らかですが、あまりにもとらえどころが無く、理解するのが難しいため、訓練を受けたことがない一般の人たちはそれを知覚することが出来ません。そうした人たちは概念で心が曇っているため究極の真理を見ることが出来ません。概念のために真理を一般的に定義された形に作り替えてしまいます。智慧を使い、正しい対象に徹底して注意を向ける(ヨーニソーマナシカーラ)ことによってのみ、概念を超えて究極の真理を観察し、それを知識として取り込むことが出来るのです。このようにパラマッタは究極のあるいは至高の知識の領域に属するものとして表現されます。 |
<お知らせ>今月は巻頭ダンマトークはお休みさせていただきます。(編集部)
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |
![]()
| 『仏教聖地巡礼 インド・ネパール七大聖地の仏跡巡り』(7)H.Y. |
| それからブッダガヤには日本寺があり、大仏が建立されているところに行きました。現地にある大仏は大乗仏教のものであり、日本と変わらない姿です。どこか異国での懐かしさを感じさせます。その後、日本寺の本堂に行く途中に、日本寺が運営する慈善活動の学園がありました。たまたま、そこで働いている方と目があったのです。軽く会釈したのですが、何か力になればと思いました。インドに来てクシナーラをはじめ物乞いの人々に何かしなければならないと感じていましたが、物乞い個人個人にお金を渡しても更生にはならない気がしました。インドの物乞いは組織化されており、それをとりまとめるボスのような者が、分け前を取ってしまうのだそうです。このような状況の中、頑張っている施設であれば、布施する価値があると思いました。 ツアーでは日本寺は自由散策となっていましたが、日本寺の僧侶の方が偶然本堂に来られました。有り難いことに突然来訪した我々ツアー客の為に、日本寺の歴史等の講話とお経をあげて下さりました。しかし僧侶と一緒に般若心経を唱えているうちに、心の奥でイライラが出てきました。原始仏教の瞑想を深める為にインドに来たのに、何故ここで大乗仏教の般若心経を唱えなければならないのかという内面的な怒りです。日本人僧侶の親切心に感謝する一方で、他宗派を否定する傲慢な考えがこのとき同時に生じました。布施したい気持ちは強くある一方で、比丘に布施をするのであれば原始仏教に基づくべきだと思い、学園への寄付に丸を付けず、わざわざ「四資具(衣・食・住・薬)」と封筒に書き、まとまった額の布施をお渡ししました。表層では日本人寺の僧侶に深い感謝を込めて布施を渡す一方で、僧侶に対しこれが原始仏教の正統な布施のやり方なのだと獅子吼する思いが心の深層でくすぶっていました。冷静に考えれば、僧侶に四資具をすること自体は良いことですが、それを相手に認めさせたいということとは別物です。また、布施を物乞いや慈善活動の子供達の為にという思いは完全に消え去っています。これでは怒りモード全開で、劣善そのものです。表面的にはとても良いことをしましたが、内面的には非常に後味の悪いものでした。 昼頃にブッダガヤを出発し、バラナシに向かいます。バラナシまでは約260kmで、約10時間と一日で最長の移動です。夜にバラナシに到着し、市内のホテルに宿泊しました。 早朝、バラナシのガンジス川の沐浴見学に行ってきました。今回のツアーの中で、唯一の仏跡以外の観光地です。参加自由だったので、参加せずにホテルの部屋で歩きの瞑想と座りの瞑想により多くの時間を使うことも考えましたが、せっかくインドに来たので仏跡以外の観光地に行っても損はないと思い、参加しました。 インドのヒンドゥー教ではガンジス川は聖なる川とされており、朝日が昇る前に川で沐浴するのが良いとされています。どこでも沐浴すれば良い訳ではなく、川が合流する場所が望ましいなどヒンドゥー教の教義があるそうです。ベナレスは沐浴に適した場所とされており、同時にベナレス最大の観光地とされています。早朝から観光客が続々と集まってきます。沐浴見学と言いつつも、観光客の方が多数で、インド人の沐浴者はそれほど多くはありませんでした。ガンジス川ではツアーが準備した船に乗り、ガンジス川の様子を一望できました。またガンジス川は火葬を行う場所でもあります。撮影は厳禁ですが、実際に火葬する場所まで船が近づき、死について考えさせられました。 ホテルに戻って朝食を食べた後、サールナートに移動します。サールナートは初転法輪の地とされ四大聖地の一つで、ブッダが初めて説法をされたところです。ブッダは覚ったあと、誰に覚りの境地を教えようかと考えとところ、無色界禅定を教わった二人の師に伝えようと思いました。神通力で調べたところ、お二人とも亡くなっていることが分かった為、次に以前一緒に修行していた5人のもとに行きました。その5人はブッダが王子時代の縁者たちで、ブッダが覚るのを見届けるために出家していました。ブッダが苦行を止めたときに失望し、5人はブッダのことを仲間だと思わないよう、申し合わせていました。しかしブッダが来ると、各人が申し合わせを破り、ブッダの足を洗うなど世話をしてしまいます。そしてブッダとの歓談が始まります。5人はブッダと対等の言葉を使いますが、ブッダが5人と同格に扱われることに反対します。ブッダが覚ったことを伝えても5人は納得しません。そこでブッダが嘘をついたことがあるかと5人に問います。当時、釈迦族は高潔な民として知られていました。その中で最も信頼の高い王子が嘘をつく等、今までありませんでした。5人ははっと気づき、ようやくブッダの説法を聞くことに合意します。 私は最初、この5人はブッダが覚ったと言っているのに何故信じないのか、ブッダが今まで嘘をついたことは無いと言って、初めて気づくのはブッダに大変失礼だと思いました。しかし「ブッダの聖地」を読み返していくうちに考えが変わっていきました。 覚っているとブッダが言っても、根拠がなければ鵜呑みにしないという5人の理性の重要性がここで述べられています。5人がゴータマ・シッダッタ王子を尊敬していて、本人が覚ったと言ったから信じる、では根拠になりません。5人がゴータマ・シッダッタ王子が今まで嘘をついたことがないことを理解し、本人が覚ったと言ったから信じることで初めて根拠となります。 世の中には、権威や著名だから納得してしまう場合が多くあります。しかしケーサプッティヤー村の逸話のように人が言ったから、伝統や聖典に書かれているからと言って鵜呑みにせず、きちんと自分で物事を確認することと同様に、この5人がその重要性を伝えてくれているのだと思いました。 サールナートには阿羅漢たちの小さなストゥーパがいくつもあります。ブッダが、覚りに達した人々の骨はちゃんとストゥーパを作って安置するよう示されたことで建てられました。また高く大きなストゥーパがあり、これはブッダが初転法輪をされた場所で、静かにたたずんでいます。ここでも1周しました。 その後、サールナートの近くにあるムーラガンダクティ・ヴィハーラ(転法輪寺)に行きました。ここは日本人がフレスコ壁画を描いたところで有名です。戦前のものですが緻密に描かれており、ブッダの一生を絵画から学ぶことができます。 昼食をホテルで食べた後、バナラシから国内線に乗る為に空港に向かいます。エアインディアは搭乗1時間前の締め切りですが、1時間前にファイナルコールと言われ、催促されます。いくらなんでも早すぎると思いつつも、なんとか搭乗します。すると出発の40分前に航空機が離陸しました。普通は予定時間より遅れることはあっても、時間前に飛び立つことを経験したことがなかったので、エアインディアの対応に驚きました。その後、夜にデリーで成田空港行きの国際線に乗り継ぎました。 9.第9日目 早朝に成田空港に無事到着し、自宅に帰りました。振り返ってみると、身体的には結構疲れた一方で、聖地巡りに思い切って行くことができて良かったと思っています。 ブッダが「信仰心のある良家の子には、次のような四つの、見るべき、畏敬の念を起こしうる場所があります」と言って、四大聖地を挙げられています。ブッダは「私を拝みに来なさい」と言っているのではなく、「これらの場所にちょっと来て、ゆっくりして、実感してください」という気軽な感じで提案しています。 もしヴィパッサナー瞑想を通じて仏教に関心を持ったのであれば、行く価値はあると思います。最近の書籍や映像で現地の様子は分かるようになっていますが、ブッダガヤの瞑想の様に現地に行ってみて初めて感じることのできる、あの暖かさを是非実感してほしいと思います。 今回の聖地巡りのご報告が、皆様の今後の修行にお役に立てれば幸いです。 出典:ブッダの聖地(サンガ文庫) https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1sEkGHJAawn8PYy-C7-KdzdtT6ClfNNwG |
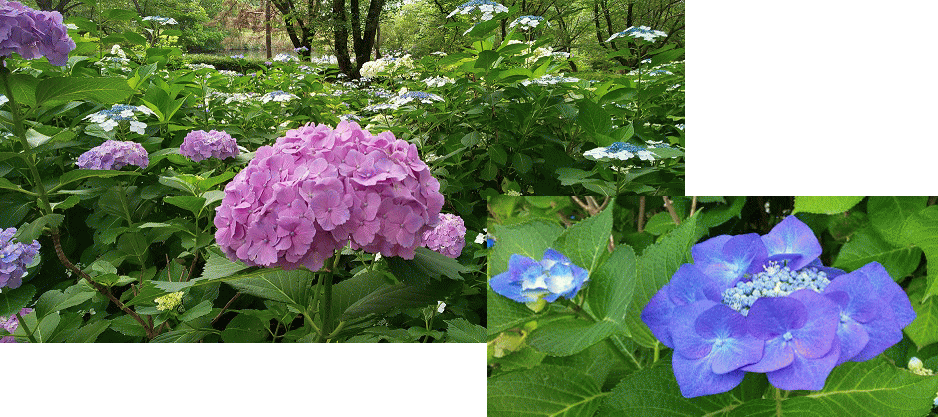 |
|||
このページの先頭へ |
|||
| 『月刊サティ!』 トップページへ |
|||
| |
|||
![]()
|
「月刊サティ!」2006年3月号、4月号に、アチャン・リー・ダンマダーロ師による「みんなのダンマ」が掲載されました。これは、「パーリ戒経」中にある仏教徒が自らを善き人間に鍛える実戦の指針で、6つの項目に分けられています。今月は4回目です。 |
![]()
![]()
| 頭木弘樹、NHK<ラジオ深夜便>取材班著 『絶望名言』(飛鳥新社、2018年) |
| 本書は「NHK<ラジオ深夜便>」の中の「絶望名言」を収録したもので、頭木弘樹氏と番組を担当した川野一宇氏との対談に捕捉を加えたものである。
頭木氏は20歳の時に潰瘍性大腸炎という難病を発症し、13年間に及ぶ療養生活を送ったが、その時に救いとなったのは、明るい言葉ではなく絶望の言葉だったと言う。氏はその時の経験をもとに、それらの言葉を「絶望名言」と名づけ、のちに、『絶望名人カフカの人生論』や『絶望読書』(ともに飛鳥新社、後に新潮文庫および河出文庫)を著した。そしてそれらを契機にしてNHKの<ラジオ深夜便>に「絶望名言」コーナーが生まれ、書籍化されたものが本書である。 頭木氏は療養中に、人を励ます「名言」もたしかに必要だが、悲しい時に悲しい曲を聴きたくなるように、辛い時には絶望的な言葉の方が「自分と一緒にいてくれて、気持ちをわかってくれて、それが救いに」なることもあるのではないかと感じたと言う。そして、希望を抱かせ前向きに生きるように促す本も「もちろん素晴らしい」のだけれども、絶望的な言葉が胸に入ることでかえって救いになるような本も、「あってもいいし、あってほしいと」思ったそうである。 対談の相手である川野氏もまた脳梗塞による闘病の経験を経ている。その際、ある先生からいただいた「あわてず、あせらず、あきらめず」という言葉の3つの「あ」を肝に銘じて日頃から暗唱していると言う。 <ラジオ深夜便>のディレクターである根田知世己氏によれば、絶望名言とは簡単に言うと「絶望した時の気持ちをぴたりと言い表した言葉」とされる。それは、「言葉にしたところで目の前の現実が変わるわけでもなく、即座に解決策が見つかるわけでもない」けれど、「言葉にすると少し距離ができ」「その間にかすかに風がそよぐ、ちょっとやわらぐ」ものでもあると言う。 たしかに、困難を乗り越えた体験談も感動的だ。しかしそれが自分にとって救いとなるかどうかは人それぞれだろう。反対に、赤裸々に苦しさや絶望が綴られたものに対しては、自分が絶望している時には共感も生まれやすいのではないか。頭木氏の場合はそれが悲常に救いになったと語っている。 頭木氏の取り上げている文学にはそのような文章が綴られている。もちろん、同じ境遇、同じ状況とは限らない。しかしそれを読むことで苦しいのは自分だけではないという思いが生まれ、「みんながそれぞれいろいろな苦労をしているので、自分もその中の一人になれる」し、それによって、「一人で苦悩している孤独とはずいぶん違う」ことが実感されたと言う。 本書は第1回から第6回までの放送で取り上げられた、カフカ、ドストエフスキー、ゲーテ、太宰治、芥川龍之介、シェークスピアの作品によっている。ここでは一部であるがそれらを紹介し、あわせて頭木氏がそれらの言葉をどう受け取ったかを見てゆくことにする。なお、「」内はことわらない限り頭木氏による。 まず、頭木氏が病院のベッドで寝たままなっている時に読んだカフカから。 「将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。将来にむかってつまずくこと、これはできます。いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」(『フェリーツェへの手紙』) これには、「絶望的すぎるというか、もう突き抜けてしまっているので、一緒に落ち込むというよりは、むしろ救いに」なったそうだ。 過酷な経験をしたことで成長する人もたしかにいる。しかし、「これはもう笑うしかないですよね」で、「倒れたまま生きていく、あるいは半分倒れたままに生きていく人生もあり」ではないかと悟ったと言う。 ところで、カフカには特段の不幸があったわけではない。それどころか、裕福な家庭に生まれ、何不自由なく育ち、大卒で、役所勤め、恋愛もし、親友もあり、亡くなる前に病気になるまでは健康で、まさに、平穏無事なごく普通な人生だったそうである。 しかしそれでも絶望している。そこがいいと言う。平凡で日常的な人生から出てきた言葉だからこそ誰でも共感できるのではないか、と頭木氏は考える。さらに、だいたい作家の日記や手紙は作品ほどには面白くないけれど、カフカの書いたものは、「作品はもちろんですけれど、手紙や日記も、作品と言っていいぐらい」だと言う。 「僕には誰もいません。ここには誰もいないのです、不安のほかには。不安とぼくは互いにしがみついて、夜通し転げ回っているのです」(『ミレナへの手紙』) 頭木「これは、じつは恋人への手紙の中の言葉なんです。普通、恋人にはなかなかこんなことを書かないと思うんですけど、カフカは恋人への手紙にも、こういう絶望的望口葉ばっかりなんです」 川野「受け取る側の恋人としては、ちょっと待ってよと言いたくなるような内容じゃないですか」 頭木「そうですね。だから付き合っていた女性のほうもたいしたものだと思うんです」 絶望というのはきわめて個人的なもので、たとえば病気になると、たとえ親身な家族であっても病人の気持ちはなかなかわかるものではないし、また、同じ病気を抱えていても症状や状況が違うから、なかなか本当には共感し合えないのではないだろうか。それは災害に遭った場合も同じだと思われる。そうなると、ひどく落ち込んだ時には、「自分の気持ちは誰にもわからない」という心境になり、「絶望するだけでも辛い」のに、おまけに「孤独がもれなくついてくる」ことになる。 川野「そうすると、絶望している人には、どう接したらいいんでしょうか?」 頭木「普通、皆さんが思うのは、励まして立ち直らせようということではないでしょうか」 しかしなかなか立ち直れない。時には何年ということもざらにある。そうすると、最初は励ましていても、「いつまで経っても立ち直らないので、だんだんイライラ」してきて、「そんなふうに、いつまでも落ち込んでいるから、いけないんだ」などと責め始め、ついには、「もう知らない」などと見捨てるような展開になってしまうのではないだろうか。 でも、「誰しもが右肩上がりに真っ直ぐ立ち直れるわけじゃない」から、「できれば、もっとあせらないようにしてほしいですね。当人も周囲も、なるべくあせらずに」、「それでも時々は連絡を取って、『立ち直れそうになったら、いつでも力を貸すよ』という形でそばにいてあげるのが、一番いいと思いますね」。 ドストエフスキーの回では、「われわれは、自分が不幸なときには、他人の不幸をより強く感じるものなのだ」(『白夜』)を紹介したあと、次に正反対のような表現を取り上げる。 「僕がどの程度に苦しんでいるものやら、他人には決してわかるもんじゃありゃしない。なぜならば、それはあくまでも他人であって、僕ではないからだ。おまけに人間ってやつは、他人を苦悩者と認めることをあまり喜ばないものだからね」(『カラマーゾフの兄弟』) この言葉は人の心のありようが単純ではないことを示している。 頭木氏は、辛い体験をした人ほど他の人の辛い気持ちもわかるからそれだけ優しくなるのは、「辛い体験をしたからこその、いいことのひとつかもしれない」としながらも、「じつはそうとは限らないんです。自分が苦労をしたせいで、よけいに人に厳しくなって、冷たい人間になってしまうということも、けっこう多いんです」とも述べている。これはその人の傷の深さと辿ってきた人生とに色濃く関係するのではないだろうか。 これは『絶望読書』によるが、長期入院していた時にドストエフスキーを読んでいたときにこんなこともあったそうだ。 はじめのうち、「よくそんなものを読むねー」と言っていたあまり本を読む習慣のないような同室の人たち。ところがまず一人が、「ちょっと貸してくれる?」と言いだしたら、次々に、「オレにも貸してみて」となって、それがどんどんハマっていき、ついには6人部屋の全員が読みふけることになったという。その様子を病室に入ってきた看護師が見てビックリ、なにしろ、「ぐるっと見回すと、みんながそろって『カラマーゾフの兄弟』や『罪と罰』を読んでいるのですから」。 ゲーテの回からは次の言葉。 「わたしはいつもみんなから、幸運に恵まれた人間だとほめそやされてきた。わたしは愚痴などこぼしたくないし、自身のこれまでの人生にけちをつけるつもりもない。しかし実際には、苦労と仕事以外の何ものでもなかった。75年の生涯で、本当に幸福だったときは、1カ月もなかったと言っていい。石を上に押し上げようと、くり返し永遠に転がしているようなものだった」(『ゲーテとの対話』) 頭木氏は、ゲーテの伝記映画がほとんどないのを、あまりに人生がうまくいっているのでドラマにならないという理由から、らしいと言う。若い時に書いた『若きウェルテルの悩み』がヨーロッパ中で有名になり、「あのナポレオンまで本を持って、わざわざ訪ねてきたくらいです。いい友達もたくさんいましたし、たくさんの女性から愛されましたし、ヴァイマルという、当時、国だったんですが、そこの大臣になって、貴族の称号をもらうんです。82歳の誕生日の前に、生涯をかけて書いた大作の『ファウスト』を完成させて、数カ月後に亡くなるという、もう大往生ですよね」と。しかし、それはあらすじからの見方であって、細かく見ていくと違った面も見えてくると言う。 「ゲーテの周りでは、大切な人が次々亡くなっていくんです」。4人の妹や弟を亡くし、1人残ったとても可愛がっていた1歳下の妹も26歳の若さで亡くなってしまう。10歳年下のシラーという親友も亡くなって、ゲーテはその時、「自分の半身を失った」と言った。その後母も亡くなり、妻も亡くなり、そして晩年の81歳の時にはたった1人の子供である息子のアウグストが、まだ40歳だったのにイタリア旅行の途中で急に亡くなってしまう。ゲーテはショックのあまり大量の血を吐いて倒れたという。 常に日の当たる場所にいたゲーテだったが、自身が、「『光の強いところでは、影も濃い』と言っているように、多くの喜びの一方で、多くの悲しみも経験しているんです」。 人生を「あらすじ」で生きている時には気づかずにいても、大きな挫折を経験したりするとこれまで気づかなかったことに否応なく気づかされる。「そういう細やかな部分にだんだん目が向くようになると、人生に対する感じ方も、ずいぶん大きく変わってくるなあと思います」。このようなことは私たちも数多く経験しているに違いない。 では、細やかな部分にだんだん目が向くようになるというのはどういうことなのか。頭木氏によれば、それは、元気な頃にはあまり関心を払わなかった味噌汁の味がとても沁みたとか温かかったとか、あるいは、普段はことさら気にすることなく越える段差も、足が弱くなると越えようとするたびに気づくとか、「そんなことが結構人生の大きな部分を占めたりする」ということだ。 太宰治の回には次の言葉。 「駄目な男というものは、幸福を受け取るに当たってさえ、下手くそを極めるものである」(『貧の意地』) 「弱虫は、幸福をさえおそれるものです。綿で怪我をするんです。幸福に傷つけられる事もあるんです」(『人間失格』) 「『綿で怪我をする』っていうんですから、もうどうしていいかわからないですよね。もう他にくるむものがないですよね、綿で怪我をされちゃあ」 この「弱さ」ということから敷衍して、世間で言われるような「弱さの強さ」という一見褒め言葉の背景には、「弱いより強い方がいい」という価値観があるのではないかと頭木氏は指摘する。さらに、「気弱い内省の窮極からでなければ、真に崇厳な光明は発し得ないと私は頑固に信じている」(『服装に就いて』)で太宰は、「弱さには、弱いからこそ価値があり、魅力がある、そう言っているんじゃないでしょうか」と推し測っている。 そしてこうも言う。 「思春期は、誰でも多かれ少なかれ、生きづらさを感じていると思うんです。(略)そういう生きづらい時は、やっぱり何か自分に問題があるんじゃないかなという心配も出てきます。あと、こんなに辛さを感じてるのは、自分だけなんじゃないかなという不安もあると思うんですよね。 そんな時に、太宰治が辛い辛いとさんざん言ってくれるわけです。これはやっぱり、ありがたいことだと思うんですよね」 で、太宰を「好きな人は、『本当に気持ちをわかってもらえる』『同じ気持ちだ』というふうになるんだと思うんですけど、一方、嫌いな人とか読まなくなった人は、そういう太宰を、『ナルシスト』だとか、『甘ったれ』だとか、『駄目な自分に酔っている』とか、そんなふうな言い方をして、けなしたりするわけです」。 この章には面白いエピソードが語られている。それは、太宰治を嫌いな人の代表として三島由紀夫をあげていることで、三島は、「最初からこれほど私に生理的反発を感じさせた作家もめずらしい」(『私の遍歴時代』)とか、「弱いライオンの方が強いライオンよりも美しく見えるなどということがあるだろうか」(『小説家の休暇』)と言ったそうだ。これについて頭木氏は、ライオンだからそうなるので、「ウサギやカピバラだったら弱々しい方がいいですよね。獰猛なカピバラとか嫌ですよね」と、少々冗談めかした言い方をしている。 また、三島が大学生の時に太宰を訪ねて行ったことがあって、「僕は太宰さんの文学は嫌いなんです」と言うと、太宰は、「そんなこと言ったって、こうして来るんだから、やっぱり好きなんだよな。なあ、やっぱり好きなんだ」(『私の遍歴時代』)と答えたので、三島はすごく怒ったそうである。 芥川龍之介の回には次の言葉が取り上げられる。 「どうせ生きているからには、苦しいのは、あたり前だと思え」(『仙人』) 若い頃、まだ名を成す前に芥川はすでにこんなことを言っていた。頭木氏は、「ちょっと偉そうな感じにも聞こえるかもしれません。上からお説教しているような。でも、じつはこれ、短編の中では、非常に貧しい男が、ねずみに向かって、こういうふうに言ってるんですね。もちろん、本当にねずみに説教しているわけではなくて、ようするに、自分に言い聞かせている言葉なんです」。 芥川は、生まれて8カ月後には母が精神病院に入ってしまい、母親の実家に預けられ伯母に育てられる。そして10歳の時に母親が亡くなる。その後、12歳の時から伯父の養子になり、芥川という名字になったのはその時からだという。 そういう生い立ちのせいもあって、この『仙人』を書く前に親友に手紙でこのように書いている。「『周囲は醜い。自己も醜い。そしてそれを目のあたりに見て生きるのは苦しい』(井川恭・宛 大正4(1915)年3月9日付)」と。つまり、小さい頃から「生きるのは苦しい」ということを実感していたと言うことだ。 川野「なるほど。『生きるのは苦しい』が、ひっくり返って、『生きているからには、苦しいのはあたり前だと思え』というふうになったんですね」 頭木「そうなんです。これ、同じようですけれど、じつはけっこう大きなちがいだと思うんです。 というのは、『生きるのは苦しい』っていうのは、本当に辛いじゃないですか。だけど、『生きているからには、苦しいのはあたり前だと思え』と言われると、そうか、生きているんだから、もう苦しいのはあたり前なのかというふうに思えて、ちょっとね、救われるところもあるというか……」 また芥川は友人に残した遺書の中で次のように書いた。 「僕の場合はただぼんやりとした不安である。何か僕の将来に対するただぼんやりとした不安である」 たしかに、病気にもよるが、病名がついて対策がはっきりすれば、心を落ち着かせる効果も期待できるかも知れない。しかし人生そのものは本来的に曖昧さに満ちているのが現実だろう。自身でも、「誰かを好きなのか嫌いなのかさえ、本当はよくわからなかったり。そういうことはいくらでもあるわけですよね」。だから、「恋愛とかでも、『本当に好きなの?』とか、はっきりさせようと問いつめたりするわけじゃないですか」。でも、「『曖昧さは、人間にとって非常に苦しいものである』というのは納得できる人が多いんじゃないでしょうか」。 名言の宝庫であるシェークスピア、多くの作品あるなかからの次の言葉。 「あとで一週間嘆くことになるとわかっていて、誰が一分間の快楽を求めるだろうか? これから先の人生の喜びのすべてと引き替えに、今ほしい物を手に入れる人がいるだろうか? 甘い葡萄一粒のために、葡萄の木を切り倒してしまう人がいるだろうか?」(ルークリース) 頭木「あとで大変なことになるとわかっているのに、目の前のしたいことをしてしまう人、そんな人がいるのかということを3回繰り返し聞いているんですけど、いるか、いないかっていうと、いるっていうことなわけですよね(笑)」 川野「そうですよね(笑)。いるから、そういうふうに言うんでしょう」 頭木「そうですね。実際には、ほとんどの人がそうだと思うんです。私自身もそうですし」 余談だが、植木等が「スーダラ節」を歌う前にかなり悩んだと言う。彼の実家は浄土真宗の寺で、父は僧侶、反対されると思ったらしい。ところが父は、「わかっちゃいるけどやめられない」は親鸞の教えに通じると言って賛成してくれ、息子を励ましたという。 しかし出来ないからと言って、しなくて良いということにはもちろんならない。そうではなく、「出来ないのが人間」ではないか、そのことを先ず認めることから始めなければならないのではないか、そう頭木氏は言う。 「明けない夜もある」(『マクベス』) 絶望している人をなぐさめる時によく聞かれるのが、「明けない夜はない」という言葉だ。これは『マクベス』に出てくると言う。それは、マクベスに妻子を殺されて嘆いている男に、別の男が「明けない夜はないよ」と言葉を投げかける場面で、実はその男もマクベスに父親を殺されている。つまり、マクベスに身内を殺された者同士だ。 頭木氏はこれにずっと違和感を覚えていたという。それは、妻や子どもをマクベスに殺されたことを、今聞かされて嘆き始めたところなのに、「明けない夜はないよ」と励ますのは早すぎるのではないかと言うことだ。 原文は“The night is long that never finds the day”。直訳すると「夜明けが来ない夜は長い」となる。でも、自然現象としての夜明けはいずれは来るわけで、「明けない夜はない」と言うのは意訳として間違いではなく、たいていはこう訳される。ただ、頭木氏は、「泣きだしたばかりの人に、『涙はいずれ乾くよ』って、いきなり言うのはおかしくないですか?」という思いがあった。 翻訳家の松岡和子氏は、ここはそんな楽観的な言葉ではなく、「覚悟をうながす言葉」ではないかと言う。その覚悟というのはつまり、「マクベスを倒さない限り、夜明けは釆ないと。悲しい夜がずっと長く続くぞ」ということだ。そして松岡氏は、「『朝が来なければ、夜は永遠に続くからな』(『シェイクスピア全集(3)マクベス』ちくま文庫)というふうに」訳しており、その訳に感激した頭木氏は、「こういう解釈もあり得るのか」と思ったそうである。 悲しみというのは、あたかも自然現象のように時間とともに消えていくと捉えてしまうのではなく、「大切な人を失ったというような深い悲しみは、いつまでも続くこともあるよと。そういう言葉としてとらえることもいいんじゃないか」。そして、「明けない夜もある」というふうに訳したいとも言っている。 時間では癒やされないような悲しみをいつまでもひきずっていると、「周囲も『これだけ時間が経つのに、いつまで悲しんでいるんだ』というふうになってきますし、自分自身も『いつまでも悲しんでいる自分はいけないんじゃないか』と、そんなふうに思いがち」になる。そうすると、悲しみが癒えない上に、自分で自分を責め周囲からも責められ、より辛いことになってしまう。 だからこそ、「現実にそういう悲しみがある以上、そういうこともあるんだよって知って」おくこと、「『明けない夜もある』『明ける夜もある』。両方知っておくほうが大事」なのではないかと言う。 頭木氏によると、最近のアメリカの心理科学会誌に発表された研究で、「時間の経過だけでは人は癒やされるとは限らない」ということが確認されたと言う。さらにこの研究チームは、「『時間が解決してくれる』と、当人や周囲が思ってしまうことで、かえって回復をさまたげたり、こじらせてしまう原因となっている」と指摘しているそうである。そして氏は、「それにしても、こうした研究のない時代に、時間が経っても癒やされない悲しみがあるということを描いたシェイクスピアは、やはりたいしたものだと思います」と結んでいる。 本書にはそのほかにもさまざまな言葉と体験が綴られている。そこでは、「死が救いに思われるほどの絶望をすくいとって言葉にしていく」ことを軸として、文豪たちが遺した名言と体験を重ね合わせられている。そして、「文豪たちの絶望名言がそうであるように、一人の苦しみをつきつめていくと普遍性を持つものです。この番組はそのプロセスの実践」であると結んでいるおもえt。本書は本当の共感とはなにかについて深く問いかけているように思える。 繰り返すが、興味を覚えられたらぜひ通読されることをお勧めしたい。私たちが抱える課題に対する見方を深める糧になると思う。本書は本当の共感とは何かについて深く問いかけているように思えたが、また私たちにとって他の意見や主張を偏りなく理解することの難しくまた重要なことかを痛感させられた。(雅) |
| このページの先頭へ |
| 『月刊サティ!』トップページへ |
| ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)トップページへ |