
| 2020年1/2月合併号 | Monthly sati! Jan. Feb. 2020 |
| 今月の内容 |
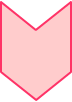 |
| |
巻頭ダンマトーク 『瞑想か? 信仰か? ・・・心の拠りどころとは』 |
| ダンマ写真 |
|
| |
Web会だより:『体を整え、心を整え、人生を整え』(前半) |
| |
ダンマの言葉 |
| |
今日のひと言:選 |
| |
読んでみました:『ホモ・デウス』 |
| 『月刊サティ!』は、地橋先生の指導のもとに、広く、客観的視点の涵養を目指しています。 |
![]()
|
今月は質問をきっかけとしたダンマトークを掲載いたします。内容は、人類が生き延びるために培った形質をふまえて、ヴィパッサナー瞑想の意義するところを俯瞰的な視点から解説しています。ぜひ、みなさまの瞑想実践のバックボーンとして活かしていただけたらと思います。(編集部) |
| 今月は質問をもととしたダンマトークを掲載いたします。内容は、人類が生き延びるために培った形質をふまえて、ヴィパッサナー瞑想の意義するところを俯瞰的な視点から解説しています。ぜひ、みなさまの瞑想実践のバックボーンとして活かしていただけたらと思います。(編集部) |
瞑想も人生も上手くいかない者には、ヴィパッサナー瞑想的ではないかもしれませんが、「すがる対象」も必要なのではないでしょうか? 先生: |
| ~ 今月のダンマ写真 ~ |
 |
| 先生より |
![]()
|
<Web会だより> |
| 『体を整え、心を整え、人生を整え』(前) E.K. |
| 16年前に仕事のストレスから心の調子を崩しうつ病になりました。その時お世話になったカウンセラーの先生の勧めで、座禅を始めたのが瞑想との出会いでした。その後、体調管理のために続けていたヨガが実は瞑想のための技法であったことを知り、それ以降は、ヨガと集中系の瞑想を生活の中に取り入れながら、心と体のメンテナンスを行ってきました。
ただ、どれだけヨガや集中系の瞑想を行っても、長年しみついた心の癖のようなものは、なかなか改善されず、生きづらさは変わりませんでした。何度も同じような悩みにぶつかり、それを乗り越えようと、自信をつけるために資格を取ったり、果ては外国留学までしてみたり・・・。そして頑張りすぎてへとへとになり、お酒や買い物、刹那的な快楽で気を紛らわしながら、いつも心の奥底でむなしさを感じていました。 そんな中、あるマインドフルネス関係の書籍と出会い、今まで集中系の瞑想では感じることのなかった「客観的に観る」ということの意味がやっとわかったのです。その後は、片っ端から書籍を読み漁り、中でも地橋先生の「ブッダの瞑想法」が一番、論理的かつ親切でわかりやすかったので、かじりつくように読みながら、実践を重ねました。そのうちに、やはりご本人に指導を仰ぎたい、という想いが強くなり、朝日カルチャーに通い始めました。 初めて地橋先生から直接、歩く瞑想の指導を受けた時のことは忘れられません。ラベリングのタイミングがこんなにも重要だとは思っていませんでした。六門からの情報の入力と(触)→識→受→想→尋の流れが初めて理解できた瞬間でした。 その日以来、歩く瞑想の素晴らしさに開眼し、毎日夢中になって行いました。毎朝20分の歩きの瞑想と座りの瞑想を、夜は時間があれば時間の許す限り行いました。 とにかく瞑想が、サティが入る感覚が楽しくて仕方がなかったのです。サティが連続して入っている時、心は完全に今に留まることができます。集中瞑想と違って、軽やかな感じも、私にはとても新鮮でした。 それからダンマトークを継続して聞くことで、法の理解が深まり、特に、無常、無我、縁起、の意味が単なる学問ではなく、「本当のこと」として理解できるようになってきました。 ある時、座りの瞑想中に呼吸を観察しながら、気づいたことがあります。今まで私は「自分が」息を吸って「自分が」吐いている、と思っていたけど、よーく観察してみると、息って勝手に起きている。止めようとしたって、止められないし、せいぜい2、3分で、苦しくなって、吸ったり吐いたりしてしまう。自分の力じゃとても太刀打ちできない。 今まで私は、自分の力で生きてきた、と思っていたけれど、この世界には、なにか得体の知れない力が、いわば「いのちの働き」のようなものがあって、そちらの方に生かされているんだ、そう思ったら涙があふれてきました。 日常生活も激変しました。日常生活全般に、自然にサティが入るようになると、最初は自分が、いかにこの世界を、瞬時にジャッジ、判断しながら生きているのかを目の当たりにして、驚きました。 道端の花を目にした瞬間、観た?ピンク?キレイ、と快を覚える心。前を歩く人の煙草の煙をかいだ瞬間、刺激臭?タバコ??くさい?無礼な人、と嫌悪する心。・・・こんなことを、一日中やっているんだ、私。そう知った時の衝撃は忘れられません。私はこの世界をありのまま観ているんじゃなくて、自分の色眼鏡を通して、世界を眺めているだけなんだ。これじゃあ、どれだけ瞑想しても、ありのままを眺めることなんて、一生かけても出来っこない。反応したくないのに、勝手に反応してしまう心。それが止められない限りは、苦しみはなくならない。それを悟ってから、反応系の修行に本気で取り組み始めました。 まず慈悲の瞑想を徹底的に、真剣に行うようになりました。毎晩、寝る前と、電車の中で行うようにしました。特に満員電車や雑踏を歩く時など、不善心所になりそうな場所、場面では、嫌悪系の反応が起きる前に行っておくと、心が穏やかに保ちやすいことがわかってきました。 私はヨガの講師をしているのですが、レッスンの前に行うことで「私が教えてあげる」というエゴ感覚が薄れて「この人たちに楽になって欲しい」という慈悲モードに意識が切り替えられて、「よく見られたい」「評価されたい」という承認欲求がなくなり、緊張することが減りました。また、なぜか生徒さんの数が増えて、クラスがキャンセル待ちになることも多くなりました。 それから、戒を守ることの大切さも身に沁みてわかってきました。五戒はどれも大切だと思いますが、私には「嘘をつかないこと」が難しかったです。私は昔から人から嫌われることが怖くて、ついお世辞を言ってしまったり、相手を傷つけないように、事実とは違うことを言ってしまうことがよくありました。「嘘も方便」って言葉もあるじゃないか。相手を傷つけないための嘘ならついてもいいんじゃないか。最初はそう思っていました。けれど、瞑想が深まって行くにつれて、相手のことを思っているようでも、その実、自分を守っているだけなのだと、いうことに気づかされました。そしてどんなに小さな嘘であっても、心が汚れることにも気づきました。 「迷った時は、心が汚れない方を選ぼう」。日常の中で、何か判断に迷う時、いつもそれを基準にすることで、自分の中に軸ができました。どんな時でも正々堂々と居られるようになり、生きていくことが楽になってきました。そして、そんな自分を信頼する気持ちが生まれてきて、生まれて初めて自信がついてきました。 自分自身との信頼関係ができてくると、不思議なことに、自分のエゴ感覚に対しても、嫌悪ではなく、ニュートラルな視線を向けられるようになりました。怒りや不善心がわいてしまう、そんな自分もあるがまま観ることができるようになり、その結果、怒りや貪りを封じ込めることなく、根本的な原因にまで洞察が及ぶようになり、自己理解が深まりました。(続く) |
☆お知らせ:<スポットライト>は今月号はお休みです。 |
![]()
|
ブッダの方法には、いかなる機器も補助器具も必要ではありません。その方法は物質性(色法)と精神性(名法)の両方を見事に扱うことができます。自分の内部で物質性と精神性の活動が生じた時に、その活動に率直な注意を固定することにより、分析という目的のために自分の心を使います。
|
![]()
![]()
| ユヴァル・ノア・ハラリ著『ホモ・デウス』 (河出書房新社 2018年) |
| 著者はイスラエルのヘブライ大学で歴史学を教えている人類史学者。本書は上・下2巻に分かれた大部である。下巻にある「訳者あとがき」には著者の意図、内容について要点が纏められていて、全体の流れを理解するのに役立つ。ではあるが、本文自体にたいへん広い知識と考察が含まれているため、腰を据えて読んでいけば、人と世界のありさまについて改めて意味をみつけることが出来る。また著者の説にはその背景となるデータや理論が示されているが、そればかりではなく、説明のためにわかりやすい例え話が示されていて、本書をなじみやすく、また納得しやすいものとしている。 さらに「謝辞」には、ゴエンカ師によってヴィパッサナー瞑想の技法の手ほどきを受けたことが記されている。それについて著者は、「この技法はこれまでずっと、私が現実をあるがままに見て取り、心とこの世界を前よりよく知るのに役立ってきた。過去15年にわたってヴィバッサナー瞑想を実践することから得られた集中力と心の平穏と洞察力なしには、本書は書けなかっただろう」と述べている。このことからも、本書がものごとの本質を的確に捉えている印象が深いのも納得がいく。 「訳者あとがき」によれば、本書は『サピエンス全史――文明の構造と人類の幸福』に続いて、該博な知識とじつに多様な分野の知見を独創的に結集して著したものである。前作は、「認知革命、農業革命、科学革命という三つの革命を重大な転機と位置づけ、虚構や幸福をはじめとする斬新な観点を持ち込みながら過去を振り返り、私たちが抱きがちな近視眼的歴史観や先入観や固定観念を揺るがせてくれ」「最終章では未来に目を転じて、サピエンスの終焉と超人誕生の筋書き、及び、それに伴う問題を簡潔に提示した」もので、本書の重点はその未来にあるとされる。 ここでは上巻の1章から第4章のみを取り上げているが、もし興味を惹かれたならぜひ通読されることをお勧めしたい。 第1章の「人類が新たに取り組むべきこと」では、何千年もの間人類の不可避的な課題となってきた飢饉、疫病、戦争の三つについて触れる。それらはこれからも大きな犠牲者を出し続けるとは思われるが、いまや制御の及ばないものではなく、対処可能になっていることをさまざまなデータを使って示している。そうすると、次に来る新しい課題は何か、それは、「何かを成し遂げたときに人間(以下、「人間」とはサピエンスのこと)の心が見せる最もありふれた反応は、充足ではなくさらなる渇望」であり、それは「人類固有の危険」であって、その究極的な中身は、「不死と幸福と神性を標的」とすると言う。この三番目の「神性」については、下巻に詳しく述べられている。 第2章「人新世」では、人間という一つの種が単独で、7万年の間に地球を多くの生態系の集合から単一の生態系へと徹底的に変えていったこと。そしてその影響は、この後100年で6500万年前に恐竜を一掃した小惑星の衝撃を超えかねないと警告する。 また、アニミズムを拒絶する態度は極めて最近のものであり、人間と動物は本質的に違っているという考え方は農業革命の副産物にすぎないとも言う。人間も動物も、生存と繁栄のために進化した感覚や情動の構造は変わらないし、「母親と幼児の絆という情動はあらゆる哺乳動物が共有している中核的なもの」なのだ。 しかし、農業革命が生み出した経済的関係は、動物に対する残酷な利用を正当化する有神論の宗教的信念の出現を促すこととなった。そしてその結果、単なる動物の一種に過ぎなかった自らを森羅万象の頂点の存在とし、人間がすべての生き物を支配し、また生態系との間を取りもつ役割にある説明として、天上にあるとイメージされる「神」というものを創り出したのである。 第3章「人間の輝き」では、動物はもちろん人間においても「魂」という存在を真っ向から否定する。すでに一神教の神話は切り崩されており、「死さえ含め、ありとあらゆる変化にも耐えられるような本質をある動物に与えることが果たして可能か」と言う。魂の存在は進化論と両立し得ないということだ。 では、「心」とは何か。それは苦痛や快楽、怒り、と言うような主観的経験の流れである。現代の通説によると脳内の電気化学的反応によって苦痛や怒りや愛情が生み出されているとされているが、今のところそのメカにズムは解明されていない。例えば、「『怒ったぞ』と私が言うときには、とても明確な感情を指している」が、その時にニューロンの化学的反応によって生じた電気信号がどのように怒りを生み出しているのか、そのことを「問う価値は依然として残」っている。 そして、動物は「私たちと同じで、彼らも意識を持っているし、感覚と情動の複雑な世界も持っている。もちろん、どの動物にもその動物ならではの特性や才能がある。人間にも人間ならではの特別な能力がある」と、豊富なデータをあげて示している。 では、その人間ならではの能力とは何か。それには二つのことを挙げる。第一に大きな集団で協力する能力であり、第二は、その協力は柔軟性を持つものである、ということだ。それが、同じく協力をする生き物としてのアリやハチとは違っているところであるし、もちろん、「ゾウやチンパンジーなどの社会的な哺乳動物は、ハチよりもはるかに柔軟に協力するが、それは少数の仲間や家族に限られ」てもいる。 ではなぜ、人間は大きな集団でありながら協力が出来たのか。それは、「現実」とは何かを考察することによって明らかにされる。多くの人は「現実」というものには「客観的現実」と「主観的現実」という二つがあると知っているが、実はそれだけではなく、「大勢の人の間のコミュニケーションに依存している」「共同主観的レベル」という第三の「現実」があるからである。そして、「歴史におけるきわめて重要な因子の多くは、共同主観的なもの」であったとする。 第4章「物語の語り手」では、この「共同主観的レベル」の虚構の物語がさまざまに展開して人間の歴史を作ってきたことを語っていく。私的にはこの第4章が最も面白く、印象に残り、この「共同主観的レベル」で物語を作り出したかどうかが、ネアンデルタール人との違いであったということにも納得がいった。 では、この「共同主観的レベル」の物語とは具体的には何なのか。そしてその前に、物語が大きく展開するために用意されたものは何っだか。それはおよそ5000年前に生まれた書字と貨幣であり、それが「人間の脳によるデータ処理の限界を打ち破った」。 書字が発明されたことで、人間は、複雑な、長く、入り組んだ物語を創作することが出来るようになった。「読み書きのできない社会では、人々はあらゆる計算や決定を頭の中で行なう。一方、読み書きのできる社会では、人々はネットワークを形成しており、各人は巨大なアルゴリズムの中の小さなステップでしかなく、アルゴリズム全体が重要な決定を下す」。 (注:アルゴリズムとは簡潔に言えば、「なにかを行うときのやり方」のこと:編集部) これらは例えば法律、規則、契約書、病院のシステム、法律、企業、国家、国境線であり、成績の点数であり、紙幣等々、挙げていけば切りがない。これらは虚構ではあるが、これらがなければ現在の社会は成り立たなくなる。「お金や国家や協力などについて、広く受け容れられている物語がなければ、複雑な人間社会は一つとして機能しえない。人が定めた同一のルールを誰もが信じていないかぎりサッカーはできないし、それと似通った想像上の物語なしでは市場や法廷の恩恵を受けることはできない」のだ。 しかしそれらはあくまで道具に過ぎないのだから、「物語を目標や基準にするべきではない。私たちは物語がただの虚構であることを忘れたら、現実を見失ってしまう」ことになる。そうすると、「『企業に莫大な収益をもたらすため』、あるいは『国益を守るため』に戦争を始めてしまう。企業やお金や国家は私たちの想像の中にしか存在しない。私たちは、自分に役立てるためにそれらを創り出した。それなのになぜ、気がつくとそれらのために自分の人生を犠牲にしているのか?」と著者は問いかける。 虚構と現実とをしっかり見極めること、それが私たちに求められる。ではどうやって。それは、「それが苦しむことがありうるか?」と自問することによって知られると言う。銀行が倒産しても「銀行」という虚構(編集部)が、国は戦争に敗れても「国」という虚構が苦しむということはない。しかし、戦場で負傷した兵士はそれ自体が苦しみ、人は食べる物が何もなければ当然に苦しむ。そしてそれこそが「現実」であるのだ、と。さらに、虚構を信じていることによっても「現実」に苦しむことがある。「たとえば、国家や宗教の神話を信じていたら、そのせいで戦争が勃発し、何百万もの人が家や手足、命さえ失いかねない。戦争の原因は虚構であっても、苦しみは100パーセント現実だ。だからこそ、虚構と現実を区別するべきなのだ」と。 そしてこのあと第5章では、「人間の方や規範や価値観に超人間的な正当性を与える網羅的な物語なら、そのどれもが宗教である」として、「21世紀にはこれまでのどんな時代にも見られなかったほど強力な虚構と全体主義的な宗教を生み出すだろう」と言う。そして、近未来の予測を述べるとともに、「虚構と現実、宗教と科学を区別するのはいよいよ難しくなるが、その能力はかつてないほど重要になる」と結び、下巻へとつながる。 下巻においても、壮大な視点から重要な問いを人間と社会に対して投げかけており、多くのことがらが縦横に検討されている。そのいくつかを挙げれば、「神への信心から人間性への信心へ(人間至上主義)」「自由意志という概念に関する諸問題」「個人主義=自由主義と人間」「人間中心からデータ中心へと言う世界観の変化」等々である。 読み通してみると、著者の眼目は未来のありさまを予見した下巻にあるのではないかと推察されるけれども、今回はそこまで紹介するには至らなかった。ただ、人類史の部分を読んだだけでも、「人間」というもののありようと世界についての見方を一歩も二歩も進めてくれてくれることは間違いないと思う。(雅) |
| このページの先頭へ |
| トップページへ |